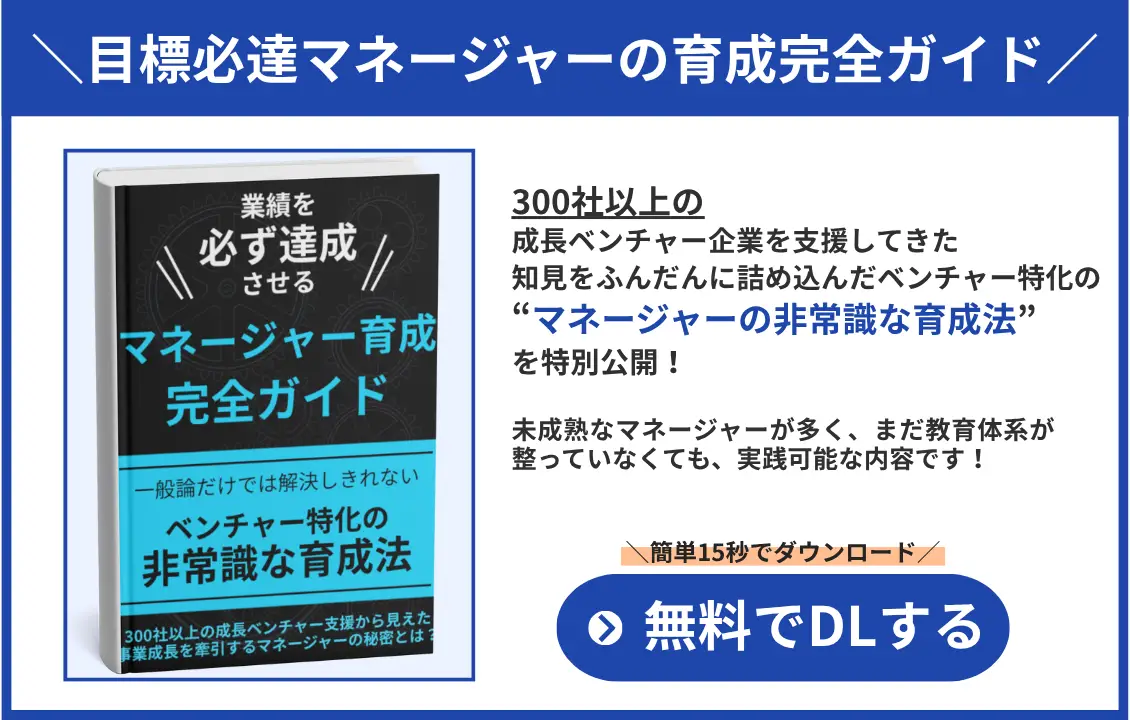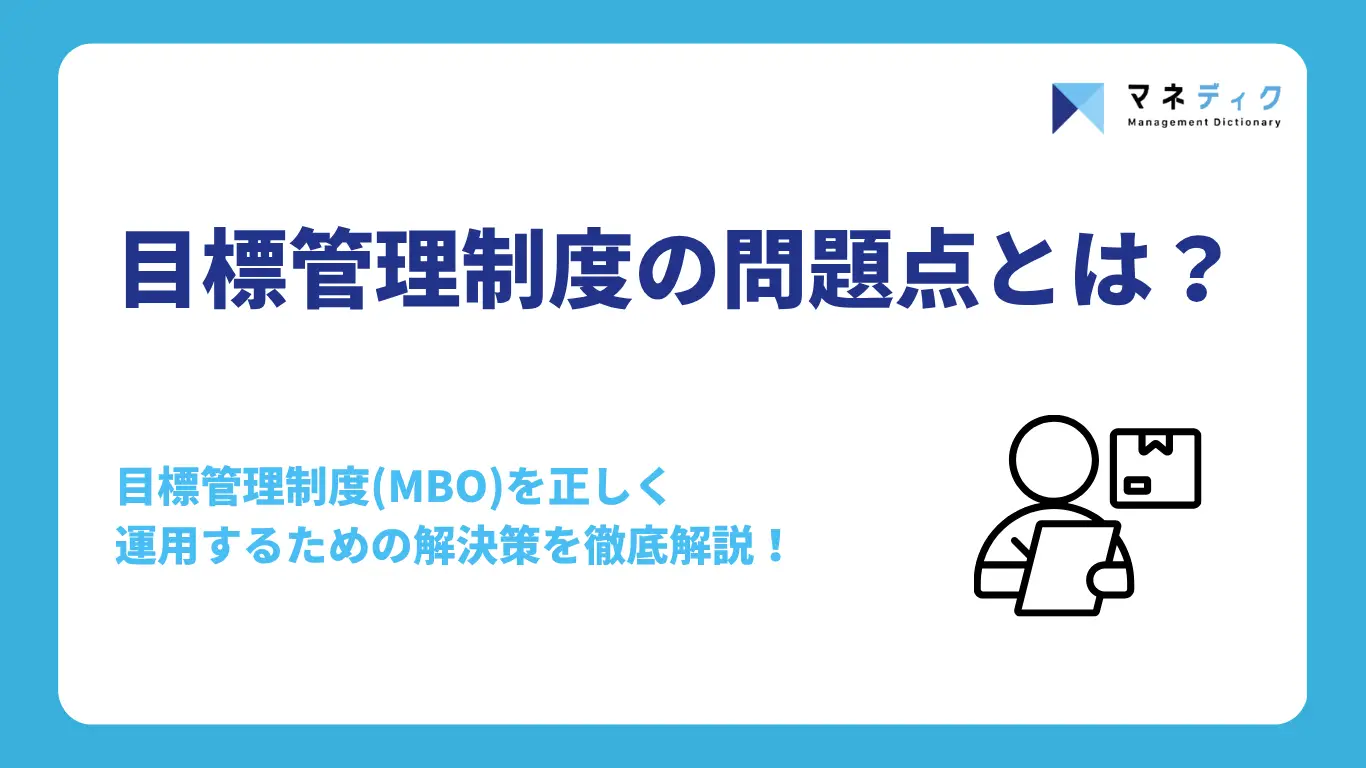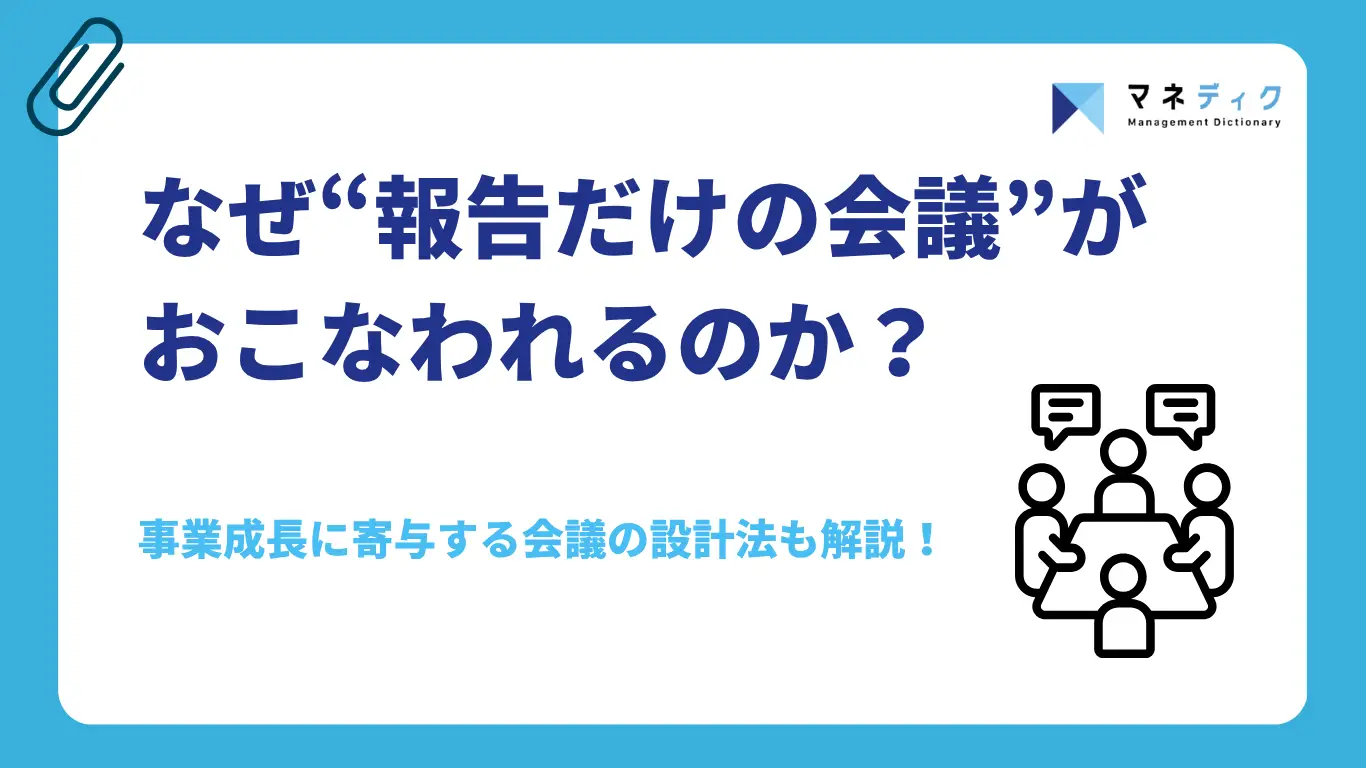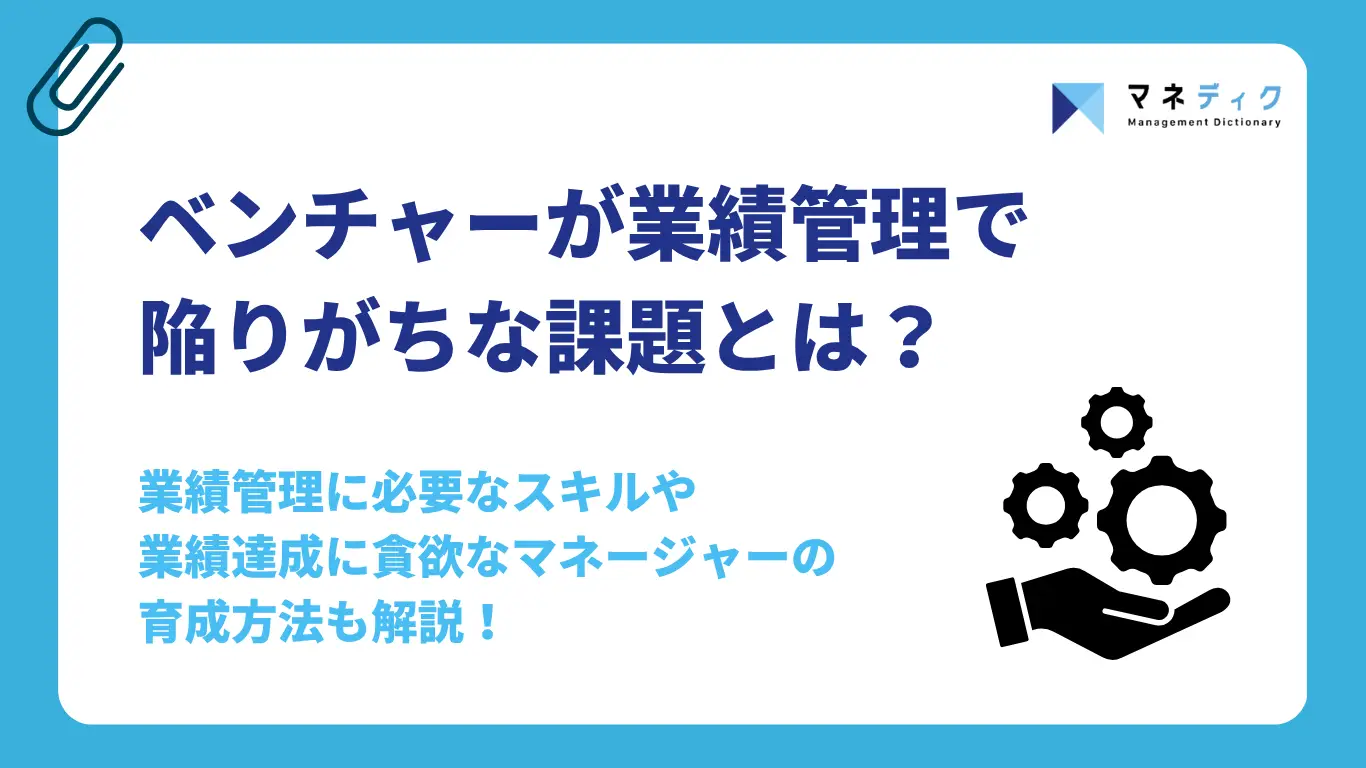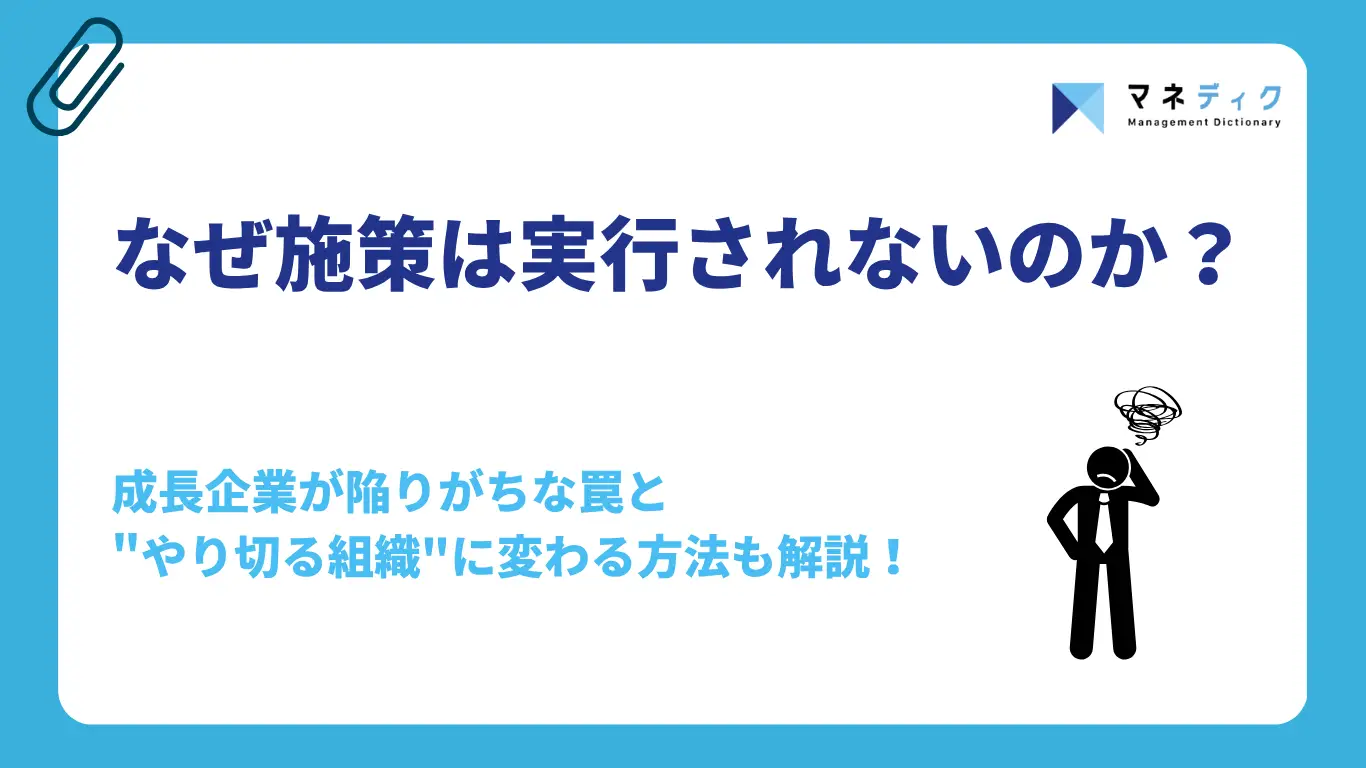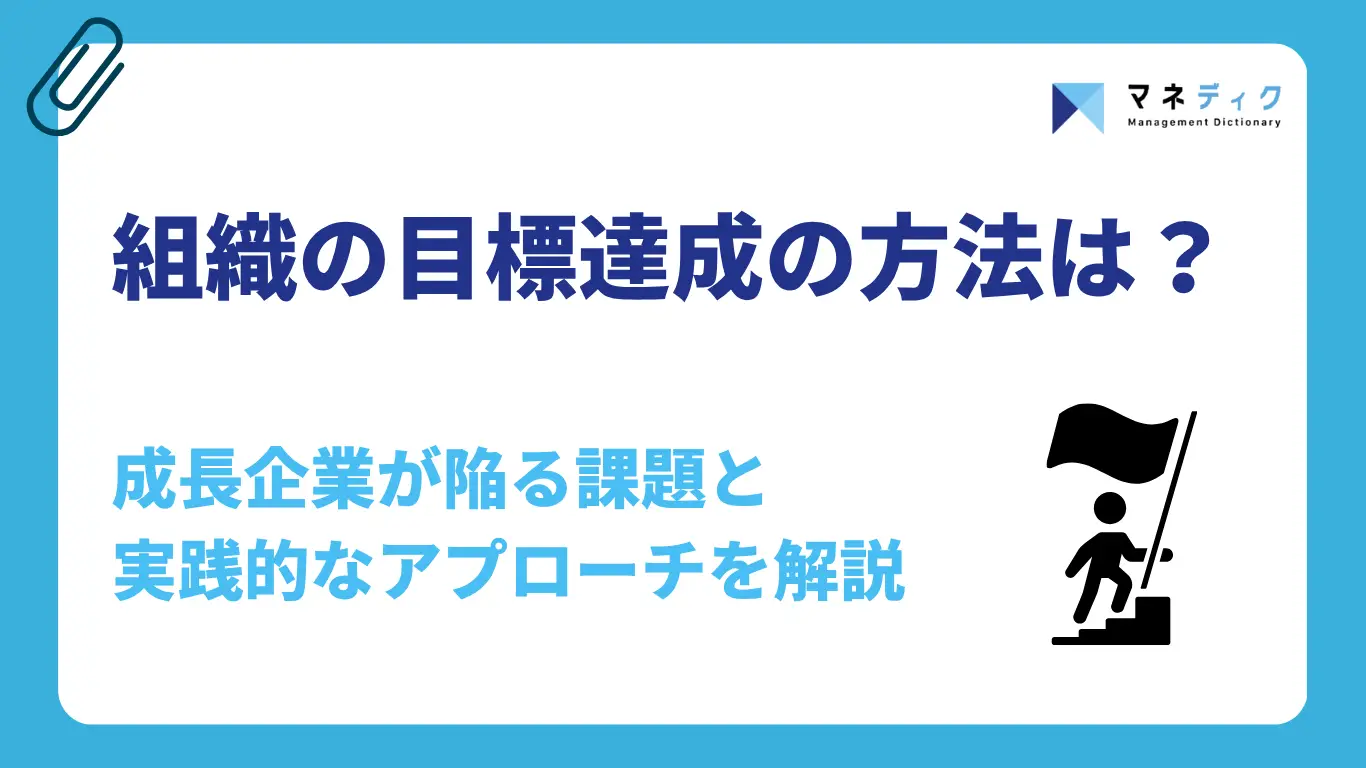ICEスコアリングモデルとは?優先順位付けの計算方法と使い方をフレームワークで解説
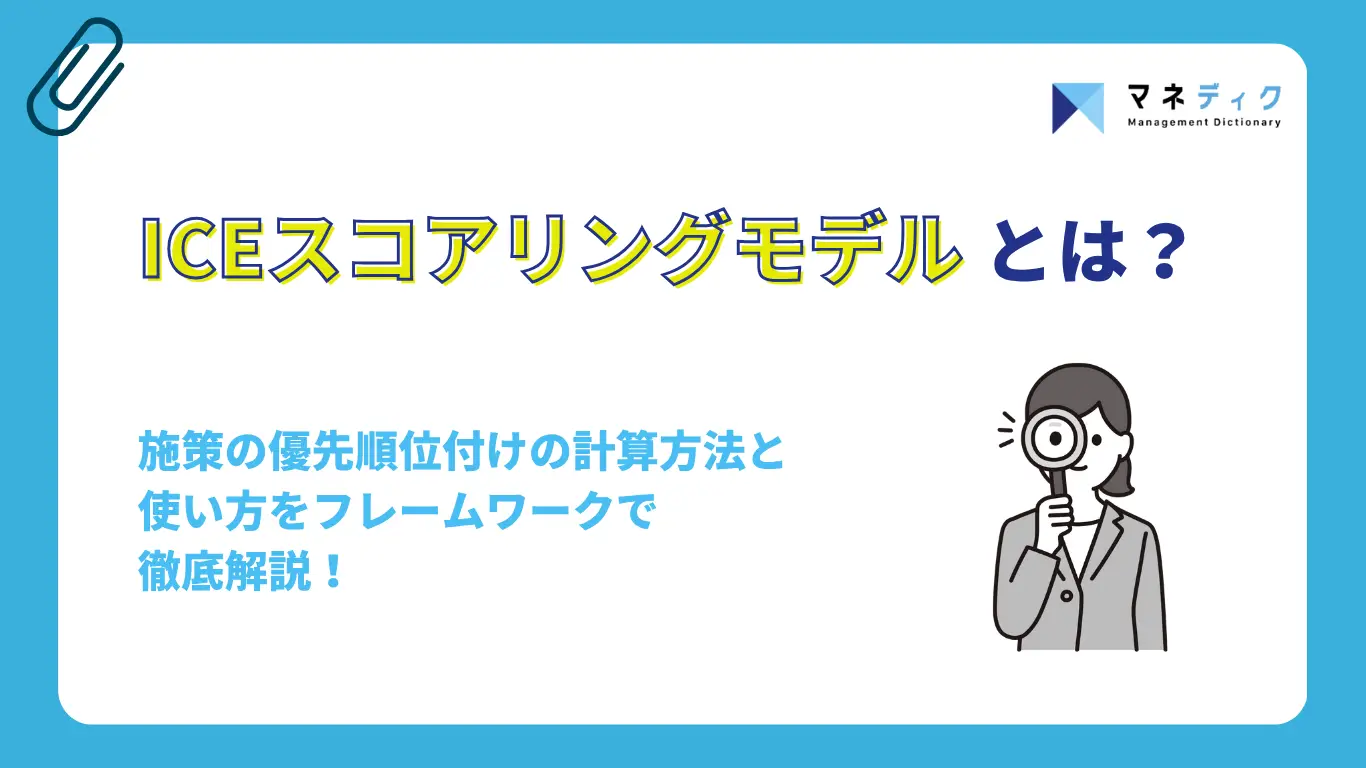
ICEスコアリングモデルとは?3つの計算要素
「やりたい施策」や「対応すべきタスク」が山積みになる一方、開発やマーケティングのリソースは常に有限です。感覚的な優先順位付けは、チーム内に不協和音を生み、事業インパクトの低い施策にリソースを割いてしまう原因となります。
こうした課題を解決するのが、ICEスコアリングモデルです。
これは、施策の優先度を「3つの要素」で客観的に評価し、数値化するフレームワークを指します。

1. Impact(影響度):施策がKGI/KPIに与える影響
Impact(インパクト)は、その施策が実行された場合に、ビジネスやユーザーにどれだけ大きな影響を与えるかを示す指標です。
ここで重要なのは、影響度を「売上」や「MAU(月間アクティブユーザー数)」、「解約率(チャーンレート)」といった、組織が追っている最重要指標(KGI/KPI)と連動させることです。リソースが限られる中で事業を成長させるには、最も成果(KGI/KPI)に直結する施策から実行する必要があるためです。KGIと連動しない施策ばかりを実行しても、現場は疲弊し、事業は前進しません。
2. Confidence(確信度):施策の成功に対する確信
Confidence(コンフィデンス)は、その施策が成功するという確信の度合いを示します。Impactが「予測される成果の大きさ」であるのに対し、Confidenceは「成果が出る確率(予測の精度)」と言えます。
この確信度は、データや顧客インタビュー、過去の類似施策の結果といった「客観的な根拠」に基づいて判断する必要があります。「大きなインパクトが期待できる(Impact=10)」施策であっても、それが単なる希望的観測や勘(Confidence=1)であれば、リソースを投下するギャンブルになってしまうからです。客観的な根拠に基づき確信度を評価することで、施策の「不確実性リスク」を判断できます。
3. Ease(容易性):施策の実行しやすさ
Ease(イーズ)は、その施策をどれだけ簡単に(低コストで)実行できるかを示す指標です。
エンジニアリング部門の開発工数だけでなく、マーケティング予算、営業部門の協力、法務チェックなど、施策完了までに必要なすべてのリソース(人・モノ・金・時間)を考慮します。スコアが高いほど「実行しやすい」ことを意味します。
どれほどImpactやConfidenceが高くても、実行に膨大な時間やコストがかかる(Ease=1)施策ばかりでは、施策の実行回数が減り、学習サイクル(Build-Measure-Learn)が遅くなってしまうためです。ROI(投資対効果)の「投資(コスト)」面を評価する重要な指標です。
4. 具体的な計算方法 (Impact × Confidence × Ease)
ICEスコアの計算は非常にシンプルです。
定義した3つの要素(I, C, E)を、それぞれ1〜10点などで点数化し、すべてを掛け合わせます。
ICEスコア = Impact × Confidence × Ease
例えば、Impactが8点、Confidenceが5点、Easeが3点の場合、スコアは「8 × 5 × 3 = 120点」となります。このスコアが高い施策ほど、優先的に取り組むべきだと判断できます。
5.RICEスコアリングモデルとの違い
ICEモデルの派生形として「RICEスコアリングモデル」も存在します。
これは、ICEの3要素に「Reach(リーチ)」を加えたものです。
Reach(リーチ):
その施策が影響を与えるユーザー数(例:期間内に何人がその機能を目にするか)
RICEモデルは、特に影響範囲(ユーザー数)が施策によって大きく異なる場合に有効です。
一方、ICEモデルはよりシンプルで、迅速な意思決定が求められるスタートアップなどで好まれます。
【特にベンチャー/スタートアップ必見】なぜICEスコアリングが有効なのか?
ICEスコアリングモデルはあらゆる組織で活用できますが、特にリソースが限られるベンチャーやスタートアップにおいて強力な武器となります。
なぜなら、ベンチャー企業は「リソース(人・モノ・金・時間)」が絶対的に不足している傾向にあるからです。
大企業のように潤沢な予算や人員で複数の施策を同時に試す体力はありません。むしろ、少ないリソースで多くの施策を高速で回し続ける必要があるからこそ、一つひとつの施策の「無駄打ち」を徹底的に排除することが求められます。
- 「Impact(影響度)」をKGIと連動させることで、数少ないリソースを「今、最も事業成長に効く施策」に集中投下できます。
- 「Ease(容易性)」を評価することで、コスト(特に開発工数)を最小限に抑え、学習サイクル(BML)を高速で回すという、ベンチャーの生命線である「スピード」を担保できます。
感覚的な意思決定による「無駄な開発」は、リソースの枯渇、ひいては事業の失敗に直結します。
ICEスコアリングモデルは、その「無駄」を徹底的に排除し、限られたリソースを最適配分するための「羅針盤」として機能するのです。
ICEスコアリングモデルのメリットとデメリット
ICEスコアリングモデルは強力なツールですが、万能ではありません。
導入前にその強みと弱みを理解しておくことが、フレームワークの形骸化を防ぐ鍵となります。
メリット
メリット1:感覚的な判断を排除し、客観的な基準を作れる
最大のメリットは、優先順位付けのプロセスから「声の大きさ」や「感覚」を排除できる点です。
「これが重要だと思う」という主観的な意見のぶつかい合いではなく、「スコアが高いから」という客観的な基準で議論を進められます。
メリット2:チームやステークホルダーとの合意形成がスムーズになる
開発チームや他部署を納得させる際、「なぜこの施策を今やるのか」を説明する「共通言語」として機能します。スコアリングのプロセスを透明化することで、意思決定の背景が共有され、チームの納得感が高まります。
メリット3:議論の時間を短縮し、施策の実行スピードを向上させる
優先順位付けの会議が「どれをやるか」の議論で毎回紛糾し、「会議が報告だけ」で終わってしまっては、貴重なリソースが浪費されます。 ICEスコアという「物差し」を導入することで、議論の時間を大幅に短縮し、チームは「どう実行するか」にリソースを集中できます。
「会議が報告だけ」になってしまう課題については、こちらの記事もご覧ください。

デメリット
デメリット1:スコアが主観的・恣意的になるリスク
最大の弱みは、スコアリングの「基準」が曖昧な場合、結局は主観的な点数の付け合いになってしまうことです。これは「業績管理の課題」として多くの企業が直面する問題でもあります。
「Impact 8点」の根拠が人によってバラバラでは、フレームワークが機能しません。この対策として、客観的な評価基準の具体例は後ほどご紹介します。
業績管理の課題については、こちらの記事もご覧ください。

デメリット2:「Ease(容易性)」の高い施策ばかりが優先される可能性
Ease(実行しやすさ)は乗算で効いてくるため、スコアが高い(簡単な)施策ばかりが優先される傾向があります。その結果、実行は難しいが中長期的にImpact(影響)が非常に大きい戦略的な施策が、後回しにされ続けるリスクがあります。
デメリット3:スコア計算が目的化してしまう
フレームワークを導入すること自体が目的化し、スコアを出すことに満足してしまうケースです。
これでは優先順位を決めただけで「施策が実行されない」状態に陥り、意味がありません。
「施策が実行されない」原因については、こちらの記事もご覧ください。

本来、優先順位付けは「事業を成長させる」という「目標達成の方法」の一つでしかありません。 スコアはあくまで意思決定の補助であり、最終的には「実行」と「成果」につなげなければ意味がありません。
目標達成の方法の全体像については、こちらの記事もご覧ください。
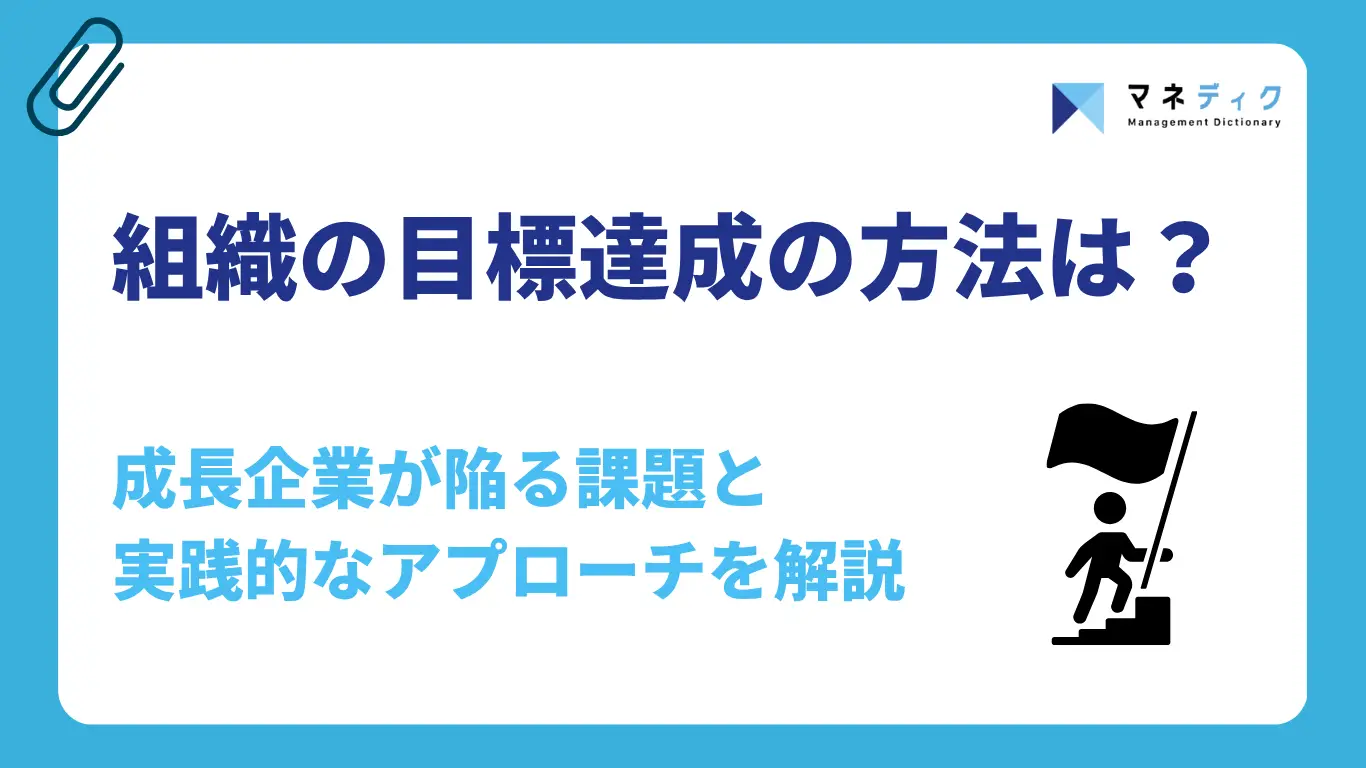
ICEスコアリングモデルの導入のステップ
では、実際にICEスコアリングモデルをチームに導入する手順を4つのステップで解説します。
ステップ1:評価する施策・アイデアをリストアップする
まず、Backlogやスプレッドシート、Notionなどに散らばっている施策やアイデアをすべて洗い出し、一元管理できるリストを作成しましょう。この時点では優劣をつけず、あらゆる施策をテーブルに並べることが重要です。
なぜ「すべて」洗い出す必要があるのでしょうか。
それは、比較対象が漏れていると、優先順位付けそのものの精度が著しく低下するためです。
「A案よりB案が優先」という判断ができても、もしリストに「C案」が漏れていれば、C案こそが最もインパクトのある施策だったかもしれません。評価の土台となる「施策リストの網羅性」が、客観的な意思決定の第一歩となります。
ステップ2:「I・C・E」の評価基準を定義する
次に、リストアップした施策を評価するための「物差し」を定義します。
このステップがICEスコアリング導入の成否を分ける、最も重要なプロセスです。
「Impactの10点とは何か」をチーム全員が同じ解釈をできるように言語化します。
なぜここが「最重要」なのでしょうか。
それは、この「物差し」が曖昧なままスコアリングを進めると、メリットで挙げた「感覚的な判断の排除」ができず、デメリットである「恣意的なスコアリング」に直結してしまうからです。
「Impact=8点」と付けた根拠が、Aさん(売上貢献)とBさん(顧客満足度)で異なっていては、比較の意味を成しません。チーム全員が納得する「共通言語」を作ることが、このステップのゴールです。
ステップ3:各項目を1〜10点でスコアリングする
定義した評価基準(物差し)に基づき、各施策のI・C・Eを点数化します。
ここでのコツは、可能な限り個人ではなくチームで行うことです。
特に「Ease(容易性)」は、PdMやマーケターだけで判断せず、実際に開発を行うエンジニアやデザイナーの意見(見積もり)が不可欠です。
スコアリングの途中で「基準が曖昧だ」と気づいたら、面倒でもステップ2に戻り、基準を再定義することが、後の手戻りを防ぐ最短ルートとなります。
ステップ4:スコアを計算し、優先順位を決定する
各施策のスコア(I × C × E)を計算し、リストをスコアの高い順に並べ替えます。
これにより、取り組むべき施策の優先順位が可視化されます。
ただし、このリストは絶対的なものではありません。
スコアはあくまで「議論のたたき台」です。例えば、デメリットで触れたように「Ease(容易性)」の高い施策(スコア高)ばかりが上位に来て、中長期的に重要な施策(スコア低)が下位に沈むことがあります。
リストを鵜呑みにせず、最終的には経営者や事業責任者が「戦略的なバランス(短期と中長期)」も加味して最終的な意思決定を行いましょう。
こうしたフレームワークは強力な「補助線」ですが、あくまでツールです。
最終的な意思決定を行い、マネジメントの最大の目的である「業績成長」 に導くためには、マネージャー自身の思考法が不可欠です。
添付の「目標必達マネージャーの育成ガイド」は、まさに「業績にコミット」できる人材の育成に役立つ資料です。この資料は、多くの企業が依存しがちな「コミットメント」という曖昧な言葉を、個人の精神論に頼るリスクから脱却させ 、「スピード」 、「各論(細部への徹底的な理解)」 、「執着(目標達成への知的な姿勢)」 という3つの具体的な行動基準として定義しています。
フレームワークを使いこなし、確実に成果を出す思考法について、ぜひこちらの資料をダウンロードして、参考にしてください。
【具体例】スコアが恣意的になるのを防ぐ「評価基準」の作り方
ICEスコアリングモデルが形骸化する最大の原因は「評価基準の曖昧さ」です。
ここでは、ペルソナの悩み(KGI連動、異種施策の比較)に基づき、客観的な評価基準の作り方を具体例で解説します。
また、KGIと連携させたICEスコアリング基準表もこちらからダウンロードいただけます。

1. Impact(影響度)は「KGI」と連動させる
Impactの点数を決める際は、「なんとなく影響がありそう」という感覚を排除しましょう。
特にスタートアップやベンチャーなどの成長企業であれば、事業フェーズごとのKGI(最重要指標)と連動した基準表を作成しましょう。
基準例:KGIが「MAU」から「解約率改善」に移行したフェーズの場合
- 10点: 既存顧客の解約率を[X]%直接改善する施策
- 7点: 新規リード獲得(MAU)に大きく貢献する施策
- 3点: 既存機能のUI改善など、間接的な満足度向上に繋がる施策
- 1点: KGIとの関連性が薄い施策
2. 異種施策は「共通のKGI」に換算して比較する
一例として「マーケ施策 vs 開発施策」を比較する場合も、ImpactとEaseを「事業部KGI(例:売上、利益)」という共通の物差しに換算します。
基準例:Impactを「四半期の売上貢献予測」で統一
- マーケ施策A(広告出稿):
予測売上 +1,000万円 → Impact: 10点 - 開発施策B(機能追加):
予測売上(アップセル)+500万円 → Impact: 5点
基準例:Easeを「総コスト」で統一
- マーケ施策A(広告費):
500万円 → Ease: 2点 - 開発施策B(開発工数):
200万円(人件費換算)→ Ease: 5点
このように基準を統一することで、施策A(スコア 10×Confidence×2)と施策B(スコア 5×Confidence×5)のROIを客観的に比較できます。
3. Confidence(確信度)は「根拠の強さ」で定義する
Confidence(確信度)は、客観的な根拠のレベルに応じて点数化します。
基準例
- 10点: 類似施策での成功実績(A/Bテスト結果)がある
- 7点: 複数名の明確な顧客インタビュー(定性)に基づいている
- 3点: データ分析(定量)に基づく仮説である
- 1点: 客観的な根拠はなく、チーム内のアイデア(感覚)である
上記はあくまで一例です。客観的でチームが納得する、より詳細な評価基準の作り方については、以下の記事で詳しく解説しています。
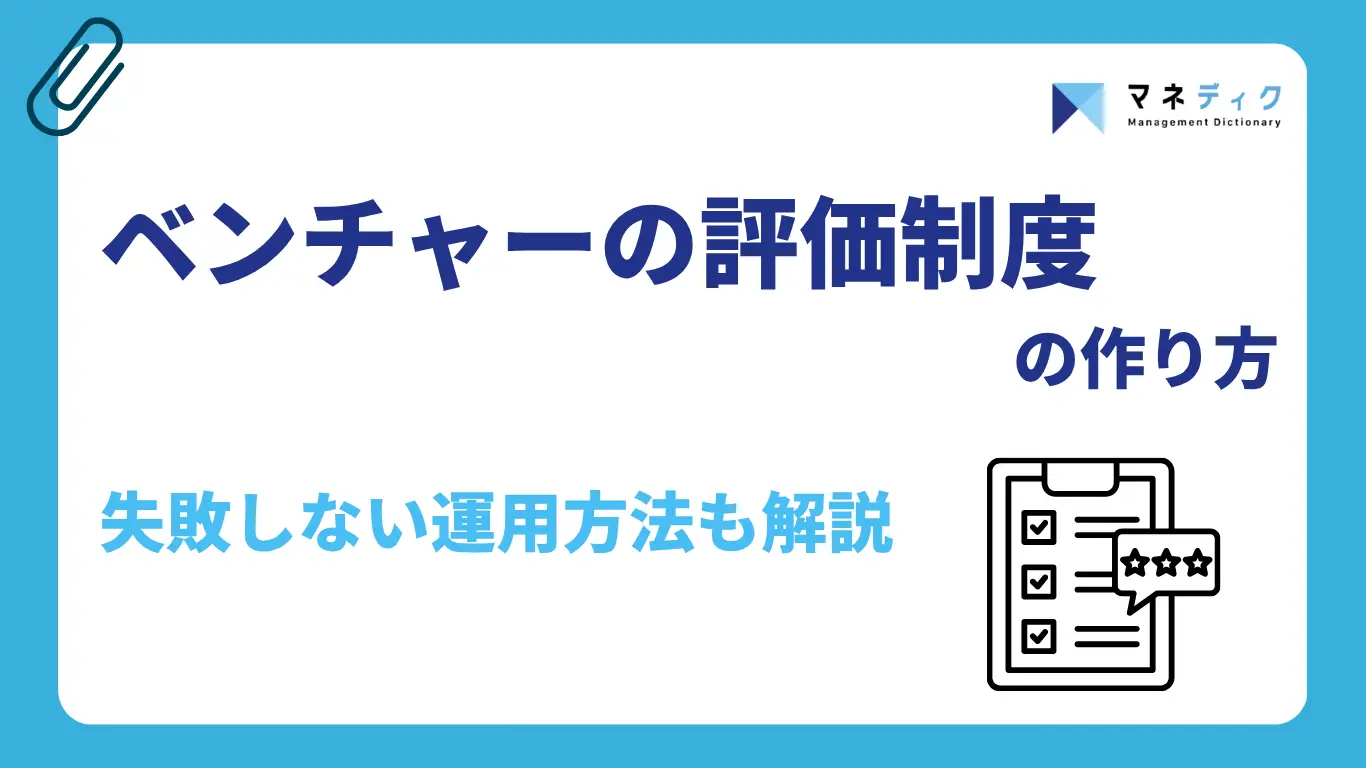
まとめ:ICEスコアリングモデルはチームの「共通言語」を作る第一歩
ICEスコアリングモデルは、施策の優先順位付けを客観的に行うための、シンプルかつ強力なフレームワークです。
しかし、私が多くの成長企業を支援する中で感じるのは、フレームワークの導入自体が目的化してはならない、ということです。
最も重要なのは、「評価基準の定義」です。あなたの組織が今どのフェーズにあり、何をKGIとして追っているのか。その「課題」を起点として基準を定義しなければ、スコアは主観的な数字の遊びに終わってしまいます。
以下の「目標必達マネージャーの育成ガイド」は、まさにこの「課題起点」で成果を出すための思考法を解説した資料です。
多くの組織が精神論で終わらせがちな「コミットメント」を、「スピード」「各論(細部への徹底的な理解)」「執着(知的な姿勢)」という3つの具体的な行動基準として定義しており、目標と現実の差を埋めるための「GAP起点の思考法」(GAPの特定、要因分解、打ち手立案) といった、目標必達のための具体的な方法論を解説しています。
感覚的な優先順位付けでリソースを無駄にし、チームが疲弊してしまう前に、まずはICEスコアリングモデルを参考に、あなたのチームだけの「共通言語」を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。その土台となる思考法や、それを文化にする方法 について、ぜひ本資料もダウンロードしてご覧ください。