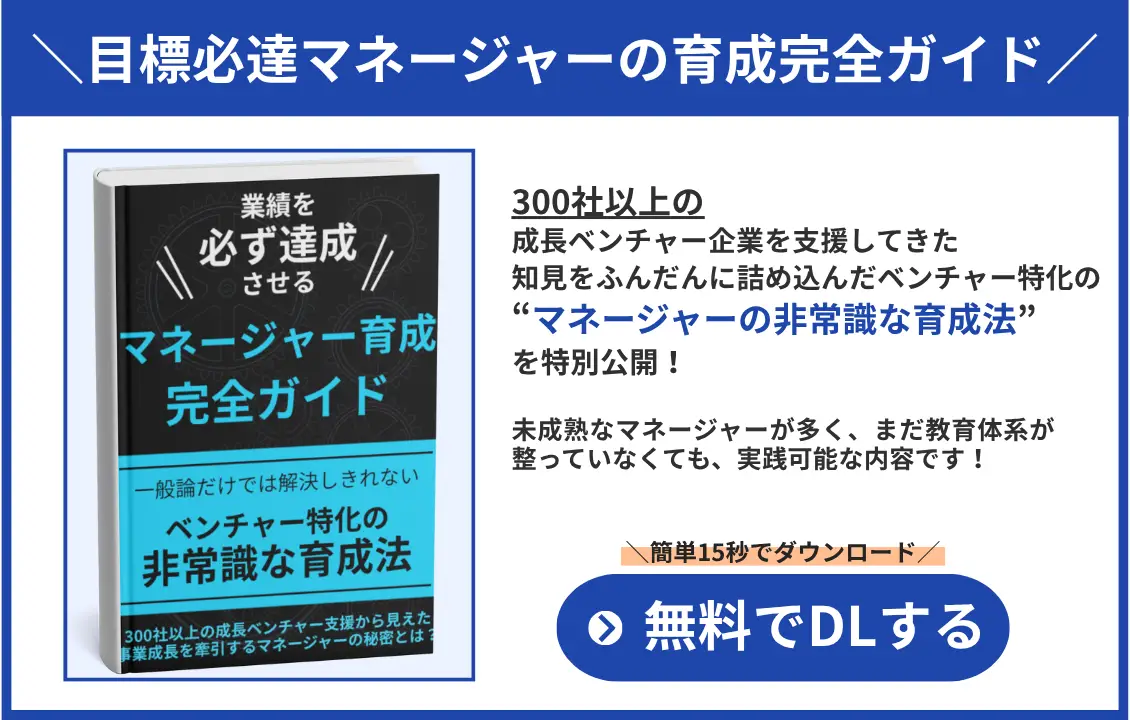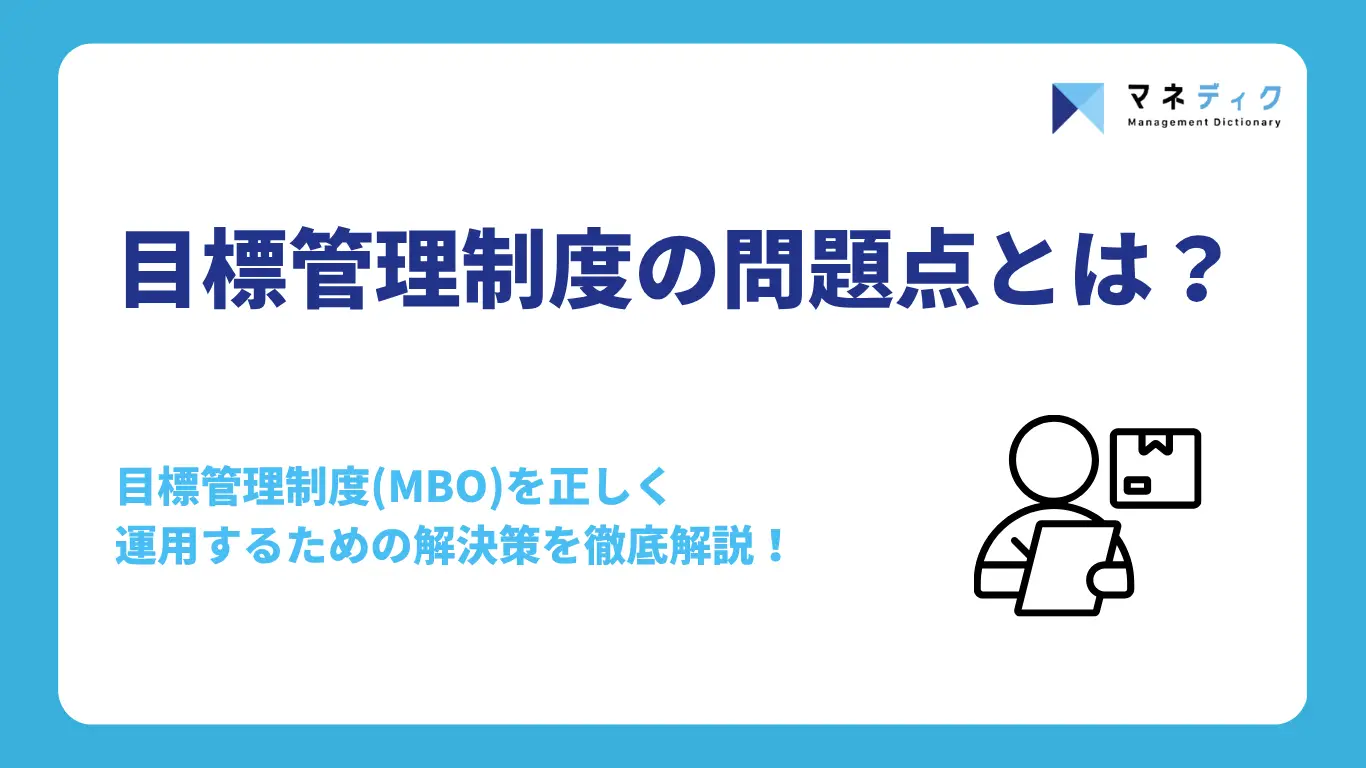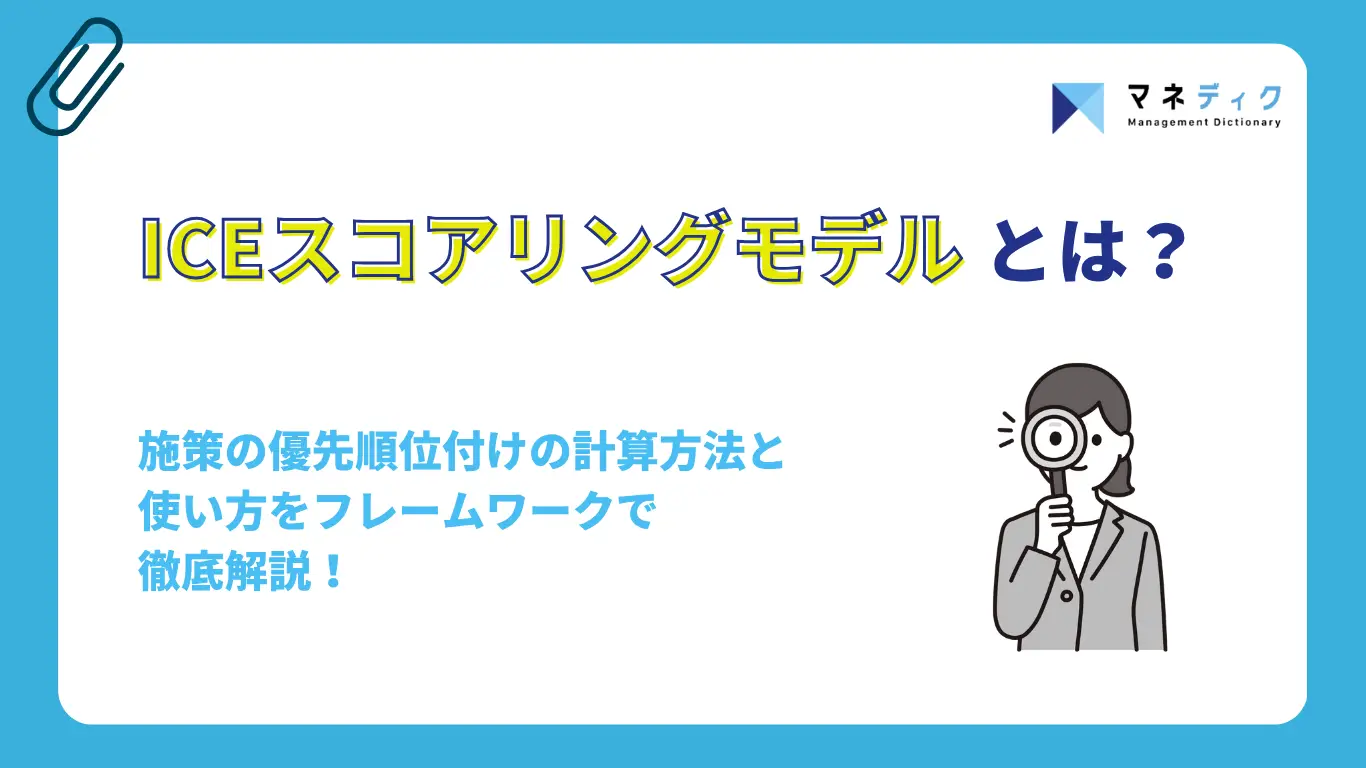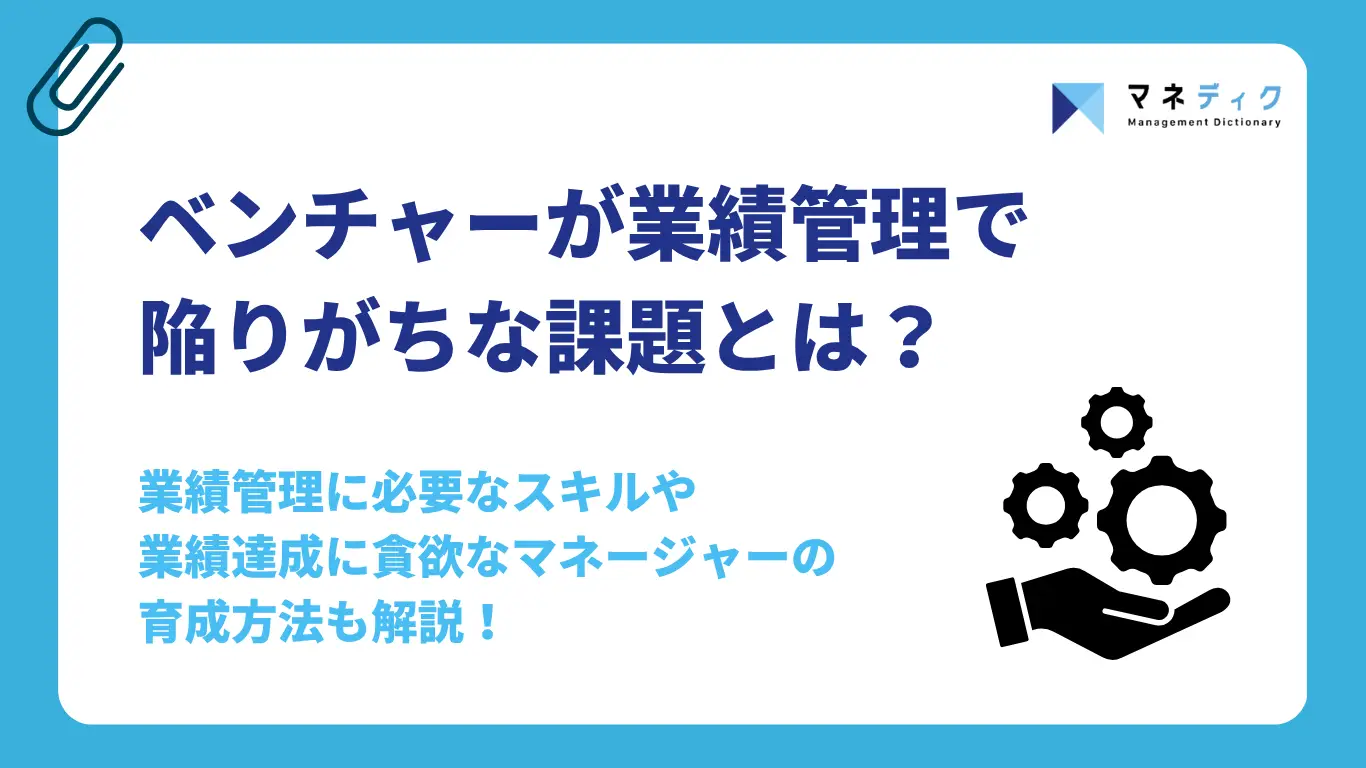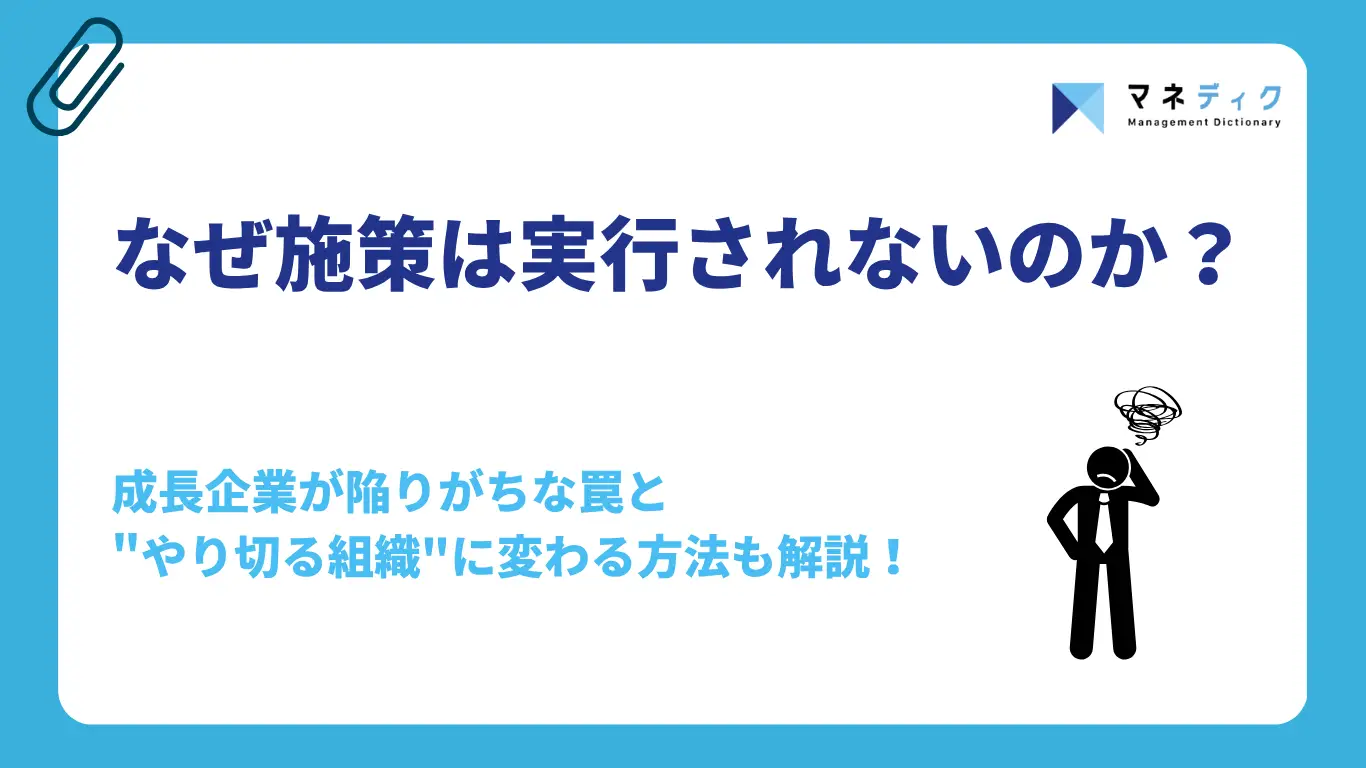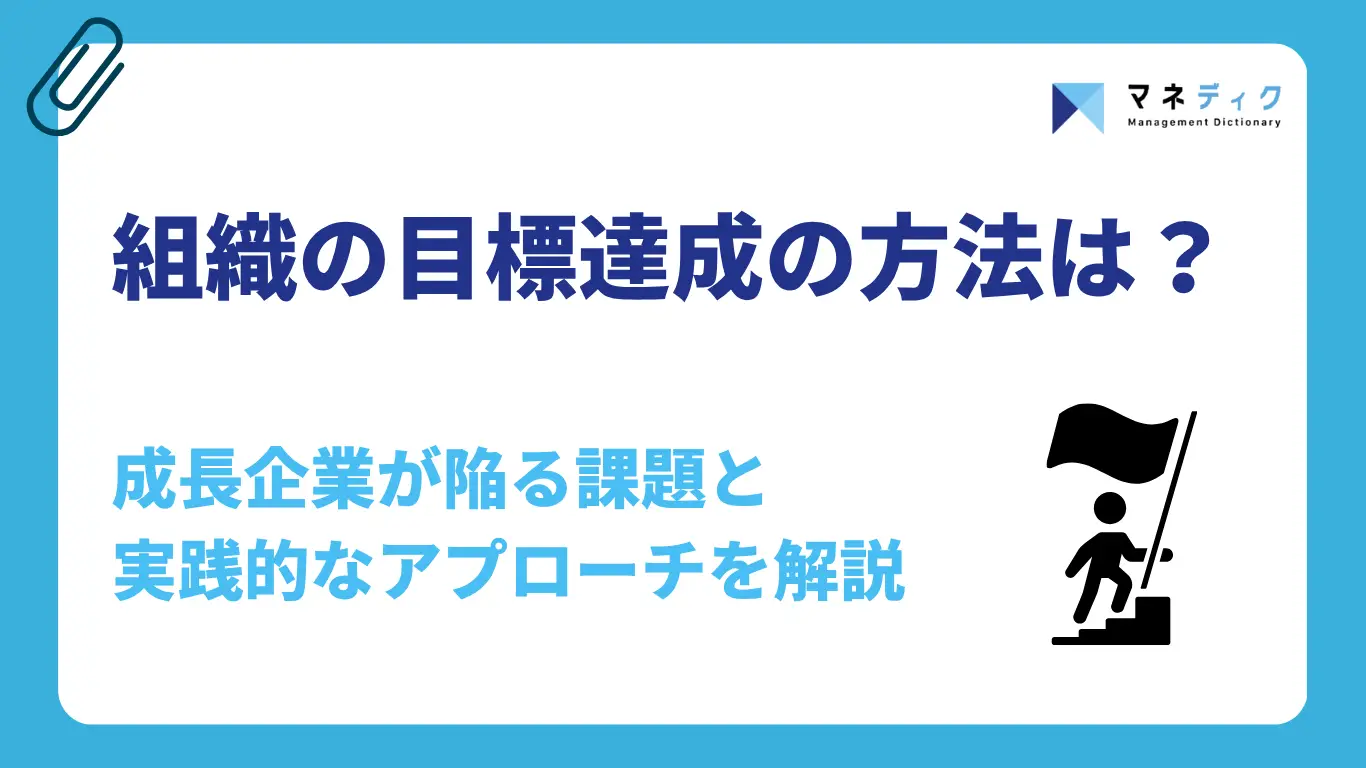なぜ「報告だけ」の会議がおこなわれるのか?事業成長に寄与する会議の設計法も解説
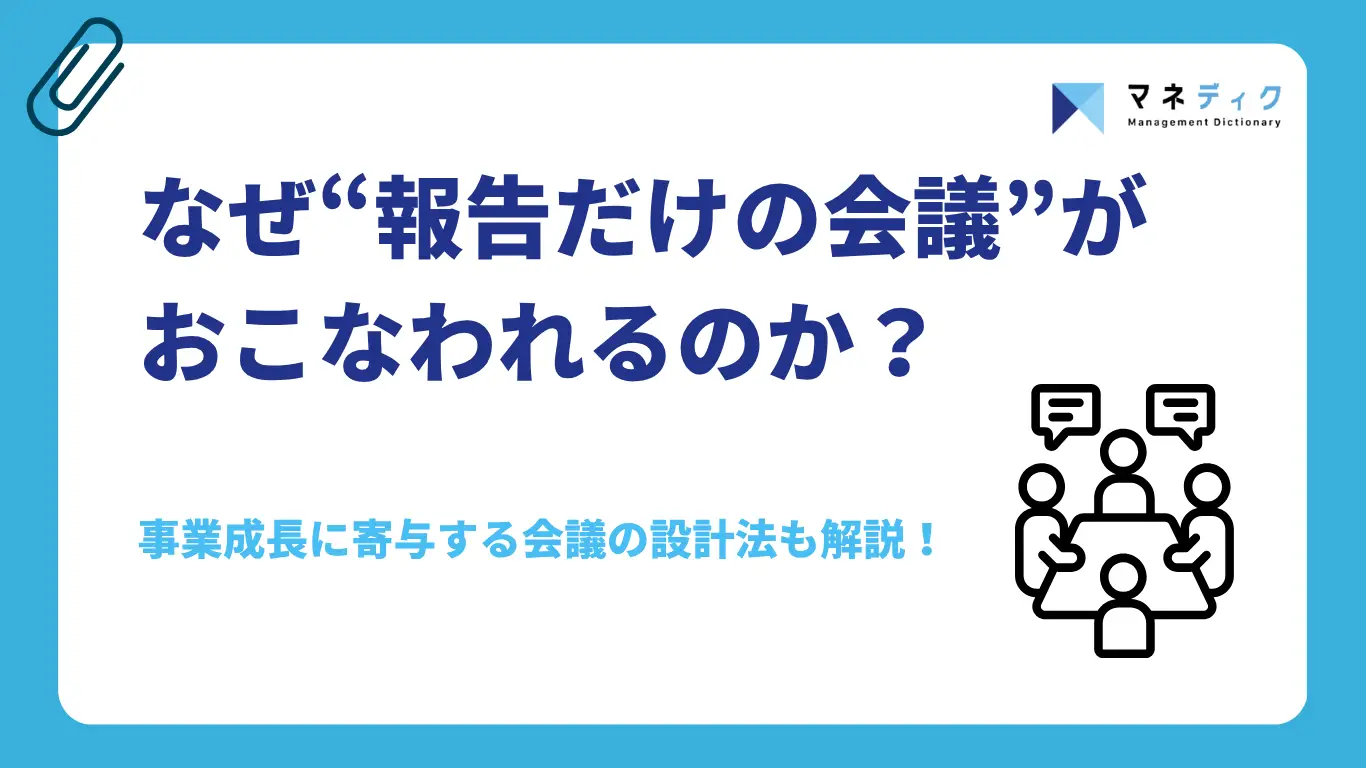
なぜ成長企業の会議は「報告だけ」になるのか?
多くの企業で「報告だけの会議」がなくならない理由は、業務の多忙さや準備不足といった表面的な要因で語られがちです。
しかし、特に急成長を遂げるベンチャー企業においては、より根深く、構造的な問題が潜んでいます。
以下で「報告だけ」の会議が横行する理由をそれぞれ詳細に解説していきます。
原因1:マネージャーの視座が「部門最適」に陥っている
「報告だけ」の会議になってしまう1つ目の原因は、マネージャーの視座が「部門最適」に陥っていることです。
組織が30名程度までの頃は、経営者が全社員を直接マネジメントできます。
しかし50名を超えると、部門長やマネージャーを介した「間接マネジメント」への移行が不可欠です。ここで最初の罠が生まれます。多くのマネージャーは、経営者から部門を任された際、自身の役割を「部門の代表者」だと誤解してしまうのです。
その結果、会議の場は「自分の部門の活動を経営者に報告し、承認を得る場」となり、視座は完全に「部門最適」に陥ります。
彼らは、他部門の課題や全社的な戦略について議論する当事者ではなく、自部門の利益を守る“報告者”に徹してしまいます。これこそが、マネディクが警鐘を鳴らす「セクショナリズム(部門間の壁)」の始まりです。
原因2:目標達成への「コミットメント」が低い
「報告だけ」の会議になってしまう2つ目の原因は、マネージャーの目標達成へのコミットメントが低いことです。
彼らは「業務を遂行すること(Doing)」と「目標を達成すること(Achieving)」を混同しています。会議で報告されるのは、あくまで「先週やったこと」という活動報告であり、「で、目標に対して今どういう状況で、どうやってGAPを埋めるのか?」という最も重要な問いへの回答ではありません。
これは、「時間」を基準に働くか、「アウトプット」を基準に働くかの違いです。アウトプット、すなわち「目標達成」にコミットしていれば、会議は自然と「目標とのGAPを埋めるための“議論の場”」になるはずなのです。
報告に終始している時点で、そのマネージャーは目標達成の当事者ではなく、単なる作業の実行者になってしまっている証拠です。
どうすればマネージャーの意識を「単なる実行者」から「目標達成の当事者」へと変革させ、会議を「目標とのGAPを埋める議論の場」にできるのでしょうか?
以下で紹介している「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、その答えとして、曖昧な「コミットメント」を精神論で終わらせないための具体的な方法論を解説しています。
資料内では、コミットメントを「スピード」「各論」「執着」という3つの行動レベルで再定義し、「目標とのGAP」に執着し続けるための思考法を詳しく紹介しています。
「報告だけの会議」を無くし、マネージャーのコミットメントを引き出す具体的なヒントを、ぜひ以下資料をダウンロードしてご確認ください。
原因3:議論するための「会議の型」が存在しない
「報告だけ」の会議になってしまう3つ目の原因は、議論するための「会議の型」が存在しないことです。
多くの成長企業では、会議の「目的」や「ルール」が明文化されておらず、属人的な運用に頼っています。その結果、最も簡単で楽な形式、つまり「各部門が順番に進捗を報告する」という形式に流れてしまいます。
本来、会議とは「意思決定」の場です。そのためには、
- 目的:この会議で「何を決めるのか」が明確か?
- アジェンダ:その意思決定に必要な「論点(Issue)」が洗い出されているか?
- ルール:報告は事前に済ませ、会議の場では「議論」に集中する、という規律が守られているか?
といった「会議の型」が必要です。
この「型」が存在しないままでは、どれだけ優秀な人材を集めても、会議は単なる情報共有の場に堕してしまいます。
「報告だけの会議」を放置する3つの経営リスク
「報告だけの会議」を放置することは、企業の事業成長を阻害する、深刻な経営リスクに直結します。
実際に、パーソル総合研究所の調査によれば、社内会議に unproductive(不生産的)な時間を少しでも感じることがあると回答した人は72.8% にものぼり、多くの企業で会議が生産性を阻害している実態が明らかになっています。
これは単なる時間の浪費に留まらず、以下のような経営的リスクを引き起こすのです。
リスク1:経営の意思決定スピードが鈍化する
1つ目のリスクは、経営の意思決定スピードが鈍化することです。
会議が報告の場になると、経営者には「順調です」という体裁の良い情報ばかりが上がってくるようになります。現場で起きているリアルな課題や、目標未達の予兆といったネガティブな情報は、報告の過程でフィルタリングされ、経営者の耳には届きません。
その結果、市場の変化への対応や、事業上の重要な問題解決が遅れ、経営の意思決定スピードは致命的に鈍化します。
リスク2:マネージャーが「ただ報告するだけの人」となり育たない
2つ目のリスクは、マネージャーが「ただ報告するだけの人」となり育たないことです。
人の成長は、困難な課題と向き合い、自ら考え、意思決定する修羅場から生まれます。会議が報告だけで終わるということは、マネージャーからこの最も重要な「成長の機会」を奪っていることに他なりません。
彼らは自ら課題を発見し、解決策を議論する能力を養うことなく、上司の指示を待つだけの「報告マシン」と化していきます。これでは、会社の未来を担う次世代の経営幹部は永遠に育ちません。
リスク3:「ダメな会社ほど会議が多い」文化が定着する
3つ目のリスクは、「ダメな会社ほど会議が多い」文化が定着することです。
「報告だけの会議」が常態化すると、組織全体に「結果を出すこと」よりも「会議でちゃんと報告すること」や「資料をきれいに作ること」が重要である、という歪んだメッセージが伝わります。
これは、「アウトプットよりもプロセスを評価する」という、成長を阻害する最悪の組織カルチャーです。
一度このような文化が定着すると、そこから抜け出すには多大なエネルギーが必要になります。
また、「報告だけの会議」が横行すると、当然ですが最終的に組織の業績達成にも悪影響が出ます。
以下の記事で、業績達成にコミットする組織の作り方も解説していますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。
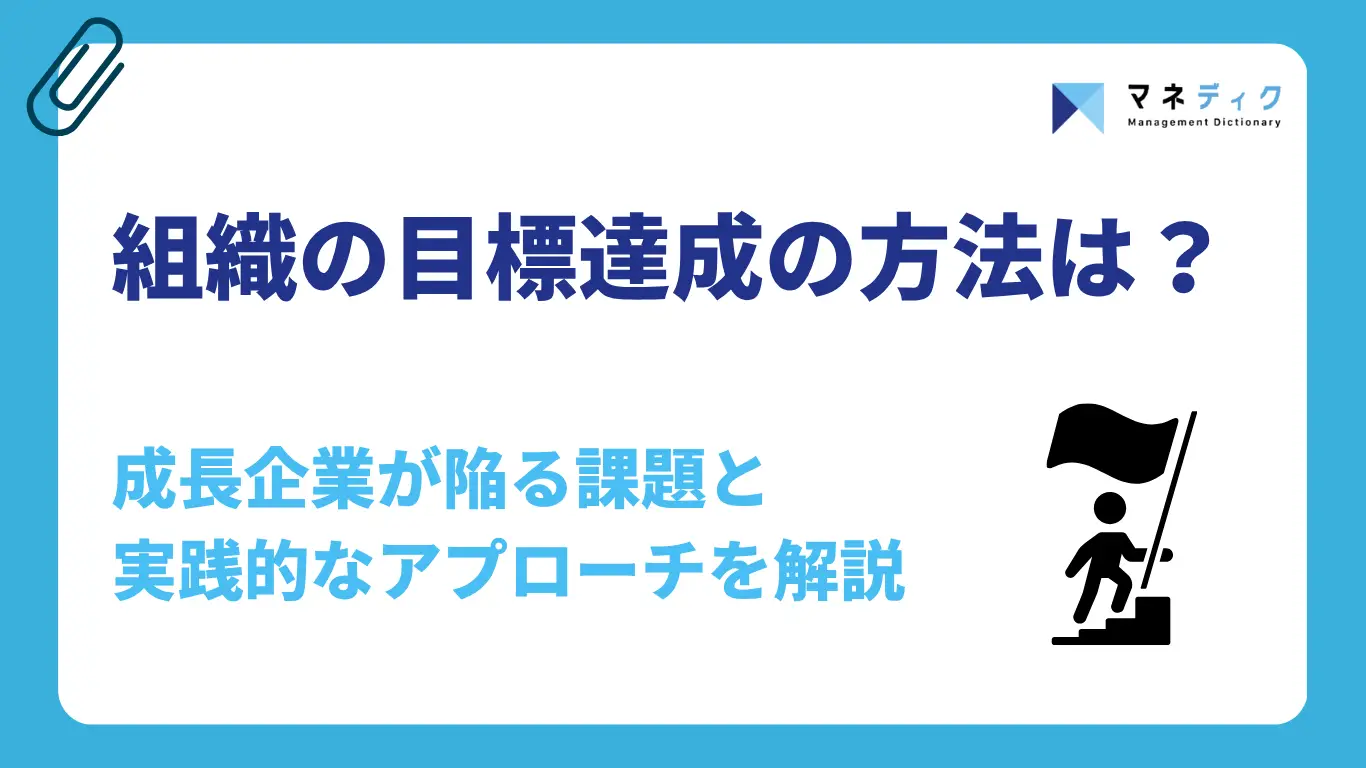
報告だけの会議を無くす「仕組み」と「会議の型」
この悪循環を断ち切るためには、精神論ではなく、明確な「仕組み」と「型」を導入することが不可欠です。
対策1:「報告・情報共有」は非同期(ツール)を徹底する
まず、経営者自身が「会議の場では、一切の報告を許さない」という断固たる決意を示す必要があります。
そして、報告や情報共有は、すべて「非同期」で行うことをルール化します。
日々の進捗や共有事項:Slackなどのチャットツール
プロジェクトのタスク管理:AsanaやTrelloなどのタスク管理ツール
KPIや業績の数値報告:ダッシュボードが見えるSaaS(マネディクSaaSなど)やスプレッドシート
これらのツールを活用し、「会議の前に、参加者全員が必要な情報をインプット済みである」状態を当たり前にするのです。会議の目的は、その情報を基に「議論し、意思決定すること」であると再定義することが重要です。
対策2:「論点(Issue)」から逆算したアジェンダを設計する
質の高い会議は、質の高いアジェンダから生まれます。
そして、良いアジェンダとは「報告事項のリスト」ではなく、「決めるべきこと(=論点)」から逆算して設計されたものです。
【ダメなアジェンダ例】
マーケティング部の進捗報告
営業部の進捗報告
開発部の進捗報告
【良いアジェンダ例】
目的:Q3の新規リード獲得目標達成に向けた、後半戦の戦術を決定する。
論点1:現状の施策では、目標に対し▲20%の未達見込み。このGAPの最大の要因は何か?
論点2:要因Aに対し、追加で打つべき施策はX案とY案のどちらか?
ゴール:会議終了時に、追加施策と担当者、期日が決まっている。
このように、「何を決めるための会議なのか」を明確にすることが、議論を活性化させる第一歩です。
対策3:ファシリテーターが「結論」にコミットする
会議のファシリテーター(多くの場合は経営者自身)は、タイムキーパーではなく、「会議を結論に導く責任者」です。
議論が本筋から逸れたら、即座に引き戻す。
意見が対立したら、判断軸を提示し、意思決定を促す。
時間内に結論が出なければ、「誰が」「いつまでに」「何を」決めるのかを明確にして会議を終える。
この「結論へのコミットメント」が、会議の生産性を決定づけます。
経営者が「報告だけの上司」を指導する具体的な方法
仕組みを導入しても、マネージャー自身の意識が変わらなければ、会議は再び形骸化します。
ここでは会議の場で、あるいは1on1で、マネージャーのスタンスを変革させるための具体的な指導法を紹介します。
指導法1:「その報告、So What?(だから何?)」正しい問いかけのニュアンス
マネージャーが長々と活動報告を始めたら、それを遮ってこう問いかけます。
しかし、その意図は相手を詰めることではありません。
「私は君を信頼している。だから、細かい活動報告は不要だ。それよりも、その報告から我々経営チームが受け取るべき“示唆”は何なのか、“議論すべき論点”は何なのかを、君の口から聞かせてほしい」というメッセージを伝えるのです。
【具体的な声のかけ方例】
「報告ありがとう。その数字の羅列から、我々は何を読み取るべきかな?」
「なるほど、それが事実(Fact)だとして、そこから言えるあなたの意見(Opinion)は?」
「その中で、事業に最もインパクトのある論点はどれか一つに絞ってくれる?」
この問いかけは、マネージャーに「報告者」から「分析者・提言者」への役割転換を促します。
指導法2:「で、目標とのGAPは?」業績コミットを求める指導法
進捗報告に対しては、必ず「目標」とセットで問いかけます。
経営者の関心事は、活動量ではなく、あくまで「目標達成」の一点にある、というスタンスを明確に示し続けるのです。
【具体的な声のかけ方例】
「活動内容は理解した。で、我々が必達すべき四半期目標に対して、今どの位置にいる?そのGAPの要因は何だと考えてる?」
「報告ありがとう。素晴らしい活動だ。ただ、その活動は目標達成にどう繋がっているのか、説明してくれるかな?」
「次の会議では、活動報告はいいから、『目標達成に向けた、今週の最重要アクション』だけを教えてほしい。」
この問いを繰り返すことで、マネージャーの意識は自然と「目標達成」にフォーカスされていきます。
指導法3:「君はどうしたい?」“報告者”から“意思決定者”へスタンスを変えさせる
問題の報告を受けた際、経営者がすぐに答えを出してはいけません。
それはマネージャーから思考の機会を奪う行為です。「この領域は君に任せている。だから、君がどうしたいのかを聞かせてほしい」とボールを返すのです。
【具体的な声のかけ方例】
「課題はよく分かった。選択肢はAとBがありそうだが、君はどちらを推奨する?その理由は?」
「もし君がこの会社の社長だったら、この状況でどういう決断を下す?」
「私を説得してみてくれ。なぜ、その打ち手に投資すべきなのか?」
これは、マネージャーに「権限」と「責任」をセットで委譲する、極めて重要な指導です。
この問いかけを通じて、彼らは単なる報告者から、自部門の未来を創る「意思決定者」へと変貌を遂げます。
ここまで経営者による指導法を解説してきましたが、これらを経営者一人が実践するだけで、全てのマネージャーの意識を変革させるのは容易ではありません。
多くの成長企業では、プレイングで高い成果を上げた優秀な人材がマネージャーに昇進しますが、彼らが過去の成功体験に固執し、「プレイヤー」意識のままでは、チームの成果を最大化できないのです。
我々マネディクの「業績コミットメント研修」は、単なる精神論ではなく、ベンチャー企業のマネージャーに求められる「マインドセット」「スキルセット」「アクション」の3つを徹底的に鍛え上げ、「チームの業績達成に執着し、やり抜く力」をインストールすることを目的としています。
2Dayのワークショップを通じて、目標達成への執着心と当事者意識を醸成し、業績GAPを埋める「思考と技術」をインストールします。
他社のリアルな失敗・成功事例を用いたケーススタディと、自社の行動基準となるスキルマップ作成により、一過性の研修で終わらせない仕組みを提供します。
「マネージャーの目標意欲が低い」「報告の解像度が粗く、目標とのGAPを埋める施策も考えられていない」こうした悩みを本気で解決したい経営者の方は、ぜひ一度、以下の資料をダウンロードして具体的な研修内容をご確認ください。
「報告だけの会議」に関するよくある質問
Q. 結局、情報共有の会議も必要ではないですか?
A. 必要ですが、「目的」を明確に分けるべきです。
情報“共有”が目的なら、それは非同期のツールで行うべきです。
時間を合わせて集まる会議は、その共有された情報を基に“議論”し“意思決定”するために行う、という原則を徹底することが重要です。
Q. 上司(経営者)自身が報告を求めてしまっている場合は?
A. まずは経営者自身が変わる必要があります。
「マイクロマネジメント」や「マイクロレポーティング」を求めず、マネージャーを信頼し、「結果(アウトプット)」で評価するスタンスに切り替えましょう。
経営者が求めるものが変われば、マネージャーの動きも変わります。
Q. 「ただの報告会」になっているチームミーティングはどうすれば?
A. チームミーティングの目的を再定義してください。
それは「課題を解決する場」なのか、「新しいアイデアを出す場」なのか、「次のアクションを決める場」なのか。目的が明確になれば、アジェンダも変わり、単なる報告会ではなくなります。