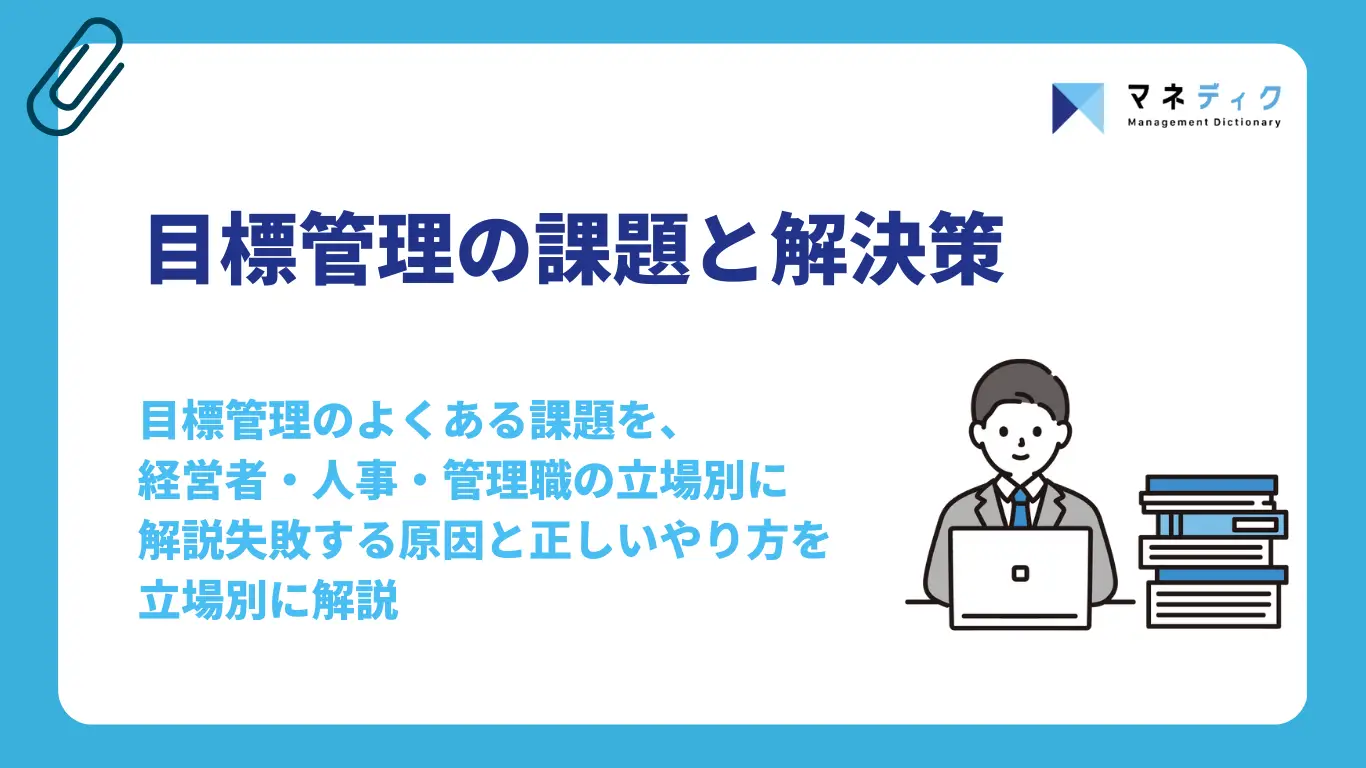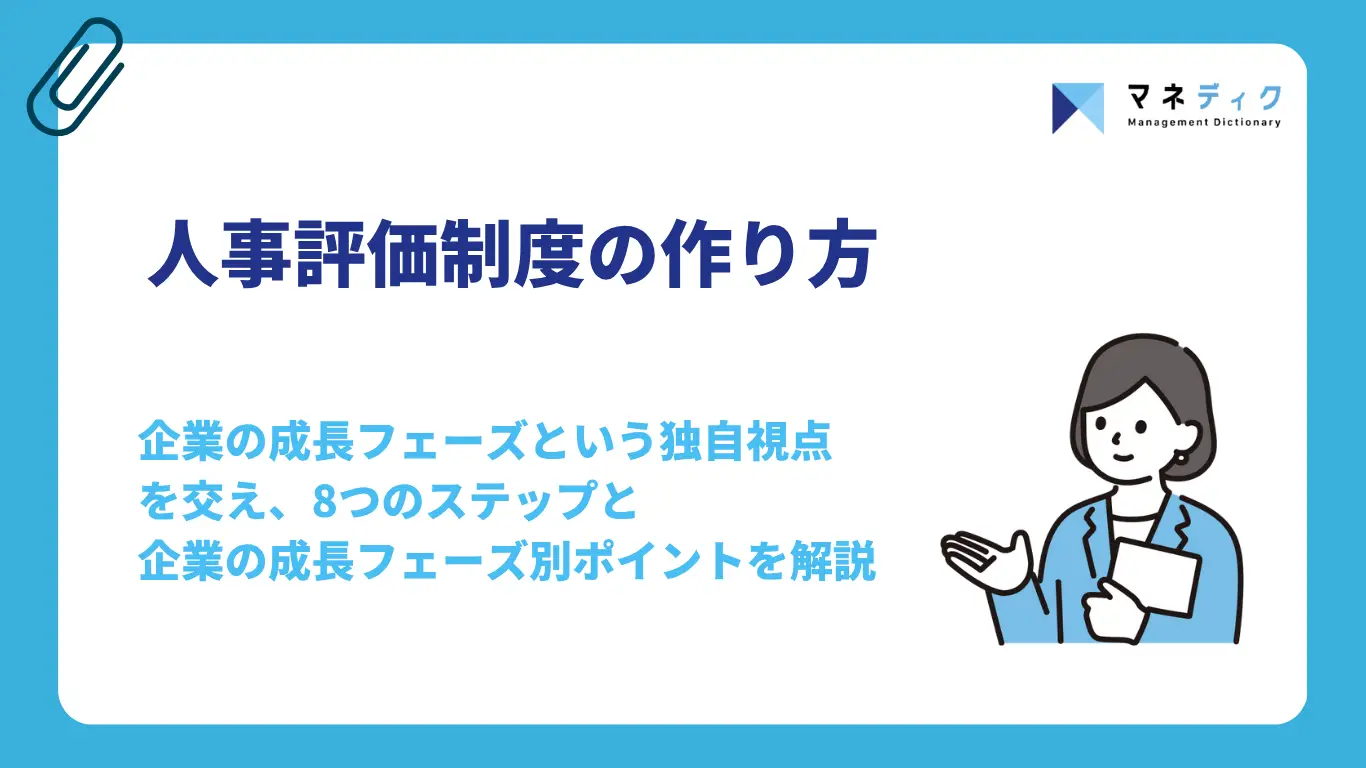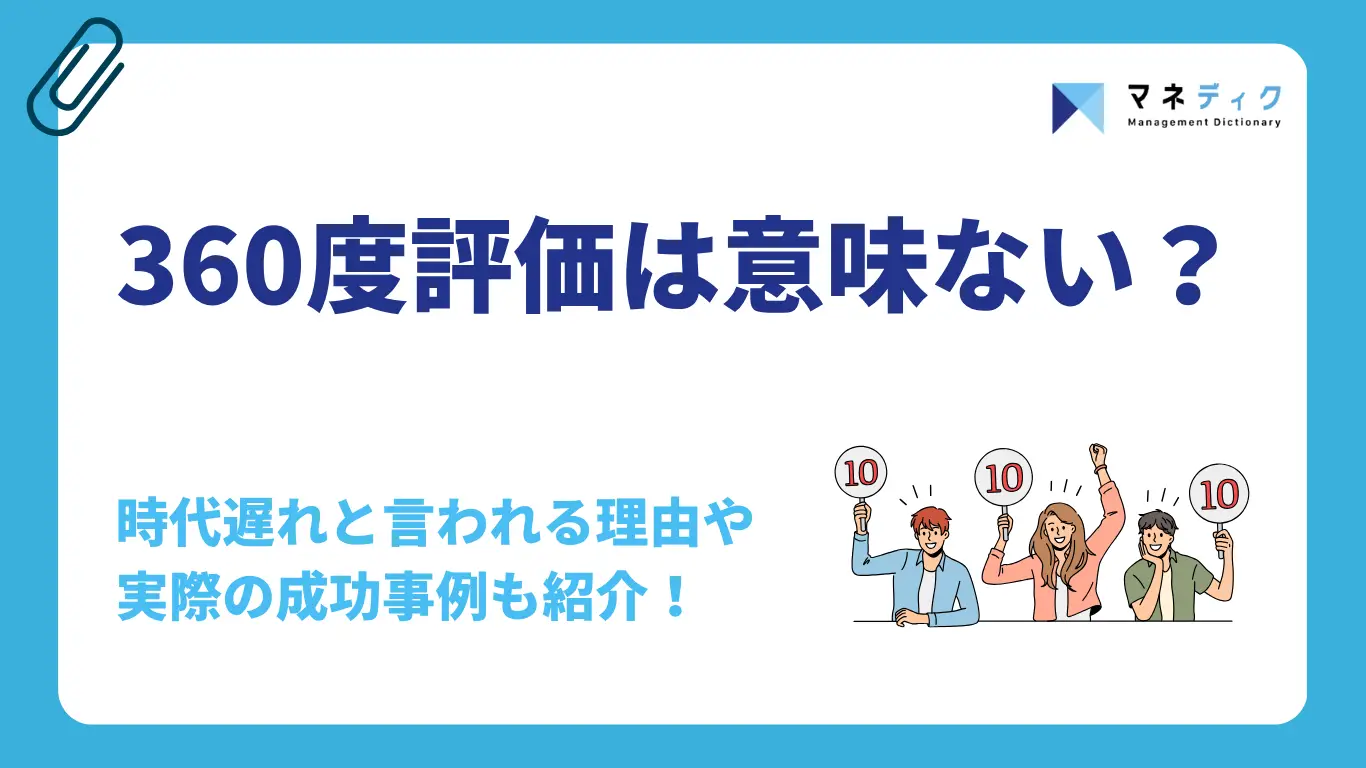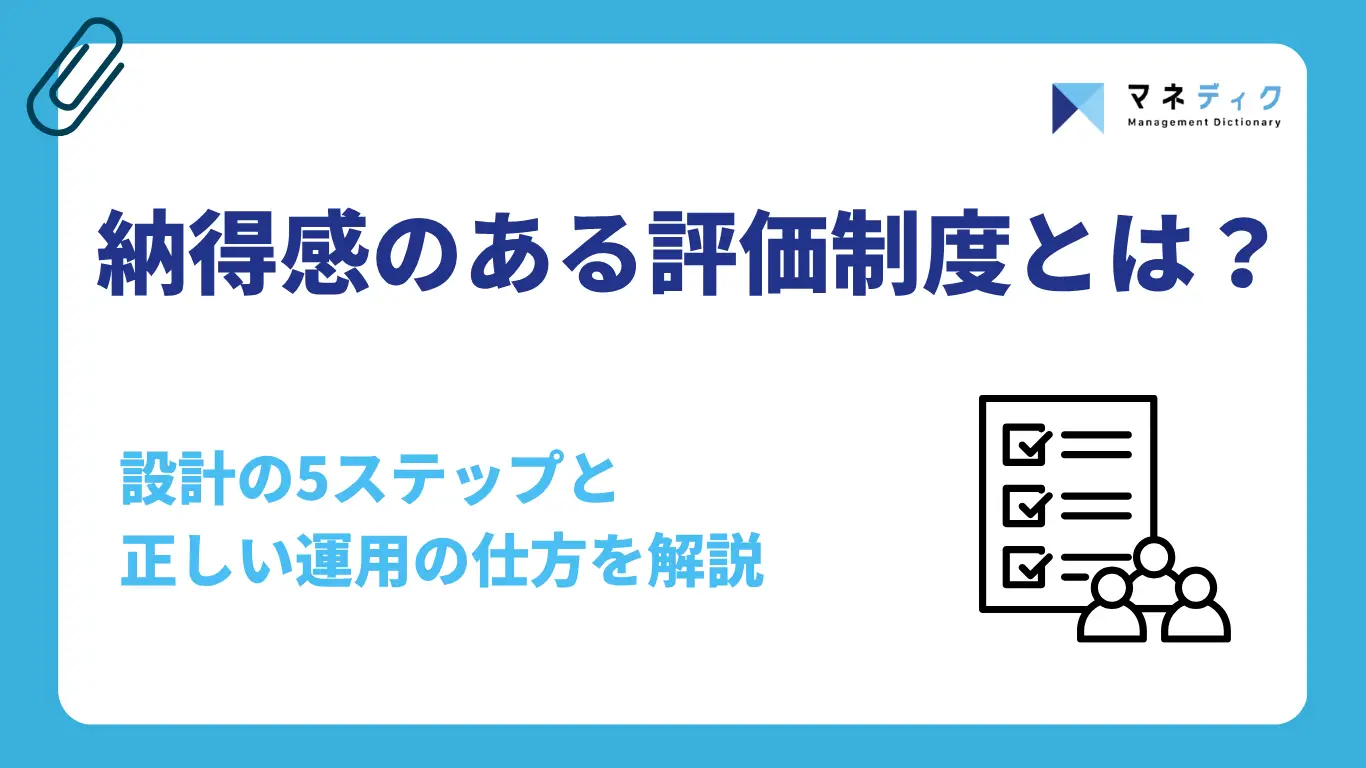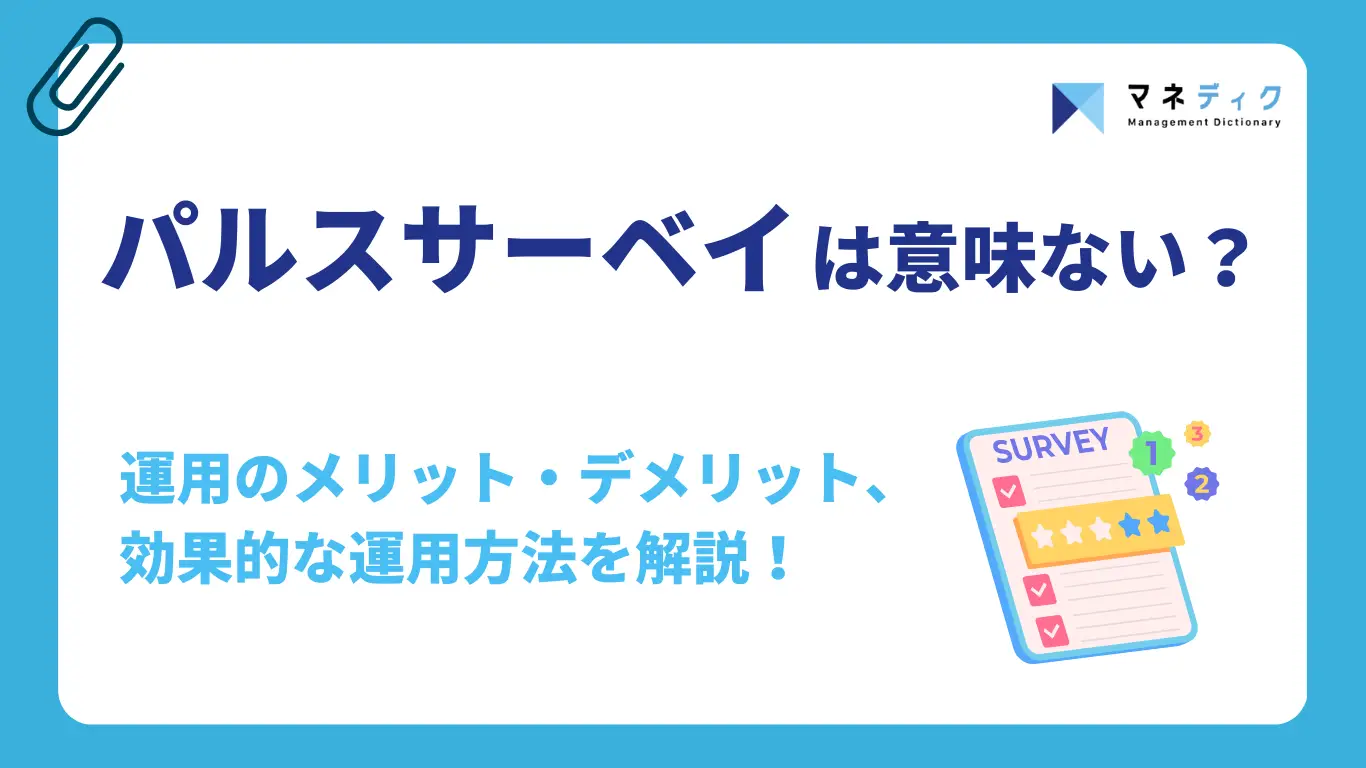ベンチャーでの評価制度の作り方|失敗しない運用方法も解説
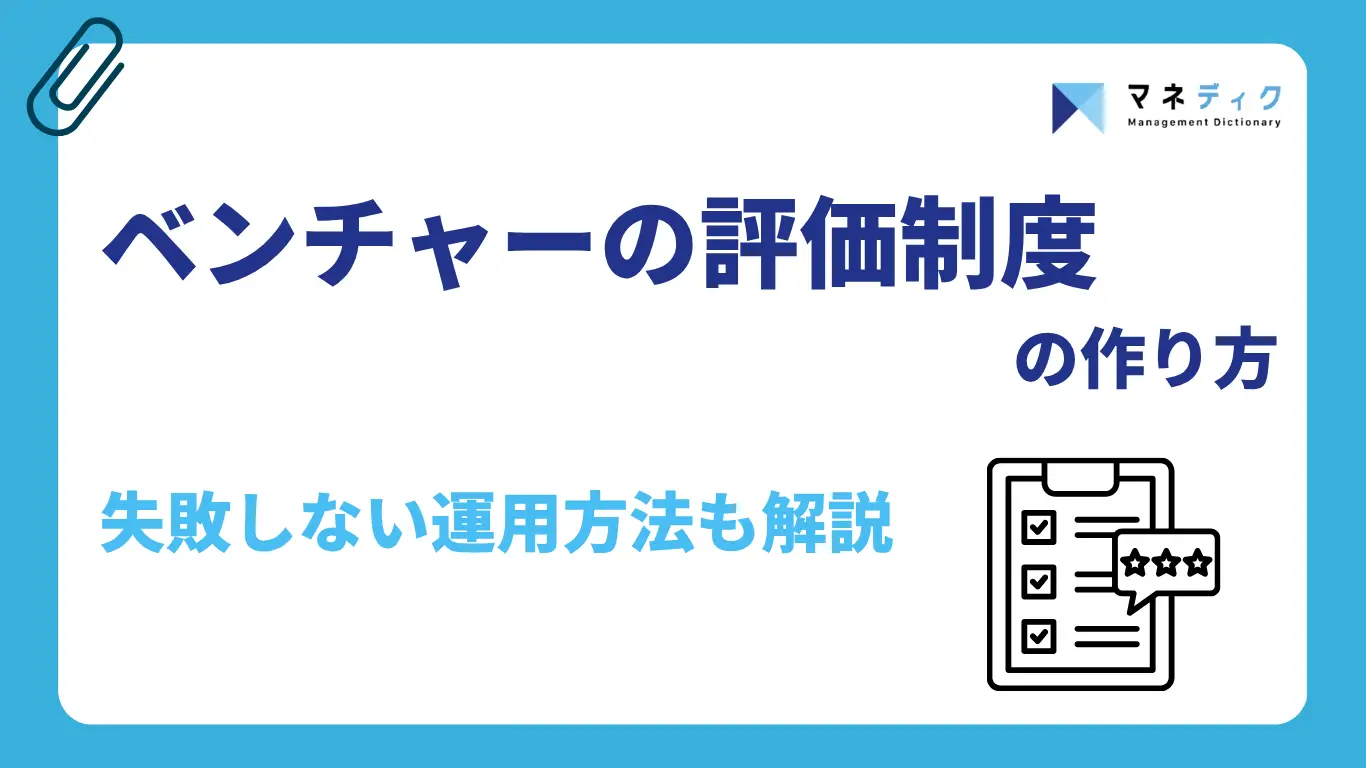
なぜ、ベンチャーの評価制度は失敗しやすいのか?
多くの経営者が「社員の公平性のため」と意気込んで評価制度を導入します。しかし、その多くが形骸化し、むしろ社員の不満の火種となってしまうのはなぜでしょうか。
それは、ベンチャーという組織が持つ特有の性質と、制度との間に生じる「ズレ」が原因です。
以下では、ベンチャーの評価制度の導入が失敗してしまう理由を3つ解説していきます。
理由1:目標が頻繁に変わる事業環境
ベンチャーの最大の武器は、市場の変化に迅速に対応するスピードです。
事業のピボットや方針転換は日常茶飯事で、半期前に立てた目標が3ヶ月後には全く意味のないものになっていることも珍しくありません。
そんな状況で、期初に設定した目標の達成度だけで評価を下せばどうなるでしょうか。
「途中からやることが変わったのに、当初の目標で評価されるのは不当だ」という不満が生まれるのは当然です。変化を恐れず挑戦すべきベンチャーで、目標の変更を拒むような人材を生み出しかねません。
成長ベンチャーでは、すべてを評価制度通りに評価することを目的に評価制度を完璧に作り込むのではなく、ある程度「あそび」をもたせた評価設計にすることが重要です。
理由2:役割を超えた貢献を評価しきれない
「営業」という肩書でも、事業のためにマーケティングを手伝い、部署間に落ちているボールを率先して拾う。そんな役割を超えて貢献してくれる人材こそ、ベンチャーにとって最も貴重な存在です。
しかし、多くの評価制度は職務や役割に基づいて設計されています。
制度通りに評価すれば、与えられた役割だけをこなした社員の方が評価されやすくなり、全体最適のために動いたキーマンの貢献は見過ごされがちです。これでは、本当に会社を支えている人材の心が離れていってしまうのも無理はありません。
1つ目の理由の話とも通ずる部分がありますが、事業成長のために役割の壁を越えて主体的に取り組んでくれるキーマンこそ、評価制度通りに評価するのではなく、全社的な貢献も加味したうえで柔軟に評価する必要があります。
理由3:制度の形骸化と不信感の増大
事業の実態と評価制度が乖離していくと、社員は制度そのものを信頼しなくなります。
評価面談は「評価期間だけ取り繕う場」となり、マネージャーは「制度だから仕方なくやる」という意識で評価を下すようになります。
こうして制度は完全に形骸化し、経営陣が伝えたかったメッセージやビジョンは誰にも届かなくなります。
残るのは、評価に対する不信感と、コミュニケーションが断絶された組織だけです。
ベンチャーでの評価制度の目的
成長ベンチャー企業では、どのような評価制度を目指すべきなのでしょうか。
重要なのは、評価制度を「社員をランク付けする査定ツール」ではなく、「組織と個人の成長を加速させるもの」として捉え直すことです。
完璧な評価制度を目指すのではなく、社員一人ひとりの「納得感」をいかに醸成するかが重要です。
以下で、成長ベンチャーで正しく機能する評価制度の目的を解説していきます。
目的1:ビジョンと個人の成長を接続する
1つ目の目的は「ビジョンと個人の成長を接続する」ことです。
評価制度は、会社のビジョンやミッションと、社員個人の日々の業務、そして成長を結びつけるための強力なコミュニケーションツールです。
「会社が目指すビジョン」と「今いる自分の立ち位置」を評価という場を通じてすり合わせることで、社員は自分の仕事の意味を理解し、日々の業務に高いモチベーションで臨むことができます。
目的2:コミュニケーションを活性化させる
2つ目の目的は「コミュニケーションを活性化させる」ことです。
評価制度の運用プロセス、特に1on1などの面談は、上司と部下が本音で対話するための絶好の機会です。
評価者が一方的に結果を伝えるのではなく、期間中の貢献への感謝や、今後の成長への期待を具体的にフィードバックする。この対話を通じて信頼関係を築き、組織の血流を良くしていくことこそが、評価制度がもたらす真の価値と言えるでしょう。
目的3:適切な人材配置と育成に繋げる
3つ目の目的は「適切な人材配置と育成に繋げる」ことです。
評価を通じて得られる「個々の強みや課題」といったデータは、感覚的な人員配置から脱却し、戦略的な人材育成や配置を行うための貴重な情報資産となります。
誰を次世代のリーダーとして抜擢するのか、どの部署にどんなスキルを持つ人材を投入すべきか。客観的なデータに基づいた判断が、組織の成長をさらに加速させます。
失敗しないベンチャーの評価制度の作り方
ここからは、実際に評価制度を構築するための具体的な3つのステップを解説します。
「何から手をつければいいか分からない」という方も、この手順に沿って進めることで、自社に合った制度の土台を築くことができるはずです。
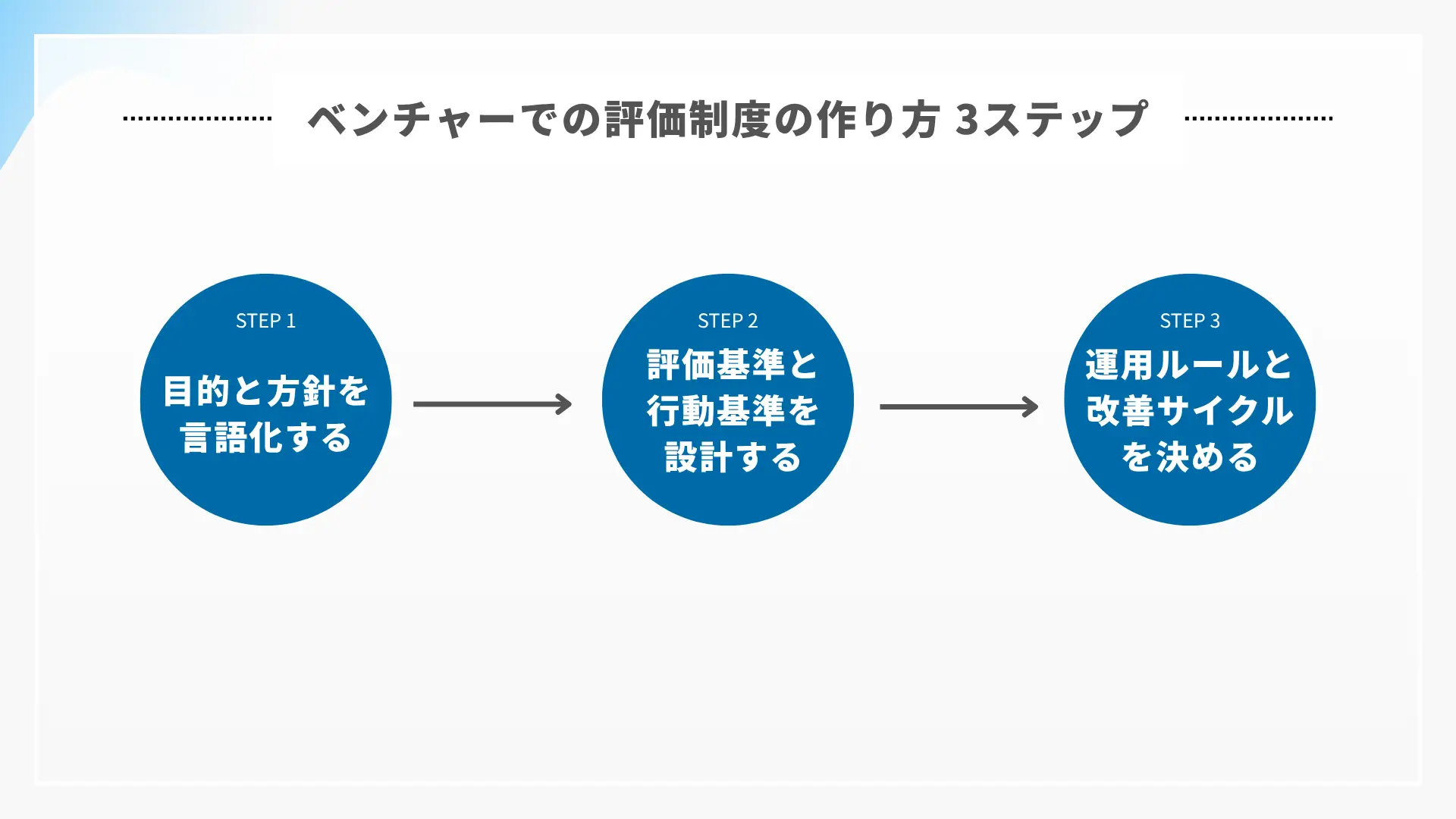
Step1:目的と方針を言語化する
まず最初に、「何のために評価制度を導入するのか」「評価を通じて社員にどうなってほしいのか」という目的と方針を経営陣が徹底的に議論し、言語化してください。
「ビジョン達成に貢献する人材を評価したい」「挑戦を奨励する文化を作りたい」など、ここがブレると、その後の評価項目や基準も全て的外れなものになってしまいます。
これは、会社の未来を決める重要な経営判断です。
Step2:評価項目と行動基準を設計する
目的が固まったら、それを体現するための評価項目と行動基準を設計します。OKR(目標と主要な成果)やコンピテンシー(行動特性)評価などが代表的な手法ですが、重要なのは手法の選択そのものではありません。
自社の目的やバリューに沿って、「何をすれば評価されるのか」を具体的に定義することです。
このプロセスには、ぜひ現場のマネージャーも巻き込んでください。トップダウンで決められた基準を押し付けるだけでは、運用段階で必ず形骸化します。
マネージャーたちが「この基準なら、部下の納得感を得られる」と感じられるか。彼らを巻き込み、共に作り上げるプロセスそのものが、制度の定着に不可欠です。
Step3:運用ルールと改善サイクルを決める
評価制度は「作って終わり」ではありません。むしろ、運用を開始してからが本番です。
評価期間、フィードバックの方法、評価者(マネージャー)間の目線合わせ(キャリブレーション)の会議など、具体的な運用ルールを定めます。
そして最も重要なのが、「この制度は未完成である」という前提に立つことです。
事業の変化に合わせて、評価制度も常にPDCAを回し、改善し続ける。この姿勢こそが、ベンチャーにおける評価制度運用の生命線です。
評価制度の種類とベンチャー企業での導入例
ここでは、ベンチャー企業でよく採用される代表的な評価制度の種類と、その運用事例をご紹介します。他社の事例を知ることで、自社での具体的な運用イメージを膨らませてください。
OKR:目標の透明性と俊敏性を高める事例
OKR(Objectives and Key Results)は、会社全体の高い目標(O)と、それを達成するための具体的な指標(KR)を全社で共有するフレームワークです。
四半期ごとなど短いサイクルで見直すため、ベンチャーの速い事業スピードに対応しやすいのが特徴です。
全社員が会社の目標と自分の業務の繋がりを意識できるため、組織の一体感を醸成する効果も期待できます。
360度評価:多面的なフィードバックで成長を促す事例
上司だけでなく、同僚や部下など、複数の視点からフィードバックを得るのが360度評価です。
上司からは見えにくい「チームへの貢献」や「リーダーシップ」などを可視化できるため、個人の気づきと成長を促す効果があります。
ただし、人間関係に配慮した慎重な運用が求められるため、導入には十分な準備が必要です。
360度評価に関しては、以下の記事にて詳しく解説をしているので、ご興味ある方は以下からご覧ください。

ノーレイティング:リアルタイムなフィードバックを重視する事例
S、A、Bといったランク付け(レイティング)を廃止し、リアルタイムなフィードバックと対話を重視する考え方です。
期末の評価に時間を費やすよりも、1on1などを通じて継続的に目標設定とフィードバックを繰り返すことで、社員の成長をスピーディに支援します。
変化の激しいベンチャーにおいて、最も実態に即した手法の一つと言えるかもしれません。
評価制度の構築・運用をさらに加速させるには
ここまで、自社で評価制度を構築・運用するための考え方とステップを解説してきました。
しかし、リソースの限られるベンチャー企業において、経営者が本来注力すべき事業から離れ、制度設計に多くの時間を費やすのは得策ではないかもしれません。
マネディクが提供する成長ベンチャー向け組織開発支援
我々マネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャーをご支援し、事業が成長するためのカルチャー作り・組織開発のお手伝いしてきました。
マネディクでは単に制度のテンプレートを提供するのではなく、各社様のビジョンや事業フェーズ、組織課題に徹底的に向き合います。ベンチャー企業は変化のスピードも速く、また会社ごとに目指す方向も大切にしたい価値観もまるで違うからです。
そして、経営陣やマネージャーの皆様と共に、本当に機能する「納得感のある評価制度」を構築し、その運用・定着までを力強くサポートします。
「自社の状況や目指す方向性に合わせて評価制度を作りたいが、中々進める時間が取れない」「自社の状況に合わせた最適な評価制度のイメージが湧かない」といった経営者の方はぜひ一度、マネディクのサービス資料をご覧ください。
▼無料ダウンロードはこちら

ベンチャーの評価制度に関するよくある質問
最後に、ベンチャー企業の経営者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q. 評価制度はいつ導入すべき?
A. 社長の目が全社員に行き届かなくなったと感じた時が、一つの目安です。
一般的には、従業員が30名〜50名を超えたあたりで検討を始める企業が多いです。
Q. 評価者の育成はどうすれば?
A. 評価の納得感を左右するのは、評価者であるマネージャーのスキルです。
評価者研修の実施はもちろん、マネージャー同士で評価基準の目線合わせを行う「キャリブレーション会議」を定期的に開催することが極めて重要です。
Q. 給与との連動は必須?
A. 必ずしも必須ではありません。
評価は「成長支援」、昇給・賞与は「成果配分」と目的を切り分けて運用する企業も増えています。連動させる場合は、そのロジックを社員に明確に説明できることが大前提です。
Q. 評価への不満が出た時の対処法は?
A. まずは、相手の意見を真摯に傾聴することが第一です。
その上で、評価の根拠となった事実と、会社の評価方針を丁寧に説明します。そして、その不満の声を「制度を改善するための貴重なフィードバック」と捉え、次の改善サイクルに活かす姿勢が大切です。
Q. 副業している社員の評価はどうする?
A. 勤務時間ではなく、本業における成果や貢献度(アウトプット)を評価の軸とすることが基本です。
副業で得たスキルが本業にどう活かされているか、といった視点も加味できると、より良い関係性を築けるでしょう。