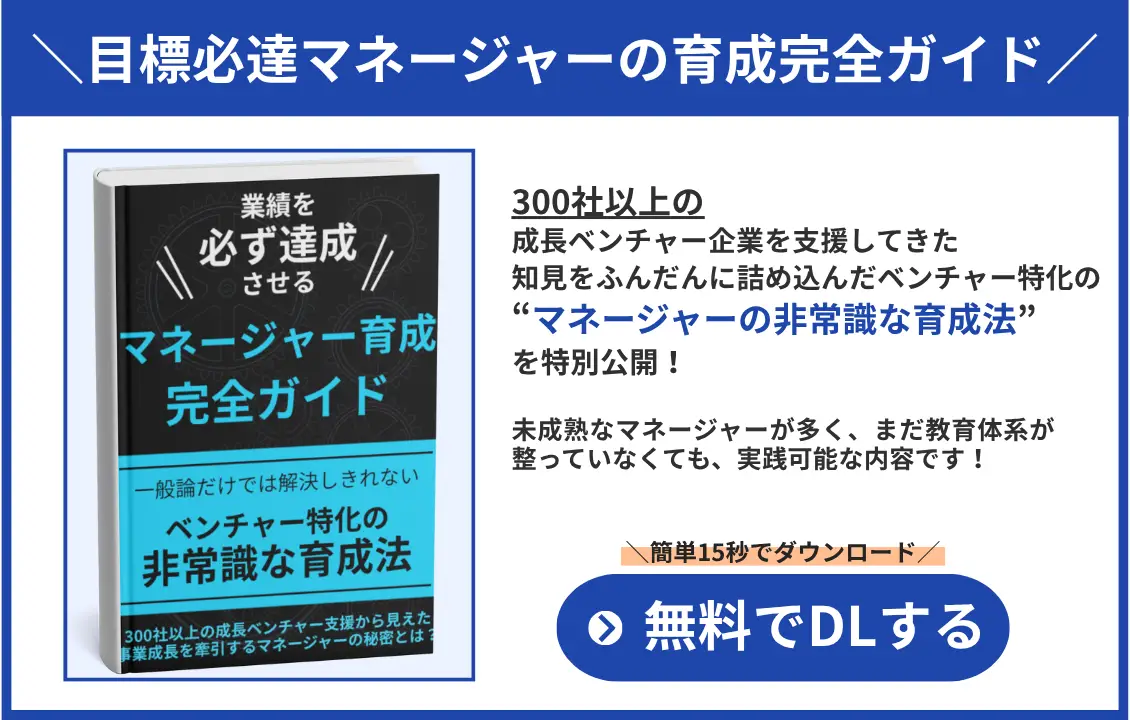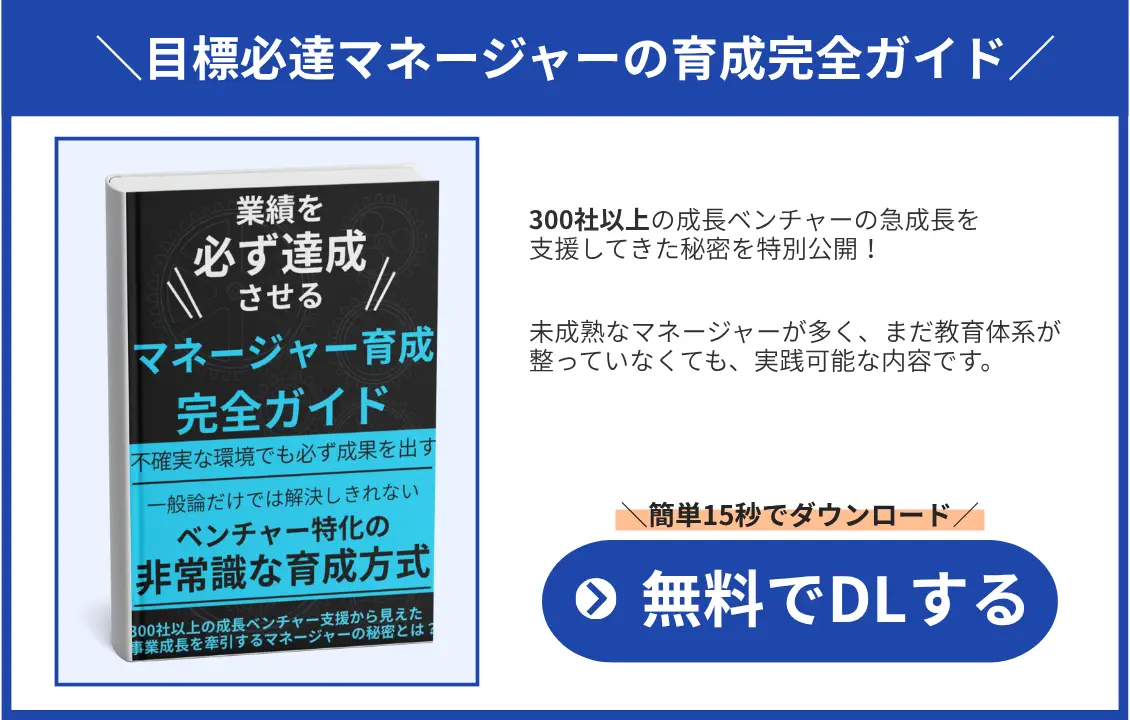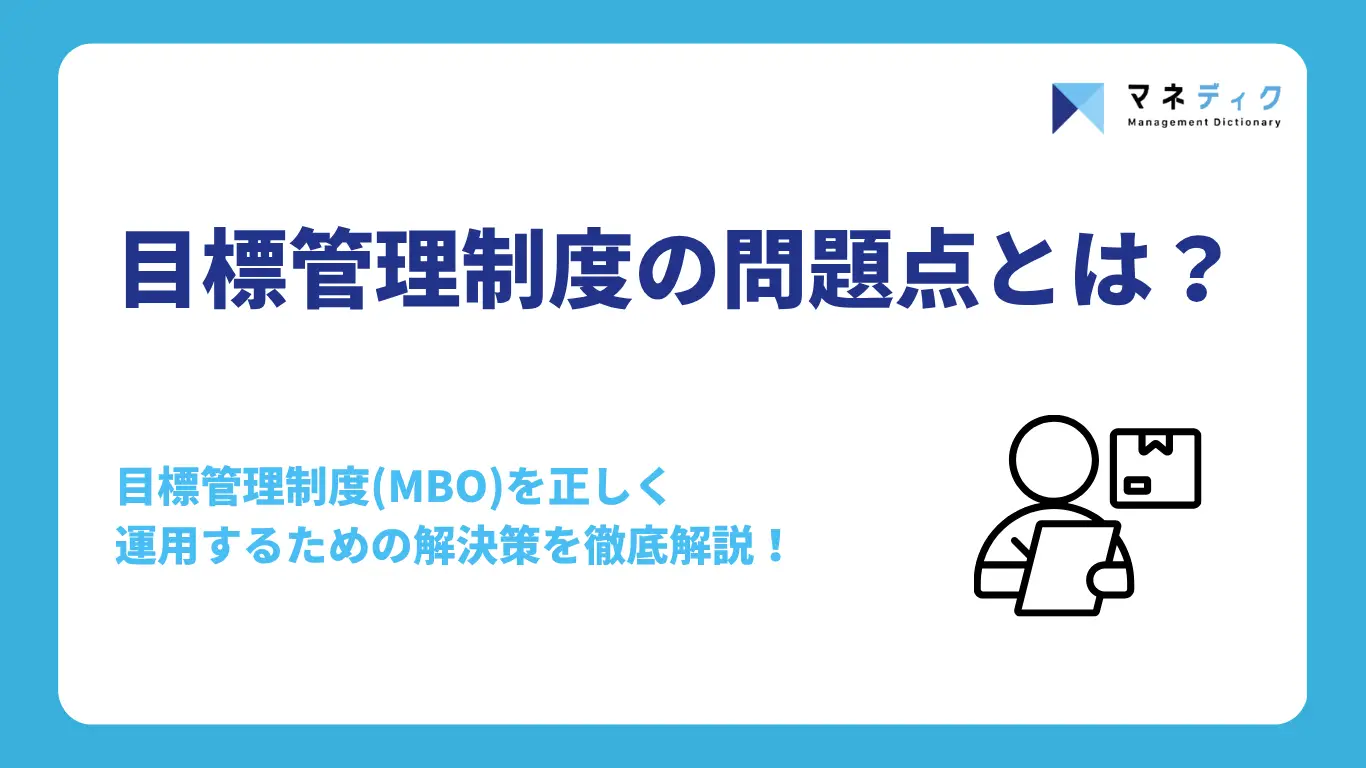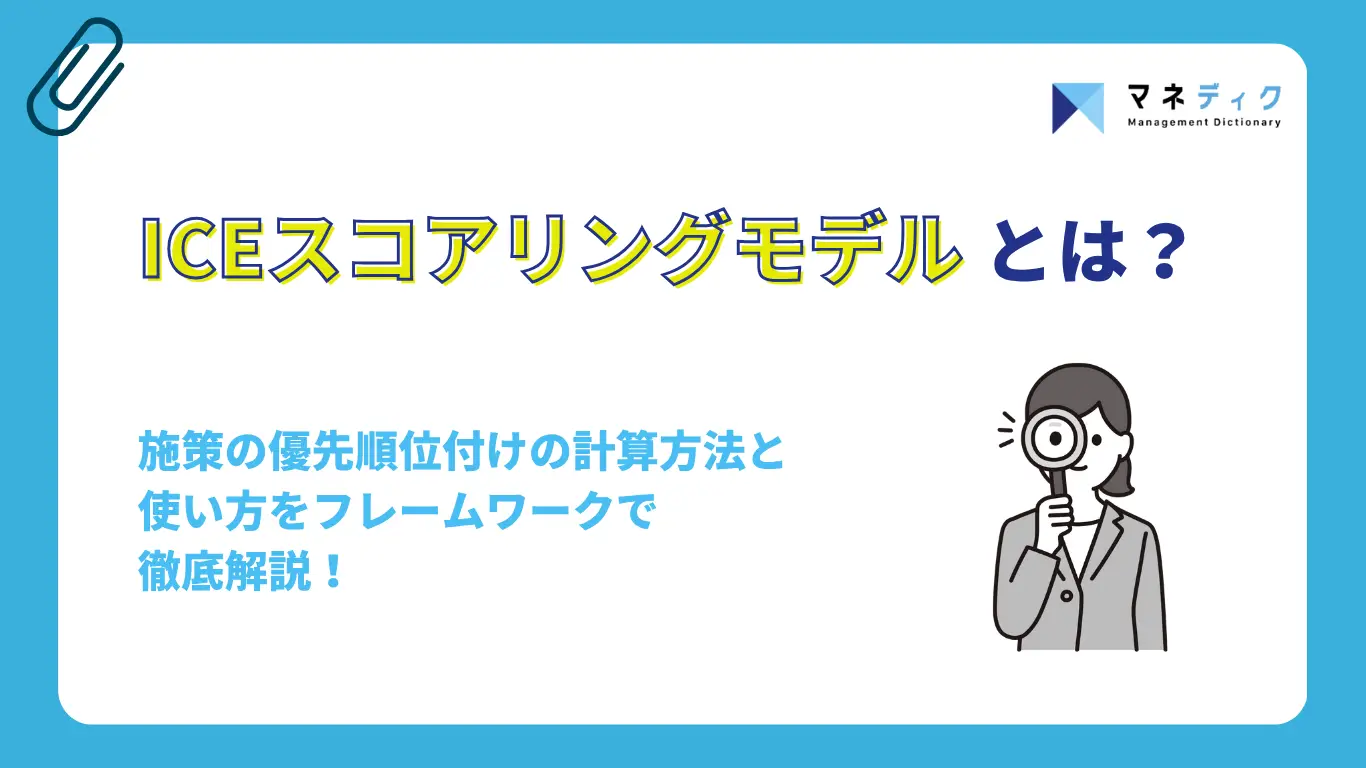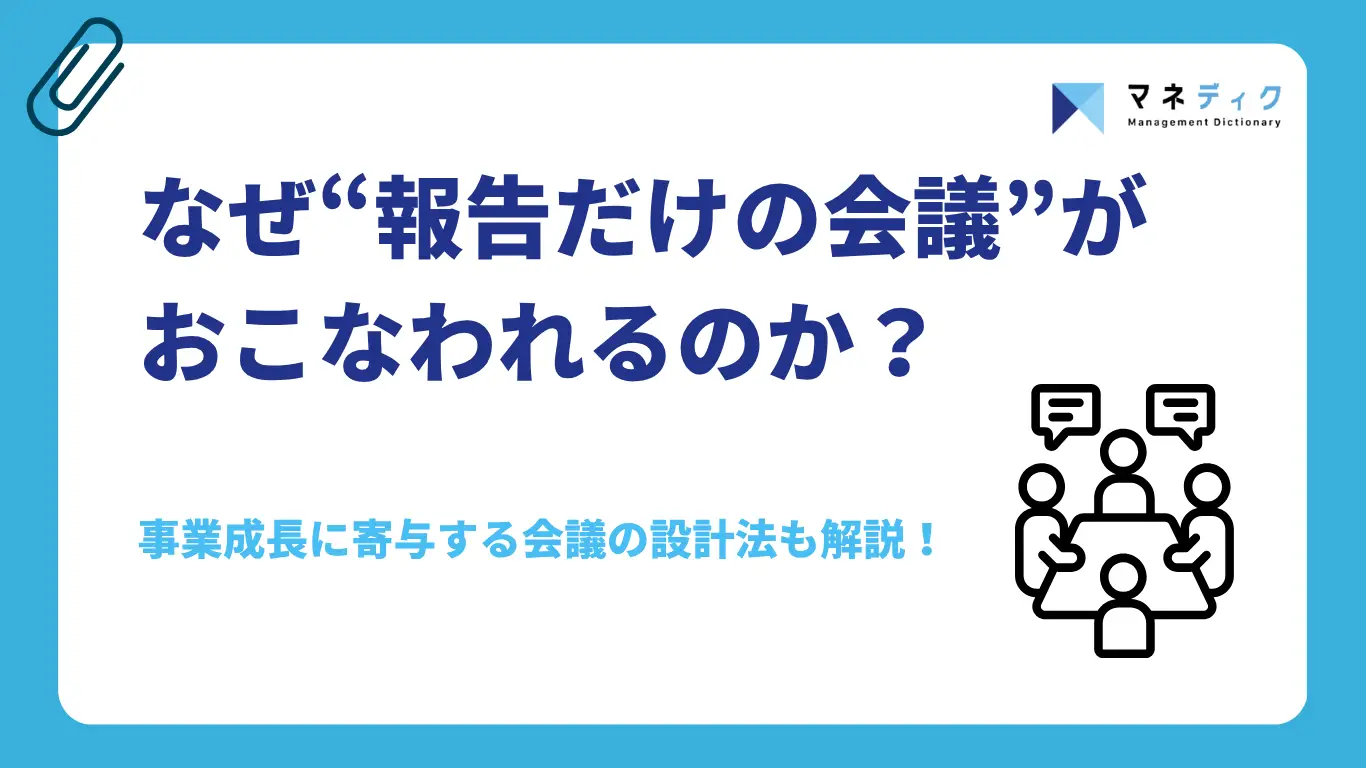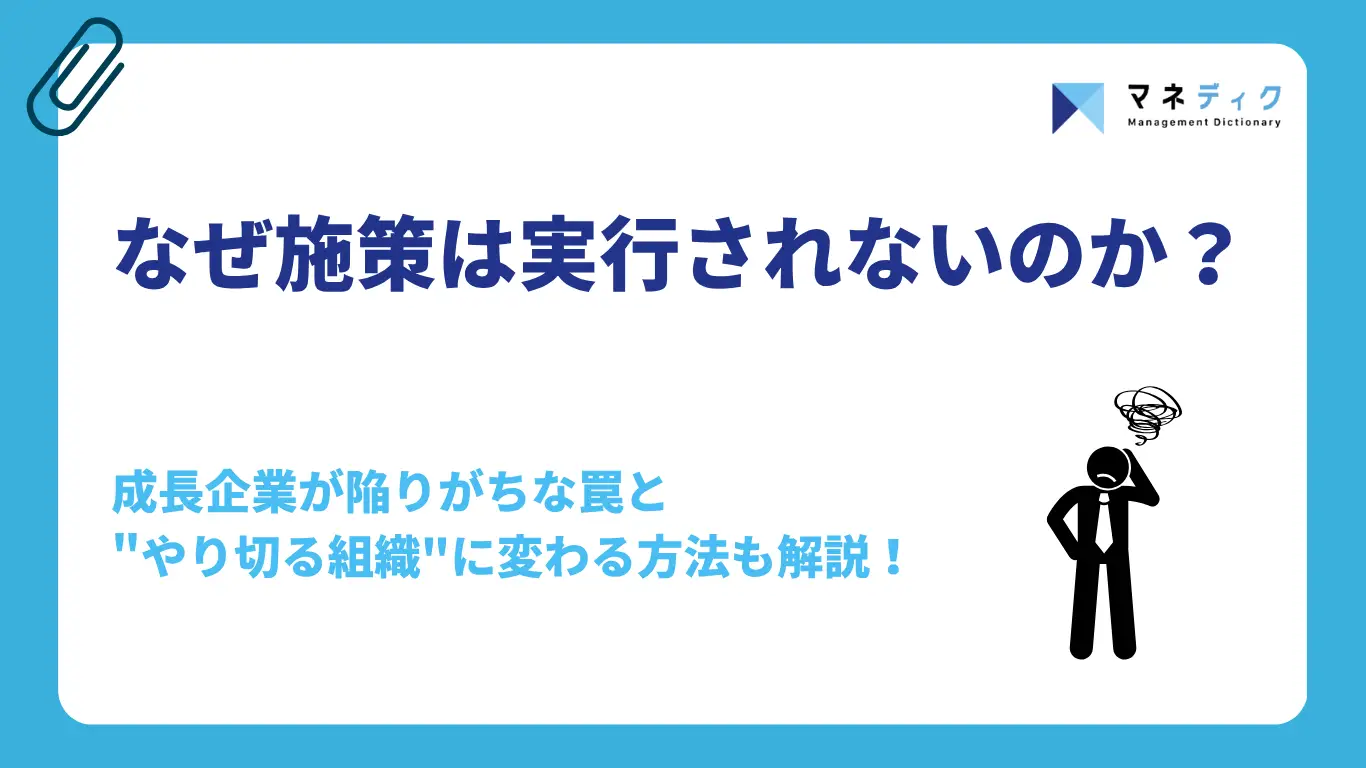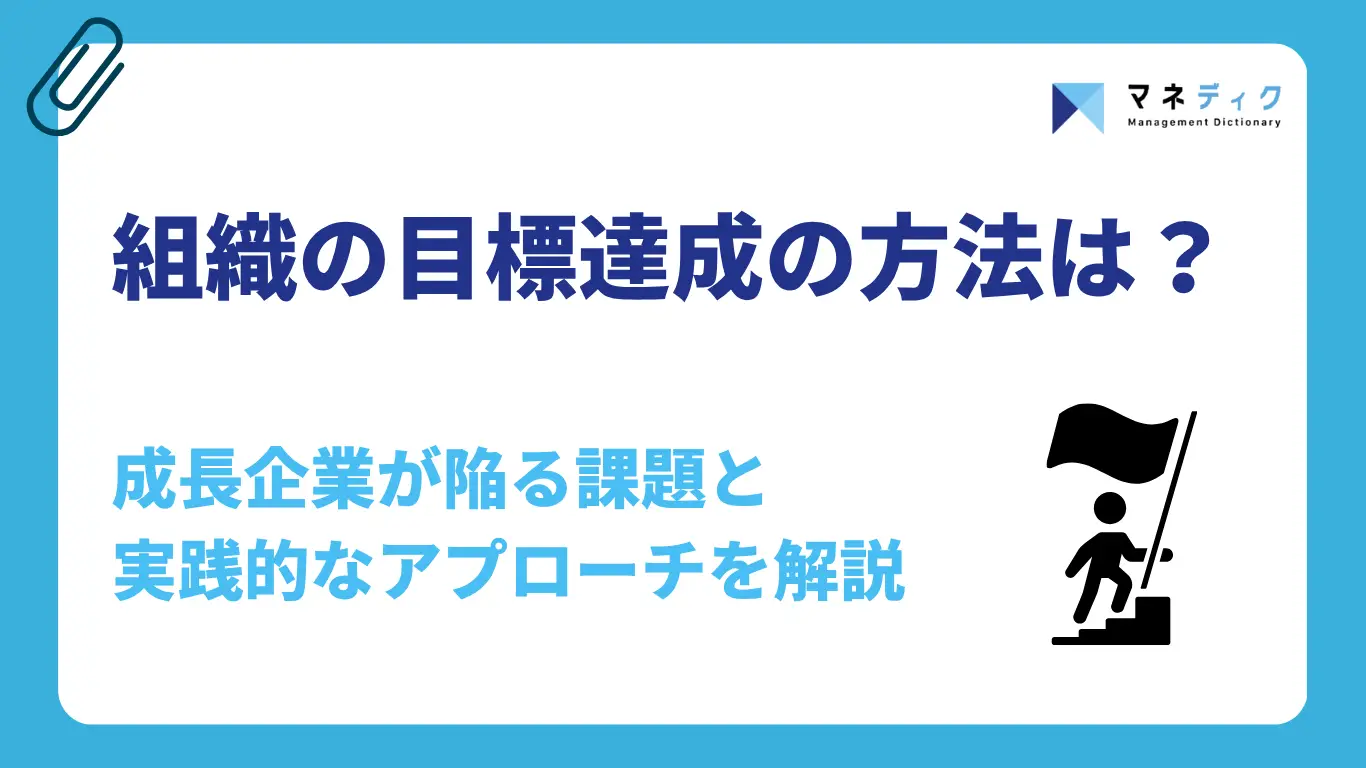ベンチャーが業績管理で陥りがちな課題とは? 業績管理に必要なスキルも解説
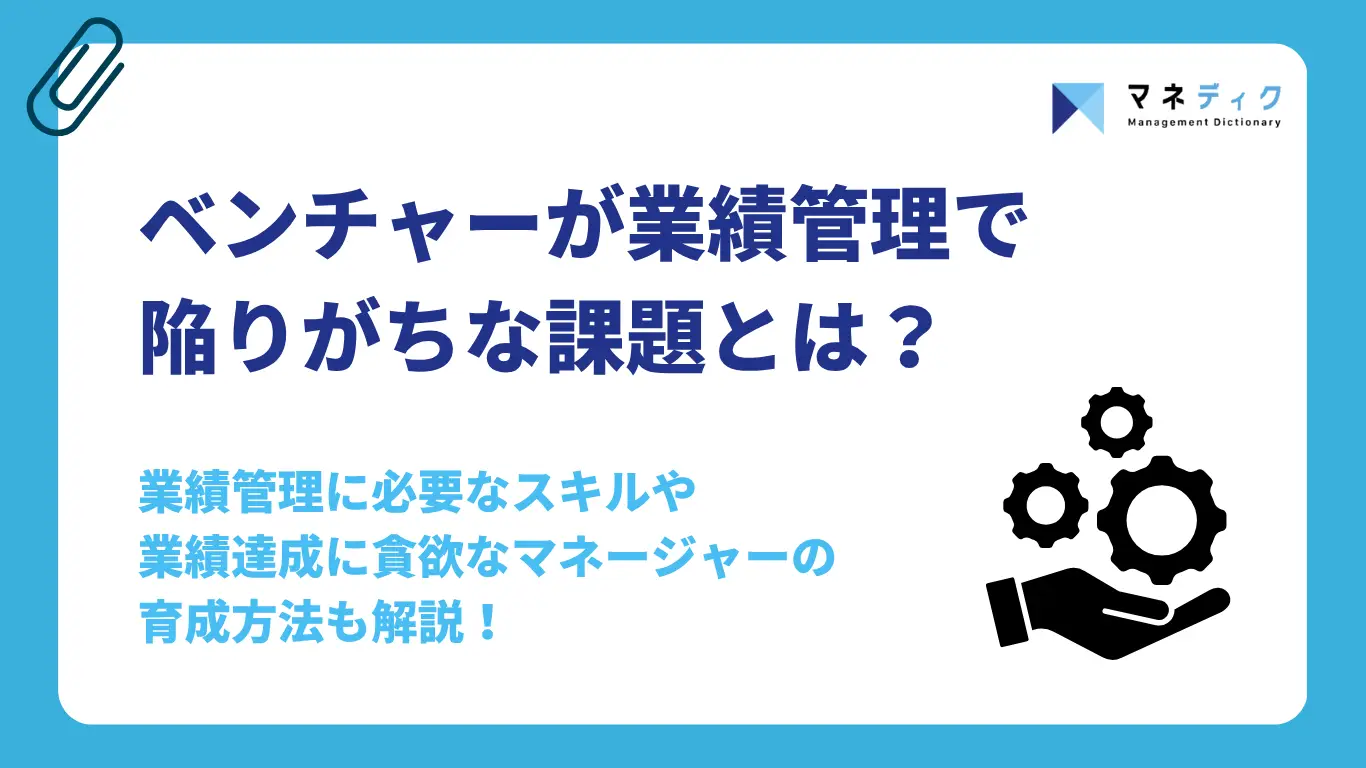
成長ベンチャーが業績管理で抱える特有の課題
「各部門長が管理するExcelはフォーマットも粒度もバラバラ。経営会議で正確な着地見込みが出てこない」
「マネージャーを抜擢したはいいが、業績への意識が低く、育成方法もわからない」
これは、多くの成長ベンチャーの経営者が抱える、生々しい悩みではないでしょうか。
事業が急成長する過程で、業績管理は必ず壁にぶつかります。これは、中小企業庁の調査などでも「組織の壁」として指摘される、多くの企業が直面する成長痛です。
業績管理の課題は、大きく「仕組み」「人(スキル)」「意識」という3つの側面に分類できます。
以下でそれぞれ詳細に解説していきます。
課題1:【仕組みの壁】管理フローが属人化・形骸化している
業績管理に関する課題の1つ目が、管理フローが属人化・形骸化していることです。
創業期は、少人数ゆえに阿吽の呼吸で業務が進みます。しかし、従業員が100名規模に近づくと、その「属人的」な管理体制は機能不全に陥ります。
各部門が独自のExcelでKPIを管理し、報告フォーマットもバラバラ。経営陣が全社のリアルタイムな業績を把握できず、迅速な経営判断の妨げとなります。
いつの間にか、業績管理が「報告のための報告」となり、本来の目的である「改善アクション」に繋がらない。これが、業績管理が「形骸化」してしまう典型的なパターンです。
課題2:【スキルの壁】マネージャーの業績管理スキルが不足している
業績管理に関する課題の2つ目が、マネージャーの業績管理スキルが不足していることです。
成長ベンチャーでは、優秀なプレイヤーがそのままマネージャーに抜擢されるケースが少なくありません。しかし、「プレイヤーとしての優秀さ」と「マネージャーとしての優秀さ」は全くの別物です。
業績管理の体系的なトレーニングを受けないままマネージャーになることがほとんどなので、部下への目標設定や進捗管理、本来求められるレベルの業績報告ができないのは当然です。
KPIの遅延に対して「なぜ?」を深掘りし、「次の打ち手」を考えさせるスキルがなければ、チームの業績を向上させることはできません。
課題3:【意識の壁】マネージャーに業績への当事者意識がない
業績管理に関する課題の3つ目が、マネージャーに業績への当事者意識がないことです。
スキル以前の、より根深い問題が「意識の壁」です。マネージャー自身が、自分のチームの業績達成に「自分ごと」としてコミットできていないケースです。
「目標は経営陣が決めるもの」「自分の役割はメンバーの管理」といった他人事の意識では、業績達成への執着は生まれません。
経営者と同じ視座で市場と向き合い、チームの業績に責任を持つという「当事者意識」の欠如こそ、「勘」に頼る経営から脱却できない根本原因なのです。
「目標は経営陣が決めるもの」「自分の役割はメンバーの管理」 こうしたマネージャーの「他人事」な姿勢や、「当事者意識の欠如」という根深い課題に直面し、頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか。
しかし、「意識」や「コミットメント」は、精神論や個人の資質に頼っていても決して解決しません。
以下の「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」は、その曖昧な「コミットメント」を、誰もが実践可能な具体的な「行動」と「仕組み」として再定義するための資料です。
資料内では、当事者意識の核となる「スピード」「各論」「執着」という3つの定義から、目標とのGAPに執着し続けるための「GAP起点の思考法」、さらには“目標必達”を組織文化として根付かせるための実践的な育成ステップまでを詳細に解説しています。
ぜひ、この機会に資料をダウンロードし、業績達成に執着する組織づくりにお役立てください。
ベンチャー企業で業績管理をするうえで必要な考え方
課題を乗り越え、業績管理を真に機能させるためには、具体的な手法の前に、まず経営陣がその「思想」を明確に持つ必要があります。
以下でベンチャー企業の業績管理について、経営者が持つべき考え方をご紹介します。
1.「管理」ではなく「成長のアクセル」だと捉える
業績管理は、ただ進捗を監視したり、現状を維持するための「守り」の取り組みではなく、事業の成長をより加速させるための「攻め」の取り組みです。
大企業的な「管理(Control)」は、ルールで縛り、逸脱を防ぐことを目的とします。一方で、ベンチャーにおける業績管理とは、組織のポテンシャルを最大化し、成長を阻害するボトルネックを発見するためのある種の「ツール」です。
数値を起点として、組織の課題をリアルタイムに発見し、「どうすればもっと良くなるか」「次の打ち手は何か」という改善アクションを生み出し続けるためのものだと捉えるべきです。このサイクルこそが、組織の学習スピードを決定します。
2. 「マネジメントの基準」が「組織の基準」を決定する
「社長やマネジメントの能力が、その対象組織の能力の上限である」とよく言われます。これは、マネージャーが許容するアウトプットの「基準」が、そのままチームの「基準」になることを意味します。
厳しい上司の下では80点のアウトプットを目指す一方、緩い上司の下では60点のアウトプットでも「指摘されないから良いか」という甘えが生まれます。業績管理は部下・メンバーの基準を決定するうえで重要な役割を担います。
私自身も実際、厳しい上司の下では80点のアウトプットが出せていたにも関わらず、基準の緩い上司の下で働いた際、「こんなものでも指摘されない」という甘えから、アウトプットのレベルが60点に下がってしまった経験があります。
業績管理が失敗する最大の理由は、経営者や上層部が「基準の番人」としての役割を放棄し、マネージャーに低いレベルの報告・アウトプットを許容してしまうことです。
仮に業績報告の場で、マネージャーの業績報告や業績への意識に対して厳しくフィードバックしておけば、マネージャー自身の基準も上がり、同時にそれを見るメンバーの基準も上がります。
業績管理とは、この「基準」を組織全体で引き上げ続けるための、マネジメントの最重要業務なのです。
目標達成に向かう組織の作り方に関しては以下の記事にて、詳細に解説しているので、ご興味ある方はぜひご覧ください。
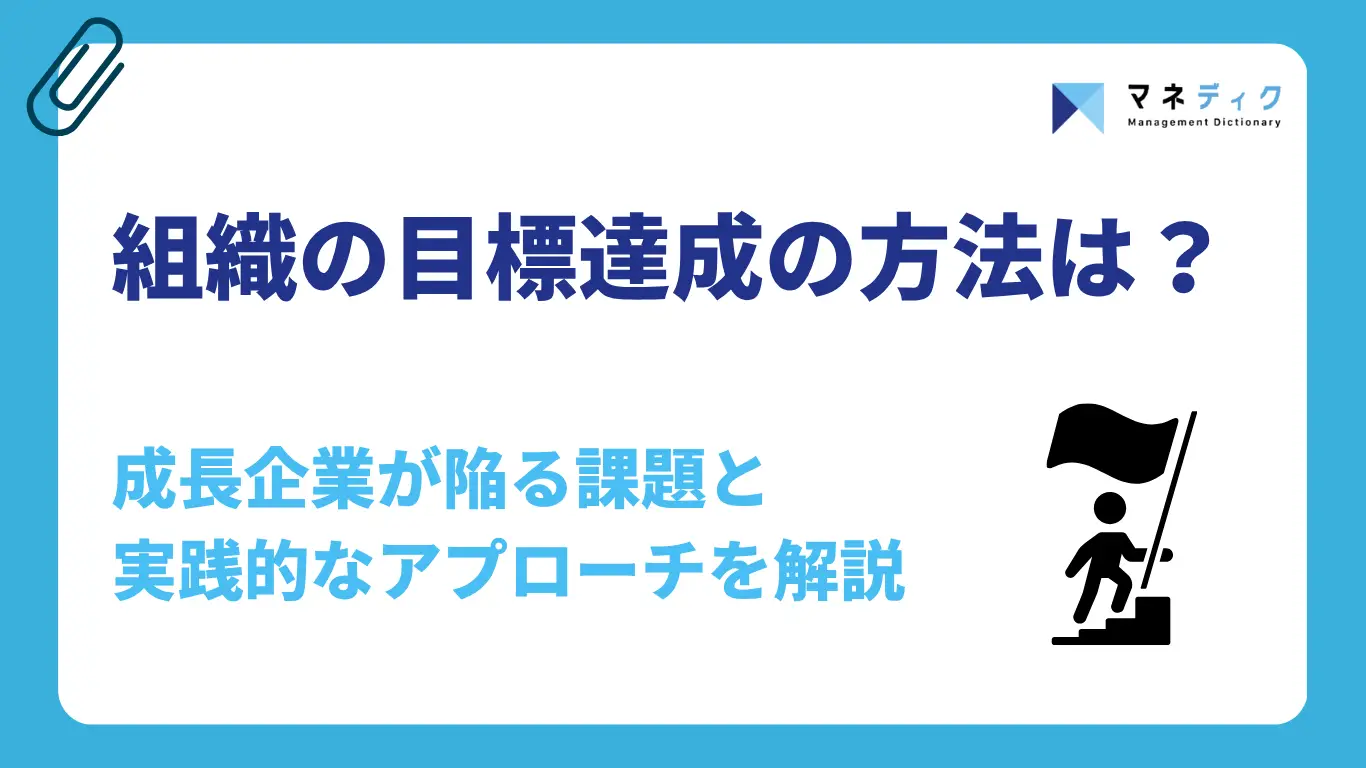
業績管理の課題を解決する「仕組み」の作り方
これらの根深い課題を解決するためには、まず土台となる「仕組み」を構築する必要があります。
ステップ1:KGI/KPIを再設定する
最初に取り組むべきは、全社共通で全員が腹落ちする「数字」を設定することです。
部門ごとにバラバラだった目標を、全社の最重要目標(KGI)と明確に連動させ、各部門の行動指標(KPI)として再設定します。
このプロセスは、単なる数値設定ではなく、会社の向かうべき方向を示す「経営方針」を全社員で共有する、極めて重要な経営活動です。
当然だと思われる方も多いかと思いますが、KGI/KPIを設定し直し、その数値の意味や実現した時の状態などをマネージャー陣に示すことで、業績達成へのコミットメントが自然と高まります。
ステップ2:業績管理の「型」となるPDCAフローを統一する
次に、「いつ」「誰が」「どの粒度で」業績を報告・分析・改善するのか、という全社共通の業績管理の「型(管理フロー)」を定めます。
例えば、「毎週月曜の朝会で各チームのKPI進捗を報告し、要因分析と次のアクションを共有する」といったサイクルをルール化します。
結局、業績管理で起きがちな「管理方法の属人化」「業績管理のスキル不足」という課題は、業績管理をどのような手順で何をやるのかが型化されていないことが原因です。
フェーズに応じて業績管理の「型」は変更していく前提で、まずは全社で業績管理のフローを統一することが重要です。
ステップ3:ツールを活用し「リアルタイムな可視化」を実現する
仕組み化の仕上げとして、テクノロジーを活用します。
Excel管理から脱却し、SaaSツール(ERP、SFAなど)を導入することで、リアルタイムな業績の可視化が可能になります。
これにより、経営者はデータに基づいた迅速な意思決定ができ、マネージャーは分析業務から解放され、より本質的な「次の打ち手」を考える時間に集中できるようになります。
あくまでステップ1、2が重要なので、適切な目標設定や業績管理の型化ができていないのにもかかわらず、テクノロジーに走ると大抵失敗します。
マネージャーに必須の「業績管理スキル」とは?
ここまで成長ベンチャー企業で起こりがちな業績管理に関する課題とその課題を解決するための考え方、具体的な方法を解説してきましたが、実際に業績管理をおこなううえでマネージャーにはどんなスキルセットが求められられるのでしょうか。
ここでは、業績管理をおこなうマネージャーに必須の3つのスキルと、その具体的な育成アクションについて解説していきます。
スキル1:目標を「自分ごと化」させる目標設定(MBO)スキル
MBOとは、組織全体の目標と個人の目標を連動させ、従業員が自ら目標を設定・管理し、その達成度合いに基づいて評価を行う仕組み
経営学者のピーター・ドラッカーが提唱した目標管理(MBO)は、単なるノルマ設定ではありません。優れたマネージャーは、会社の目標をチームの目標、さらにはメンバー個人の目標へとブレイクダウンし、「なぜこの目標を追うのか」を納得させることができます。
【具体的なアクション】
経営者自らがマネージャーと1on1を実施し、「なぜこの目標なのか」という背景にある経営イシュー(市場の動向、競合の脅威など)を徹底的にすり合わせましょう。背景を理解して初めて、目標は「自分ごと」になります。
スキル2:数値に基づき「次の打ち手」を考えさせる分析スキル
「進捗どう?」で終わるマネージャーの下では、人は育ちません。
KPIの進捗が「良い/悪い」という事実に対し、「なぜそうなったのか(要因分析)」「だから何をすべきか(次の打ち手)」を問い、考えさせることが重要です。
【具体的なアクション】
週次の業績管理会議で、経営者がファシリテーターとなり、マネージャーに対して「なぜ?」「だから次のアクションは?」という問いを徹底してください。この思考のクセが、組織全体の分析スキルを向上させます。
スキル3:実行を支援し「再現性」を高めるフィードバック力
打ち手が決まっても、実行されなければ意味がありません。
打ち手の実行状況を週次などで確認し、うまくいかない場合はタイムリーにフィードバック(軌道修正)することが、業績管理の「再現性」を高めます。
【具体的なアクション】
マネージャーとの1on1で、「部下へのフィードバックが適切か」をテーマに議論しましょう。経営者がマネージャーの育成(=コーチングをコーチングする)にコミットすることが、現場の実行力を飛躍的に高めます。
マネージャーの「当事者意識」を醸成する本質的な方法
業績管理をするスキル自体も当然重要ですが、何よりもマネージャー自身の業績達成に対する当事者意識が何よりも重要です。
以下でマネージャーの「当事者意識」を醸成する本質的な方法について解説していきます。
経営陣が「業績」への覚悟と透明性を一貫して示す
マネージャーの意識を変えるには、まず経営陣が変わる必要があります。
経営陣が業績達成に本気でコミットする「覚悟」を見せ、経営状況をオープンにすることが、マネージャーの意識変革の第一歩です。
【具体的なアクション】
これまでブラックボックスだった「経営会議の議事録」を、マネージャー陣に原則公開しましょう。会社の生々しい数字と経営者の危機感を共有することが、マネージャーの視座を引き上げます。
マネージャー同士が「業績」について議論する「場」を設ける
マネージャーは孤独です。その孤独感を解消し、視座を高めるためには、他部門のマネージャーが「何を考え、どう業績と向きあっているか」を知る「場」が不可欠です。
【具体的なアクション】
月1回の「マネージャー陣による業績報告・議論会」を「仕組み(場)」として導入しましょう。経営者がファシリテーターとなり、各部門の課題や成功事例を共有し、部門を超えた集合知を生み出す場として設計することが重要です。
経営陣による情報開示や「場」の設置など、当事者意識を醸成する具体的な方法を解説してきましたが、これらを取り組んでもそう簡単には当事者意識や業績達成への執着は醸成されません。
それでは、どうすればその「当事者意識」や「業績への執着」を、単なる精神論ではなく、具体的な行動レベルまで落とし込み、組織に根付かせることができるのでしょうか。
「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、まさにその曖昧な「コミットメント」を、誰もが実践可能な「行動」と「仕組み」として再定義しています。
資料内では、
当事者意識の核となる「スピード」「各論」「執着」という3つの定義
業績とのGAP(ギャップ)を埋めるための具体的な「GAP起点の思考法」
そして、それらを組織文化として定着させるための実践的な育成ステップ
まで、詳細に解説しています。
経営陣の覚悟や「場」の設置と合わせて、マネージャー自身の「思考法」と「行動」を変革する具体的なアプローチを、ぜひ以下資料をダウンロードしてご確認ください。