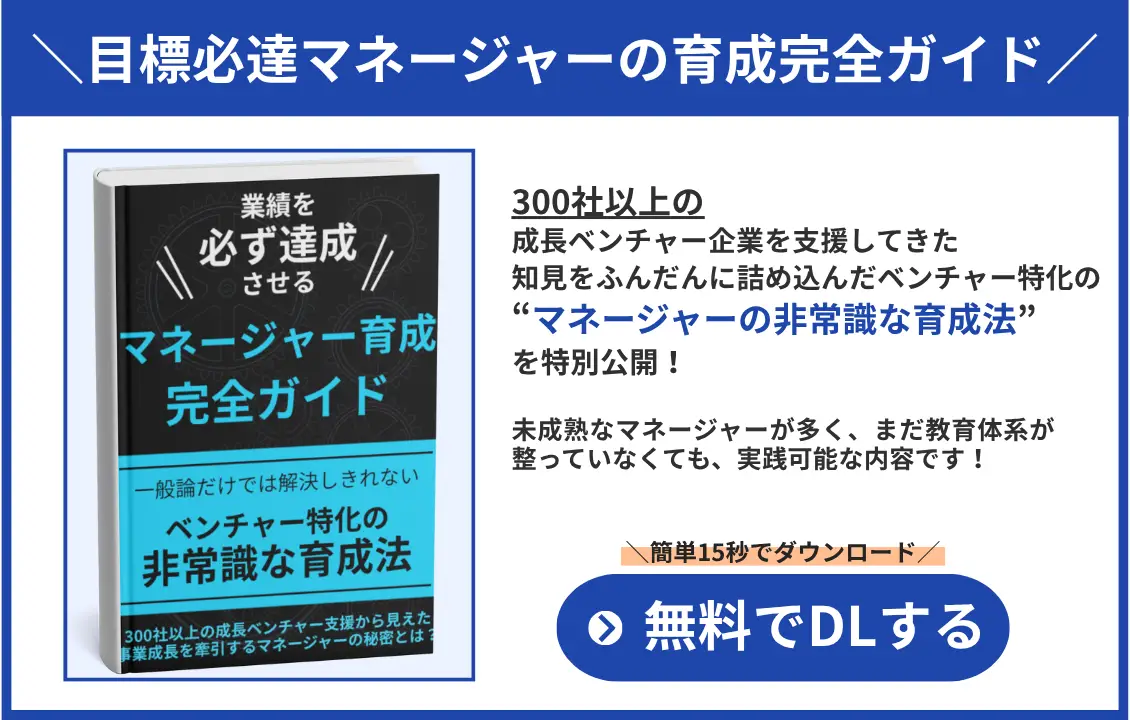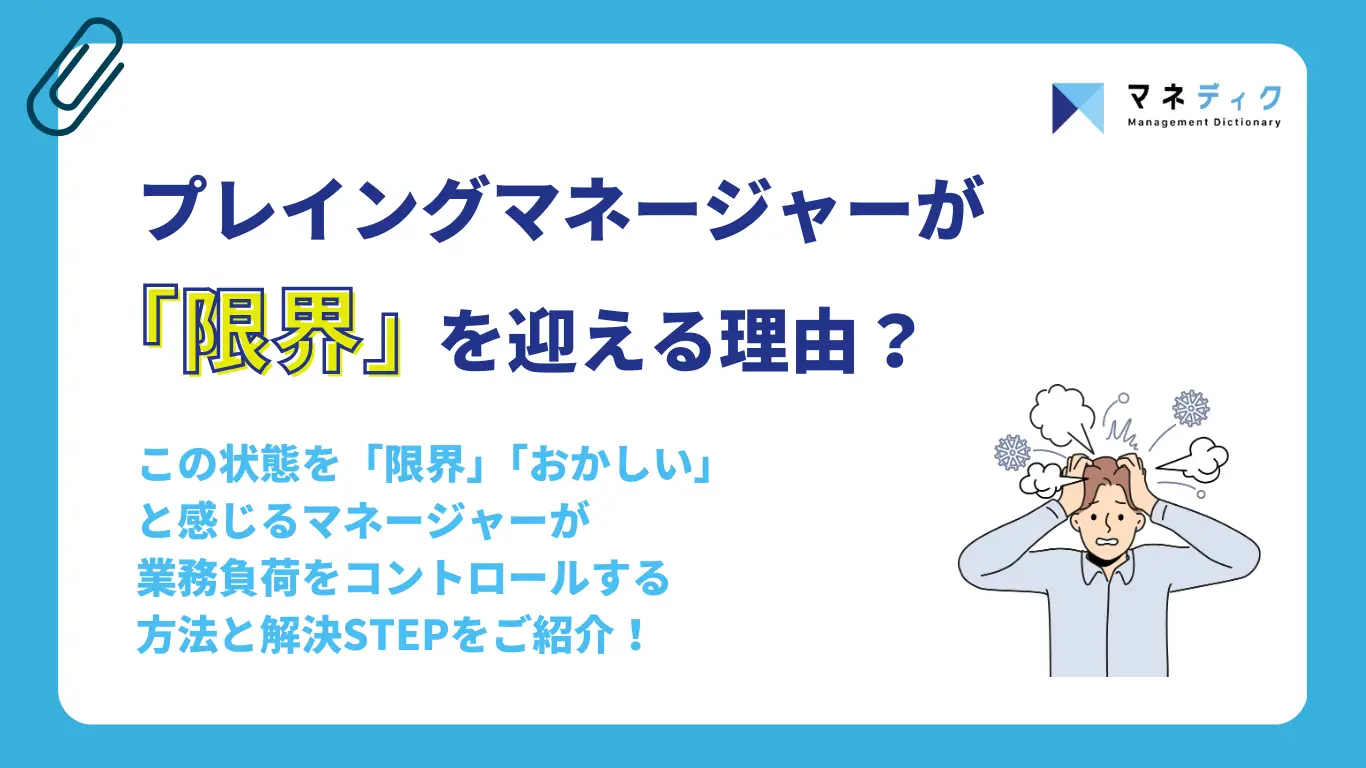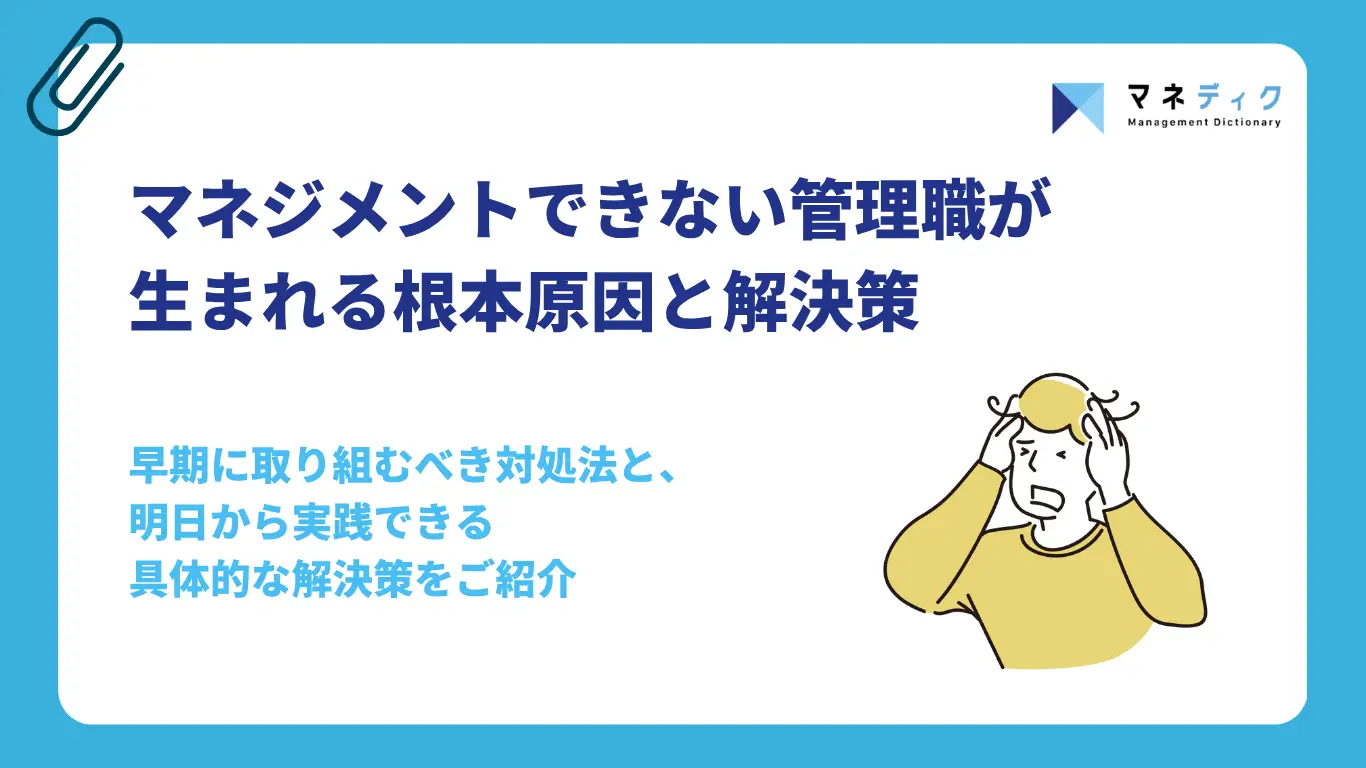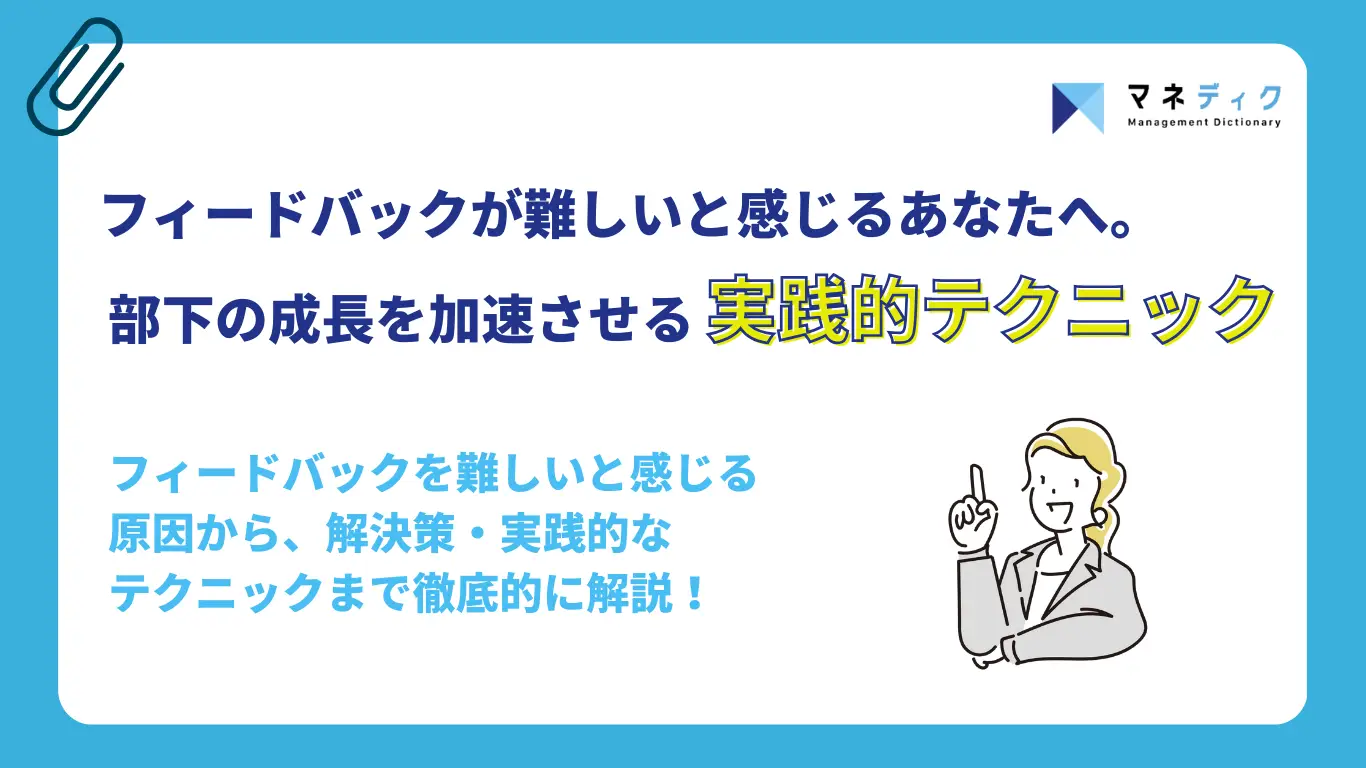コミットメントが低い原因とは?社員の主体性を引き出し、組織の壁を越える方法をマネジメントのプロが解説

コミットメントとは?エンゲージメントやモチベーションとの違いを解説
コミットメント:「目標達成への責任」と「組織への帰属意識」
ビジネスシーンにおける「コミットメント」とは、「与えられた役割や目標達成に対して、責任を持って主体的に関わること」を指します。
さらに、個人が組織の一員として「組織の目標やビジョンに貢献したい」という帰属意識も重要な要素です。つまり、コミットメントが高い状態とは、社員一人ひとりが自らの仕事に責任感を持ち、会社の成功を自分事として捉え、能動的に行動している状態と言えるでしょう。
エンゲージメントやモチベーションとの明確な違い
コミットメントは、「エンゲージメント」や「モチベーション」と混同されがちですが、それぞれ焦点が異なります。
意味合いの違い
- コミットメント(責任・貢献):
モチベーションやエンゲージメントといった感情や状態を、具体的な「行動」に結びつける責任感です。目標達成のために困難な課題にも向き合い、最後までやり遂げるという主体的な関与を意味します。 - モチベーション(意欲):
行動を起こすための「動機」や「意欲」そのものを指す、感情的なエネルギーです。「やる気がある」状態がこれにあたります。 - エンゲージメント(愛着・熱意):
組織と社員が互いに貢献し合う関係性の中で生まれる、ポジティブで充実した心理状態です。仕事への熱意や誇り、一体感などが含まれます。
つまり、「モチベーション」がエンジンのガソリン、「エンゲージメント」が良好な運転状態だとすれば、「コミットメント」は「目的地まで責任を持って運転する」というドライバー自身の意志と行動なのです。
コミットメントが高い状態を組織として作るには、組織の核を担うマネージャーが誰よりもコミットメントが高くないといけません。マネージャーが誰よりも目標達成に責任を持ち、事業成長に貪欲でないといけません。
以下資料ではそんな目標達成にコミットするマネージャーの育成方法を、これまでの300社以上のベンチャー企業様のご支援をもとに紹介しています。
ぜひダウンロードしてご活用ください。
以下からコミットメントが低い組織の状態、コミットメントを高めるにはどうすれば良いかを解説していきます。
コミットメントが低い組織の「状態」とは
「やらされ仕事」が蔓延し、主体性が見られない
「これ、やっといて」と指示されたことはやるものの、それ以上の提案や改善アクションが出てこない。
会議ではいつも受け身で、新しい挑戦を避けようとする空気が漂う。
このような「やらされ仕事」の蔓延は、コミットメントが低い組織の典型的な状態です。
メンバーは自らの業務を「自分事」として捉えられず、ただの作業としてこなしているため、主体的な行動が生まれません。
結果として、優秀な中堅社員ほどこの状況に失望し、静かに会社を去っていく「キーマンの離職」を引き起こします。
当事者意識を引き出し、コミットメントを高める方法は以下の記事でもご説明しています。

組織急拡大で理念が希薄化し「他人事」の集団になる
創業期には暗黙のうちに共有されていた価値観や行動規範といった「カルチャー(組織文化)」が、組織の急拡大によって希薄化していく。新たに入社したメンバーにはかつての「阿吽の呼吸」は通用せず、経営陣がビジョンを語っても、それが日々の行動にまで落とし込まれない状態です。
結果として、組織への一体感が失われ、自分の部署の利益だけを優先する「サイロ化」が進行し。組織・社員が「自分事」として物事を考えられない状態に変わってしまうのです。
課題の真因を見極められず、施策が空回りしている
エンゲージメントサーベイの結果が悪い、離職率が上がってきた、といった目に見える「症状」に対して、場当たり的な対策に終始してしまうこともコミットメントが低い組織ではよく見られます。
例えば、コミュニケーション不足が課題だと考え、研修を増やしたり、新たなツールを導入したりする。しかし、本質を捉え、導入の背景や目指す姿が浸透していなければ、現場からは「また仕事が増えた」という不満の声が上がるだけで、根本的な解決には至りません。
これは、組織課題の真因を見極められないまま、表層的な施策が空回りしている状態です。
コミットメントが低いのは「個人の資質」ではなく「組織とマネジメント」の問題
これらの状態を見て、「最近の若手はやる気がない」「社員の当事者意識が低い」と結論づけるのは早計です。コミットメントの低下は、決して社員個人の資質の問題ではありません。
ワークライフバランスが重視される現代、「コミットメント」という言葉は、ともすれば「長時間労働」や「滅私奉公」といった古い価値観を想起させがちです。
しかし、本来のコミットメントは労働時間とは無関係です。特に変化の激しい現代、とりわけベンチャー・成長企業において求められるコミットメントとは、「自責」の念から生まれる「当事者意識」に他なりません。
外部環境や上司の指示が目まぐるしく変わる中で、ただ指示を待つだけでは事業は失速します。
「どうすれば目標を達成できるか」「自分に何ができるか」を考え、自らボールを拾いに行く姿勢こそが、組織の成長を支えるのです。
この「何としてでも自分が達成させる」という当事者意識(コミットメント)を育むか、削いでしまうかは、社員を取り巻く「組織の仕組み」と「日々のマネジメント」にかかっています。
社員のコミットメントが低い原因と対策
コミットメントの低下は組織の成長を鈍化させる深刻な問題ですが、「コミットメントが高い状態」とは具体的にどのような行動を指すのでしょうか。
マネディクでは、コミットメントを精神論ではなく、以下の3つの具体的な「行動」として現れると定義しています。
コミットメントが高い人材が共通して体現している行動
- スピード:
顧客への返信、社内の意思決定、問題発生時のリカバリーなど、全てのレスポンスやアクションが迅速であること。ベンチャーにとってスピードは生命線であり、最も重要な差別化要因です。 - 各論(細部へのこだわり):
担当領域のKPIや数値の微細な変化、顧客の声、競合の動向など、成果に関連する細部の情報を誰よりも熟知していること。「確認します」ではなく、即座に具体的に答えられる状態を目指します。 - 執着:
目標達成への強い意志を持ち、困難な状況でも諦めずに最後までやり抜くこと。他責にせず、「できない理由」ではなく「どうすればできるか」を考え続け、行動し続ける姿勢です。
これらの行動が見られない、あるいは弱い場合、その背景には必ず原因があります。
ここでは、コミットメント低下の原因を「土台」「個人」「組織」の3つのステップに分け、それぞれの対策を解説します。
土台作り:2つの「安全性」の欠如
原因:挑戦や成長を阻む「安全性」の欠如
コミットメント向上の土台が揺らいでいる原因の一端として、「心理的安全性」と「キャリアの安全性」の欠如があります。
「俺の背中を見て学べ」といった一方的なマネジメントスタイルや、失敗を過度に責める文化は、メンバーから挑戦意欲を奪い、「言われたことだけやればいい」という守りの姿勢を生み出します。
これでは、主体的なコミットメントが生まれるはずがありません。
▼対策
2つの「安全性」の確保とバランスを意識しましょう。
コミットメント向上の第一歩は、社員が安心して挑戦し、成長できる土台を築くことです。
そのためには、「心理的安全性」と「キャリアの安全性」という2つの要素が不可欠です。

心理的安全性とは、非難される不安なく、自分の考えや意見を素直に発言できる状態を指します。
しかし、これを「ぬるま湯」と誤解してはいけません。心理的安全性を重視しすぎるあまり、必要な指導や厳しいフィードバックを怠ると、組織は規律のない「ゆるい職場」となり、かえって成長意欲の高い社員のキャリアの安全性を脅かします。
一方で、キャリアの安全性とは、「この会社にいれば成長できる」「市場価値の高い人材になれる」と社員が感じられる状態です。
心理的安全性を担保しつつも、メンバーの成長のためには、伝えるべきことは適切にフィードバックすることが極めて重要です。
まずはエンゲージメントサーベイや1on1を通じて、自社の現状をこの2つの「安全性」の観点から正しく把握し、コミットメント低下の根本原因がどこにあるのか仮説を立てましょう。
「個人」へのアプローチ:対話による動機付けと当事者意識の醸成
土台が整ったら、次はマネージャーが中心となり、メンバー一人ひとりへのアプローチを強化します。
原因:目標が「他人事」になっている
▼対策
1on1等のタイミングでWill(やりたいこと)とMission(やるべきこと)のバランスをとり、接続させましょう。
メンバーのコミットメントが低い最大の原因は、目標が「他人事」になっていることです。
1on1等の場で、本人のキャリアプラン(Will)と会社の目標(Mission)を丁寧に接続し、「この目標は自分の成長のためにある」と認識してもらう対話が不可欠です。
原因:「背中を見ろ」型のマネジメント
▼対策
部下の「自責」と「当事者意識」を引き出すフィードバックを心がけましょう。
常日頃、感情的な叱責を行なっている場合は、相手を「どうすれば怒られないか」という他責思考に陥らせています。
「ネガティブフィードバックのポイント」

特にネガティブな事象ほど、失敗を責めるのではなく、冷静に事実を振り返り、「この経験から何を学べるか?」と内省を促す問いかけをすることが重要です。ネガディブフィードバックをする際には、ぜひ画像の7つのポイントを意識しながらコミュニケーションを取るようにしてみてください。
この関わり方が、失敗を自分事として捉える「自責」の念と、未来志向の「当事者意識」を育みます。
「組織」へのアプローチ:理念浸透と貢献を可視化する仕組み化
個人の意識変革と並行して、組織全体でコミットメントを育む「仕組み」を構築しましょう。
原因:ビジョン・ミッションが「お題目」になっている
▼対策
経営が語り続け、マネージャー層がコミットメントを体現する「仕組み」を作りましょう!

理念浸透は精神論ではありません。
経営陣が全社会議などあらゆる場でビジョンを語り続け、マネージャー層がそれを各チームの目標に翻訳し、さらに理念を体現する行動(バリュー)を人事評価に組み込む、といった一連の「仕組み」が必要です。
原因:評価・称賛の仕組みが曖昧
▼対策
OKRやバリュー評価で「組織への貢献」を正当に評価しましょう。
個人の成果だけでなく、組織への貢献を可視化し、称賛する仕組みを導入するのが効果的です。
自分の仕事が会社のどの目標に貢献しているかを全社で共有する「OKR」の導入や、数字に表れにくい貢献を社員同士で称賛し合える「ピアボーナス®︎」の活用などが有効です。
このような評価制度の作り方に関しては、以下の記事で詳細をご確認ください。

まとめ:コミットメントは「管理」するものではなく「引き出す」もの
社員のコミットメントは、ルールや制度で「管理」しようとしても、決して高まりません。
それは、適切な環境と真摯なマネジメント、そして貢献を正当に評価する仕組みによって、社員の「内側から引き出す」ものだからです。
また、組織全体のコミットメントを高めるには、各事業部・チームのマネージャーが誰よりも成果・目標達成にコミットしている必要があります。マネージャーが100%コミットしていれば、自ずとシャインのコミットメントも高まります。
以下の資料では、これまで300社以上の成長ベンチャー企業をご支援してきた知見をもとに、ベンチャーのマネージャーがどうやったら目標達成にコミットするようになるか、誰よりも目標GAPを埋めようと必死になるマネージャーを育成できるかを解説しています。
業績へコミットメントするマネージャーを育成して、組織のコミットメントを高めたい経営者の方はぜひダウンロードしてご活用ください。