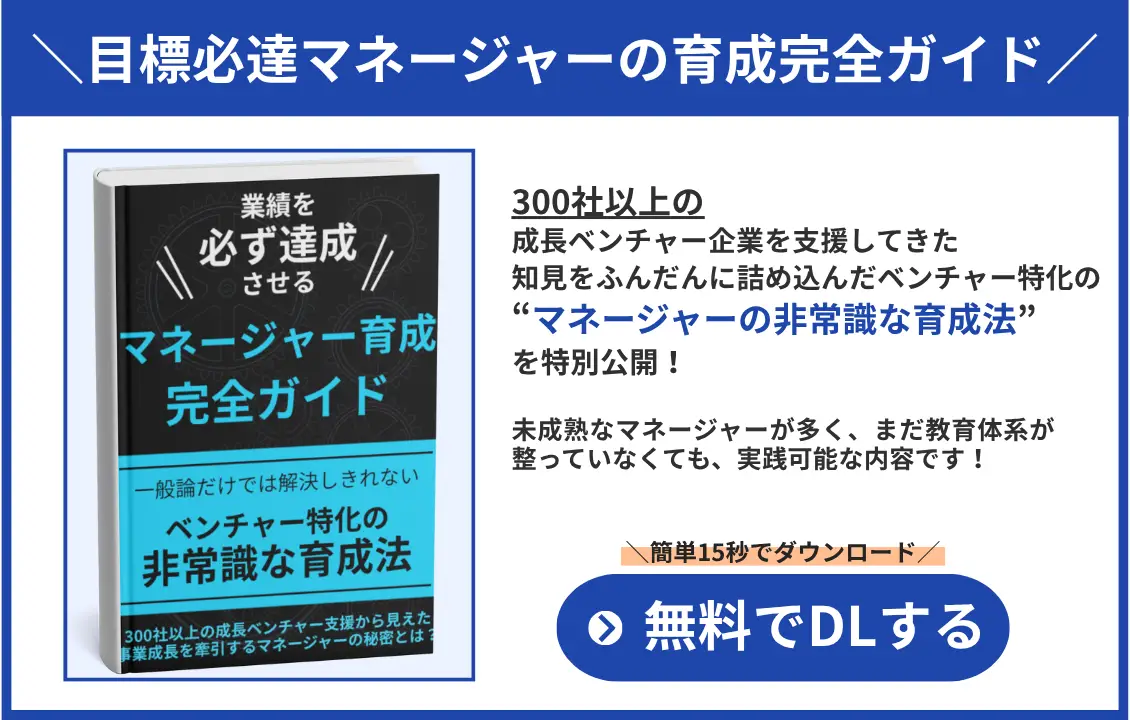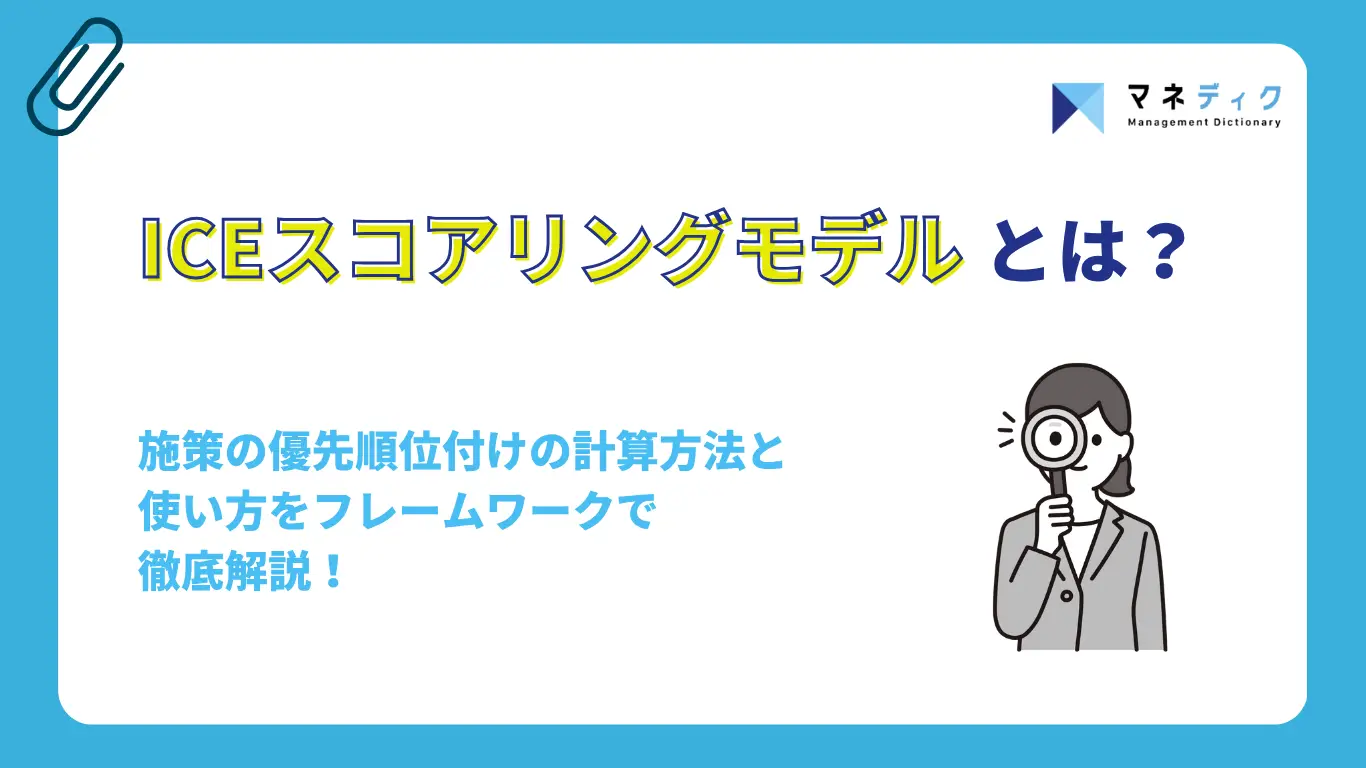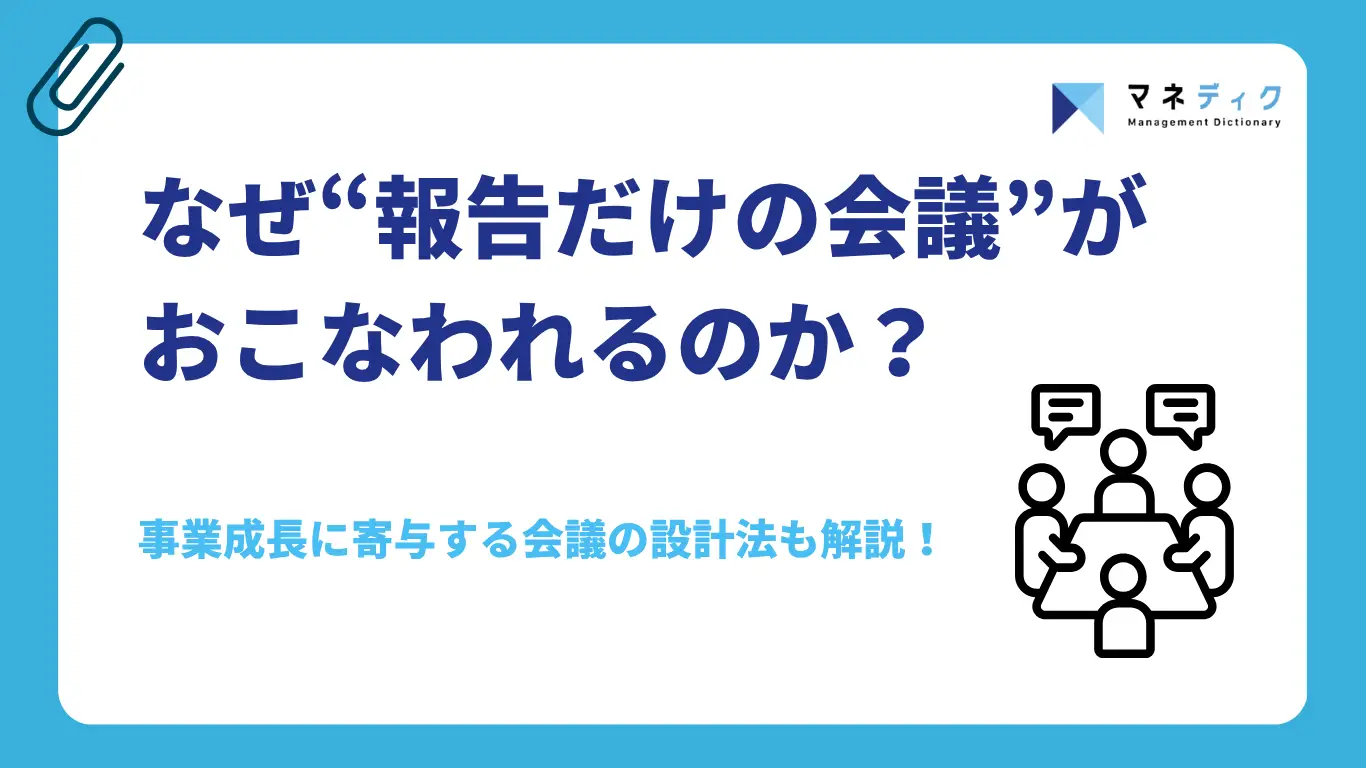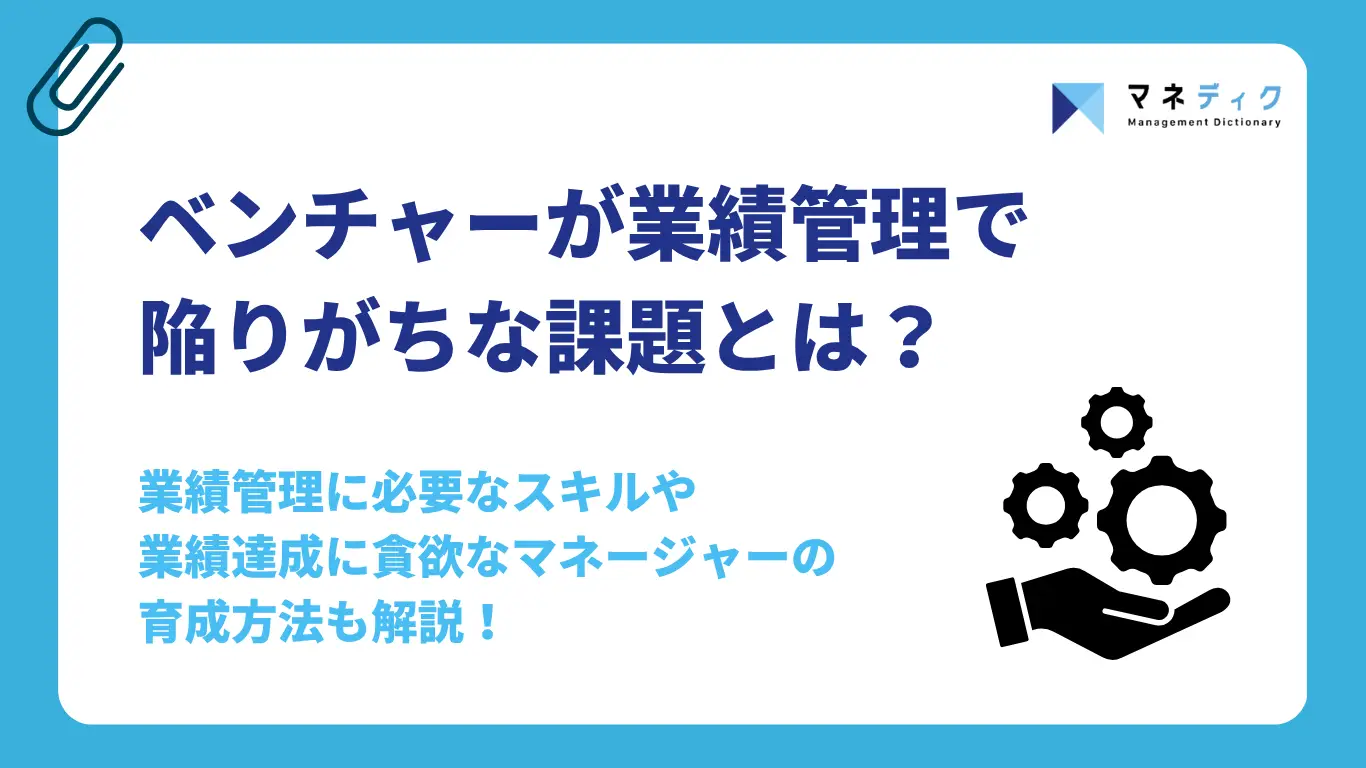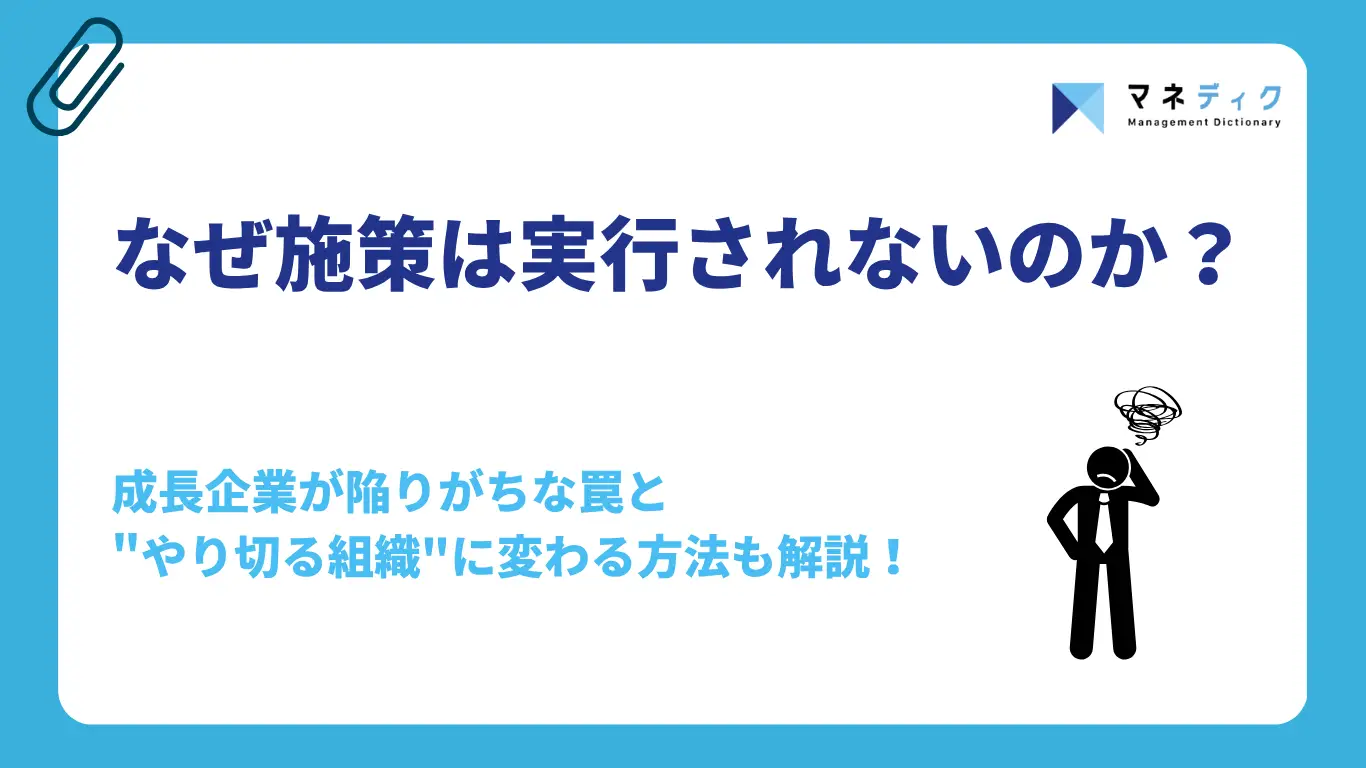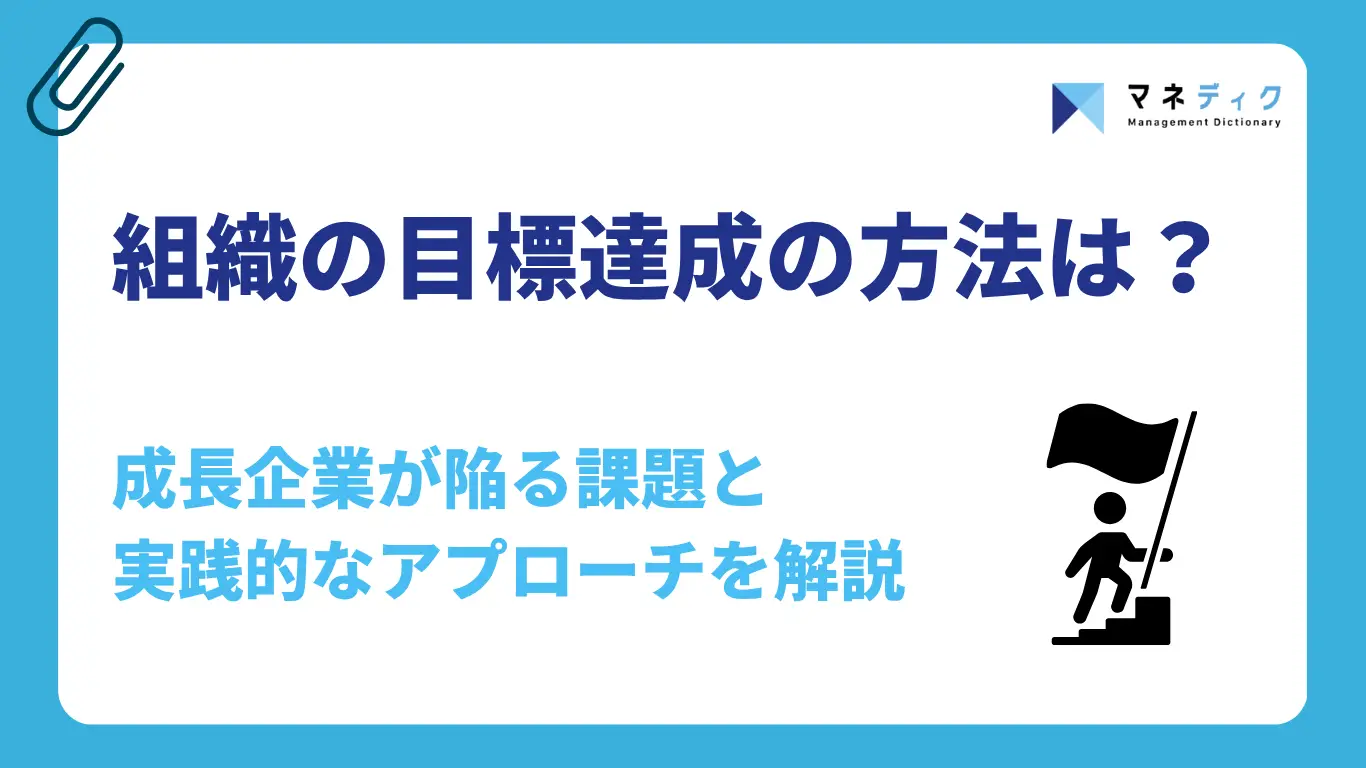目標管理制度の問題点とその解決策について徹底解説!
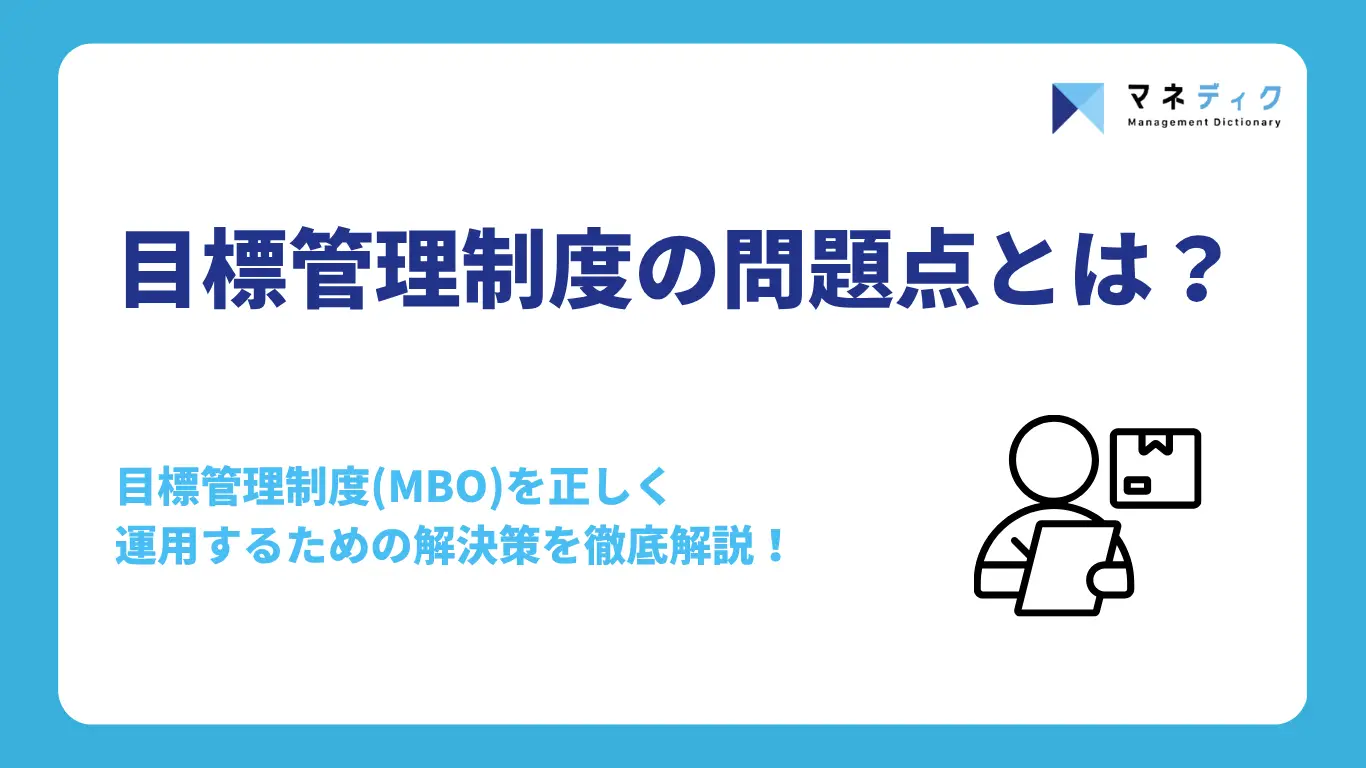
そもそも目標管理制度(MBO)とは?
まず、議論の前提として目標管理制度(MBO)の基本的な定義を再確認します。
目標管理制度(MBO:Management By Objectives)とは、経営学者ピーター・ドラッカーが提唱した組織マネジメントの手法です。
単なるノルマ管理ではなく、従業員が自ら個人目標を設定し、その進捗や達成度を自ら管理することを特徴とします。
目標管理制度(MBO)の目的とメリット
MBOの最大の目的は、企業の目標達成と個人の成長を連動させることにあります。正しく運用されれば、組織と個人双方に大きなメリットをもたらします。
- 従業員の主体性・モチベーションの向上
- 最大のメリットは、従業員が「やらされ仕事」ではなく、自ら目標設定のプロセスに関与する点です。組織目標を理解した上で、自身の役割や貢献を意識して目標を立てるため、達成へのコミットメントや主体性が引き出されます。
- 組織目標の達成と個人の成長
- 全社目標が部門、チーム、そして個人へとブレイクダウンされることで、従業員は自分の業務が組織全体のどの部分に貢献しているかを明確に認識できます。これにより、日々の業務に意義を見出しやすくなり、組織全体の業績向上と個人のスキルアップが両立します。
- 公正な評価基準の明確化
- 目標が具体的に言語化・数値化されるため、「何を達成すれば評価されるのか」という基準が明確になります。これにより、評価の納得感が高まり、上司と部下の間での認識のズレを防ぐ効果も期待できます。
目標管理制度(MBO)のデメリットと限界
一方で、MBOは運用が非常に難しく、多くの企業がそのデメリットや限界に直面しています。
- 制度運用にかかる工数の増大
- 目標設定、中間面談、期末の評価フィードバックといった一連のプロセスは、特に管理職(マネージャー)に膨大な運用工数を強いることになります。多忙なマネージャーがこの工数を確保できず、面談が形式的なものになるケースは少なくありません。
- 目標設定の難易度と質のバラつき
- 従業員や評価者のスキルによって、設定される目標の「質」に大きなバラつきが出ることが課題です。低すぎる目標は成長に繋がりませんし、高すぎる目標はモチベーションの低下を招きます。適切な難易度の目標を設定し続けることは容易ではありません。
- 短期的な成果主義への偏り
- MBOは、評価と報酬を連動させやすいため、どうしても「今期の目標達成」という短期的な成果ばかりが重視されがちです。その結果、時間のかかる人材育成や、イノベーションに向けた長期的な取り組みが軽視される危険性をはらんでいます。
目標管理制度(MBO)が抱える5つの問題点
前述のデメリットに加え、目標管理制度(MBO)という仕組み自体が、その構造上「問題点」を抱えやすいという側面があります。
多くの企業が「うまく運用できない」と悩むのは、この構造的問題点に起因することが多いのです。
問題点1:目標の「質」が評価者のスキルに依存する
目標管理制度の問題点の1つ目は、目標の「質」が評価者のスキルに依存することです。
MBOの成否は、現場の管理職(マネージャー)のスキルに大きく依存します。部下の能力を見極め、適切な難易度の目標を設定し、ビジョンと連動するように導く能力が求められます。
しかし、この「目標設定スキル」や「フィードバックスキル」が不足している場合、部下は納得感のある目標を持つことができません。結果として、制度全体への不信感に繋がります。
問題点2:「ノルマ管理」と誤解され、主体性が失われる
目標管理制度の問題点の2つ目は、「ノルマ管理」と誤解され、主体性が失われることです。
MBOは本来、部下の主体性を引き出すための仕組みです。しかし、運用を誤ると、単なる「ノルマ管理」のツールになってしまいます。
上司が一方的に目標を「押し付け」、進捗を厳しく「管理」するだけでは、部下は自ら考えることをやめてしまいます。ドラッカーが意図した「自己管理(セルフコントロール)」とは正反対の状態に陥ります。
問題点1と通ずる部分もありますが、目標管理制度(MBO)の運用は管理職・マネージャー自身のスキルの有無によって意味のないものに変わってしまいます。
以下の資料で、業績成長をしていくうえでマネージャーに必要なスキル、そしてそんなマネージャーの育成法を実践的な内容で解説しているので、マネージャー育成に課題を感じられているベンチャー経営者の方はぜひダウンロードしてご活用ください。
問題点3:評価への意識が強すぎ、挑戦が生まれにくい
目標管理制度の問題点の3つ目は、評価への意識が強すぎ、挑戦が生まれにくいことです。
「目標の達成度=評価・報酬」という側面が強すぎると、従業員は合理的な行動を取ります。それは、「達成可能な、低い目標」を設定することです。
目標を100%達成することが最優先となり、本来組織の成長に必要な「挑戦的な目標(ストレッチゴール)」が設定されなくなります。
失敗を恐れるあまり、組織全体が保守的になるリスクは、MBOの最大の構造的問題点と言えます。
問題点4:個人の目標が「部分最適」に陥りやすい
目標管理制度の問題点の4つ目は、個人の目標が「部分最適」に陥りやすいことです。
MBOは「個人」の目標達成に焦点が当たりやすいため、組織全体としての連携が疎かになることがあります。
各従業員が自身の目標達成のみを追求した結果、部署間の連携が失われたり、セクショナリズム(部署最適)が助長されたりするケースです。
個人最適の積み重ねが、必ずしも組織全体の「全体最適」になるとは限らないのです。
問題点5:制度の運用自体が目的化する
目標管理制度の問題点の5つ目は、制度の運用自体が目的化することです。
これは目標管理制度(MBO)だけに限った話ではありませんが、制度は正しくその目的を伝えられていなかったり、腹落ち感がないとその運用自体が目的化してしまいます。
MBOを導入・運用すること自体が目的化し、本来の「業績向上」や「人材育成」という目的が見失われることも重大な問題点です。
期日までに目標管理シートを「埋める」ことがタスクとなり、その内容については誰も深く議論しない。このような「制度のための仕事」が増えれば、現場の従業員が「目標管理はくだらない」と感じるのも無理はありません。
目標管理制度が形骸化してしまう根本原因
前述した問題点は、いわば「制度自体の問題点」にすぎません。なぜこれらの事象が起きるのか、経営者として向き合うべき「根本原因」はさらに奥深くにあります。
制度が機能しない本質的な原因は、次の2つに集約されます。
原因1:目標管理の「仕組み」より「カルチャー」が未熟
多くの経営者が誤解している点ですが、MBOやOKRは「仕組み」である以前に、それを支える「カルチャー」がなければ絶対に機能しません。
ここでいうカルチャーとは「〇〇な状況では△△のように動く」という組織の中で統一された行動様式のことを指します。どれほど優れた戦略や目標管理制度などのツール、優秀な人材がいても、結局実行の質を担保するのはカルチャーになります。
例えば、「挑戦を推奨し、失敗から学ぶ」というカルチャーが浸透していない組織にOKRを導入しても、誰も挑戦的な目標は設定しません。
統一された行動様式、つまり「組織のOS」であるカルチャーこそが、あらゆる仕組みの土台となります。
原因2:管理職(マネージャー)が制度を運用しきれていない
制度の成否を握る「ボトルネック」は、いつだって管理職(マネージャー)です。
経営ビジョンを現場の言葉に「翻訳」し、部下の目標設定を支援し、日々の進捗を管理する。この重要な役割をマネージャーが果たせていない、あるいはそのためのスキルが不足している場合、制度は必ず現場で詰まります。
管理職・マネージャーの視座・当事者意識が低いと、「経営層が言うから仕方ない」「とりあえず目標下ろそう」というように腹落ち感が生まれないまま、MBOが使われ、結果形骸化してしまうといったことになりかねません。
先ほどの原因1で述べた「カルチャーの浸透」において重要な役割を担うのも経営と現場をつなぐ管理職・マネージャーになります。マネージャーがどれだけ高い視座を持ち、組織の当事者になれるかが事業成長の可否を決定すると言っても過言ではありません。
そしてまずは、チーム・事業の目標達成にコミットするマネージャーの育成が急務です。
以下の「目標必達マネージャーの育成完全ガイド」では、これまで成長ベンチャー企業を300社以上ご支援させていただいた経験・知見をもとに、事業の目標達成にコミットするマネージャーの育成方法を具体的に解説しております。
ぜひダウンロードをして、貴社のマネージャー育成にお役立てください。
事業成長を加速させる目標管理制度の運用法
では、これらの問題点や根本原因を踏まえ、経営者自身は明日から何をすべきか。
制度を「捨てる」のではなく、事業成長のために「活かす」ための具体的な解決プランを3つご紹介していきます。
解決策1:評価(査定)面談と目標設定(育成)の場を完全に分離する
まず実行すべきは、「評価」と「育成」の分離です。「達成率=評価」という構図が、挑戦しない風土を生む諸悪の根源だからです。
特にベンチャー企業だと、目標が流動的に変わることが日常的に起きうるかと思います。
評価(査定)は半期に一度行うとしても、目標設定や進捗確認(1on1など)は、あくまで「事業成長」と「個人の育成」のための場として再定義し、評価とは切り離して運用することを強く推奨します。
そのため、あらかじめ「目標達成率だけで評価はしないこと」は合意しておき、評価面談の場では目標達成率に加え組織・事業に対するその他の貢献も評価項目に入れてあげる設計にするのが良いでしょう。
解決策2:OKRを「ビジョン連動のツール」として正しく導入し直す
MBOの弱点を補うのがOKR(Objectives and Key Results)です。OKRは目標管理制度(MBO)と比べて、挑戦的な目標を設定して組織全体のモチベーション上げをすることが主な目的です。
OKRを正しく導入するとは、「ビジョンと全社目標が、現場の個人目標まで一本の線で繋がっている状態」を作ることです。
評価と切り離し、「挑戦的な目標(O)」と「連動した計測可能な指標(KR)」を、経営者から現場まで浸透させることが重要です。
解決策3:マネージャーの「目標翻訳スキル」を育成する
目標管理制度を事業成長に正しく向かうために運用するには、前述の通りマネージャーが鍵を握っています。
経営者がマネージャーに対して「何のための目標か」を語った上で、マネージャーがそれを「現場のタスク」レベルまで具体的に翻訳し、部下の目標に落とし込むスキルが不可欠です。
この「目標翻訳スキル」と「運用力(1on1スキル)」は、外部の力も活用して、徹底的に鍛えるべき経営投資です。そのためにまずは、経営者自身が直下のマネージャーに対して、掲げている目標の意義・意味を腹落ちするレベルで伝達して、『自分ごと化』してもらうことが先決です。
組織で目標達成をしていくための具体的な方法に関しては、以下の記事でも詳細に解説しているのでご興味ある方はぜひご覧ください。
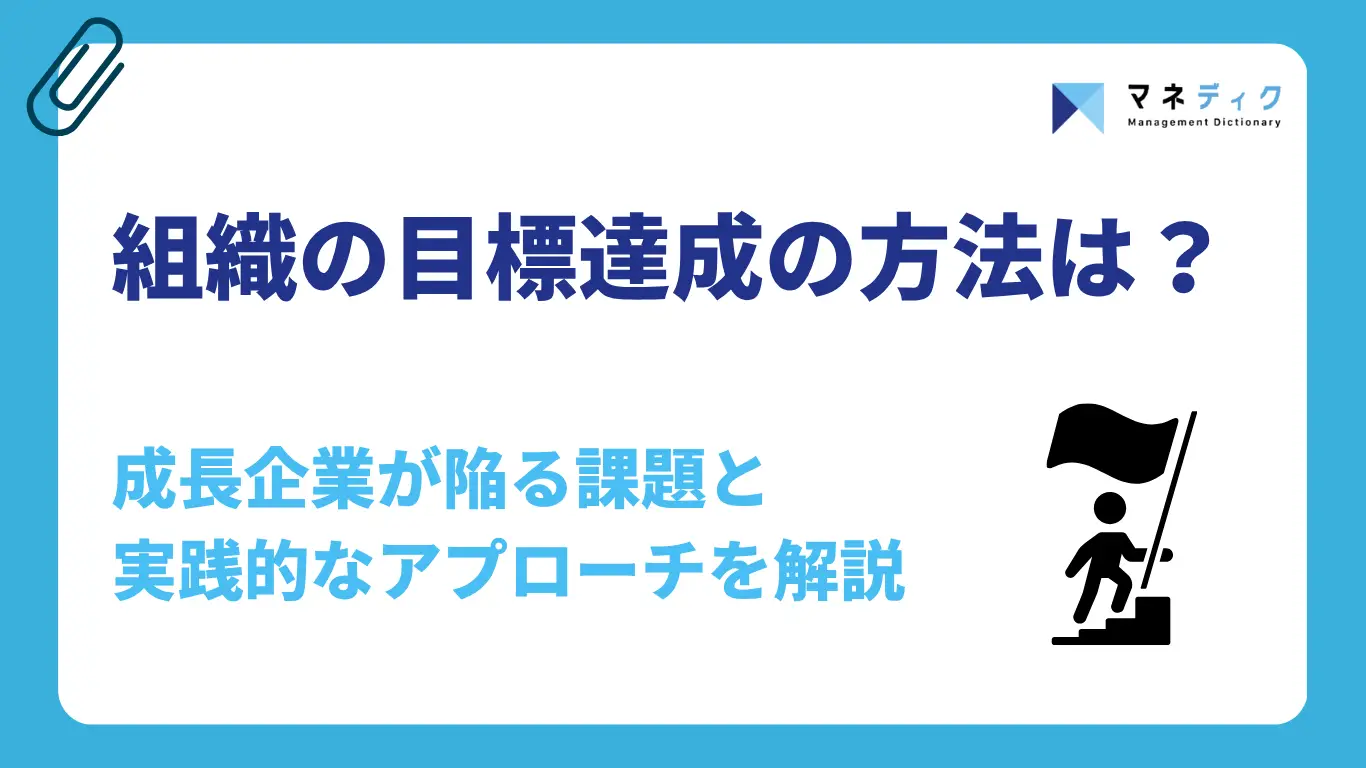
目標管理制度の問題に関するよくある質問
Q1:目標管理制度が「時代遅れ」と言われる理由は?
「時代遅れ」と言われる主な理由は、変化のスピードにあります。
従来のMBOが持つ「半期や通期」といった長いスパンでの目標設定が、現代の目まぐるしい市場や事業戦略の変化に追いつかなくなっているためです。
また、個人の価値観が多様化し、会社からの一律の目標設定が機能しにくくなっている側面もあります。
Q2:目標管理制度の廃止を検討すべきサインは?
以下のようなサインが見られたら、制度の抜本的な見直しや廃止を検討すべきです。
- ほぼ全員が「達成率100%」になるよう、低い目標しか設定しない。
- 期末の評価時期以外、誰も目標管理シートを開かない。
目標の進捗について、上司と部下の間で会話が一切ない。
「制度のための仕事」が増え、現場から不満が噴出している。
Q3:目標管理制度によるモチベーション低下を防ぐには?
最も重要なのは、目標の「押し付け」をやめることです。
会社や上司からの一方的な目標(Must)だけではなく、従業員本人がキャリアで実現したいこと(Will)と、目標をすり合わせるプロセスが不可欠です。
本人の「やりたいこと」と会社の「やってほしいこと」が重なる部分を見つける支援こそが、モチベーションの源泉となります。
Q4:MBOとOKRの根本的な違いは何ですか?
MBO(目標管理制度)が主に「個人の業績評価(管理)」のツールとして使われることが多いのに対し、OKRは「組織全体の目標達成(連動と挑戦)」のためのツールである点が根本的に異なります。
OKRは、評価とは切り離し、ビジョン実現のために組織と個人が挑戦的な目標にアラインメント(連動)することを最重要視します。