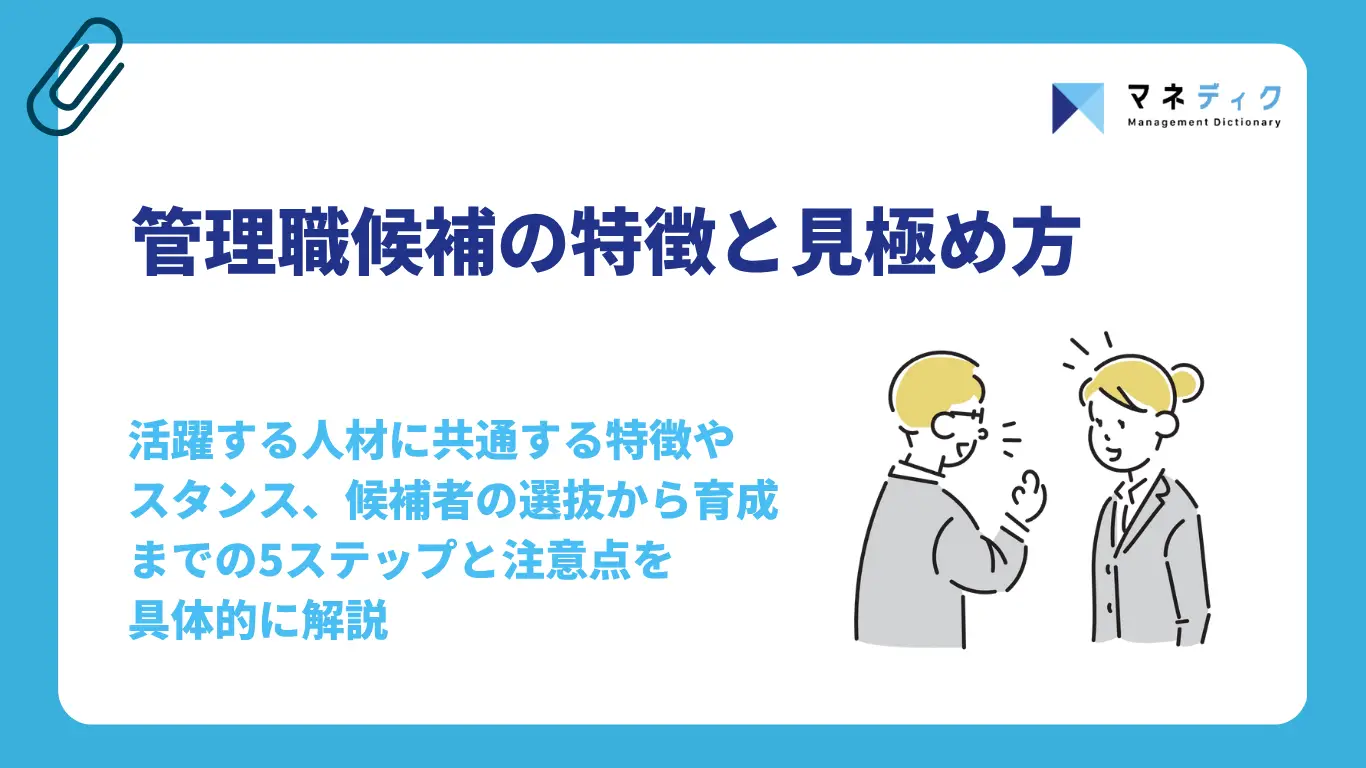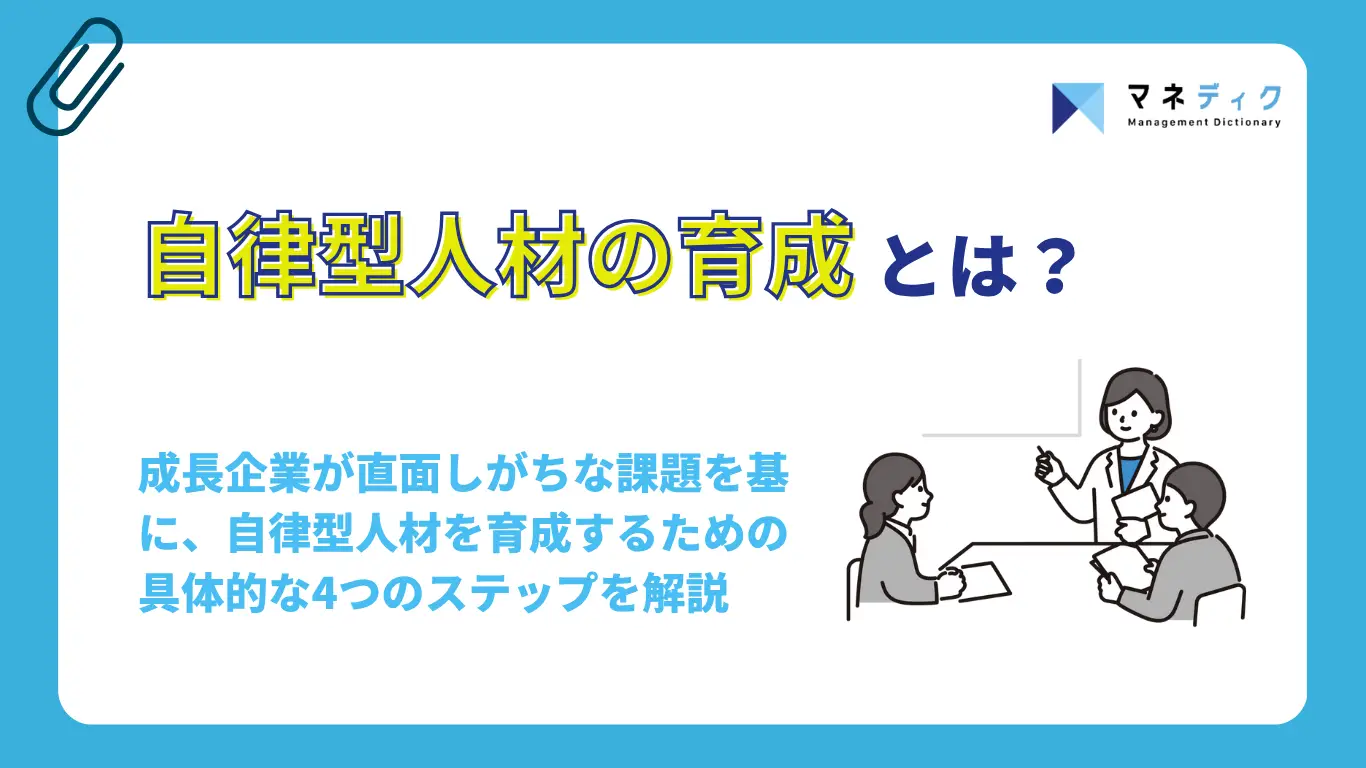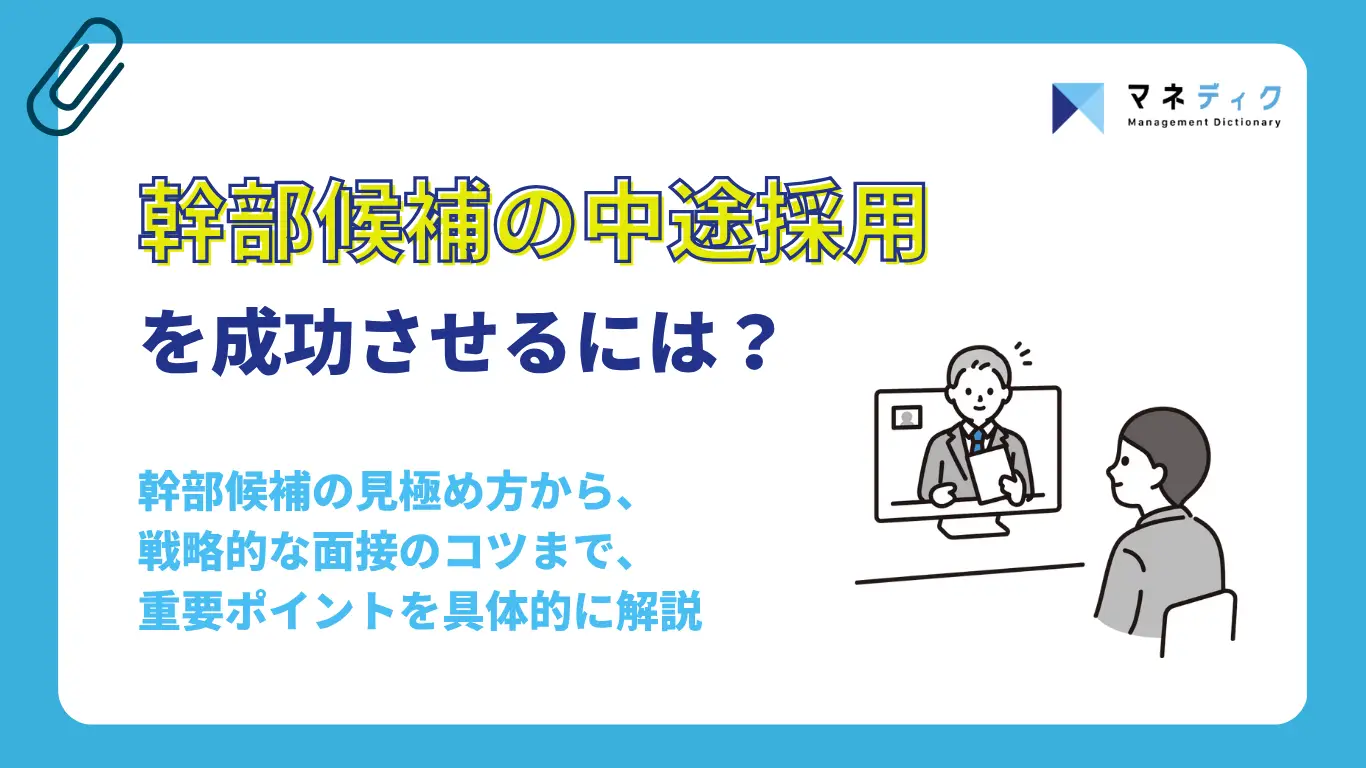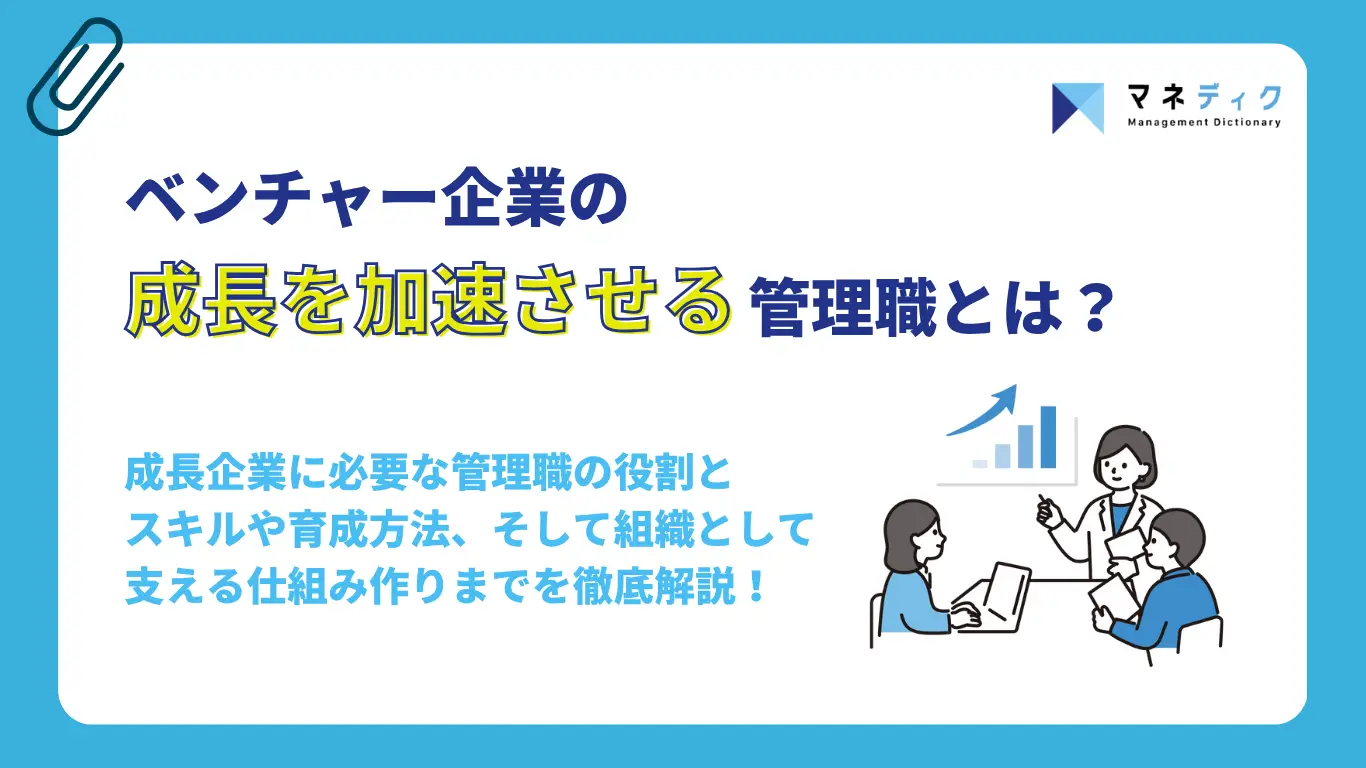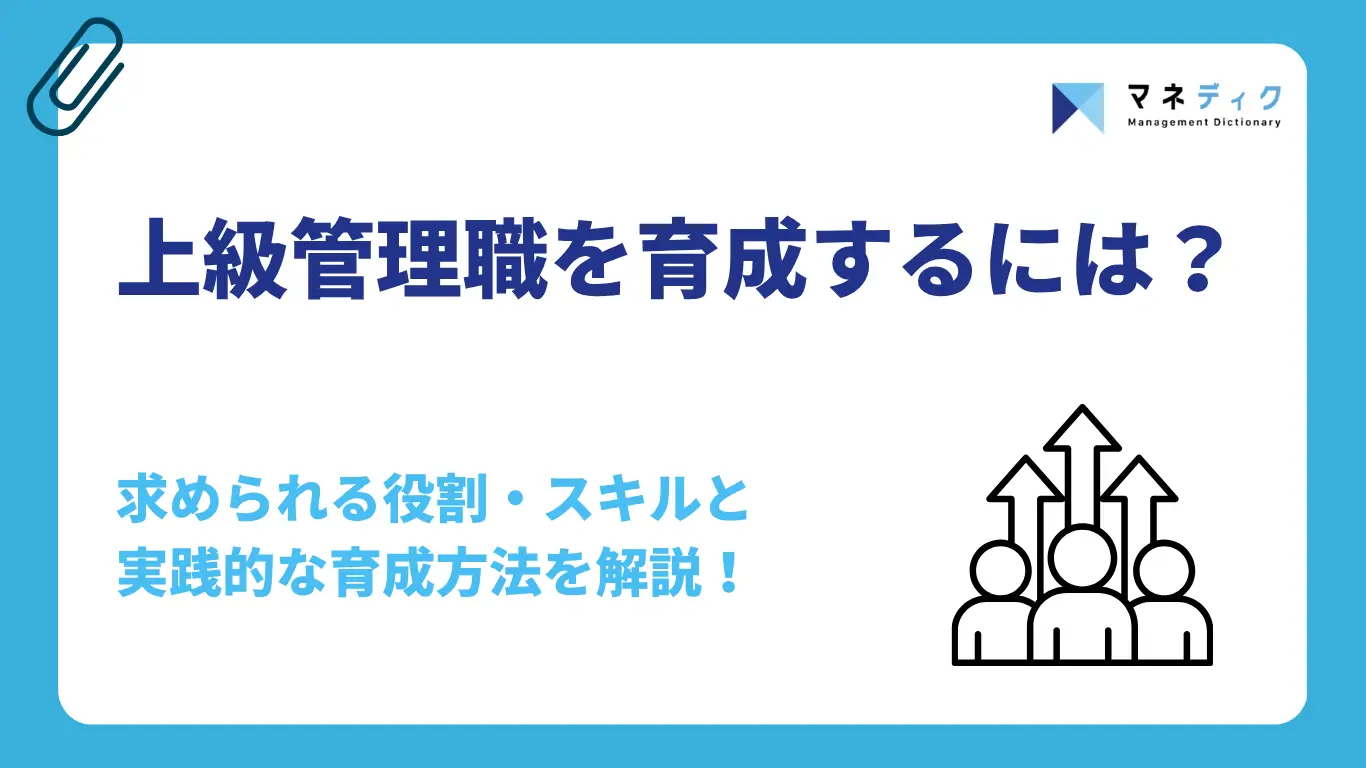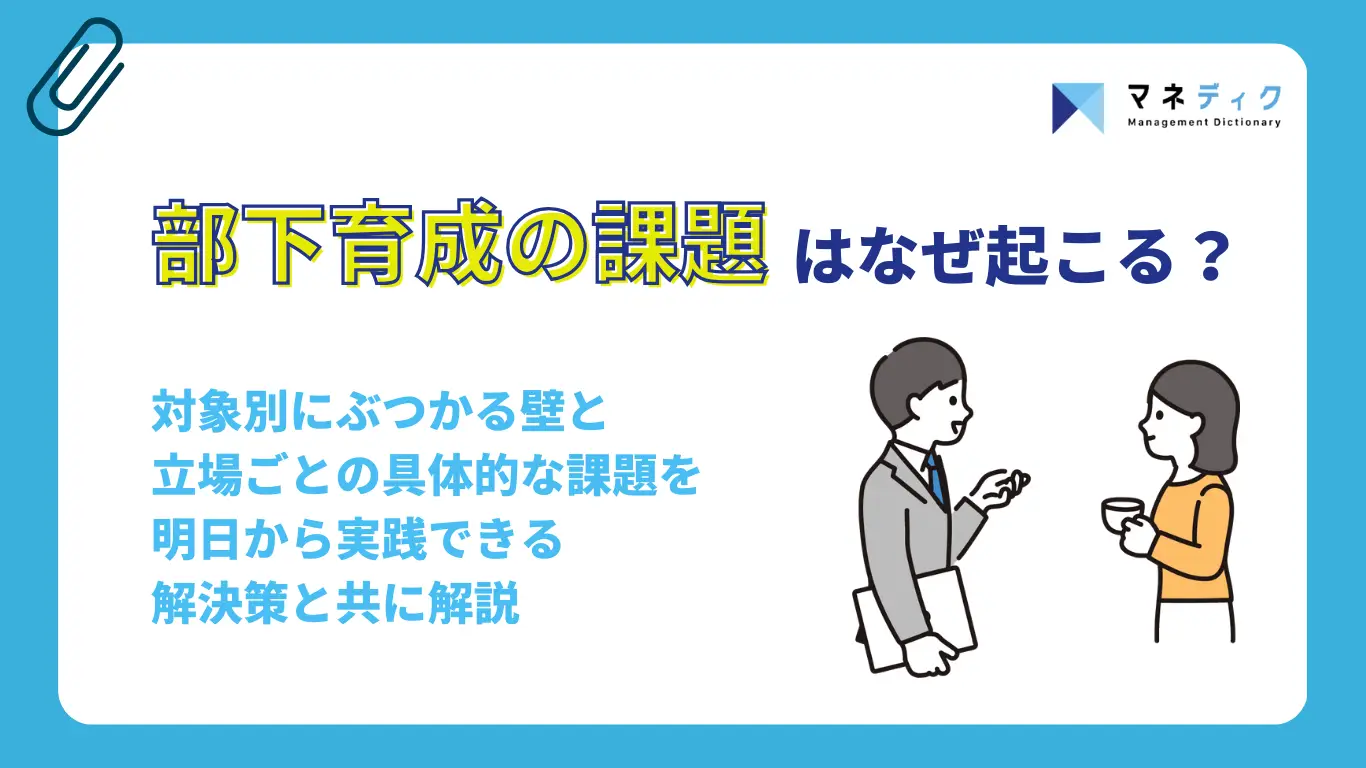ベンチャーでのマネージャー抜擢方法は?失敗しない選定基準と育成法も解説
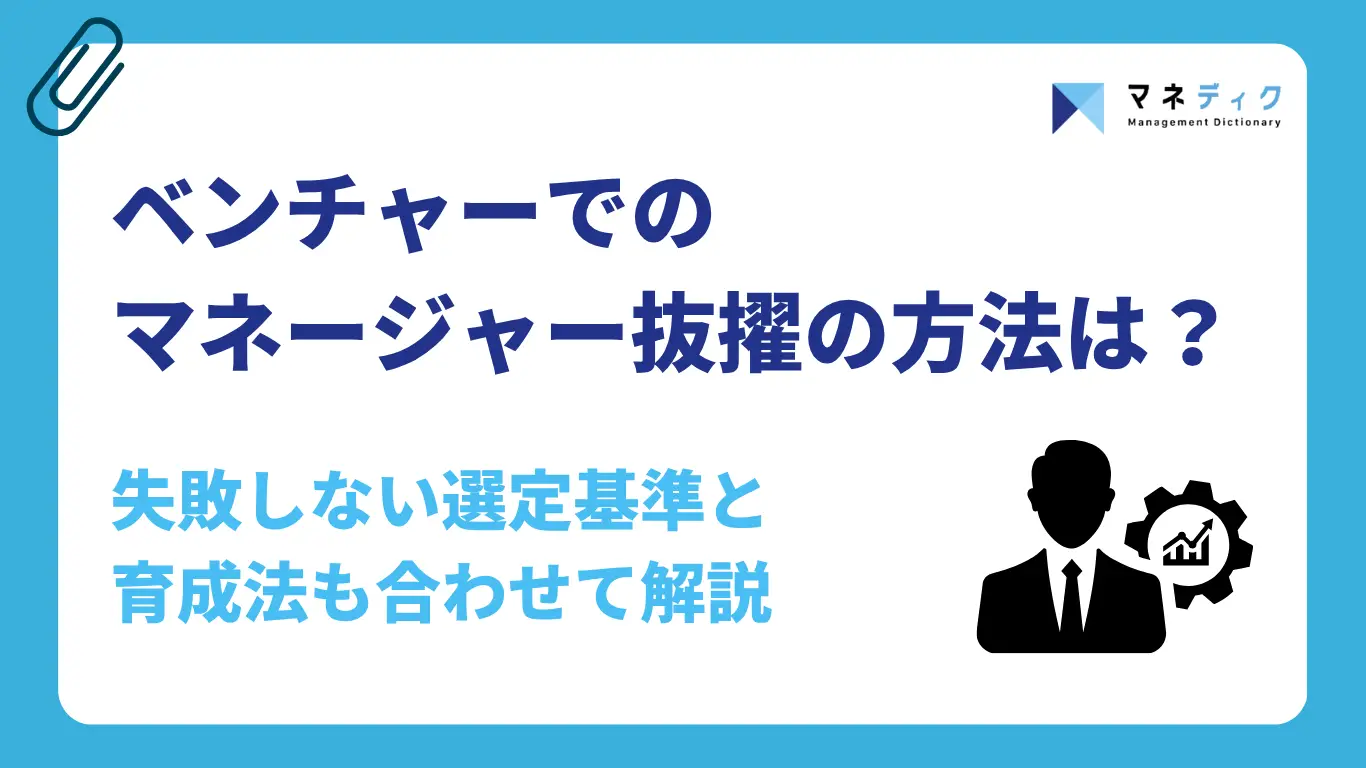
ベンチャー企業でマネージャーを抜擢する際に陥りがちな失敗例
事業の成長を願い、期待を込めて行ったはずのマネージャー抜擢が、なぜか上手くいかない・機能しないというケースは少なくありません。
特に、事業の方向性が頻繁に変わる流動性の高いベンチャーでは、大企業と同じような抜擢をしていては、組織の歪みを生むだけです。
ここでは、成長ベンチャーでマネージャーを抜擢する際に、特に陥りがちな3つの失敗パターンを解説します。
失敗パターン1:トッププレイヤーを安易に抜擢してしまう
よくある失敗の1つ目が「トッププレイヤーを安易に抜擢してしまう」ことです。
「営業成績がトップだから」「エンジニアとして技術力が高いから」という理由は、一見すると最も合理的です。
しかし、これが最大の罠です。個人のプレイングスキルと、チームを率いるマネジメントスキルは全くの別物で「名選手、必ずしも名監督にあらず」です。
ベンチャーでは、エースプレイヤーは事業の生命線です。その人材をマネージャーにすることで、チームから最強のプレイヤーが一人いなくなるという損失も同時に発生します。
本人は得意なプレイングの癖が抜けず、メンバーの仕事に手を出してしまい、結果的に育成を阻害する。これは、会社にとって二重の損失となります。
失敗パターン2:抜擢基準が曖昧で、言語化されていない
よくある失敗例の2つ目が「抜擢基準が曖昧で、言語化されていない」ことです。
「あいつはリーダーシップがありそうだ」「そろそろ役職をつけないと辞めてしまうかもしれない」といった、期待や不安、温情といった感覚的な理由で抜擢を決めてしまっている場合は大抵マネジメントが機能しません。
事業のスピードを優先するあまり、抜擢の基準を言語化するプロセスを飛ばしてしまう。これはベンチャーでよく見られる光景です。
しかし、基準なき抜擢は「社長の好き嫌いで決まる」という不信感を組織に蔓延させます。抜擢された本人も、何を期待されているのかが不明確なため、プレッシャーだけを感じて空回りしてしまいます。
失敗パターン3:抜擢した後のサポート体制がない
よくある失敗例の3つ目が「抜擢した後のサポート体制がない」ことです。
「マネージャーに任命したのだから、あとはよろしく」という丸投げ。これも、リソースの限られたベンチャーで頻発する失敗です。
大企業のように手厚い研修制度がないのは当然です。しかし、意図的なサポートがないまま放置された新任マネージャーは、上からは事業目標のプレッシャー、下からはメンバーの突き上げを受け、板挟み状態で孤立します。
特に未経験者の場合、誰にも相談できずに一人で抱え込み、バーンアウトしてしまう。これは抜擢ではなく、もはや「放置」です。
抜擢の前に定義すべき「マネージャーの役割」とは?
抜擢の失敗を防ぐための第一歩は、基準を考える前に「自社にとってのマネージャーの役割は何か」を明確に定義することです。
企業の成長フェーズや組織文化によって、マネージャーに求められる役割は大きく異なります。
特に、朝令暮改も厭わない変化の激しいベンチャーにおいては、以下の3つの役割が極めて重要になります。
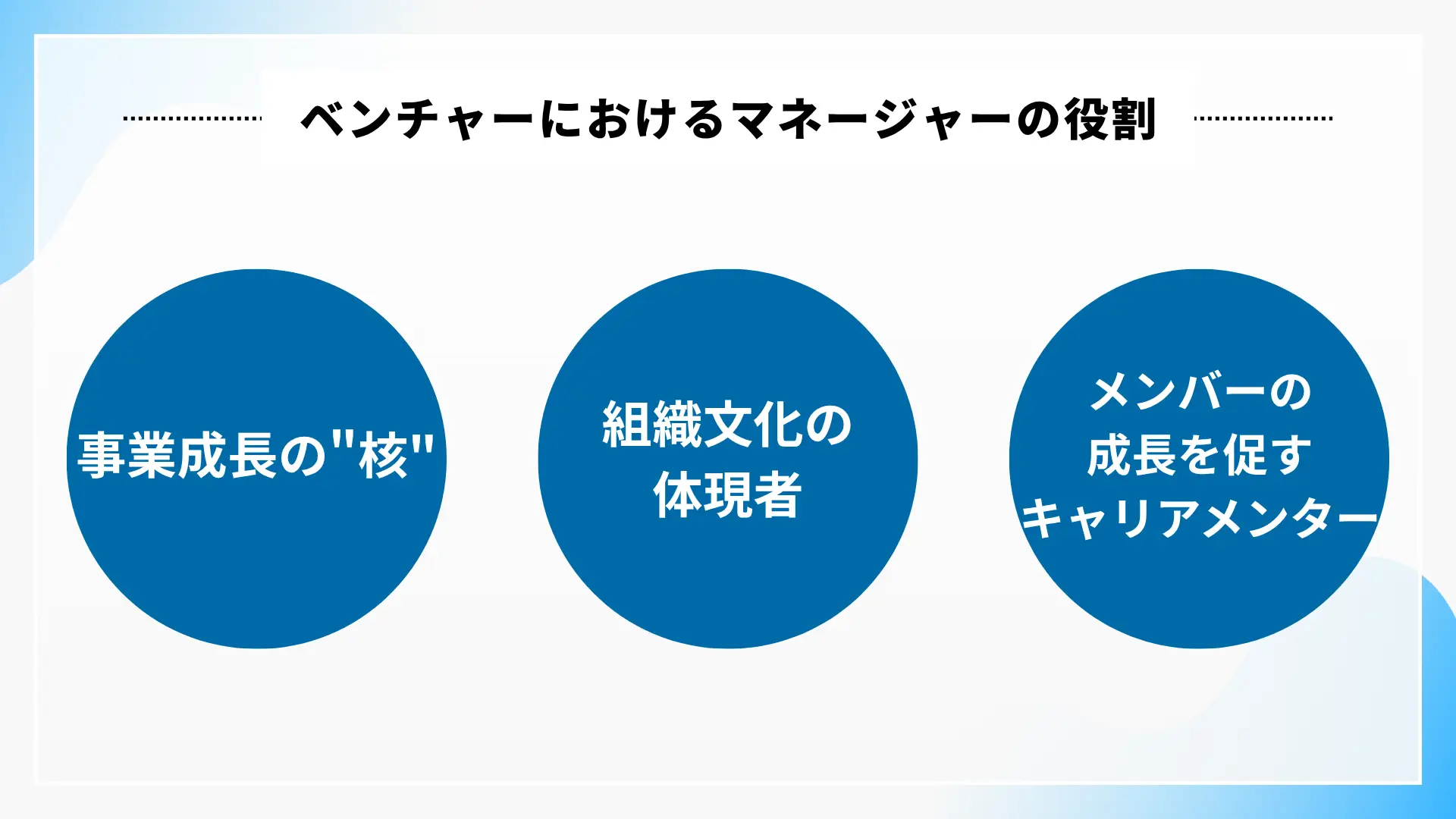
それぞれ詳しく解説していきます。
ただ各企業で大切にされている価値観や目指す方向性が違うので、成長ベンチャー企業に共通する汎用的かつ若干抽象的な内容になっているので、ご了承ください。
役割1:事業成長の"核"としての役割
マネージャーは、単なる「現場のまとめ役」ではありません。
ベンチャー企業におけるマネージャーは、経営陣が描く事業戦略を深く理解し、それを現場の戦術に落とし込み、チームの目標達成に強くコミットする存在でなければなりません。
要は、そのチーム・組織で最もコミットメントが高い人材でなければなりません。
変化する市場環境の中で、KPI達成はもちろんのこと、常に事業全体の視点を持ち、指示を待つのではなく自ら課題を発見し、解決策を実行する「ミニCEO」としての動きが求められます。
役割2:組織文化の体現者としての役割
経営者の想いやビジョン、価値観(カルチャー)は、マネージャーを通じて現場に浸透していきます。
特に組織が急拡大するベンチャーでは、カルチャーは簡単に薄まります。
マネージャー自身が誰よりも組織文化や経営理念を理解し、日々の言動で体現する「翻訳者」でなければなりません。
メンバーが判断に迷った時、その拠り所となるのは、マニュアルではなくマネージャーの姿勢そのものです。
役割3:メンバーの成長を促すキャリアメンターとしての役割
ベンチャーのマネージャーには、メンバー一人ひとりの強みや才能を見出し、その成長を支援する役割が強く求められます。
というのも、成長ベンチャー企業に入ってくるメンバーは成長意欲の高いメンバーが多く、逆にこの環境では成長できないと感じられると簡単に離職してしまいます。そのため、いかに成長を実感させ続けられるかが重要です。
固定化された役割分担に固執せず、メンバーの隠れた才能を見つけて新たなミッションを任せるなど、個人の成長と事業の成長をダイナミックに結びつける動きが、組織のポテンシャルを最大化させます。
【チェックリスト付】失敗しないためのマネージャー抜擢基準
自社におけるマネージャーの役割を定義できたら、次はいよいよ具体的な抜擢基準を定めます。
ここでは、候補者の「スキル(能力)」と「スタンス(姿勢)」の2つの側面から評価するためのチェックリストを紹介します。
このリストを基に、自社独自の基準へとカスタマイズしてみてください。
スキル面:見極めるべき3つの能力
チェック項目 | 見極めのポイント(ベンチャー特有の視点) | |
1 | 課題発見・解決能力 | 指示待ちではなく、自ら課題を見つけ出し、定義できるか。情報が不十分な中でも、仮説を立てて行動し、解決策を導き出せるか。 |
2 | コミュニケーション能力 | 事業の「なぜ」を自分の言葉で語り、メンバーを動機づけられるか。複雑な状況をシンプルに整理し、率直なフィードバックを恐れないか。 |
3 | プロジェクトマネジメント能力 | 不確実な状況下で、大胆な優先順位付けができるか。限られたリソース(人・モノ・金)を、事業インパクトが最大化するポイントに集中投下できるか。 |
スタンス面:最も重要な5つの姿勢
スキル以上に重要視すべきなのが、仕事に対する姿勢や価値観です。
特に変化の激しいベンチャーにおいては、以下のスタンスを持つ人材こそが、マネージャーとして活躍する可能性を秘めています。
チェック項目 | 見極めのポイント(ベンチャー特有の視点) | |
1 | 当事者意識 | チームや会社で起きた問題を「自分ごと」として捉え、「それは自分の仕事ではない」という言葉を使わないか。役割の範囲を超えてでもボールを拾いに行くか。 |
2 | 誠実さ | 自分の間違いを素直に認め、他責にしないか。良い情報も悪い情報も、隠さずに迅速かつ正確に上司に報告できるか。 |
3 | 成長意欲 | 過去の成功体験をアンラーン(学習棄却)し、新しいやり方を貪欲に吸収できるか。自分より優秀なメンバーの意見を素直に聞き入れられるか。 |
4 | 変化への柔軟性(曖昧耐性) | 仕様変更や方針転換を「成長の機会」とポジティブに捉えられるか。ルールやフローが未整備なカオスな状況を楽しめるか。 |
5 | 利他性 | 自分の成功よりも、チームやメンバーの成功を自分のことのように喜べるか。スポットライトをメンバーに当てることができるか。 |
マネージャーにしてはいけない人の3つの特徴
抜擢基準と合わせて、候補者が「マネージャーにしてはいけない人」の特徴に当てはまらないかを確認することも極めて重要です。
どんなにスキルが高くても、以下のような特徴を持つ人材を抜擢すると、組織に深刻なダメージを与える可能性があります。
特徴1:自己の成果にしか興味がない
いわゆる「自分本位なエース」タイプです。
チームの目標達成やメンバーの成長よりも、自分の手柄や評価を優先します。
このような人材がマネージャーになると、メンバーを「自分の目標達成のための駒」としか見なさないため、マイクロマネジメントに走り、成果を独り占めします。
結果、優秀なメンバーから愛想を尽くされ、チームは崩壊へと向かいます。
特徴2:他責思考で、自分の非を認めない
何か問題が起きた際に、「環境が悪い」「部下が使えない」「指示が曖昧だった」など、原因を自分以外の他に求めるタイプです。
ベンチャーでは問題が起きるのが当たり前。その度に他責にするマネージャーの下では、誰もリスクを取って挑戦しなくなります。
このような態度は、メンバーからの信頼を著しく損ない、「この人にはついていけない」という空気をチームに蔓延させます。
特徴3:感情のコントロールができない
その日の気分によって指示がころころ変わったり、気に入らないことがあるとメンバーを高圧的な態度で叱責したりするタイプです。
このようなマネージャーの下では、メンバーは常に顔色を伺い、萎縮してしまいます。
心理的安全性が確保されていないチームでは、活発な議論やイノベーションは絶対に生まれません。
抜擢を成功に導くための具体的な4ステップ
抜擢基準が固まったら、次はその基準に沿って、丁寧なプロセスを踏みましょう。
一方的な通達ではなく、候補者本人や周囲のメンバーの納得感をいかに醸成するかが重要です。
ステップ1:候補者のリストアップと多角的な評価
まずは、作成した基準を基に、候補者となりうる人材をリストアップします。
その際、経営者や特定の上司一人の視点だけで判断するのは危険です。
同僚や他部署のメンバーなど、複数の関係者から候補者の仕事ぶりや評判についてヒアリングし、「あの人は、困難な状況でどう振る舞っていたか?」といった具体的なエピソードを集め、多角的な視点で評価することが重要です。
ステップ2:候補者との1on1での意思確認と期待値調整
候補者を絞り込んだら、1on1の場で本人と直接対話します。
ここでは、本人のキャリア観やマネジメントへの意欲を確認すると同時に、会社が期待する役割を具体的に伝える「期待値調整」が最も重要です。
【ベンチャー経営者向け・覚悟を引き出す質問例】
- 「もし、事業の方向性が明日180度変わったら、チームをどう導く?」
- 「目標達成のために、今のチームに足りないものは何だと思う?それをどう解決する?」
- 「マネージャーとして、自分個人の成果よりも、チームの成果を優先できるか?」
【会話例】
経営者: 「〇〇さん、いつも事業への貢献ありがとう。今回は、〇〇さんの今後のキャリアについて、少し大事な話をしたいと思って時間をもらいました。単刀直入に言うと、会社として、新しく立ち上げる△△チームのマネージャーを〇〇さんに任せたいと考えています。」
経営者: 「もちろん、これは決定事項ではなく、まずは〇〇さんの意思を聞かせてほしい。マネジメントという役割について、率直にどう思う?」
経営者: 「(本人の意思を確認した後)ありがとう。もし引き受けてもらえるなら、会社として期待したい役割が3つある。1つ目は…。2つ目は…。そして3つ目は…。特に、うちのようなベンチャーでは、予測できない問題が次々に起こる。そのカオスな状況を楽しみながら、チームを率いてほしい。大変な役割だと思うけど、会社としても全力でサポートするつもりだ。どうかな?」
ステップ3:抜擢の背景と期待を全社に伝える
本人の内諾を得たら、辞令を出すタイミングで、なぜその人を抜擢したのか、その背景と会社としての期待を、経営者自身の言葉で全社に説明します。
特に、抜擢基準のどの項目を高く評価したのかを具体的に伝えることで、他の社員にとっても「どういう行動が評価されるのか」という明確なメッセージとなり、組織全体の成長を促します。
ステップ4:抜擢直後の手厚いオンボーディング
抜擢後の最初の1ヶ月が、新任マネージャーの成否を分ける最も重要な期間です。
この期間は、経営者や人事が週に1回など、高い頻度で1on1を実施し、「何か困っていることはないか」「誰にも言えない悩みはないか」を丁寧にキャッチアップしましょう。
CEOとの「共同操縦」期間と位置づけ、重要な意思決定を一緒に行うなど、孤独にさせないことが何よりも重要です。
新任マネージャーの成長を支える育成・サポート体制
マネージャーの抜擢は、ゴールではなく、未来の組織を創るためのスタートラインです。
特にマネジメント未経験者を抜擢した場合は、その成長を継続的に支援する仕組みが、組織全体の成長角度を決定づけます。
経営陣との定期的な壁打ち
新任マネージャーが経営視点を養うためには、経営陣と対等に議論する場が不可欠です。
担当チームの課題だけでなく、全社的な事業課題や組織課題について、経営陣と定期的に壁打ちする機会を設けましょう。
これにより、視座が高まり、より戦略的な意思決定ができるようになります。
マネージャー同士が学び合う場の提供
新任マネージャーが抱える悩みは、他のマネージャーも同じように経験してきた道です。
マネージャー同士が部署の垣根を越えて、悩みを共有し、成功事例を学び合う「マネージャー会」などを定期的に開催しましょう。
横の繋がりが、孤立を防ぎ、互いに切磋琢磨する文化を醸成します。
外部研修や書籍購入補助などの学習機会の提供
OJT(現場での実践)だけでなく、マネジメントの原理原則を体系的に学ぶ機会を提供することも重要です。
外部のマネジメント研修に参加させたり、関連書籍の購入を会社として補助したりすることで、本人の学習意欲をサポートし、成長を加速させることができます。
ベンチャーのマネージャー抜擢に関してよくある質問
最後に、成長ベンチャーの経営者からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。
Q1. マネジメント経験のない若手を抜擢しても大丈夫でしょうか?
A1. はい、問題ありません。むしろ、成長ベンチャーにおいては必要不可欠な判断です。
重要なのは過去の経験ではなく、未来のポテンシャルです。本記事で解説した「スキル」と「スタンス」の基準、特に「スタンス」面をクリアしているのであれば、積極的に抜擢すべきです。
ただし、その際は「抜擢した後の手厚いサポート」が絶対条件です。経営者がメンターとなり、二人三脚で成功体験を積ませる覚悟が求められます。
Q2. 抜擢を打診した本人に断られた場合はどうすればよいですか?
A2. 無理強いは絶対に禁物です。まずは、本人がなぜ断るのか、その理由を真摯に傾聴してください。
「自分にはまだ早い」という自信の無さなのか、「プレイヤーとしてもっと成果を出したい」というキャリア観の違いなのか、理由によって次の打ち手は変わります。
もし自信の無さが原因であれば、会社としてどのようなサポートができるかを具体的に提示し、不安を払拭することが重要です。キャリア観の違いであれば、その意思を尊重し、別の形で会社に貢献してもらう道を一緒に探しましょう。
Q3. 抜擢したマネージャーが上手く機能していない場合、どうすればよいですか?
A3. 「個人の失敗」と断罪する前に、「仕組みの失敗」と捉え、原因を特定することが重要です。
まずは1on1で本人と向き合い、何に困っているのか、どんなサポートが必要なのかを具体的にヒアリングしてください。
期待する役割と本人の認識にズレが生じているのかもしれませんし、単にスキルや知識が不足しているだけかもしれません。原因に応じて、追加の研修機会を提供したり、メンターをつけたり、場合によっては一時的に経営者が業務の一部を巻き取るなどのサポートが必要です。
降格などの判断は、あらゆる手を尽くした後の最終手段と考えるべきです。
本記事のまとめ
本記事では、成長ベンチャーにおけるマネージャー抜擢というテーマについて、具体的な基準から育成方法までを解説しました。
重要なのは、マネージャーの抜擢を単なる「人事異動」ではなく、「会社の未来を創る、最も重要な経営判断」と捉えることです。
抜擢の失敗は、曖昧な基準とサポート不足から生まれる。
成功の鍵は、自社の「あるべきマネージャー像」を言語化すること。
基準はスキル以上に、「誠実さ」や「当事者意識」といったスタンスを重視する。
抜擢はゴールではなくスタート。経営者がコミットする育成の仕組みが不可欠。
もし今、「誰を抜擢すべきか」「どう育てればいいか」と判断に迷っているのであれば、それは当然のことです。その問いは、会社の未来そのものを作る重要な判断です。
我々マネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャーの企業様と共に、その問いに向き合ってきました。マネディクでは、単なるノウハウ提供や形骸化しがちな単発研修は提供していません。
成長ベンチャーに特化した動画教材での「学習」、経営層から管理職までが参加し、会社の価値観を具体的な行動リストに落とし込む「ワークショップ」、そして実践度合いを可視化し、日々の育成に活用する「スキルマップ」を連動させます 。(もちろん課題に合わせて、単発でのご提供・切り売りも可能です。)
このサイクルを通じて「研修をやって終わり」にせず、貴社が自律的に成果を創出し続ける「文化」の定着をサポートします 。
もし「マネージャーを抜擢したいがどのような基準でどのような方法で抜擢すれば良いか分からない」「組織拡大のタイミングで複数の組織課題が起き始めている」などの成長ベンチャー企業特有のお悩みをお持ちでしたら、一度以下から「マネディク」サービス資料をダウンロードして、ご利用のご検討をいただけますと幸いです。