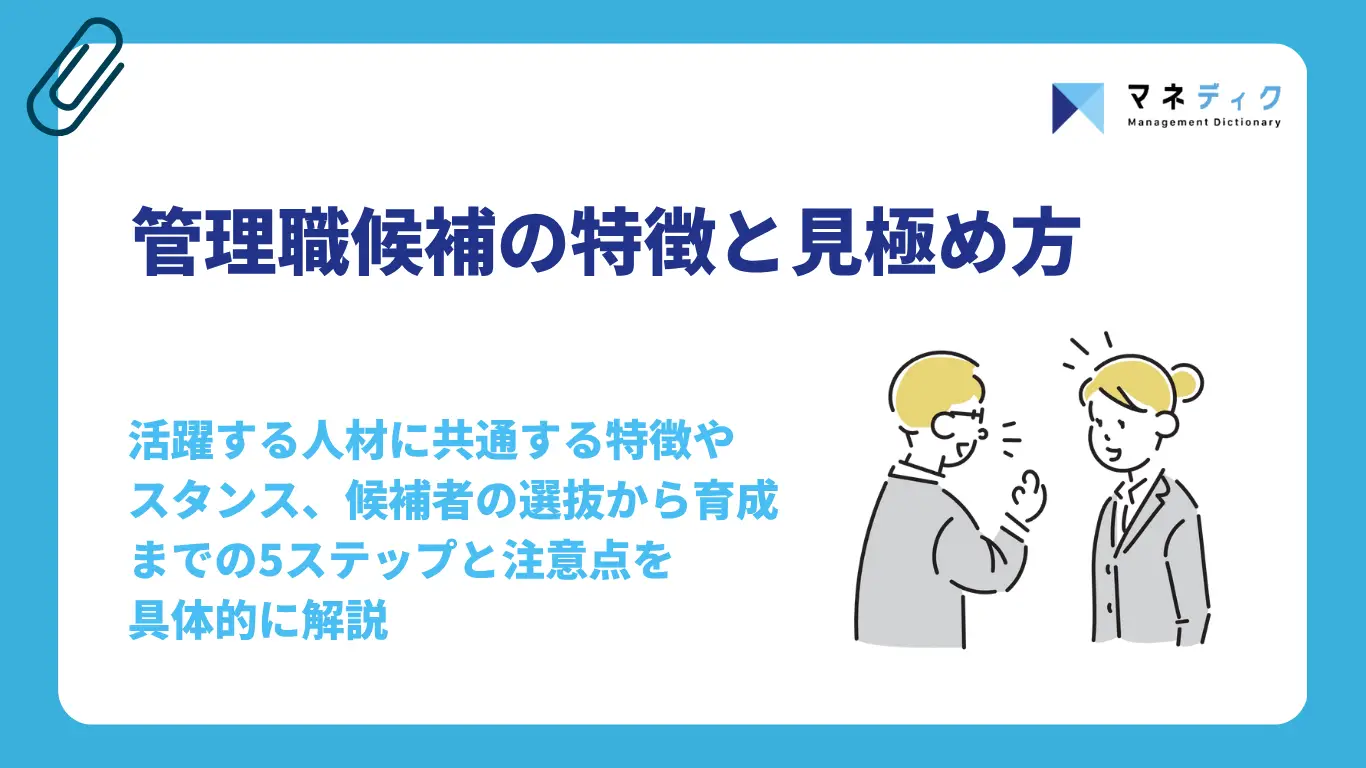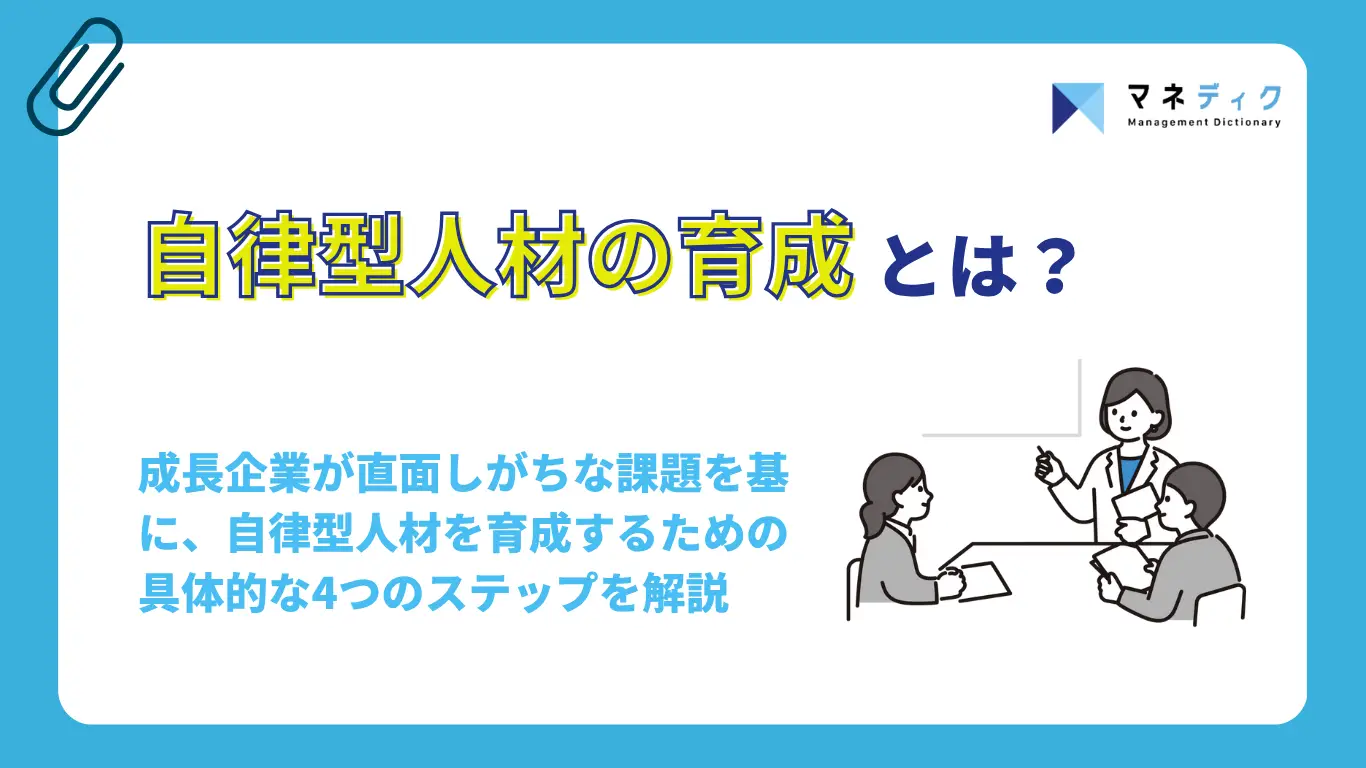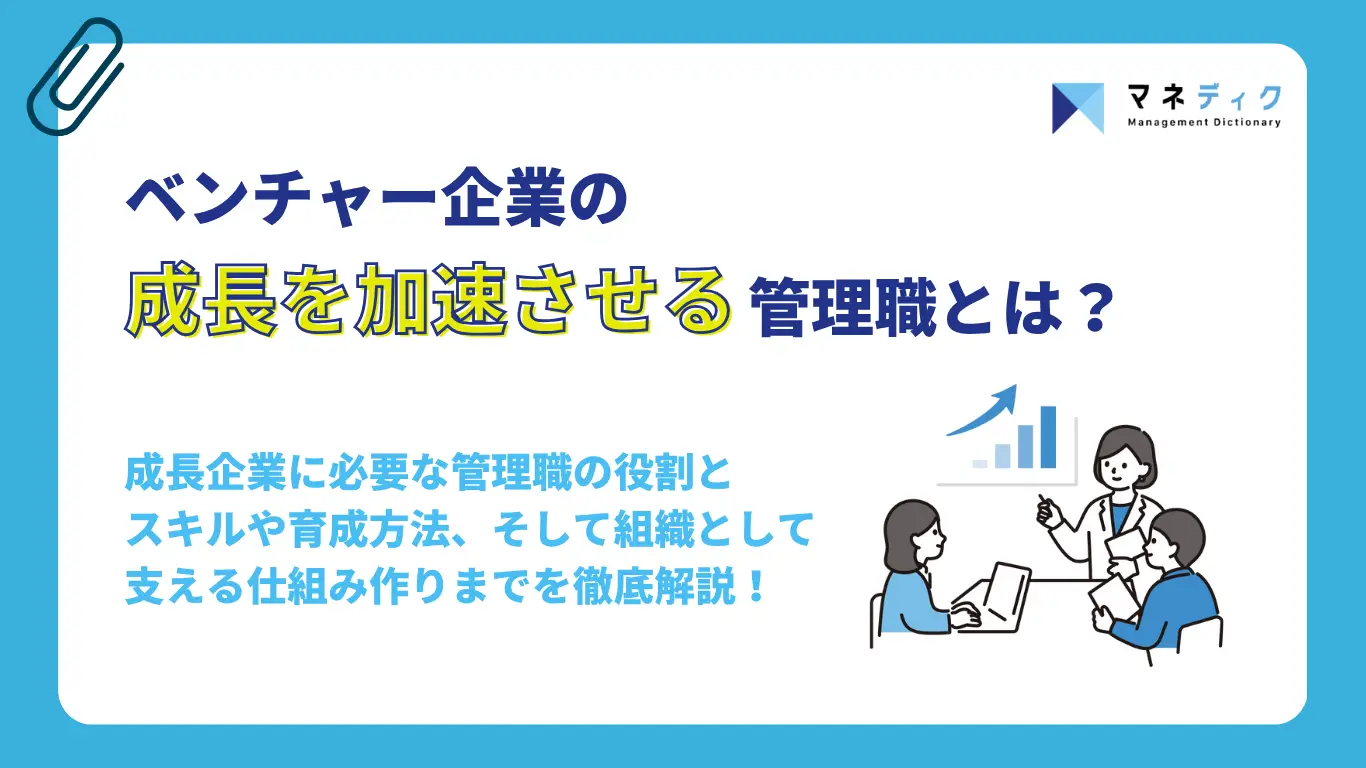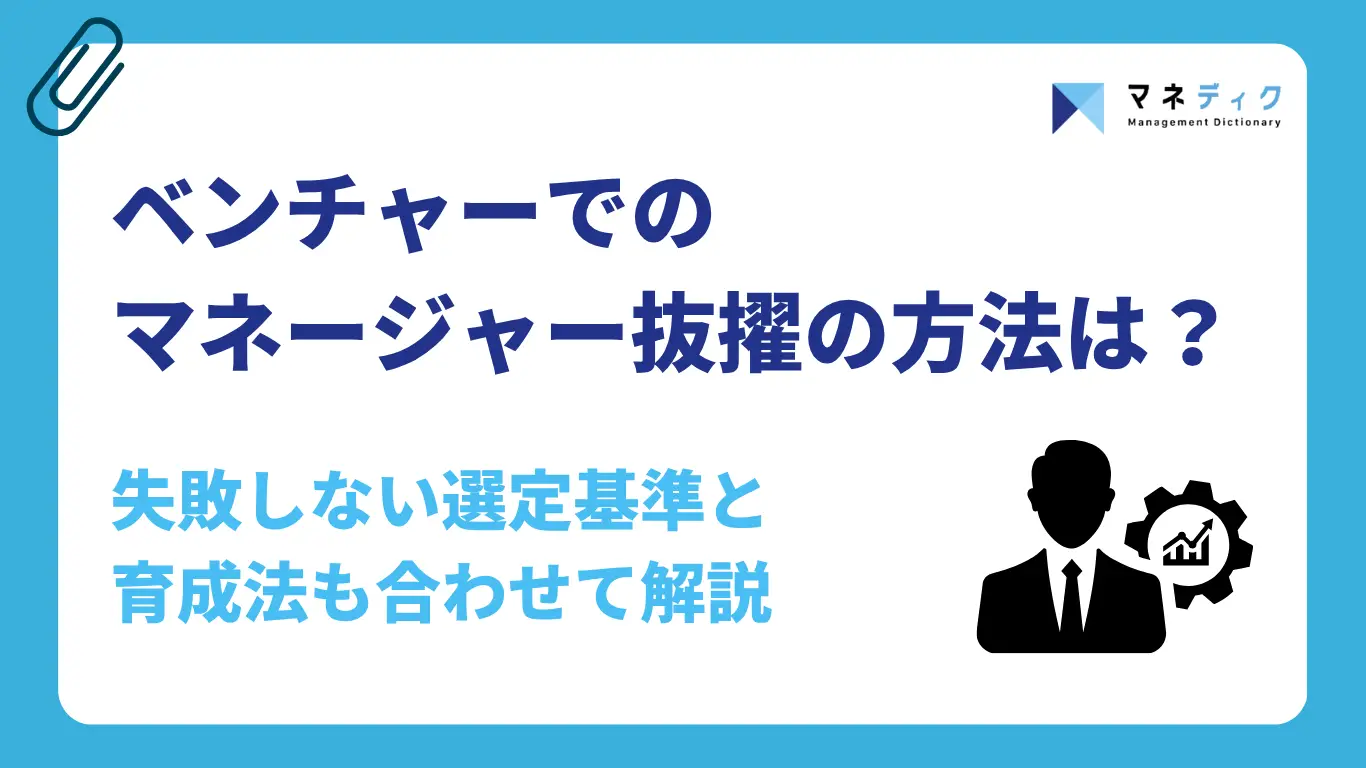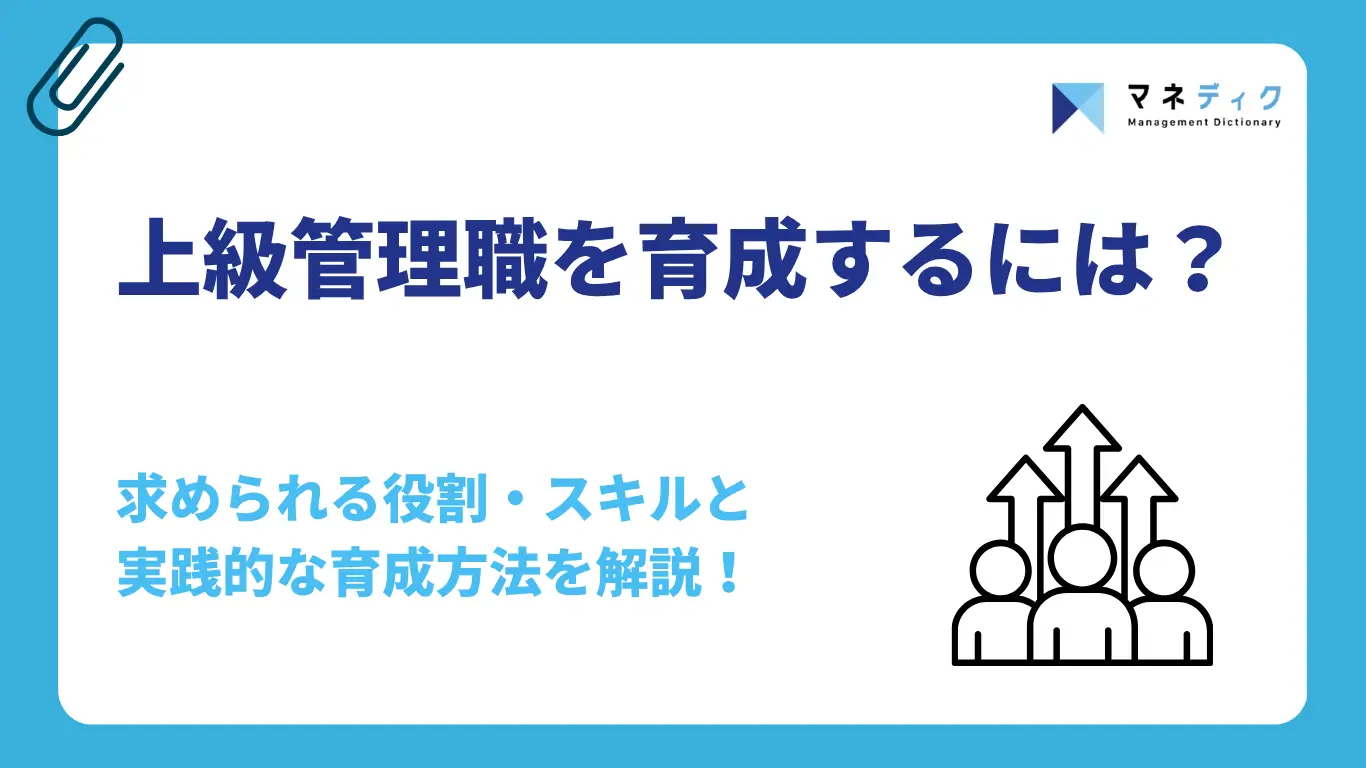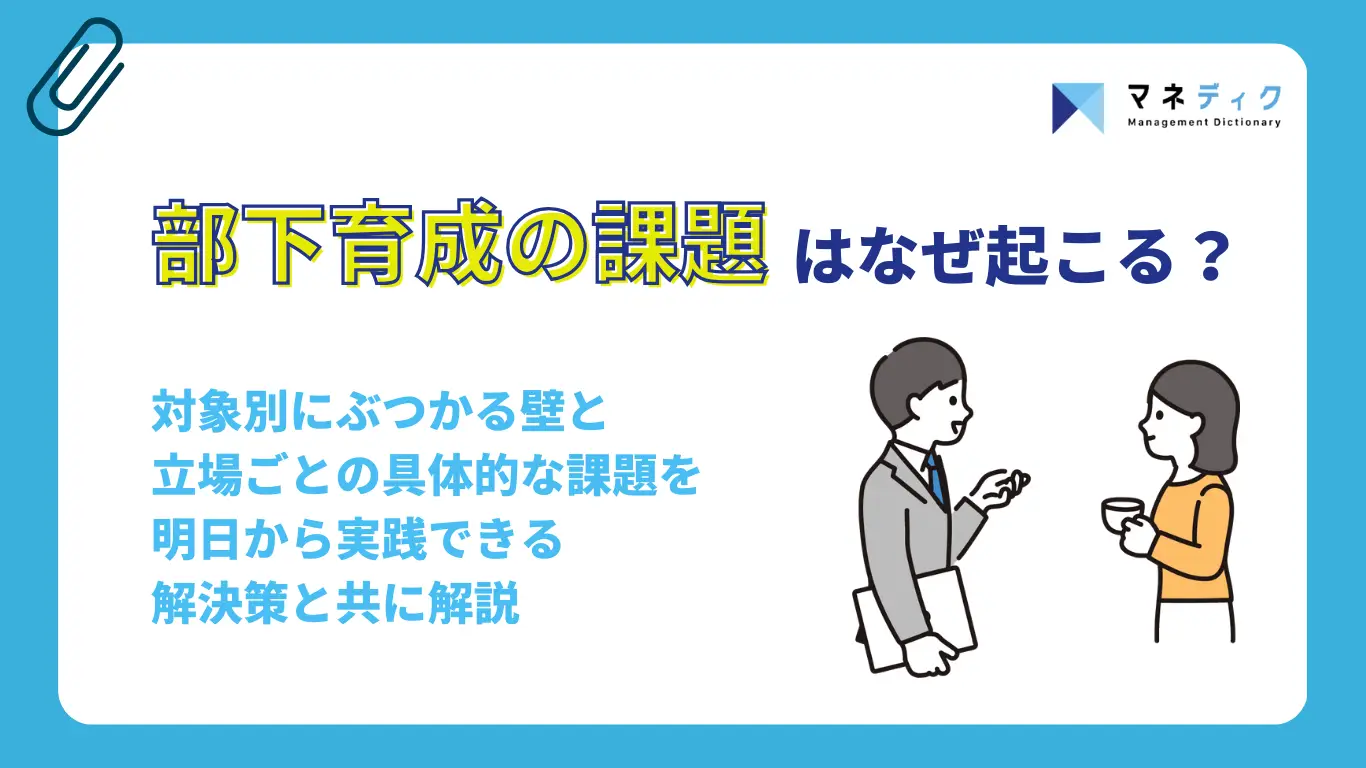幹部候補の中途採用を成功させるには?鍵となる重要ポイントを解説
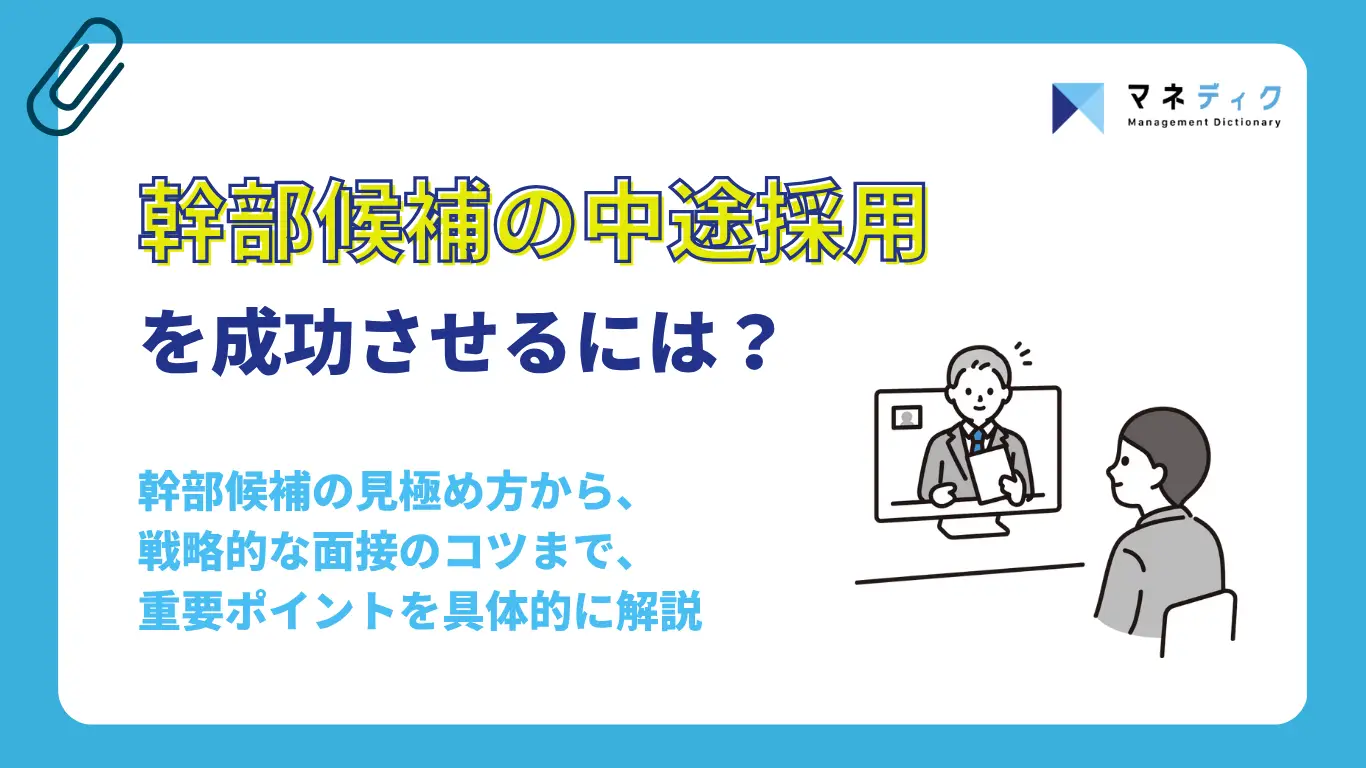
1. そもそも「幹部候補」とは?中途採用で見極めるべき3つの要件
中途採用における「幹部候補」とは、単に優れた実績を持つ「管理職」とは期待される役割が異なります。
管理職が特定のチームや部署のマネジメントを通じて目標達成にコミットするのに対し、幹部候補は将来的に経営層の一員として、事業全体や会社そのものの舵取りを担う視座が求められる人材です。
もちろん、管理職を経験した上で幹部候補となるケースは多くあります。
だからこそ、採用の見極めにおいては、目先のマネジメントスキルだけでなく、「会社全体の課題を自分ごと化できるか」といった、より長期的かつ視座の高い観点が不可欠になります。
採用を成功に導くため、まず最初に、貴社にとっての幹部候補像を明確にすることから始めましょう。
要件1:事業フェーズとカルチャーへの適合性
幹部候補の採用において、スキルや経歴以上にまず確認すべきなのが、自社との適合性です。
中でも特に重要なのは、候補者が自社の「今」と「未来」に適合しているかという点です。
例えば、0→1の創業期で活躍した人材が、組織が拡大する10→100の成長期でも同じように活躍できるとは限りません。事業フェーズによって、求められるリーダーシップのスタイルや意思決定の尺度は全く異なるからです。
自社の事業は今どの段階にあるのか、そして3年後どこを目指しているのか。
その変化に対応し、組織を牽引できる人物かを見極める視点が不可欠です。
要件2:スキルや実績以上の「再現性」と「ポテンシャル」
華々しい実績を持つ候補者でも、その成功が環境の違う企業で再現できるとは限りません。前職のブランド力や潤沢なリソースがあったからこその成功かもしれないのです。
重要なのは、実績そのものではなく、その成果を出すに至った思考プロセスや行動特性に「再現性」があるかです。
特に、大企業から成長ベンチャーへ転職した幹部候補が、新しい環境に適応できずに失敗するケースは少なくありません。具体的には、以下のような失敗例が挙げられます。
⚫︎「評論家」になってしまう:
自身で手を動かさず、課題の指摘や批判に終始してしまう。
リソースが限られる中で、実行よりも分析や戦略ばかりを優先し、現場との温度差が生まれる。
⚫︎過去の成功体験に固執する:
前職で成功した大規模な施策や管理手法を、そのまま導入しようとして失敗する。
事業フェーズや組織文化の違いを考慮できず、現場が混乱する。
⚫︎「待ち」の姿勢が抜けない:
誰かがデータや資料を整えてくれるのを待ってしまい、自ら率先して行動できない。
指示待ちの姿勢が、スピードを重視するベンチャーの文化と衝突する。
このような失敗は、周囲のメンバーとの間に深刻な軋轢を生み、チーム全体のパフォーマンス低下にもつながりかねません。
そのため、成長ベンチャーでは、ルールやフローが未整備な中でも自ら考えて動ける「曖昧耐性」や、新しいことを素早く吸収する「学習能力」などが、過去の実績以上に重要になるのです。
以下の記事ではベンチャーのマネジメント層に必要なスキルを解説していますので、是非ご確認ください。
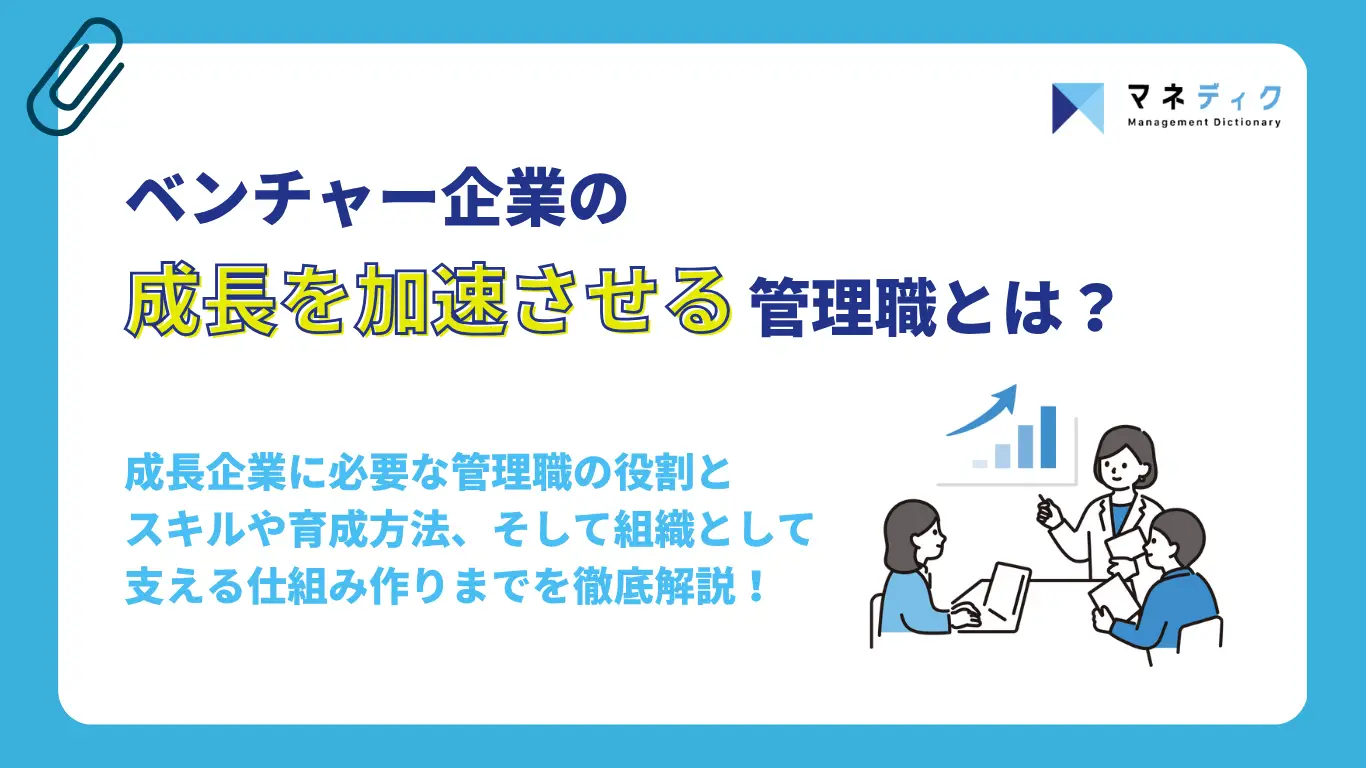
要件3:会社全体を自分ごと化する「当事者意識」
単なる管理職と、未来の経営を担う幹部を分ける決定的な違いは、「当事者意識」の適応範囲です。
自分の部署や役割の範囲だけで仕事をするのではなく、会社全体で起きている課題を自らの課題として捉え、部門を超えて行動できるか。
「それは自分の仕事ではない」という発想がなく、常に全体最適を考えて動ける人物こそ、会社の未来を託するに足る幹部候補と言えるでしょう。このスタンスは、事業を非連続に成長させる上で不可欠な要素です。
2. 幹部候補は「採用」すべきか「育成」すべきか?
幹部候補を確保する手段は、外部からの「採用」だけではありません。
社内の人材を「育成」する選択肢もあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の状況に合わせた最適な判断を下すことが重要です。
中途採用のメリット・デメリット
【メリット】
即戦力性:
育成にかかる時間を短縮でき、スピーディーに経営課題の解決に着手できます。外部の知見:
自社にはない新しいスキルやノウハウ、異なる視点を取り入れることで、組織の変革やイノベーションを促進できます。組織への刺激:
外部から優秀な人材が加わることで、既存社員の刺激となり、組織全体の活性化が期待できます。
【デメリット】
カルチャーフィットのリスク:
どんなに優秀でも、自社の文化や価値観に馴染めなければ、本来のパフォーマンスを発揮できない可能性があります。採用コスト:
ヘッドハンティングなどを利用する場合、採用コストが高額になる傾向があります。既存社員のモチベーション低下:
外部からの登用に、既存社員が不満を感じる可能性があります。
社内育成のメリット・デメリット
【メリット】
カルチャーフィット:
企業文化や価値観を深く理解しているため、ミスマッチのリスクが低いです。エンゲージメント向上:
育成の機会があることは、社員のモチベーションや会社への帰属意識を高めます。採用コストの抑制:
外部採用に比べてコストを抑えられます。
【デメリット】
育成の時間とコスト:
幹部として活躍できるまでには、相応の時間と育成コストがかかります。同質的な組織になるリスク:
内部の論理に偏り、新しい発想や変革が生まれにくくなる可能性があります。候補者不足:
社内に適任者がいない場合もあります。
結論として、事業のスピードを最優先し、外部から幹部候補を入れてでも変革を急ぐフェーズであれば「採用」が、長期的な視点で組織の継続性を重視するならば「育成」が有効と言えるでしょう。
3. 幹部候補の中途採用で陥りがちな課題・注意点
外部からの幹部候補採用は、成功すれば大きなリターンがありますが、一方で特有の難しさも存在します。事前に課題を把握し、対策を講じることが重要です。
採用ミスマッチが事業に与える深刻な影響
一般社員の採用ミスマッチと比べ、幹部候補のミスマッチは事業に与える影響が桁違いに大きくなります。
たとえ入社直後から経営の最終決定に関わるわけではなくとも、彼らは事業の根幹を担う重要なポジションであり、軽率な言動はチーム全体、ひいては事業の方向性に大きな影響を与えます。
そのため、ここでミスマッチが起きると、重要なプロジェクトが停滞するだけでなく、その影響力の大きさゆえに周囲の社員のモチベーションを大きく損ない、組織崩壊の引き金になることさえあります。
転職市場に優秀な候補者が少ない現実
そもそも、企業の未来を託せるほど優秀な人材は、どの企業でも中核を担っており、転職市場に出てくることは稀です。
求人媒体で待っているだけでは、まず出会えません。
そのため、ヘッドハンティングやリファラルなど、企業側から能動的にアプローチしていく採用手法が不可欠になります。
既存社員との軋轢を生む可能性
外部から来た人材が、いきなり自分より上のポジションに就くことに対して、既存社員が反発を感じるのは自然なことです。特に、創業期から会社を支えてきたメンバーがいる場合は、慎重なコミュニケーションが求められます。
全社員でなくても、少なくとも事業部等で関わりがある人には「なぜこの人を迎え入れることにしたのか」「彼(彼女)に何を期待しているのか」を経営者もしくは責任者が自分の言葉で丁寧に説明し、社内の理解を得るプロセスを省略しないようにしましょう。
4. 幹部候補の中途採用を成功に導くための事前準備
幹部候補の採用を成功させる上で最も重要なのが、候補者探しを始める「前」の段階にあります。
経営陣の間で採用の目的や期待値を明確にすり合わせておくことで、入社後の活躍を確かなものにし、最高のスタートを切ることができます。
ミッション定義と期待値の言語化
「どんなスキルが必要か?」を議論する前に、まず「そのポジションで、3年後に何を成し遂げてほしいのか?」というミッションを具体的に言語化することが重要です。
なぜなら、ミッションが曖昧なままでは、採用された幹部候補と経営陣の間で「成功の定義」がズレてしまい、「こんなはずではなかった」というミスマッチの最大の原因となるからです。
事業計画と連動させ、「売上を〇〇億円にする」「新規事業を○月までに軌道に乗せる」といった具体的なゴールを設定し、そのために必要な役割と責任を明確にすることで、候補者が迷いなくパフォーマンスを発揮できる土台を作ることができます。
既存役員との権限移譲の「線引き」を明確にする
外部から幹部を迎える際、既存の役員(上級管理職)との間で権限や役割の重複が問題になることがよくあります。
特に創業メンバーがいる場合、感情的なしこりを生むことにもなりかねません。
この線引きが曖昧だと、採用された幹部候補は思うようにリーダーシップを発揮できず、既存役員との間で不要な権力闘争や部門間のコンフリクトを生み出す火種となります。
誰が、どの領域の最終意思決定権を持つのか。
新しく迎える幹部にどこまで権限を委譲するのか。
その「線引き」を事前に経営チーム内ですり合わせ、全員が納得した状態を作っておくことが、事業のスピードを落とさず、組織全体の生産性を高める上で極めて重要です。
中途幹部の「アンラーニング」を促すオンボーディング
新卒と違い、中途採用の幹部候補は前職での成功体験や「当たり前」を持っています。
多くの経営誌でも指摘されているように、転職した幹部候補が活躍できない失敗要因の多くはスキル不足ではなく、前職の当たり前に囚われてしまい、新組織の文化に適応できないことにあります。
これは、企業文化や事業フェーズによって「成果に繋がる行動」が全く異なるためです。
例えば、緻密な分析と合意形成を重視する大企業と、朝令暮改を恐れずスピードを重視するベンチャーとでは、評価される行動が正反対であることも少なくありません。
このプロセスを軽視すると、どんなに優秀な人材でも組織に馴染めず孤立し、本来のパフォーマンスを発揮する前に「能力不足」のレッテルを貼られてしまう危険性があります。そのため、入社後に前職のやり方を一旦手放し、自社のやり方やベースとなる考え方を学んでもらう「アンラーニング(学びほぐし)」を意図的に促す仕組みが有効になります。
メンターとなる役員をつけたり、定期的に経営陣とすり合わせの場を設けたりと、組織の「暗黙知」を形式知化して伝え、意図的に立ち上がりを支援するオンボーディングプランを設計しましょう。
採用基準(CAN/WILL/MUST)を言語化する
最後に、これまでの議論を具体的な採用基準に落とし込みましょう。
これらを言語化する最大の目的は、面接官の「主観」や「好み」による評価のブレをなくし、採用判断の客観性を担保することです。
全員が同じ物差しを持つことで、初めて自社にとって本当に必要な人材を戦略的に見極めることが可能になります。
- CAN:業務遂行に必要なスキルや経験
WILL: 候補者自身の価値観やキャリアで成し遂げたいこと
MUST: 企業として絶対に譲れない価値観やスタンス
この3つの観点で求める要件を言語化し、経営陣や面接官の間で目線を合わせることで、採用の精度は飛躍的に向上します。
採用した人材のポテンシャルを最大限に引き出す、受け入れ体制の構築やマネジメントの仕組み作りは、事業成長の生命線になります。
まずは3分でわかる「マネディク」のサービス資料をダウンロードして、300社以上の成長企業を支援してきたノウハウをご確認ください。

5. 候補者の本質を見抜く「戦略的な面接」のコツ
面接は、候補者を一方的に評価する場ではありません。
候補者の本質を見極めると同時に、自社の魅力を伝え、候補者の入社意欲を高める「相互理解の場」と捉えるべきです。
過去の「事実」から未来の「再現性」を確認する質問とは?
候補者の能力を見極めるには、抽象的な質問ではなく、過去の具体的な「事実」に基づく質問が有効です。
例えば、「リーダーシップはありますか?」と聞くのではなく、「過去に最も困難だったプロジェクトで、どのようにチームを率いて乗り越えましたか?」と質問します。
その状況、課された役割、具体的な行動、そしてもたらされた結果(STARメソッド)を深掘りすることで、その人の思考プロセスや行動特性、そして自社での「再現性」が見えやすくなります。

候補者の入社意欲を高める「魅力付け」の対話術
優秀な候補者ほど、複数の選択肢を持っており、「選ばれる側」であると同時に、「選ぶ側」です。
そのため、面接では自社の良い面だけでなく、現在抱えている課題や困難な状況も正直に開示することが、入社後のギャップ防止につながります。
その上で、「この困難な課題を、あなたの力で一緒に乗り越えていきたい」という期待を伝えることが、何よりもの魅力付けになります。候補者に「この人たちと、この課題解決に挑戦したい」と思わせることが、戦略的な面接の一手になります。
まとめ
幹部候補の中途採用は、成長し続ける会社を創るためにも、力を入れて進めていくべきことです。
2章でもお伝えしたように、成功の鍵は候補者を探し始める前の「事前設計」にあります。
経営陣で徹底的に議論を尽し、採用の軸を固めること。そして、迎えるための万全な受け入れ体制を整えること。この土台があって初めて、戦略的な採用活動が可能になります。
私たちマネディクは、300社以上の成長ベンチャーをご支援してきた知見を活かし、採用した幹部候補が早期に活躍するための受け入れ体制の構築や、事業成長を加速させる組織開発をサポートしています。
少しでもご関心のある方は、ぜひ一度ご相談ください。