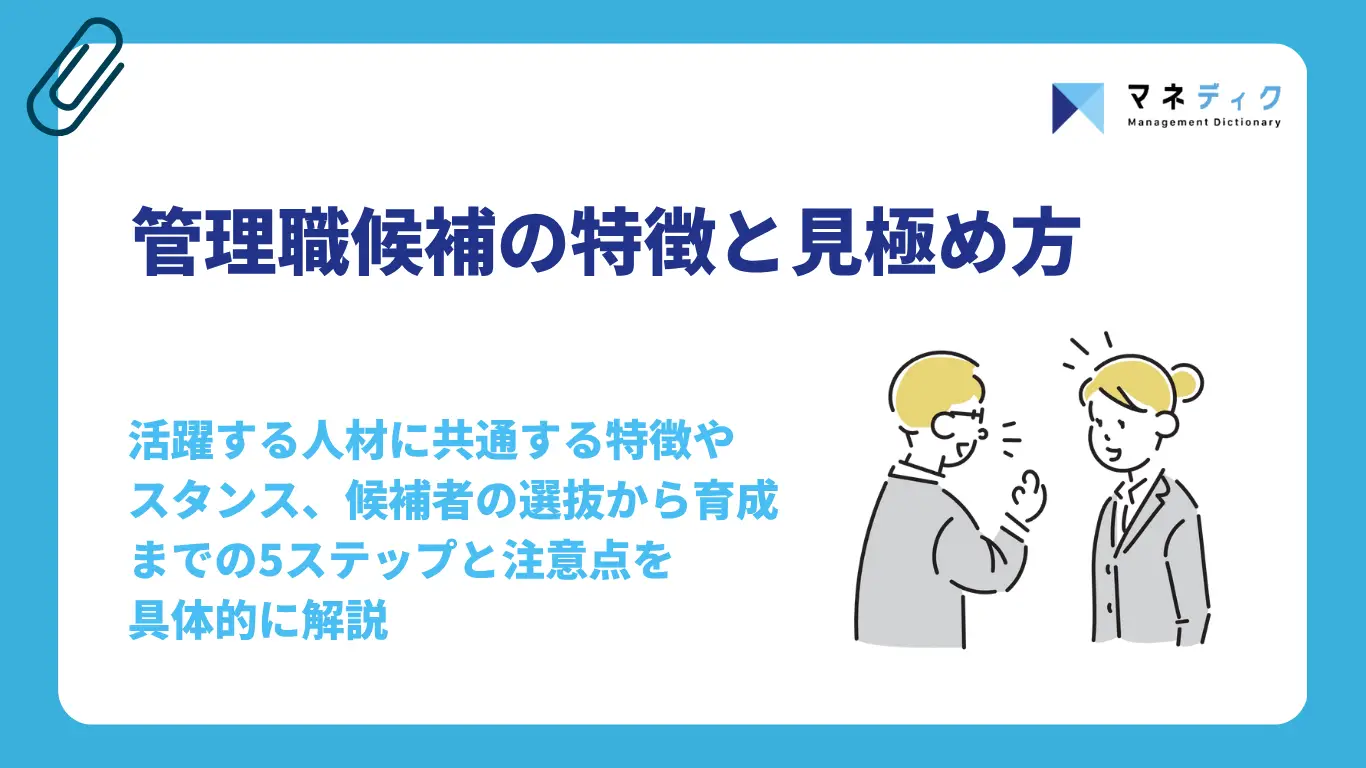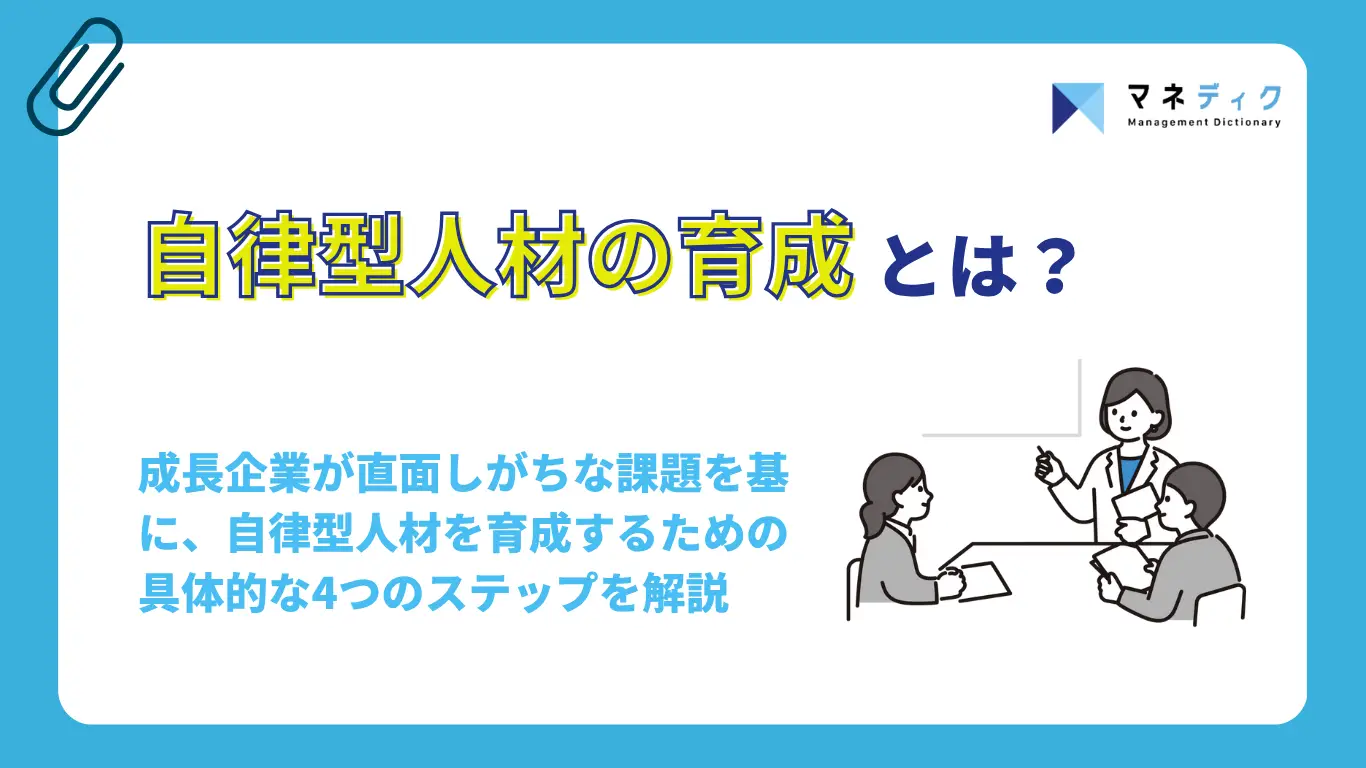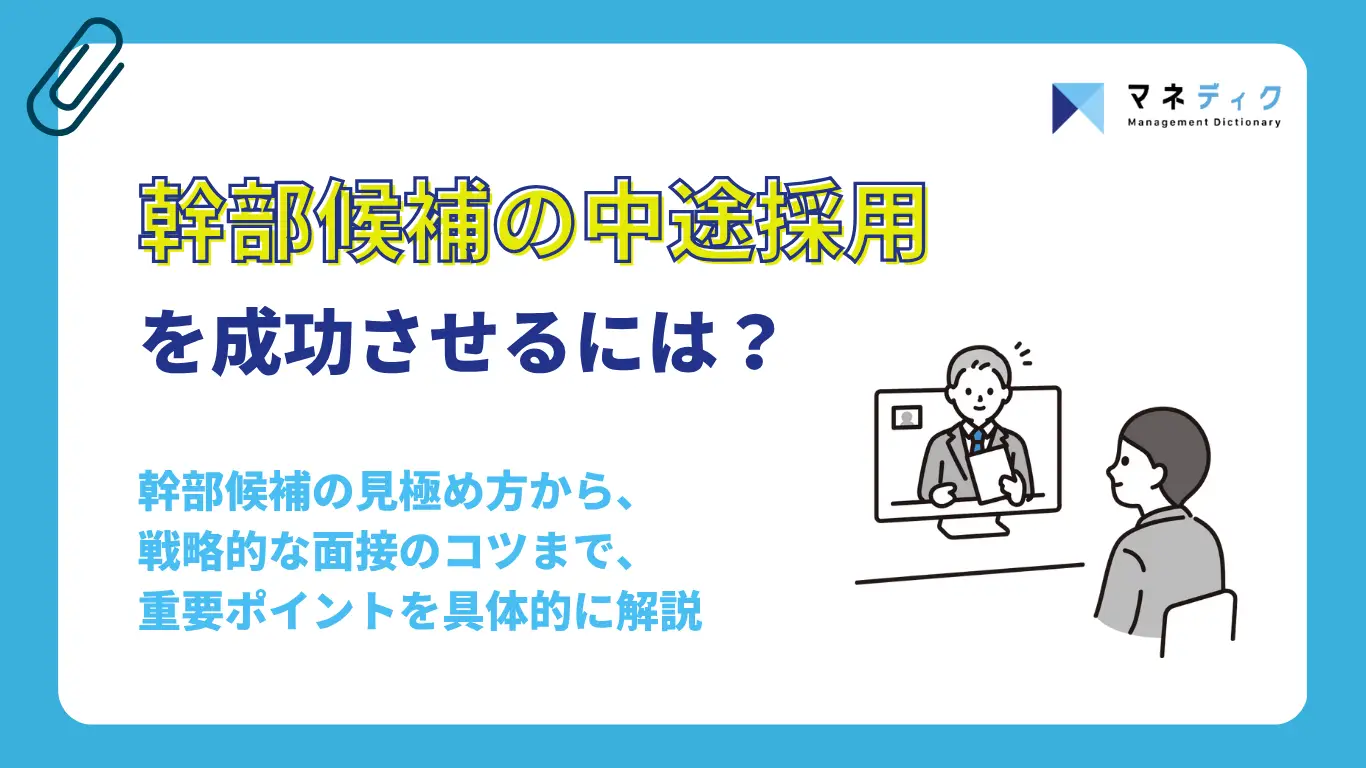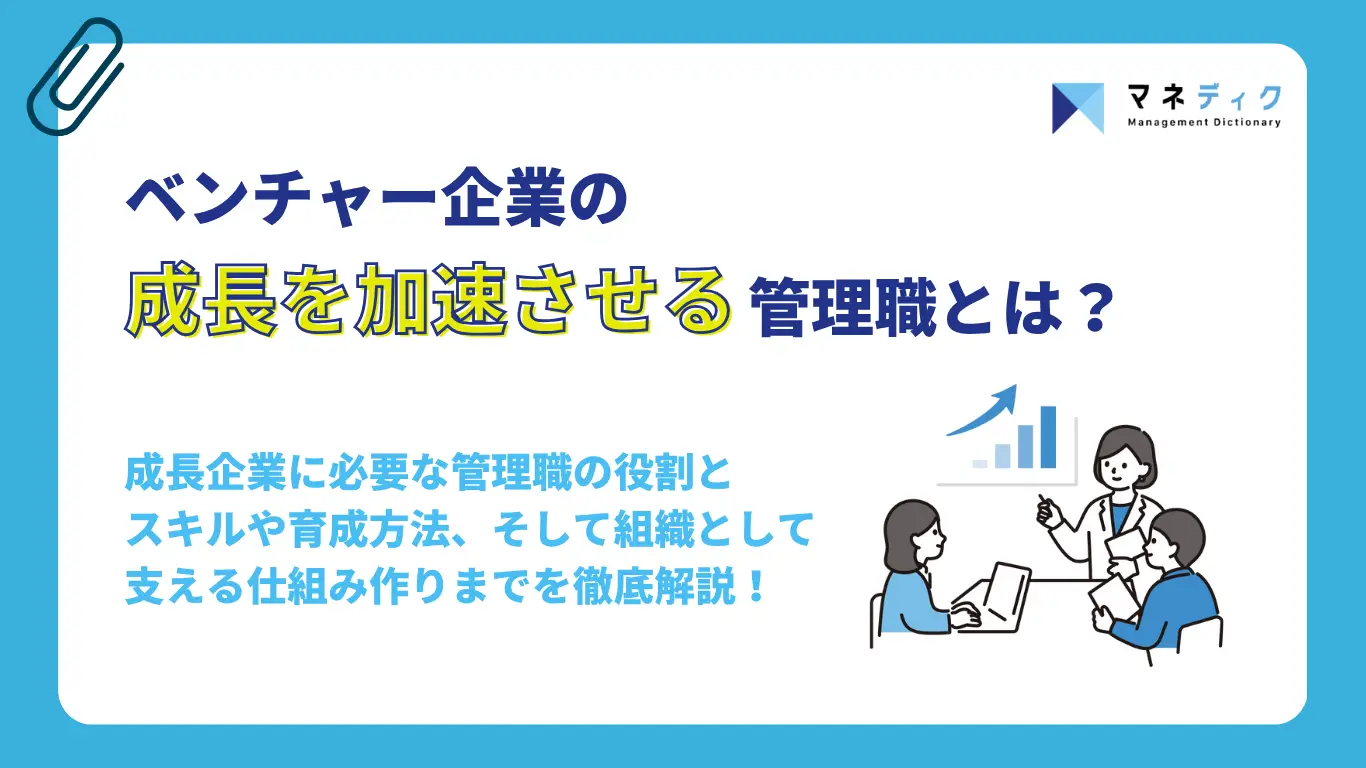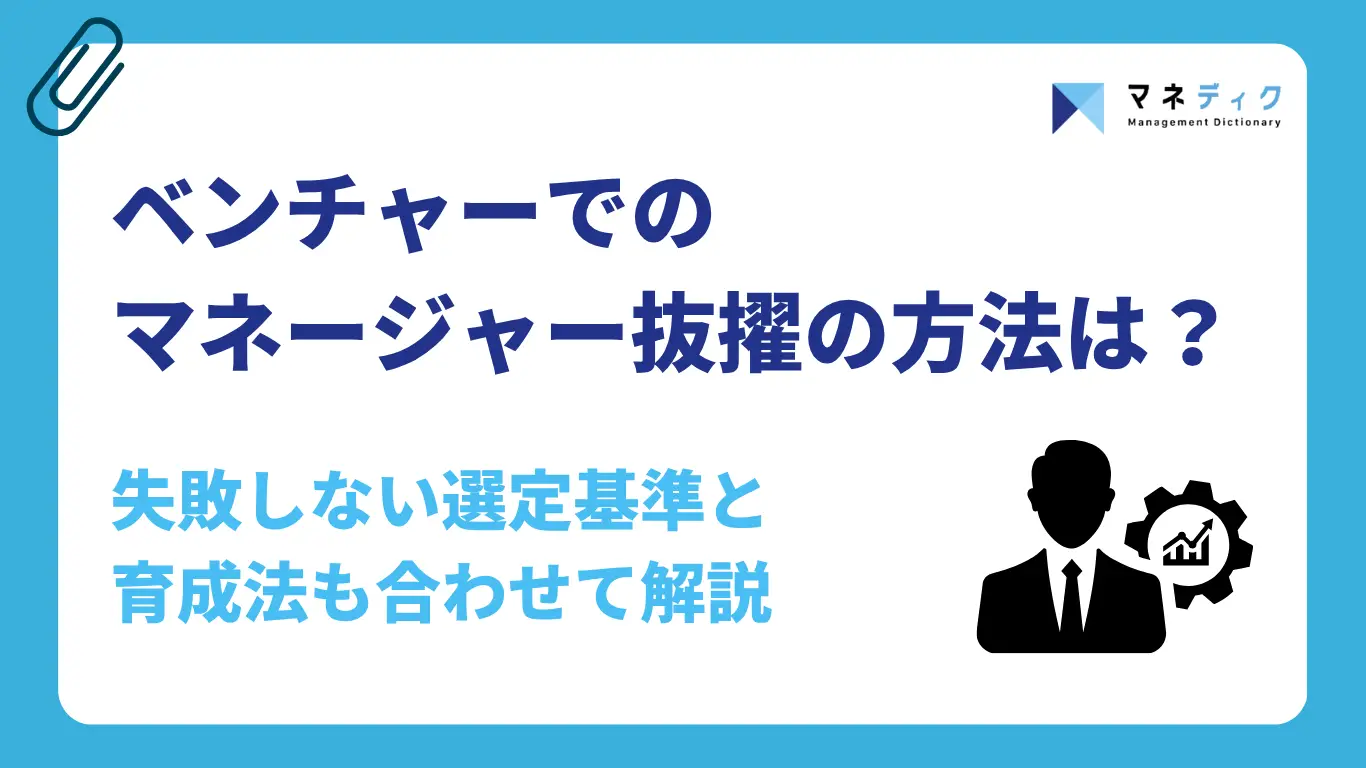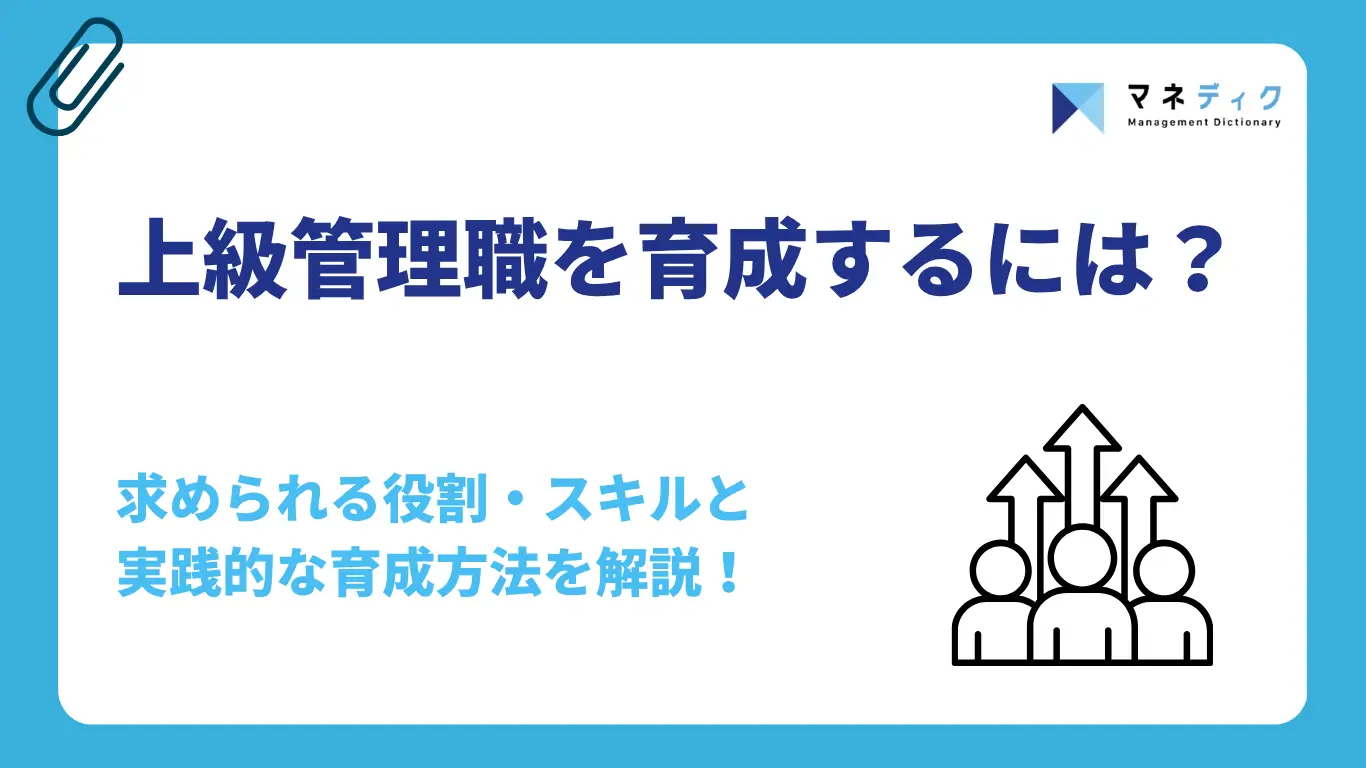中堅社員が育たないのはなぜ?5つの本質的要因と明日から使える育成の仕組み化を徹底解説
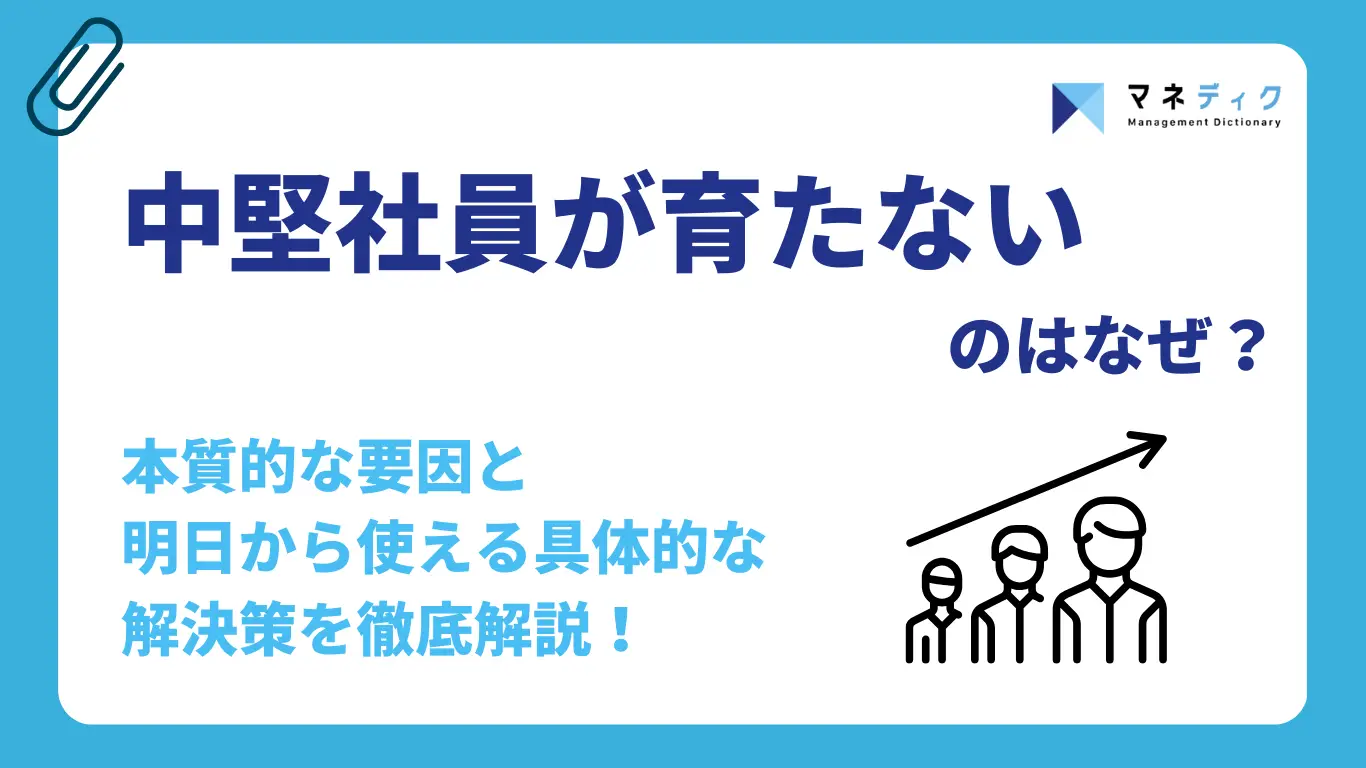
なぜ、あなたの中堅社員は育たないのか?5つの本質的要因
中堅社員の成長が止まるのは、本人の意欲だけの問題ではありません。
多くの場合、その原因は組織の仕組みや環境に根ざしています。自社に当てはまるものはないか、チェックしてみてください。
【要因1】役割定義の曖昧さ
中堅社員が育たない要因の1つ目が、役割定義の曖昧さです。
多くの企業で、中堅社員に期待される役割は「プレイヤーとして成果を出しつつ、後輩の面倒も見る」といった曖昧なものです。
明確な期待値が示されないまま、彼らは「自分は一体何に注力すべきなのか」と混乱します。
結果、慣れ親しんだプレイヤーとしての業務に逃げ込み、マネジメントや育成といった新たな役割への挑戦を避けてしまい、育成がなされないといった事象が起きます。
【要因2】成長を促さない評価制度
中堅社員が育たない要因の2つ目が、成長を促さない評価制度です。
評価制度が個人の売上や目標達成率といった、いわゆる「プレイヤーとしての成果」に偏っていないでしょうか?
後輩の育成やチームへの貢献といった、組織の未来を作るための行動が評価されなければ、中堅社員がそちらに時間と労力を割く動機は生まれません。評価される行動を優先するのは当然のことです。
【要因3】キャリアパスの不透明性
中堅社員が育たない要因の3つ目が、キャリアパスの不透明性です。
「今の仕事を続けていった先に、どんなキャリアが待っているのか?」という問いに、会社は明確な道筋を示せているでしょうか?
ロールモデルとなる先輩社員の不在や、管理職以外のキャリアパスの欠如は、中堅社員から「この会社で成長し続けられそう」という期待を奪います。結果として、守りの姿勢に入り、現状維持を良しとしてしまうのです。
また、ただ現状維持に走るだけならまだ良いですが、「この会社にいても仕方がない」と見切られ、離職されてしまうと、それこそ会社としては大きな損失です。
【要因4】心理的安全性の欠如
中堅社員が育たない要因の4つ目が、心理的安全性の欠如です。
中堅社員は、上司と部下の板挟みになり、「失敗できない」という強いプレッシャーを感じやすいポジションです。
新しい役割への挑戦には失敗がつきものですが、それを許容する文化がなければ、彼らはリスクを取ることを恐れます。結果、安全な既存業務の範囲内でしか行動しなくなります。
【要因5】育成文化の不在
中堅社員が育たない要因の5つ目が、育成文化の不在です。
「育成は気合と根性」「俺の背中を見て学べ」といった、属人的な指導がまかり通っていませんか?多くの管理職は「教え方」を学んだことがなく、自身の成功体験を押し付けるばかりです。
これでは育成は標準化されず、中堅社員は効果的な指導を受けられません。結果、成長の機会を失ってしまうのです。
「中堅社員が育たない」ことが組織に与えるリスク
中堅社員が育たないことは組織に多大な影響を与えます。
ここでは短期視点・中長期視点で、起こり得るリスクを解説していきます。
【短期的リスク】若手の離職率悪化と、現場管理職の疲弊
短期的に最も顕著に現れるのが、「若手人材の流出」と「現場管理職の疲弊」という、組織の活力を奪う二つのリスクです。
以下でそれぞれ解説していきます。
1. 若手の早期離職という「負の連鎖」
短期的なリスクの1つ目は「若手の離職率悪化」です。
人は、他者を観察し模倣することで自身の行動を学習します(社会学習理論)。
若手社員にとって、最も身近な観察対象、つまりロールモデルは直属の先輩である中堅社員です。そのロールモデルが、もし成長意欲を失い、変化を恐れ、疲弊した表情で毎日同じ業務をこなしているだけだとしたら、どうでしょうか?
若手は「この会社で数年働くと、ああなるのか」「ここでは成長に必要なスキルやスタンスは学べない」と、自身のキャリアの未来に絶望します。特に優秀で成長意欲の高い若手ほど、この「キャリアの天井」を敏感に察知し、成長できる環境を求めて早期に見切りをつけてしまいます。
結果として、組織には成長意欲の低い人材ばかりが残り、新たな活力が生まれないという「負の連鎖」が始まります。
2. 管理職のバーンアウト(燃え尽き症候群)
中堅社員が育たないことの短期的なリスクの2つ目は「現場管理職の疲弊」です。
育たない中堅社員が生み出す業務の穴を埋めるのは、現場の管理職です。
彼らは、本来中堅社員が担うべき「後輩指導」や「現場の細かな意思決定」といった業務まで抱え込むことになります。
これに自身のプレイング業務が加わることで、管理職は完全にキャパシティオーバーに陥ります。結果、目先のトラブルシューティングに追われ、本来注力すべき「事業の未来を創るための戦略的思考」や「新たな仕組み作り」といった付加価値の高い業務に時間を全く使えなくなります。これは、組織全体の成長機会の損失に他なりません。
この状態が続けば、心身ともに疲弊し、管理職自身のバーンアウト(燃え尽き症候群)を引き起こします。組織の要である管理職が機能不全に陥ることは、一部署のパフォーマンス低下にとどまらず、会社全体の土台を揺るがす深刻な事態なのです。
【中長期的リスク】事業成長の停滞と、次世代の経営幹部候補の枯渇
中堅社員が育たないことによる中長期的なリスクとして、「事業成長の停滞」と「次世代の経営幹部候補の枯渇」が挙げられます。
以下でそれぞれ解説していきます。
1. 「組織能力の陳腐化」による事業停滞
中堅社員は、経営層が描く戦略を現場に落とし込み、実行する「事業の要」となる存在です。
この中堅社員が学習を止め、古いやり方に固執すれば、組織全体の「組織能力」は時代遅れになっていきます。
市場や顧客が変化しているにも関わらず、過去の成功体験から抜け出せず、新しい挑戦を避け続ける。これは、組織が環境変化に適応できなくなることを意味します。
また、優れた組織では、経営層のトップダウンと現場のボトムアップを、中間層である中堅社員が媒介する「ミドルアップダウン・マネジメント」が機能し、イノベーションが生まれます。
中堅社員が育たない組織では、経営と現場が分断され、現場のリアルな声やアイデアが経営に届きません。結果、戦略は形骸化し、事業は確実に成長の壁にぶつかります。
2. 「リーダーシップ・パイプライン」の断絶
経営幹部は、ある日突然生まれるものではありません。現場のリーダー、チームマネージャー、事業部長といった段階的な経験を経て、計画的に育成されるものです。
この育成経路を「リーダーシップ・パイプライン」と呼びます。
中堅社員が育たないということは、このパイプラインの入り口が完全に詰まっている状態を意味します。パイプラインに人材が流れ込まなければ、数年後、経営陣が代替わりするタイミングで、後を託せる人間が誰もいないという悪夢のような現実に直面します。
これは、事業継続のための後継者育成計画(サクセッションプラン)が完全に崩壊することを意味し、創業者が築き上げてきた企業文化の継承すら困難にする、極めて深刻な経営リスクになりえます。
【要因別】中堅社員を育てるための具体的解決策
ここまで中堅社員が育たない本質的な要因や中堅社員が育たないことで生まれるリスクを紹介してきましたが、ここからは「中堅社員が育つようになる」ための具体的な解決策を解説していきます。
対策1:期待値調整のための1on1フレームワークを導入する
役割の曖昧さを解消するには、上司と本人の間で「期待する役割」を徹底的にすり合わせることが不可欠です。月に一度の1on1ミーティングを設け、以下のフレームワークで対話しましょう。
【期待値調整1on1テンプレート】
- 会社・チームからの期待の伝達:
- 「チームとして今このフェーズで、あなたにはプレイヤーとしての成果7割、後輩育成3割の役割を期待している。具体的には…」
- 本人の認識の確認:
- 「今の役割について、自分ではどう捉えている?何に難しさを感じている?」
- ギャップのすり合わせ:
- 「期待と現状のギャップを埋めるために、明日から何ができそうか?私(上司)がサポートできることは?」
- 具体的なアクションプランの設定:
- 「では、次の1ヶ月は〇〇を意識して行動してみよう。困ったらすぐに相談してほしい」
対策2:チーム貢献や後輩育成を評価項目に反映させる
行動を変えるには、評価を変えるのが最も効果的です。「育成やチーム貢献はやって当たり前の業務」ではなく、「会社の未来を創るための重要なミッション」として、評価制度に明確に位置づけましょう。
現在の評価制度を見直し、例えば成果評価全体の30%を占めるウェイトで、以下のような項目を導入します。
【評価項目・目標設定(MBO) 具体例】
- グレード:リーダー候補
- 目標項目(定量): 担当する後輩メンバー2名の目標達成率を80%から100%へ引き上げる。
- 目標項目(定性): 自身の持つ営業ノウハウを言語化し、チーム内に展開するための勉強会を四半期に1度主催する。
- 達成基準:
- S評価:後輩メンバーが目標達成率120%以上を達成し、かつ勉強会へのチームメンバー満足度が90%以上。
- A評価:後輩メンバーが目標達成率100%を達成し、かつ勉強会を計画通り実施。
- B評価:...
このように、「何を」「どれくらい」やれば評価されるのかを具体的に示すことで、中堅社員は安心して育成やチーム貢献に時間とエネルギーを注ぐことができるようになります。
対策3:社内で目指せる複数のキャリアモデルを提示し、選択肢を与える
「この会社で頑張れば、こんな未来が手に入る」という希望を具体的に示すことが、中堅社員のエンゲージメントを維持する上で極めて重要です。
管理職という単一のゴールではなく、多様なキャリアパスを会社として正式に用意し、それぞれの役割定義を明確にしましょう。
| キャリアコース | 等級 | 主な役割と責任 | 求められるスキルセット |
| マネジメント | M1 | 3〜5名のチームの目標達成責任、メンバーの育成と評価 | 目標設定力、ピープルマネジメント、課題解決力 |
| M2 | 複数チームを統括する部署のPL責任、事業計画の策定 | 事業計画策定、組織開発、部門間調整力 | |
| スペシャリスト | S1 | 特定領域におけるエースプレイヤー、チームの技術的課題解決 | 担当領域における高度な専門知識、後輩への技術指導力 |
| S2 | 担当領域の第一人者として、全社的に戦略立案に貢献 | 業界レベルの専門知識、R&D、外部発信力 | |
| プレイング マネージャー | P1 | 複数部門を横断する中規模プロジェクトの推進・管理 | プロジェクト管理(PMP)、ファシリテーション、リスク管理 |
| P2 | 全社の重要戦略に関わる大規模プロジェクトの責任者 | 高度なプロジェクトマネジメント、ステークホルダーマネジメント |
このようなキャリアマップを提示した上で、半年に一度のキャリア面談を実施し、「半年後、1年後、3年後にどのようになっていたいか」「そのために今、何に取り組むべきか」を上司と本人がすり合わせる機会を設けることが極めて有効です。
対策4:「挑戦の称賛」と「失敗からの学び」を促す文化を醸成する
心理的安全性を高めるには、経営層や管理職が率先して「失敗」に対する捉え方を変える必要があります。うまくいかなかった挑戦を責めるのではなく、「なぜうまくいかなかったのか」「次にどう活かすか」をチームで建設的に議論する場を設けましょう。「挑戦したこと自体が素晴らしい」というメッセージを、言葉と行動で一貫して伝え続けることが重要です。
【明日から導入できる仕組み・行動例】
- 週次定例での「ナイスチャレンジ共有」:
- 結果の成否に関わらず、今週最も大きな挑戦をした、あるいは賢い失敗をした個人・チームを称賛する時間を5分設ける。「〇〇さんのアプローチは結果に繋がらなかったが、新しい顧客層にアプローチしたという挑戦自体が素晴らしい」といった形で、プロセスを称賛します。
- 失敗からの学びを資産化する「Postmortem(ポストモーテム)会議」:
- うまくいかなかった施策について、犯人探しではなく「この経験から得られた学びは何か?」「次に活かせる教訓は何か?」を建設的に議論し、議事録として全社に共有します。失敗は隠すものではなく、組織全体の資産であるという文化を醸成します。
- 経営者・役員による「失敗談の共有」:
- 経営者や役員が、自身の過去の大きな失敗談と、そこから何を学んだのかを全社朝礼や社内報で赤裸々に語ります。トップが自ら弱さを開示することで、「この組織では失敗しても大丈夫なのだ」という強力なメッセージとなります。
対策5:「教えるスキル」そのものを言語化・仕組み化する
育成を属人化させないためには、「教えるスキル」自体を会社の共通言語・仕組みとして標準化し、誰でも質の高い指導ができる環境を整えることが不可欠です。
まずは、具体的なフィードバックのフレームワークを導入し、全管理職に研修を実施します。例えば、効果的なフィードバックの型として知られる「SBIモデル」が良いでしょう。
【フィードバックの型(SBIモデル)】
- S (Situation):状況:いつ、どこでのことか
- B (Behavior):行動:相手が具体的にとった行動
- I (Impact):影響:その行動が、周囲にどのような影響を与えたか
このような型を用いることで、指摘が人格否定にならず、「改善すべき行動」にフォーカスした建設的な対話が可能になります。
このような「教える型」を導入するだけでなく、さらに一歩進んで、育成の仕組みそのものを組織に根付かせ、自社で好循環を回し続けることが、持続的な企業成長の鍵となります。
我々マネディクが提供する組織開発プログラムは、一過性の研修で終わるものではありません。最終的に外部コンサルタントに依存することなく、貴社内に育成の担い手(ファシリテーター)を養成し、育成ノウハウを資産として蓄積できる「自走化(インハウス化)」の支援に特化しているのが最大の特徴ですƒ。
ご提供するサービス資料では、学習した内容を確実に実践・定着させるための具体的なプログラムの全貌や、貴社自身が主体となって育成文化を醸成していくためのステップを詳しく解説しています。ご興味のある方は、ぜひ一度資料をダウンロードしてみてください。

中堅社員の育成を成功させる3つのポイント・注意点
上記の施策を効果的に進めるために、以下の3つのポイントを意識してください。
「丸投げ」でも「過干渉」でもなく、「権限移譲」を意識する
仕事を任せる際、「あとはよろしく」という「丸投げ」や、細かく口を出す「過干渉」はNGです。
重要なのは、目的とゴールを明確に伝えた上で、「この範囲の意思決定は君に任せる」という「権限移譲」を行うことです。
失敗した際のリスクは上司が取るという覚悟を持つことで、中堅社員は安心して挑戦できます。
会社が期待する役割と本人のキャリアビジョンを定期的にすり合わせる
会社の期待と本人の「やりたいこと」が乖離すると、モチベーションは著しく低下します。
1on1などを通じて、本人が将来どうなりたいのか(キャリアビジョン)を定期的にヒアリングし、会社の期待する役割との接点を見つけ出す努力が不可欠です。
「この仕事は、君のキャリアにとってこういう意味がある」と接続してあげることが、当事者意識を引き出します。
研修の「やりっぱなし」を防ぎ、現場での実践までをセットで設計する
研修はあくまで知識を得る「きっかけ」に過ぎません。
重要なのは、学んだことを現場で実践し、振り返るサイクルを回すことです。
研修後には、上司を巻き込んだ実践目標の設定や、数ヶ月後のフォローアップ面談を必ずセットで設計し、「やりっぱなし」を防ぎましょう。
中堅社員の成長は、仕組みとカルチャーで解決
この記事を通して、中堅社員が育たない5つの本質的な要因、それによって引き起こされる深刻なリスク、そして具体的な解決策までを解説してきました。
個人の意欲や能力だけに原因を求めるのではなく、役割定義の明確化、貢献が報われる評価制度、希望の持てるキャリアパスといった具体的な「仕組み」を整えることが、育成の第一歩であることはご理解いただけたかと思います。
しかし、多くの成長企業が次に直面するのは、「正しい仕組みを作ったはずなのに、なぜか組織が動かない」という、より根深い壁です。どれだけ優れた制度も、それを使う社員の「スタンス」や「価値観」が伴わなければ形骸化してしまいます。
私たちマネディクは、まさにそのような成長ベンチャーが直面する「組織の壁」に特化し、事業が成長するための土台作りを支援する組織開発のプロフェッショナル集団です。300社以上の企業をご支援してきた中で見えてきたのは、優れた仕組みを真に機能させるためには、その土壌となる「カルチャー(統一された行動様式)」の存在が不可欠であるという事実でした。
ご提供するサービス資料では、今回ご紹介したような育成の仕組み作りはもちろんのこと、一過性の研修で終わらせないための「学習→実践→評価→改善」のサイクルを回す具体的なアプローチや、社内に育成ノウハウを蓄積し、自走できる組織を作るためのカルチャー醸成について、より詳しく解説しています。
中堅社員の育成、そしてその先の事業成長を本気で加速させたいとお考えの経営者・人事責任者の方は、ぜひ一度、以下のボタンから資料をダウンロードいただき、自社の可能性を最大化するヒントを掴んでください。