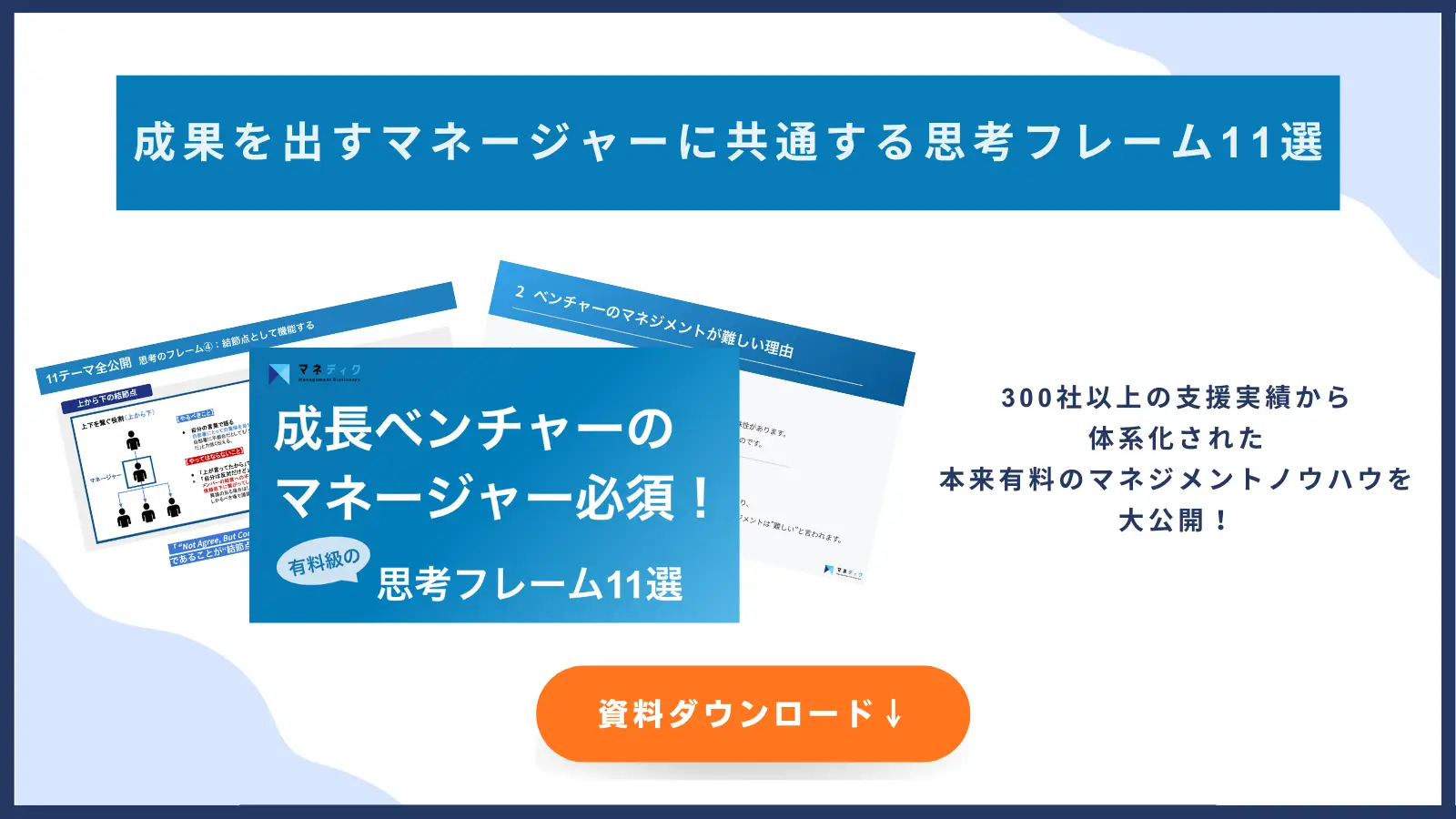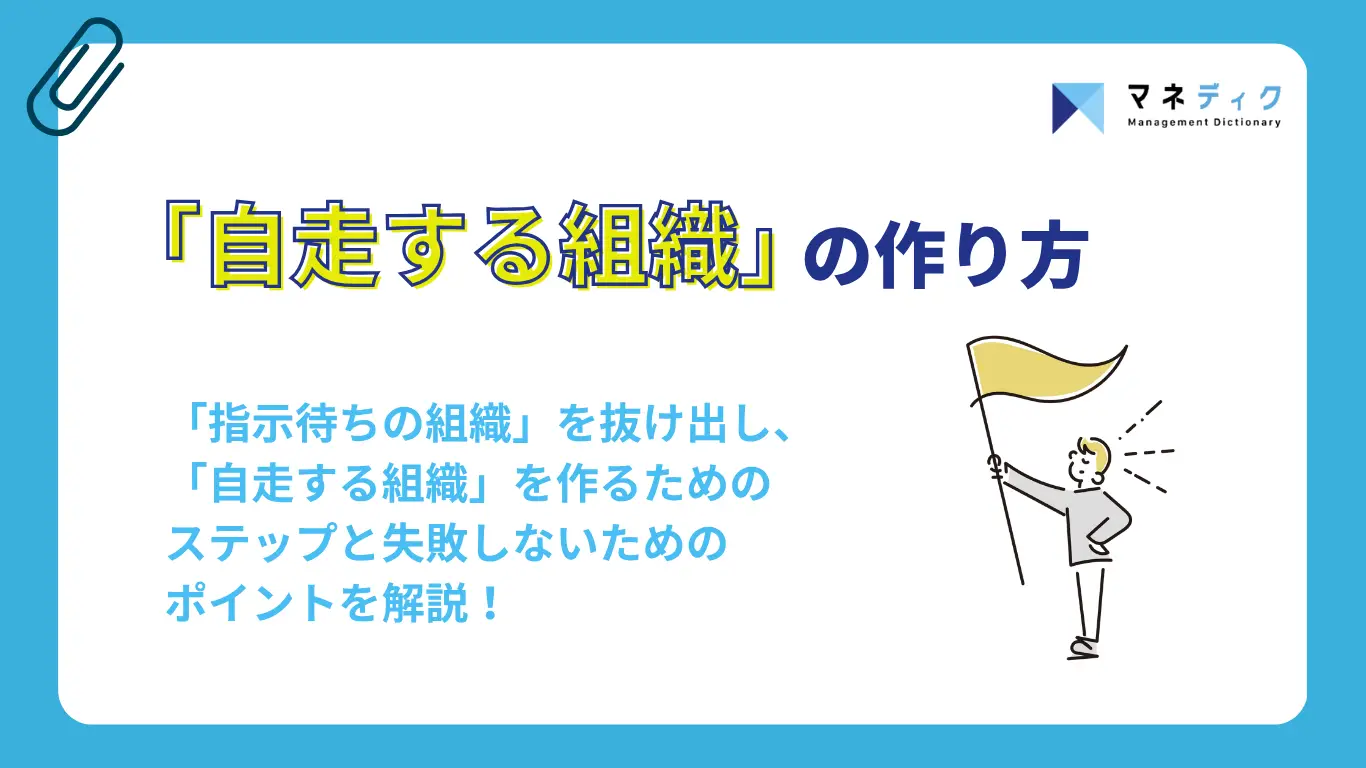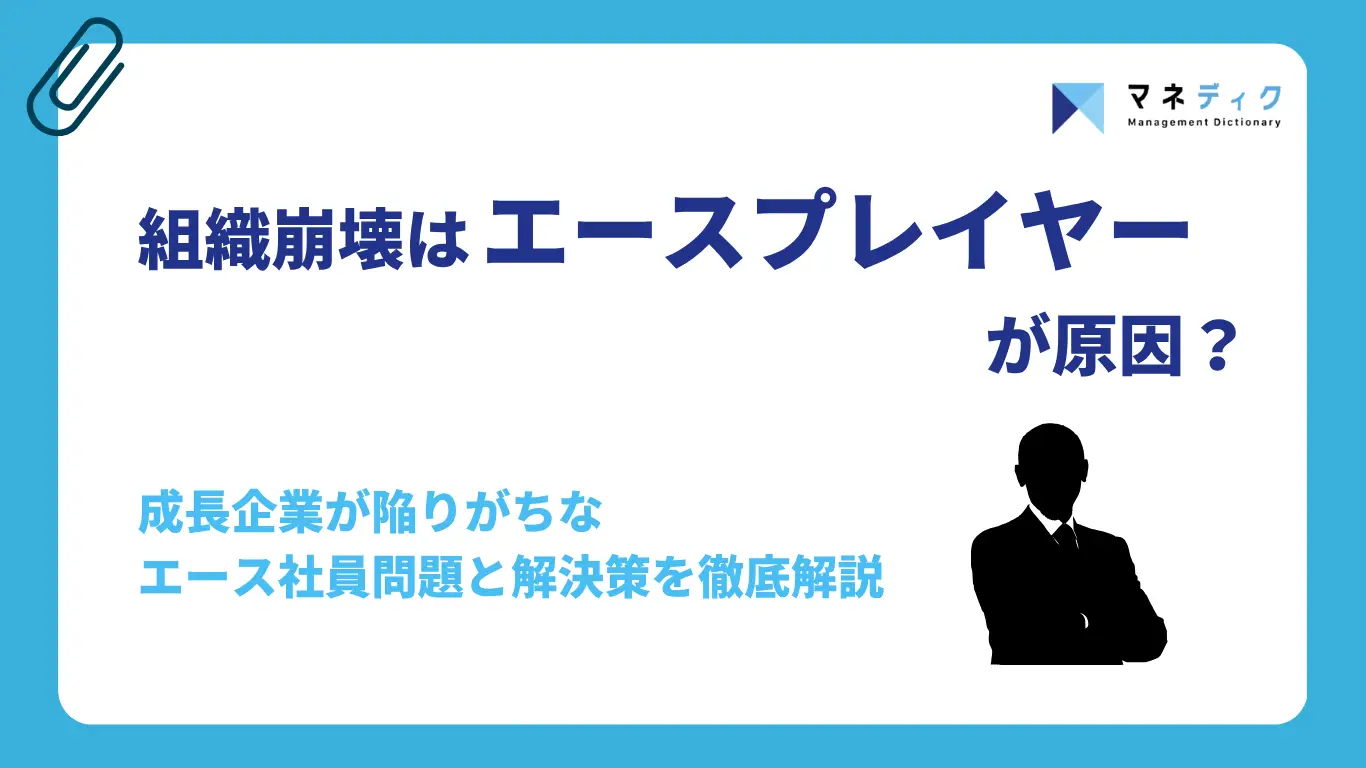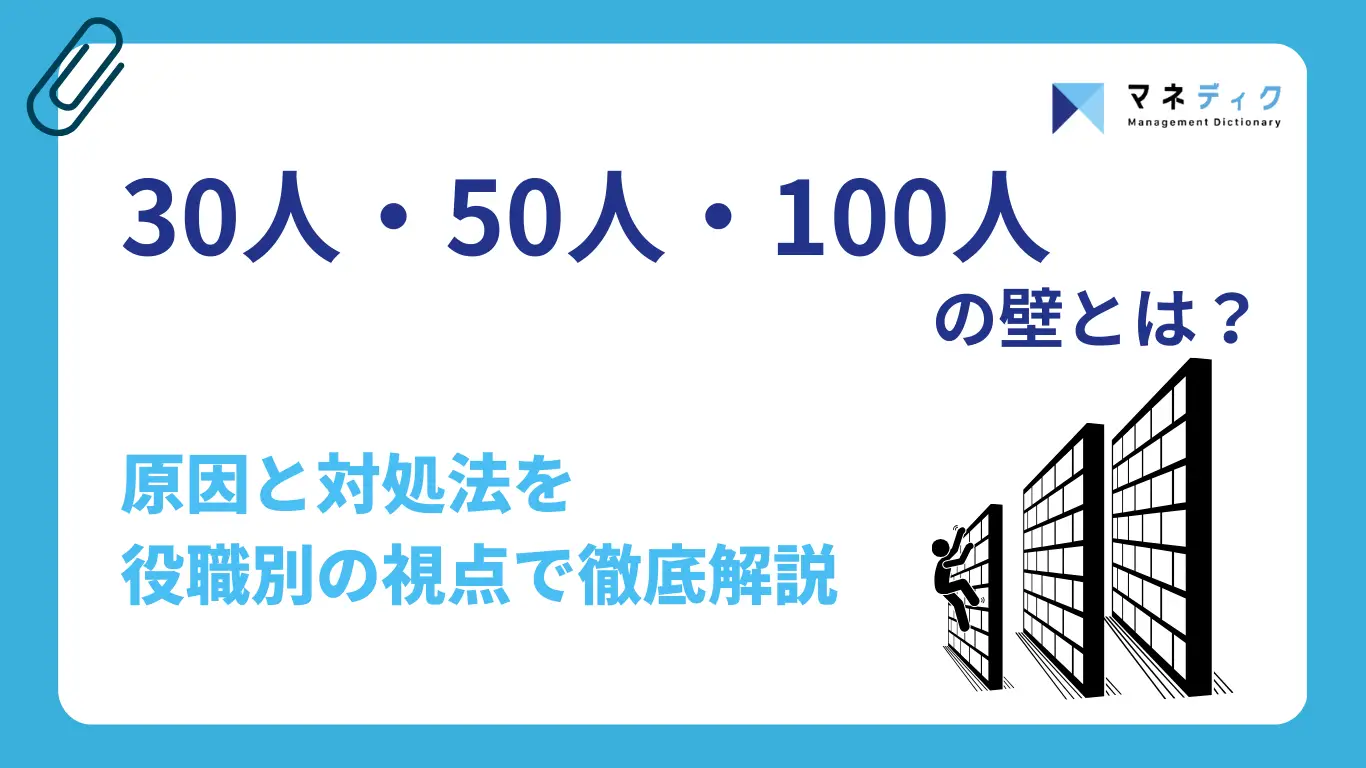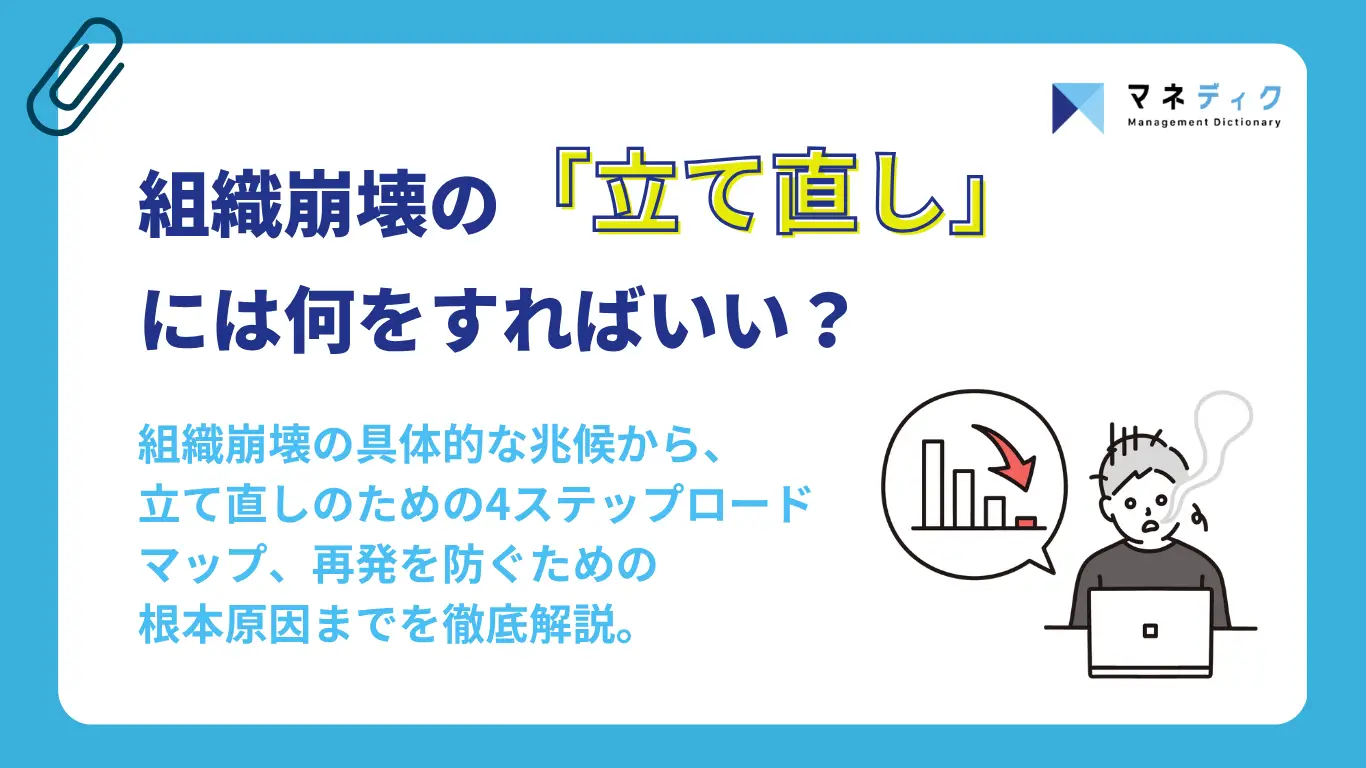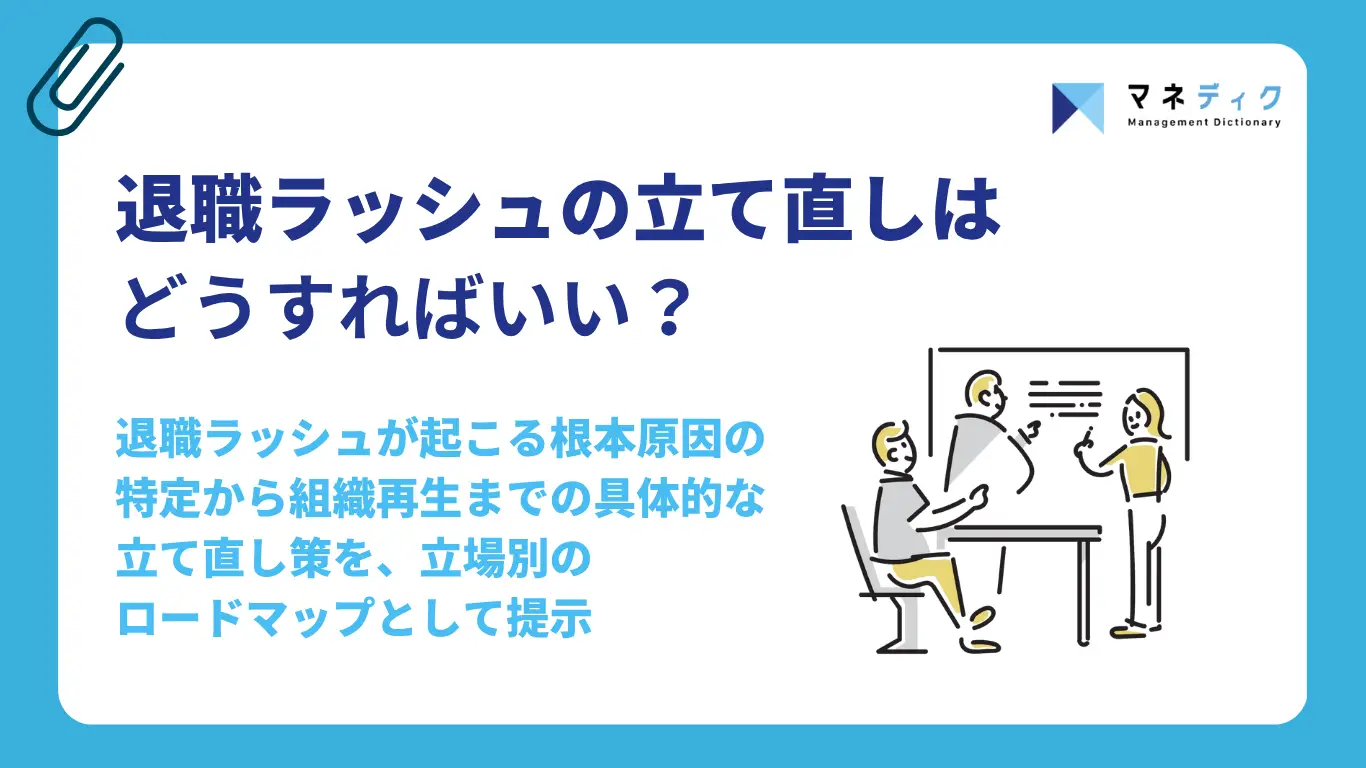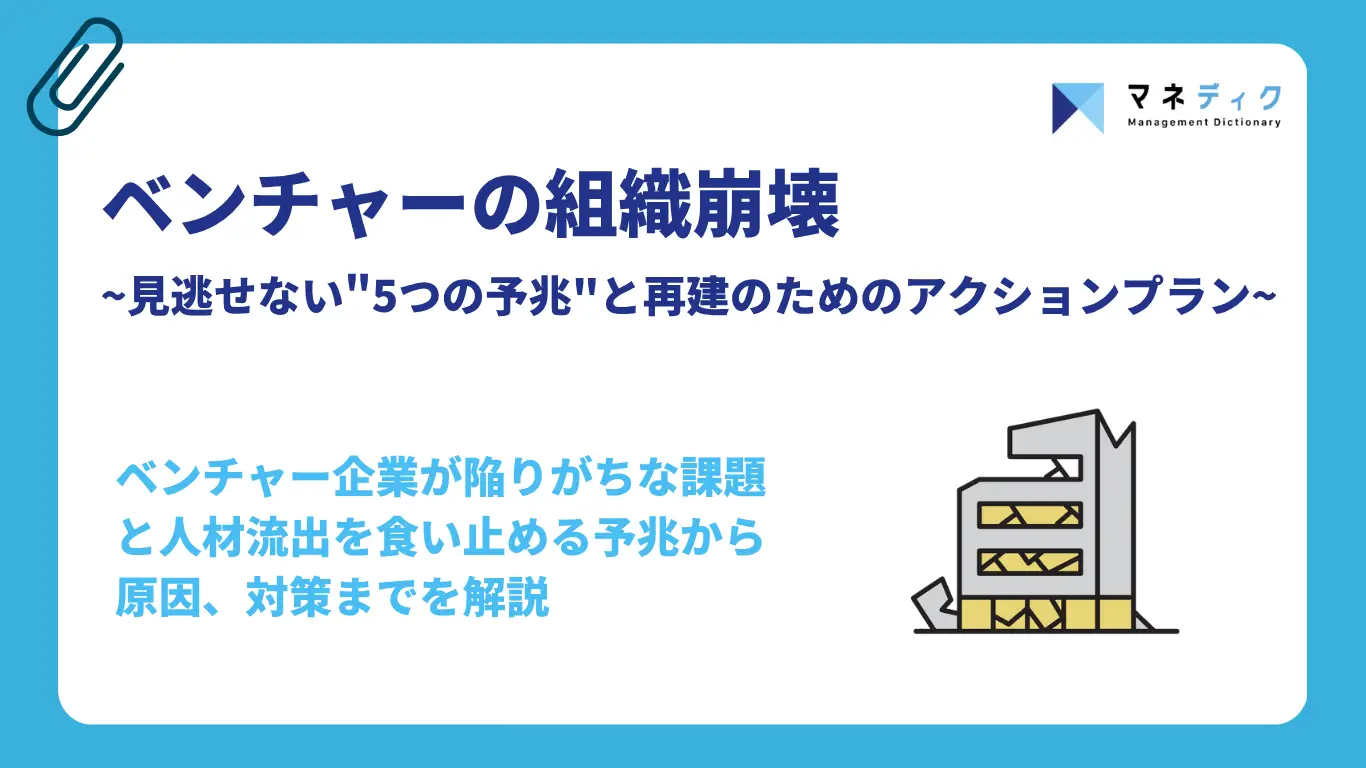マネジメントの仕組み化とは?属人化を防ぎ、自走する組織を作る4ステップ
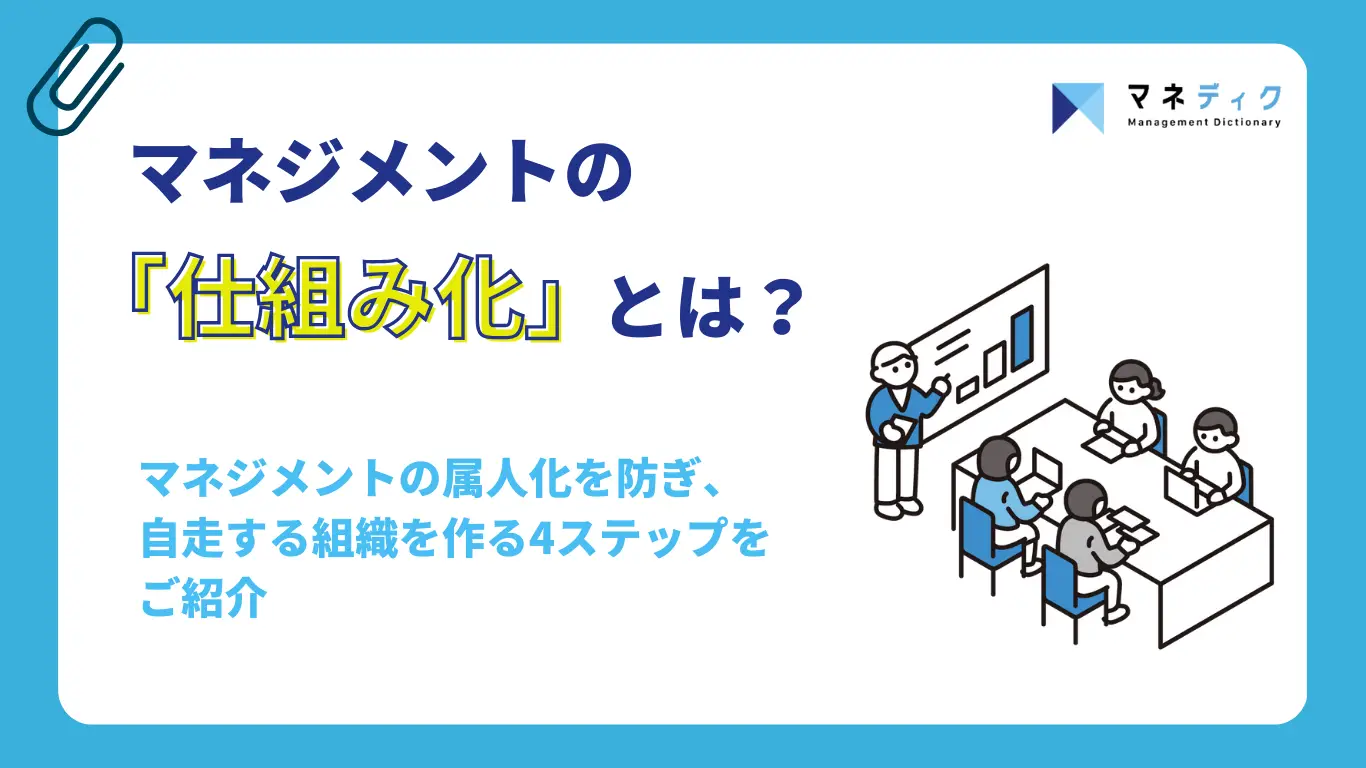
はじめに:そのマネジメント、属人化していませんか?
マネジメントが属人化し、部下の育成やチームの成果に悩んでいませんか?
属人化とは、特定の人に業務が依存する状態で、組織成長の壁となります。
本記事では、誰がやっても成果を出せる「自走する組織」を作るためのマネジメントの仕組み化を、具体的な4ステップで解説します。
また、本記事では「仕組み化」についてご説明していますが、その土台となる「成長ベンチャーのマネージャーに必須の思考フレーム11選」を以下から無料でご確認いただけます。
「仕組み化」に合わせて土台となる考え方が気になる方は、是非ご覧ください。
マネジメントの仕組み化とは?
そもそも「マネジメントの仕組み化」とは、一体何なのでしょうか。
一言で言えば、「個人のスキルや経験といった暗黙知に依存していたマネジメントを、誰がやっても一定の成果を出せる『再現性のある型』に落とし込むこと」です。
野球の指導に例えるなら、「ボールが来たらギュッと打て」と感覚的に教えるのが、仕組み化されていない状態です。これでは一部の天才しか育ちません。
一方で、「スタンスは肩幅に開き、ボールをここまで引きつけて水平にスイングする」と具体的な動作や基準を定義して教えるのが、仕組み化された状態です。
組織における「仕組み化」の有無で、具体的にどのような違いが生まれるのか比較してみましょう。
このように、仕組み化は単なるルール作りではありません。
組織が持続的に成長するための「OS」をインストールするようなものなのです。
なぜ今、マネジメントの仕組み化が必要なのか?
多くのリーダーがその重要性を感じながらも、日々の業務に追われ、後回しにしがちな「仕組み化」。しかし、それを放置すると、組織は確実に成長の壁にぶつかります。
実際に、株式会社EdWorksの調査によると、管理職が抱える悩みとして「どう育成して良いかわからない(46%)」となっています。さらに、62%もの管理職が「部下の育成に関して会社からの支援が足りていない」と感じています。
(出典:PR TIMES「企業の管理職の『部下育成の課題』に関する実態調査 2024年版」)
これらの悩みは、個々の管理職の能力不足というよりも、育成の「仕組み」が組織に存在しないことが根本的な原因です。
ではなぜ、今こそ仕組み化が必要なのでしょうか。その理由は大きく3つあります。
理由1:事業成長のボトルネックとなる「属人化」を防ぐため
創業期を支えるのは、経営者の圧倒的なリーダーシップと個人の才覚です。
しかし、組織が30人、50人と拡大するにつれ、その「個の力」が逆に成長の足かせとなることがあります。
実際にマネジメントが属人化すると、再現性が失われます。
特定のスタープレイヤーがいなければ成果が出ない組織は、その人が離れた瞬間に崩壊するリスクを常に抱えています。つまり、事業を安定的にスケールさせるためには、誰がやっても一定の品質を担保できる「仕組み」による標準化が不可欠なのです。
理由2:マネージャーの力量差をなくし、組織力を底上げするため
「Aチームは達成するが、Cチームは未達が続く…」
多くの成長企業が直面しているこの問題は、多くの組織で起こりがちです。
原因は、各マネージャーのスキルや経験のバラつきにあります。
目標のブレイクダウン、メンバーへのフィードバック、1on1の質。
これらが個々のマネージャーのやり方に委ねられていると、チームの成果は安定しません。
マネジメントの「型」を組織の共通言語として持つことで、初めて組織全体のパフォーマンスを底上げし、安定させることができるのです。
理由3:「自己流マネジメント」の迷いから抜け出すため
プレイヤーとしては優秀でも、マネージャーになった途端に壁にぶつかる人は少なくありません。
「良かれと思って」やったことが裏目に出たり、メンバーとの関係構築に悩んだりするのは、マネジメントの「正解」を知らないからです。
我流で手探りを続けるのは、本人にとっても組織にとっても大きなロスです。
体系化されたマネジメントの「型」を学ぶことは、リーダー自身が迷いなく行動するための指標を手に入れることであり、確かな自信と成長に繋がります。
マネジメントを仕組み化する4つのステップ
では、具体的にどうすればマネジメントを仕組み化できるのでしょうか。ここでは、組織の根幹から変えていくための4つのステップをご紹介します。
Step1:思考の仕組み化|判断基準をそろえる
全ての仕組みの土台となるのが、「何を目指し、何を大切にするか」という価値観(カルチャー)の浸透です。これがなければ、どんなルールを作っても形骸化してしまいます。
マネージャーの役割は、この価値観をチームの「思考のOS」としてインストールし、自らの言葉で噛み砕いたものをメンバーに伝えていくことです。
例えば、「顧客への価値提供」というバリューがあるなら、メンバーが日々の業務で判断に迷った際に「どちらがより顧客のためになるか?」という共通のモノサシで考えられるように導きます。具体的には、1on1で「この判断は、会社のどのバリューに基づいている?」と問いかけたり、チームの目標設定を会社のミッションと紐付けて説明したりすることが、思考を仕組み化する第一歩となります。
Step2:情報共有の仕組み化|コミュニケーションロスをなくす
組織が大きくなるほど、部門間の連携不足や情報伝達の遅れが問題になります。
これを防ぐのが、情報共有の仕組み化です。
具体的には、会議のアジェンダや議事録のフォーマットを統一する、日報や週報で報告すべき項目をテンプレート化する、といったアクションが有効です。
また、Slackなどのコミュニケーションツールでは、チャンネルの命名規則(例:#pj-〇〇 #team-営業)を定めたり、AsanaやTrelloといったタスク管理ツールで「誰が」「何を」「いつまでに行うか」を可視化したりすることも、認識のズレや業務の抜け漏れを防ぐ上で非常に効果的です。
Step3:業務の仕組み化|再現性を高める
特定のスキルを持つ人にしかできない業務をなくし、誰でも一定の品質で業務を遂行できるようにするのが、業務の仕組み化です。
その代表的な手法が、業務マニュアルやチェックリストの作成です。
しかし、単なるマニュアルで終わらせないためには、その業務の「目的」や「背景」、「なぜこの手順が必要なのか」といったWHYの部分まで言語化し、共有することが重要です。
これにより、メンバーは単なる作業者ではなく、目的を理解した上で主体的に業務に取り組みやすくなります。
Step4:育成の仕組み化|成長を加速させる
メンバーの成長を個々のマネージャーの力量任せにせず、組織として体系的に支援するのが育成の仕組み化です。
例えば、1on1ミーティングの目的を「メンバーの成長支援」と明確に定義し、話すべき内容をアジェンダとしてテンプレート化しておけば、雑談で終わることを防げます。
また、新人や中途入社者が早期に活躍するために「どのようなスキルを、どのレベルまで習得すれば成長と評価に繋がるのか」を明確に定義することも、組織全体の育成力を高める上で不可欠です。
しかし、これをゼロから設計し、効果的な研修コンテンツまで用意するのは容易ではありません。
そうした課題に対し、外部の専門知識を活用するのも有効な選択肢です。
マネディクでは、300社以上の成長ベンチャーを支援してきた知見を基に、貴社のフェーズに合った育成の仕組みづくりをサポートできる体制を整えています。

マネジメントの仕組み化が「難しい」と感じる3つの壁と乗り越え方
仕組み化の重要性を理解していても、実践には困難が伴います。
ここでは、よくある3つの壁とその乗り越え方について解説します。
壁1:「仕組み」が形骸化し、使われなくなる
最も多い失敗が、立派なルールやマニュアルを作ったものの、いつの間にか誰も使わなくなり形骸化してしまうケースです。これは、現場の実態とかけ離れた、一方的な「トップダウン」の仕組み化が原因であることがほとんどです。
乗り越え方
仕組みが形骸化する最大の原因は、それが現場の「自分ごと」になっていない点にあります。
特に、仕組みの土台となる価値観(カルチャー)は、ポスターに書いてあるだけでは浸透しません。これを生きた仕組みにするには、マネージャーが日々の業務の中で価値観を「使い続ける」姿勢が不可欠です。
例えば、1on1のフィードバックで「〇〇さんの今の行動は、まさにうちのバリューである『まずやってみる』を体現していたね」と具体的に紐づけたり、チームの意思決定で迷った際に「私たちのミッションに立ち返ると、どちらを選ぶべきだろう?」と問いかけたりする。このように、マネージャー自らが価値観を判断の「モノサシ」として使い続けることで、メンバーにもその思考が伝播し、カルチャーが血の通った生きた仕組みとして組織に根付いていきます。
壁2:メンバーのモチベーションが低下する
仕組み化を進めると、「管理が厳しくなった」「マイクロマネジメントされているようで窮屈だ」といったメンバーからの反発が生まれることがあります。ルールで縛ることが、かえってメンバーの主体性やモチベーションを奪ってしまうのです。
乗り越え方
仕組み化の「目的」を、メンバー一人ひとりに丁寧に伝え続けることが不可欠です。
仕組みはメンバーを管理・束縛するためのものではなく、
- 「無駄な作業をなくし、より創造的な仕事に集中するため」
- 「公正な評価を行い、頑張った人が報われるようにするため」のツールである、
というメッセージを繰り返し伝える必要があります。
仕組みの導入によって、メンバー自身にどのようなメリットがあるのかを明確に示すことが、納得感を得るための鍵となります。
壁3:仕組みづくりに時間を割けない
特に、自身もプレイヤーとして成果を求められるプレイングマネージャーは、「仕組みづくりが重要なのは分かるが、そんな時間はどこにもない」というジレマに陥りがちです。日々の業務に追われ、緊急度は低いが重要な「仕組みづくり」が、どうしても後回しにされてしまいます。
乗り越え方
全てを自分でやろうとせず、積極的に外部のテンプレートやツールを活用しましょう。
例えば、1on1のアジェンダや目標設定シートは、インターネットで検索すれば質の高いテンプレートがすぐに見つかります。
まずはそうしたものを活用し、自社に合わせてカスタマイズしていく方が、ゼロから作るより圧倒的に効率的です。
また、「今月は情報共有の仕組みだけ」「まずは業務マニュアルを一つだけ作る」というように、一度に全てをやろうとせず、領域を絞って少しずつ着手していくことが、挫折しないための現実的な進め方です。
まとめ
本記事では、属人化したマネジメントから脱却し、誰がやっても成果を出せる「自走する組織」を作るための具体的な方法論として、マネジメントの仕組み化を4つのステップで解説しました。
マネジメントの仕組み化は、一朝一夕に完成するものではありません。しかし、それは組織の成長痛を乗り越え、次のステージへ進むために不可欠な投資です。
とはいえ、日々の業務に追われる中で、何から手をつければ良いのか、自社に合った仕組みが何なのかを見極めるのは簡単ではありません。
そこで、この組織の仕組み化を確実に進めるための土台として、 300社以上の成長ベンチャーを支援する中で体系化された 「マネージャーに必須の11の思考フレーム」をご用意しました。
ベンチャー特有の「変化の大きさ」や「曖昧さ」に適応し、自律的に成果を生み出すための 具体的な考え方を全て公開していますので、ぜひご覧ください。