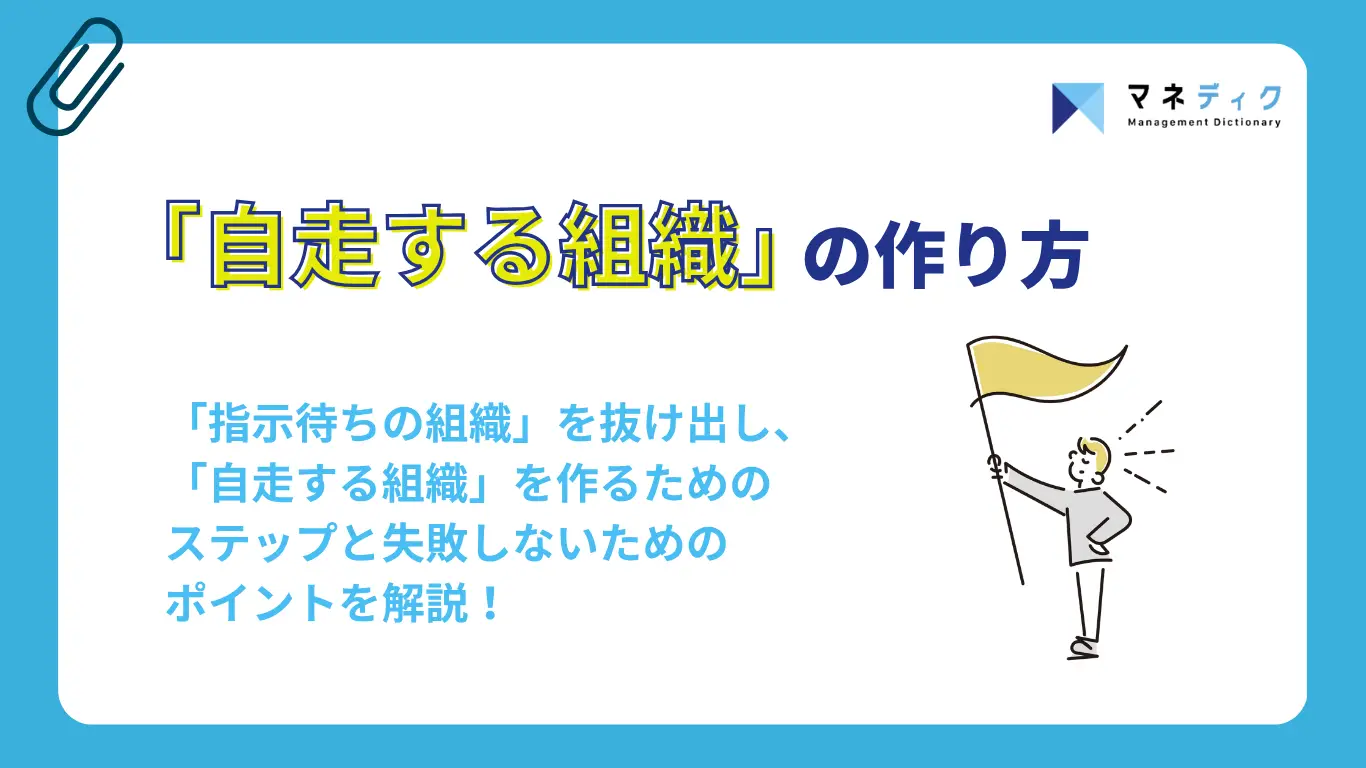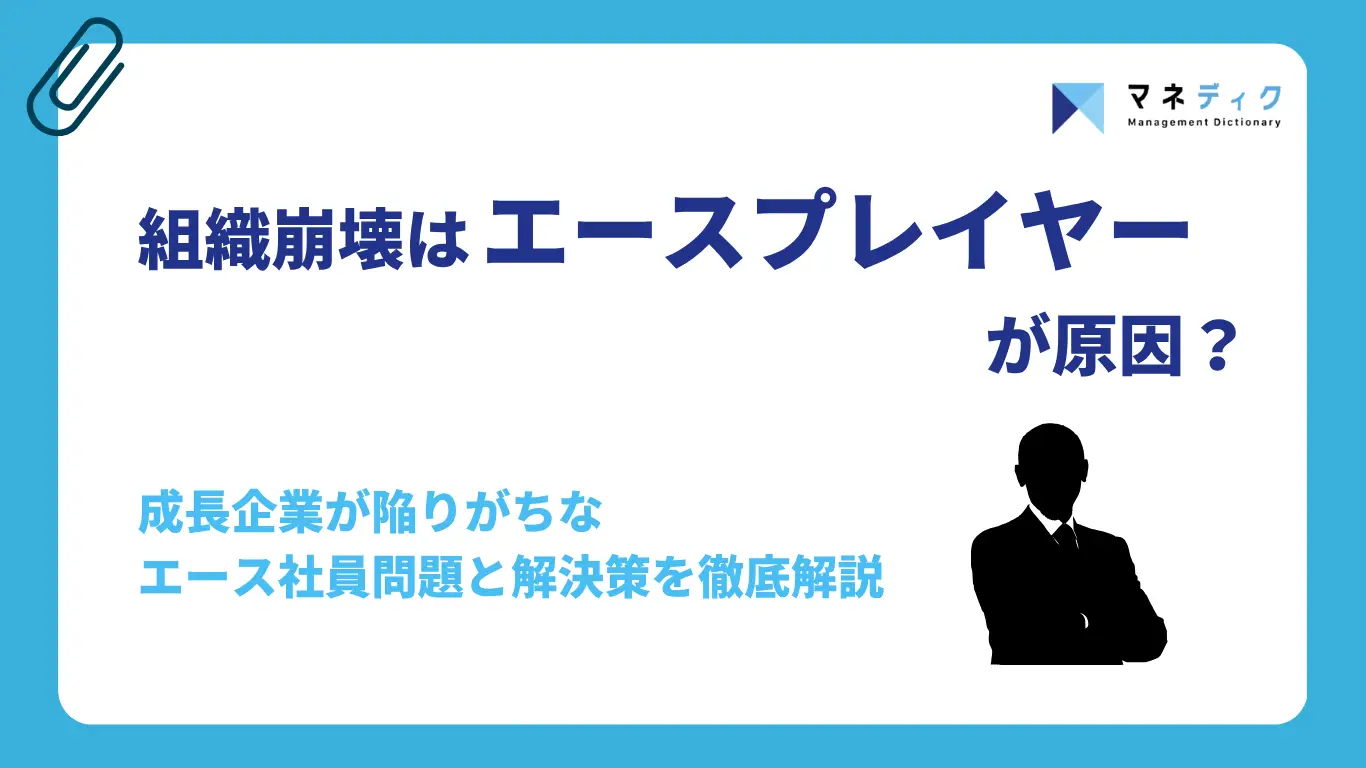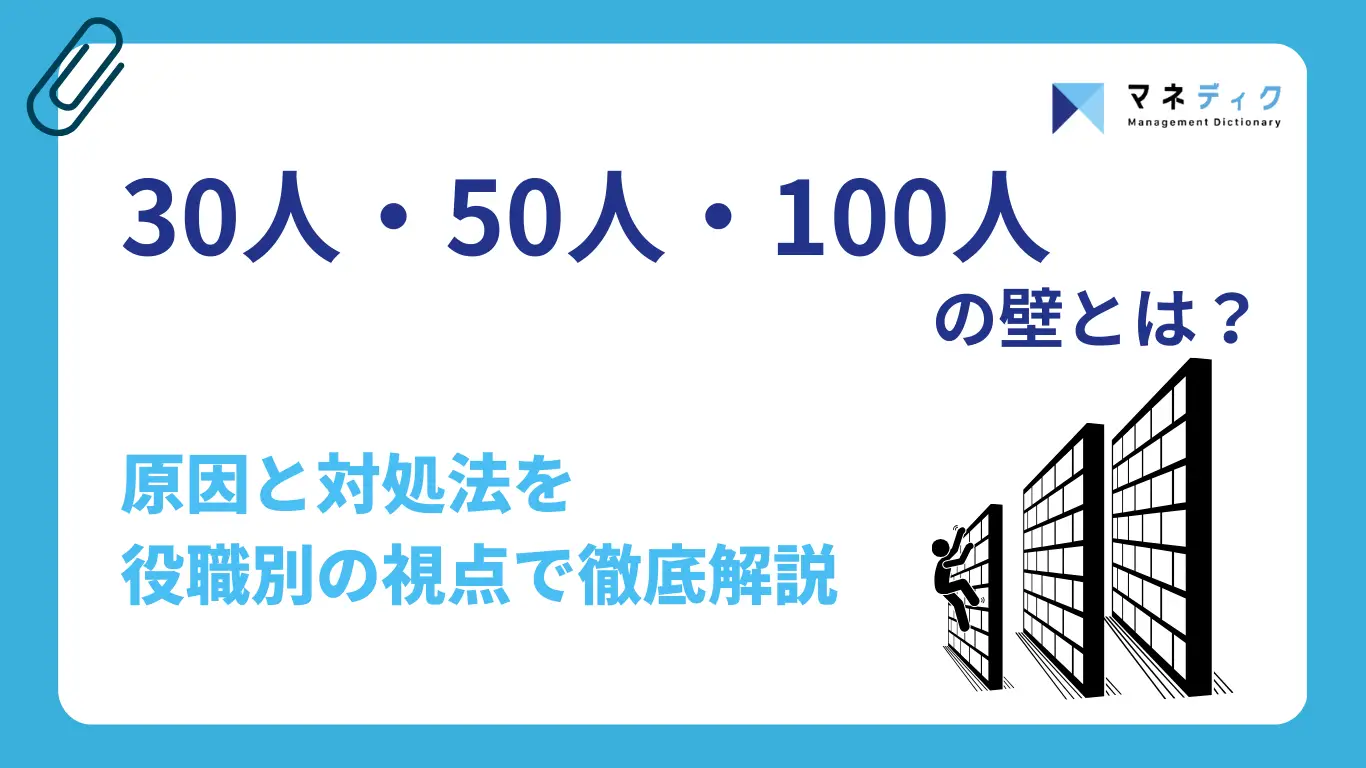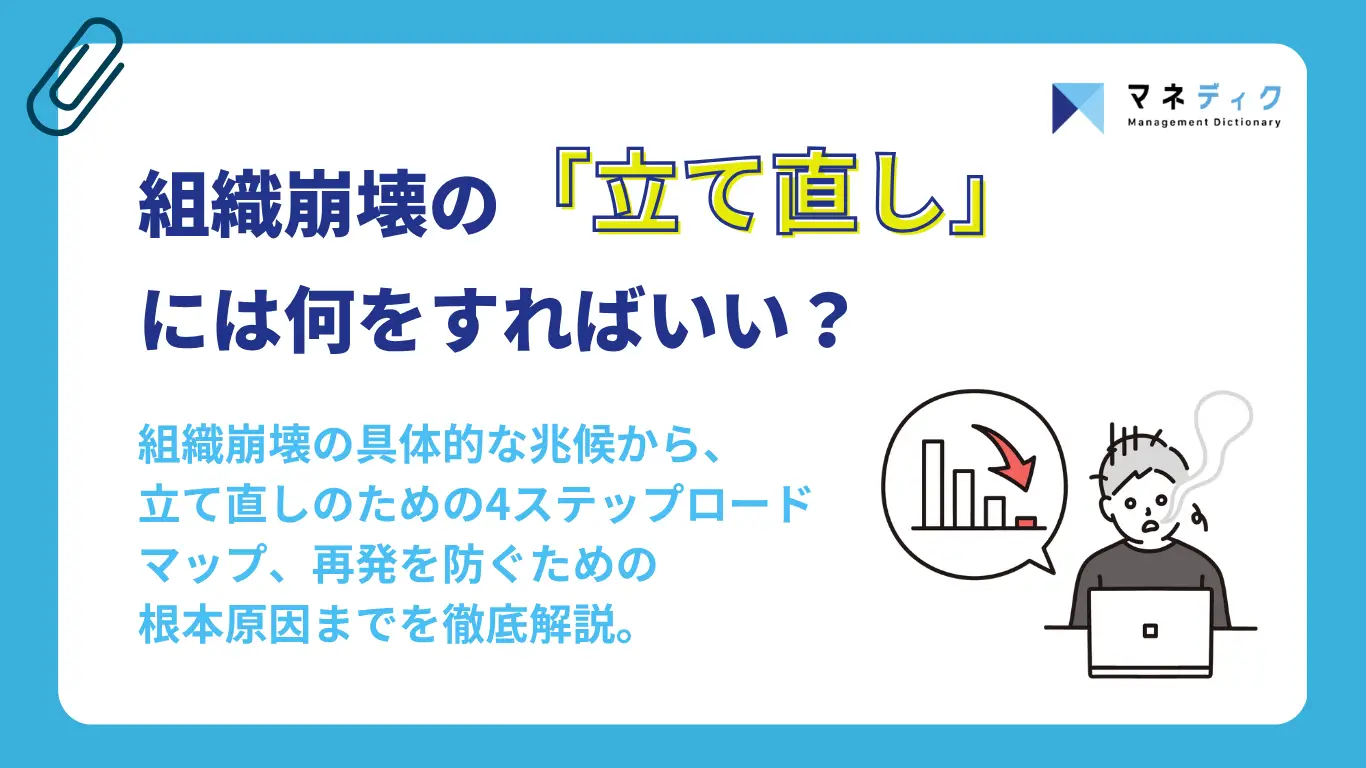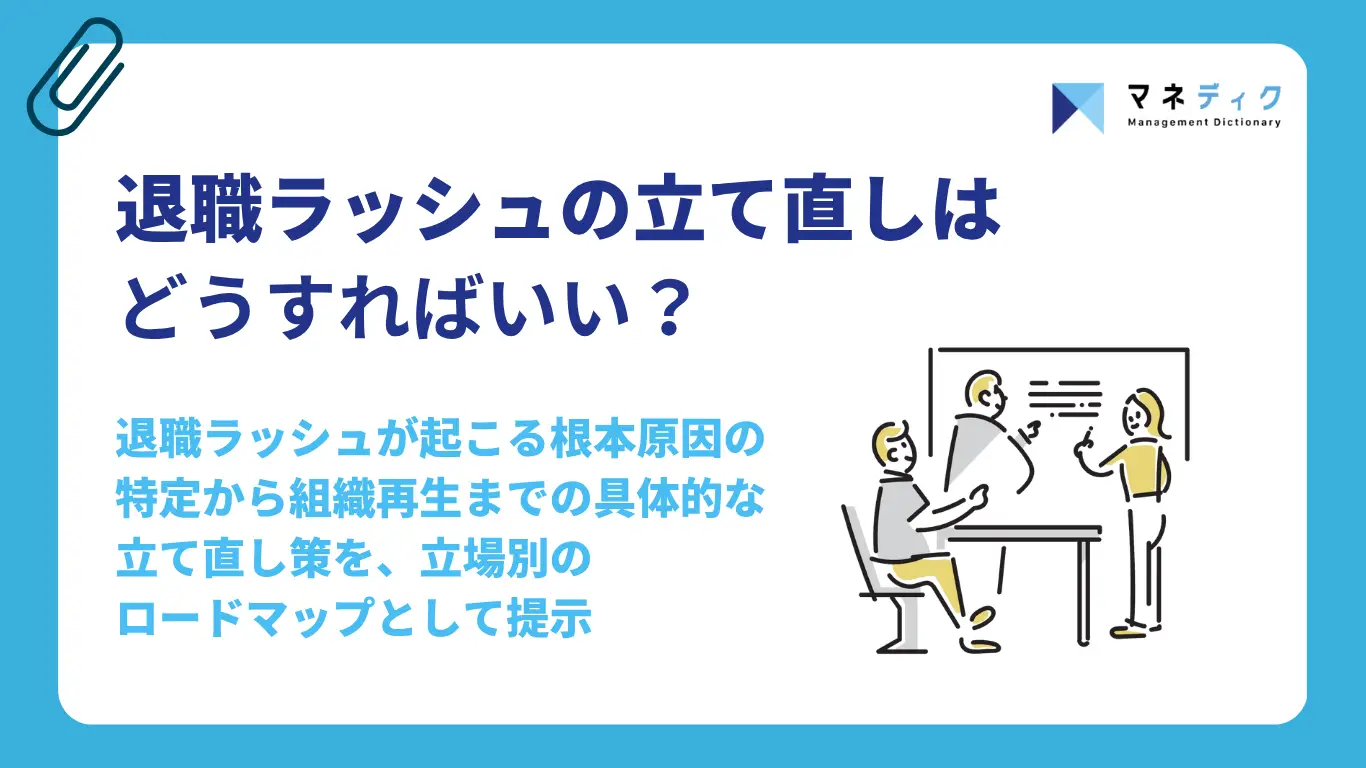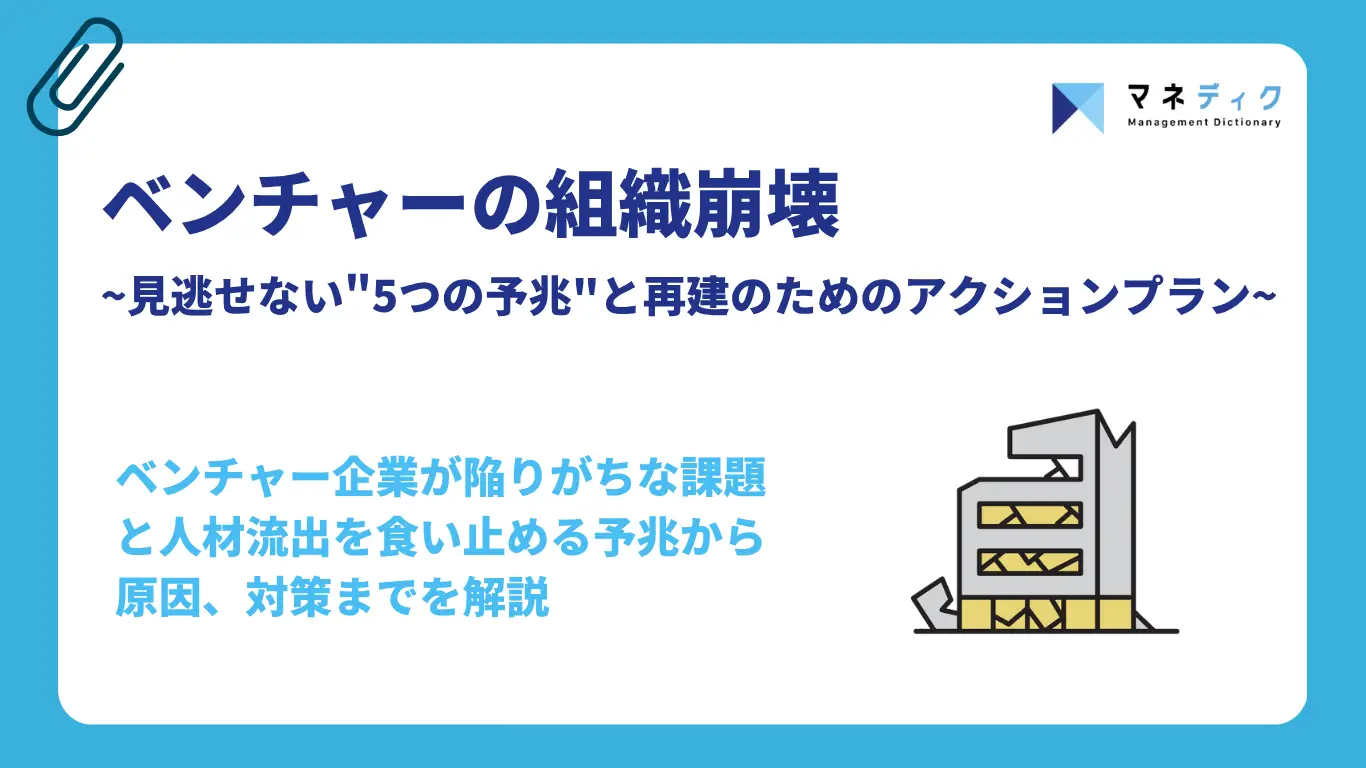離職防止に効果的な施策8選!成長企業の成功事例から学ぶ原因別の対策を徹底解説
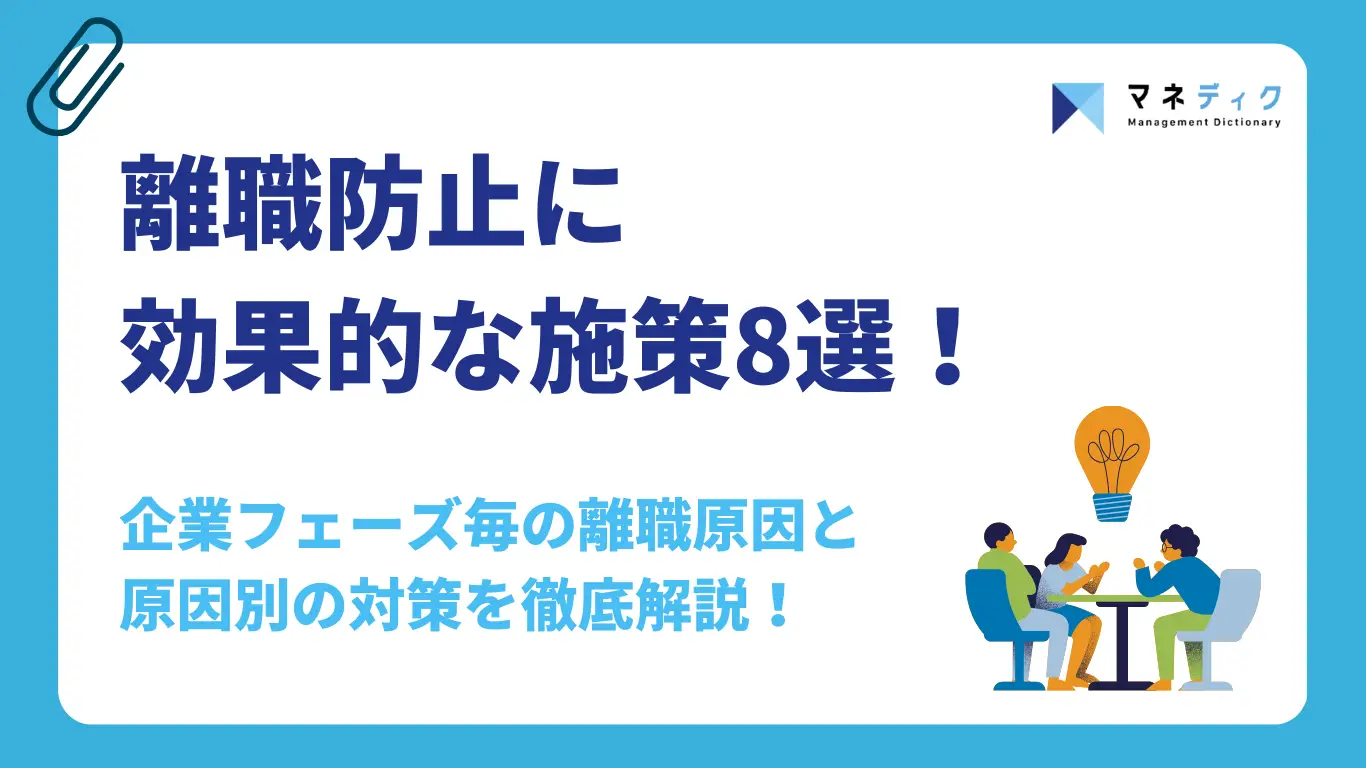
なぜ、あなたの会社の離職防止施策はうまくいかないのか?
「最近、期待していた若手が立て続けに辞めてしまう…」
「魅力的な福利厚生を導入したのに、離職率が改善しない…」
多くの経営者や人事担当者が、このような悩みを抱えているかと思います。
離職防止は、企業の持続的な成長に不可欠なテーマですが、多くの施策が期待したほどの効果を上げていないのが実情です。なぜ、あなたの会社の取り組みはうまくいかないのでしょうか。その根本的な原因を探ることから始めましょう。
離職の本当の理由は「個人のわがまま」ではない
社員が会社を去る時、その理由は「給与への不満」や「人間関係」といった言葉で語られがちです。しかし、それらはあくまで表面的なきっかけに過ぎません。
多くの場合、離職の根本原因は「個人のわがまま」ではなく、組織全体が抱える構造的な課題にあります。
特に、急成長しているベンチャー企業では、事業の拡大スピードに組織の成長が追いつかず、様々な歪みが生まれます。その歪みが、「働きがい」「成長実感」「公平な評価」といった、社員が求める要素を蝕んでいくのです。離職は、その結果として現れる危険信号と言えます。
「とりあえず福利厚生」は的外れな施策の典型
離職防止の施策と聞いて、多くの人が思い浮かべるのが「福利厚生の充実」や「インセンティブ制度の導入」です。
もちろん、これらも全く無意味ではありません。しかし、それだけで離職を防止することは不可能です。
なぜなら、これらは組織の本質的な課題解決には繋がらない、いわば対症療法に過ぎないからです。家の土台が傾いているのに、壁紙を新しく張り替えるようなものです。
組織の根本的なOS、すなわち「カルチャー」や「仕組み」に目を向けなければ、どんなに魅力的な制度を導入しても、社員の流出を止めることはできません。
企業の成長フェーズで離職の原因は変化する
さらに重要なのは、離職を引き起こす原因が企業の成長フェーズによって刻々と変化するという事実です。
創業期には問題にならなかったことが、「30名の壁」「100名の壁」といった組織の拡大期において、深刻な課題として浮上してきます。
| 企業フェーズ | 状況・課題 |
| 創業期〜30名 | 社長の想いが直接伝わり、一体感で乗り切れる時期。 |
| 30名〜100名 | 新しいメンバーが増え、創業期からの価値観が揺らぎ始める。マネジメントや評価の仕組みが必要になる時期。 |
| 100名〜 | 部署間の連携が希薄になり、組織としての一体感が失われがちになる。理念の再浸透が不可欠な時期。 |
自社の現状がどのフェーズにあるのかを正しく認識し、その段階で起こりうる特有の課題に先手を打つことこそ、効果的な離職防止策の第一歩です。
【企業の壁別】離職の根本原因と対策の方向性
先ほど軽くご紹介したように、組織フェーズ毎に離職の根本原因は変わります。
ここでは、フェーズごとの根本原因と、打つべき施策の方向性を解説します。
【〜30名の壁】ビジョン・カルチャーの浸透不足
従業員が30名を超えると、社長が全社員と直接コミュニケーションを取ることが難しくなり、ビジョンやバリュー、カルチャーの浸透不足という課題にぶつかります。
これまでは暗黙のうちに共有されていたはずの「会社の目指す方向性(ビジョン)」や「行動指針(カルチャー)」が、新しく入社したメンバーには正しく伝わらなくなるのです。
結果として、「何のためにこの仕事をしているのか分からない」「会社の方向性が見えない」といった不安や迷いが生じ、初期の離職に繋がります。
【施策の方向性】
- このフェーズで重要なのは、これまで無形だったビジョンやカルチャーを「言語化」し、組織内のメンバーで徹底的に擦り合わせることです。具体的な対策としては、ワークショップや定期的な全社でのイベントを通じて擦り合わせるのが有効です。
【30〜100名の壁】評価・育成の仕組みの未整備
組織がさらに拡大し、50名、100名と近づくにつれて、次なる壁が訪れます。
それは、マネジメント層の不足と、評価・育成の仕組みが未整備であることから生じる混乱です。
プレイヤーとして優秀だった社員が突然マネージャーになり、手探りのマネジメントで部下を疲弊させてしまう。あるいは、誰が何を基準に評価されているのかが不透明で、「頑張っても報われない」という不公平感が蔓延する。
このような状態は、特に成長意欲の高い中堅社員の離職を加速させます。
【施策の方向性】
- このフェーズでは、属人的なマネジメントから脱却し、「公平性と納得感のある評価制度」を構築すること、そして、管理職を体系的に育成するプログラムへの投資が急務となります。具体的には、ベンチャー・中小企業向けの管理職研修や定期的なマネージャー会議の実施が有効です。
【100名〜の壁】組織の一体感の希薄化
従業員が100名を超えると、組織は良くも悪くも「会社」らしくなります。
部署ごとの縦割りが進み、他のチームが何をやっているのか見えにくくなる「セクショナリズム」が蔓延。創業期にあったはずの組織の一体感は失われ、「自分の仕事が会社全体のどこに貢献しているのか」という実感を得にくくなります。
このフェーズでは、組織のサイロ化によるコミュニケーション不全や、会社への帰属意識の低下が主な離職原因となります。
【施策の方向性】
- 改めて企業の理念やビジョンに立ち返り、それを組織の隅々まで浸透させるための意図的な仕組みや、部門横断的なコミュニケーションを活性化させる仕掛けが不可欠です。
明日から実践できる!具体的な離職防止施策8選
企業のフェーズごとの課題を理解した上で、具体的にどのようなアクションを取るべきか。ここでは、明日から実践できる8つの離職防止施策を、「なぜそれが必要なのか」という視点と共に解説します。
1. 「キャリア面談」で、会社のビジョンと個人のキャリアを接続する
1つ目の施策は、企業のビジョンと社員一人ひとりのキャリアを接続することです。
そのビジョンの中で、社員一人ひとりが「どのような役割を果たし、どう成長できるのか」という個人のキャリアパスを具体的に示して、会社のビジョンと接続することが重要です。
月に一度、もしくは半期に一度のタイミングで直属の上司が「キャリア面談」の時間を設け、本人の希望を聞き、会社として提供できる成長機会やポジションを具体的に話し合います。
会社の成長ベクトルと個人の成長ベクトルが重なる部分を見つけることが、「自分ごと」として仕事に取り組む強力な動機付けになります。
2. 評価項目に「バリュー評価」を導入し、評価者同士で「目線合わせ会議」を実施する
「何をすれば評価されるのか」を明確にするため、評価項目に「売上」などの定量目標だけでなく、「カルチャーやバリューに沿った行動ができたか」という項目を加えましょう(例:評価全体の30%をバリュー評価とする)。
さらに、評価者である管理職を集め、「Aさんのこの行動は、バリューの〇〇を体現しているのでS評価」「Bさんの目標達成は素晴らしいが、行動はB評価」といったように、具体的な事例を基に評価基準の目線合わせを行う「評価キャリブレーション会議」を必ず実施してください。
評価項目の中に「バリュー評価」を追加することで、成果だけでなく成果に向かった行動も評価されるので、納得感が劇的に高まります。
3. 1on1のアジェンダを「P・C・P」で設計する
形骸化しがちな1on1を意味あるものにするため、アジェンダを「P:Performance(業務進捗)」「C:Condition(心身の健康)」「P:Private(プライベート含めた個人の状況)」の3つの観点で設計しましょう。
特に「Condition」と「Private」に時間を割くことで、メンバーが抱える悩みや離職のサインを早期に察知できます。
1on1を形骸化させないための適切な効果測定法は以下の記事にて詳細に解説しているので、ご興味ある方はご覧ください。

4. 新任管理職向けに「マネジメント研修」を必須化する
プレイヤーとして優秀だった人材が、優れたマネージャーになれるとは限りません。
新しく管理職に就任した社員には、「目標設定」「コーチング」「フィードバック」「労務管理」といったマネジメントの基礎を学ぶ研修を必須プログラムとして提供しましょう。
特に、部下の本音を引き出し、成長を支援するための「フィードバックスキル」は、ロールプレイング形式で徹底的にトレーニングすることが効果的です。
5. エンゲージメントサーベイの結果を基に、部署ごとの「改善アクションプラン」の作成を義務付ける
エンゲージメントサーベイは、実施して終わりでは意味がありません。
サーベイツールで得られた結果を基に、各部署の管理職が主体となって「私たちの部署の強み・弱みは何か」「次の四半期で、この数値を改善するために具体的に何をするか」という改善アクションプランを作成し、全社に公開することをルールにしましょう。
組織改善に本気で取り組む姿勢を示すことが、社員の信頼に繋がります。
6. 採用プロセスに「カルチャーフィット面接」と「リファレンスチェック」を導入する
スキルや経歴だけで採用を決めると、入社後に「価値観が合わない」というミスマッチが起こりがちです。
一次・二次面接とは別に、人事担当者や役員が候補者の価値観や仕事観を深掘りする「カルチャーフィット面接」のステップを設けましょう。
また、候補者の許可を得て、前職の上司や同僚に働きぶりについてヒアリングする「リファレンスチェック」を行うことも、ミスマッチ防止に極めて有効です。
7. 「ピアボーナス制度」や「書籍購入・資格取得支援制度」を導入する
給与や賞与といった会社からの報酬だけでなく、社員同士が日々の感謝や称賛をポイントとして送り合える「ピアボーナス制度」は、コミュニケーションの活性化と承認文化の醸成に繋がります。
また、「月額1万円まで書籍購入・セミナー参加費を補助」といったスキルアップ補助制度は、社員の自律的な学習意欲をサポートし、「成長できる環境だ」という実感をもたらします。
8. ポジティブな退職を支援する文化を創る
一見矛盾するようですが、円満な退職を認め、卒業生を応援する文化は、結果的に組織の魅力を高めます。
「この会社は社員のキャリアを本気で考えてくれる」という信頼感が、現役社員のエンゲージメント向上にも繋がるのです。
アルムナイ(退職者)ネットワークを築き、将来的な協業や再入社の可能性を残すことも有効な戦略です。
ここでは8つの具体的な離職防止施策をご紹介してきましたが、これらの施策を継続的に実施して効果測定をし、離職防止まで繋げるのはかなり工数がかかります。
特にベンチャー/急成長企業だとなおさらリソースも時間もないと思います。
ただ社員の離職防止は組織運営をするうえで、最も重要な項目の1つなので思いきって投資すべきかと思います。特に優秀人材(キーマン)の離職は、単に1人の社員が離職するだけでなく、組織全体に莫大なインパクトを与えます。
我々マネディクでは特に成長ベンチャー企業に特化した複数の組織開発サービスをご提供しており、これまで300社以上のベンチャー/急成長企業の組織開発を支援してきました。
ご相談いただければ、離職防止のための1on1の設計から運用、ベンチャー管理職向けの研修、社員のエンゲージメント向上・定着率向上のカルチャーワークショップなど様々なサービスを各社のご状況にカスタマイズしてご支援させていただきます。
ご興味をお持ちいただけましたら、まずは下記より詳しいサービス内容や導入事例、料金体系をまとめた資料を無料でダウンロードしてご覧ください。

【取り組み別】離職防止に成功した企業の事例3選
ここでは、実際に離職率の改善に成功した企業の事例を、その取り組みの背景と共に紹介します。自社の課題と照らし合わせながら、ご覧ください。
事例1:A社「カルチャーブックで理念浸透」
急成長に伴い社員数が50名を超えたITベンチャーA社では、「創業時の熱量が伝わらない」という課題に直面。そこで、会社の価値観や行動指針を明文化した「カルチャーブック」を作成し、全社員に配布。採用面接や新人研修、日々の意思決定の場面で活用することで、組織のOSを統一。結果、理念への共感を軸とした一体感が生まれ、若手社員の定着率が大幅に向上しました。
事例2:B社「評価制度の全面改定で納得感を醸成」
100名規模のB社では、旧来の評価制度への不満が噴出していました。そこで、マネージャーと人事が一体となり、数ヶ月かけて評価制度を全面改定。「会社のバリューを体現する行動」を評価項目に加えることで、業績だけでなくプロセスや組織貢献も正当に評価される仕組みを構築。評価の納得感が高まり、社員のモチベーション向上に繋がりました。
事例3:C社「1on1の徹底でマネージャーとメンバーの信頼関係を構築」
チームの離職に悩んでいたC社の開発部門。原因は、管理職のマネジメントスキル不足にありました。そこで、全管理職を対象に1on1の研修を実施。「聞く」スキルと「フィードバック」の技術を徹底的にトレーニングしました。質の高い対話が増えたことで、管理職とメンバーの信頼関係が深まり、チームの心理的安全性が向上。個々のパフォーマンスも改善し、離職に歯止めがかかりました。
離職防止の施策に関するよくある質問
最後のパートでは、離職防止、離職防止施策に関するよくある質問に回答していきます。
Q1. 社員が離職する最も多い原因は何ですか?
A. 厚生労働省の雇用動向調査などを見ると、男性は「給与」、女性は「労働条件」や「人間関係」が上位に来ることが多いです。
しかし、これらは表面的な理由であることも少なくありません。その背景には、本記事で解説したような「正当に評価されていないと感じる」「この会社でのキャリアパスが見えない」「成長機会がない」といった、より本質的な課題が隠れているケースが非常に多いです。
Q2. 離職防止に活用できる助成金はありますか?
A. はい、あります。
代表的なものに、厚生労働省が管轄する「人材確保等支援助成金」があります。これは、魅力的な職場づくりのために、評価・処遇制度や研修制度、健康づくり制度などを導入し、従業員の離職率低下に取り組む事業主に対して助成する制度です。
制度の詳細は年度によって変わるため、必ず厚生労働省の公式サイトで最新の情報をご確認ください。
Q3. 社員の離職予兆に気づくサインはありますか?
A. 明確なサインはありませんが、いくつかの変化が予兆となることがあります。
例えば、「会議での発言が減った」「同僚とのコミュニケーションを避けるようになった」「将来の話をしなくなった」「業務へのモチベーションが明らかに低下している」「休みがちになった」などが挙げられます。
こうした変化にいち早く気づくためにも、日頃からのコミュニケーションや1on1ミーティングが重要になります。