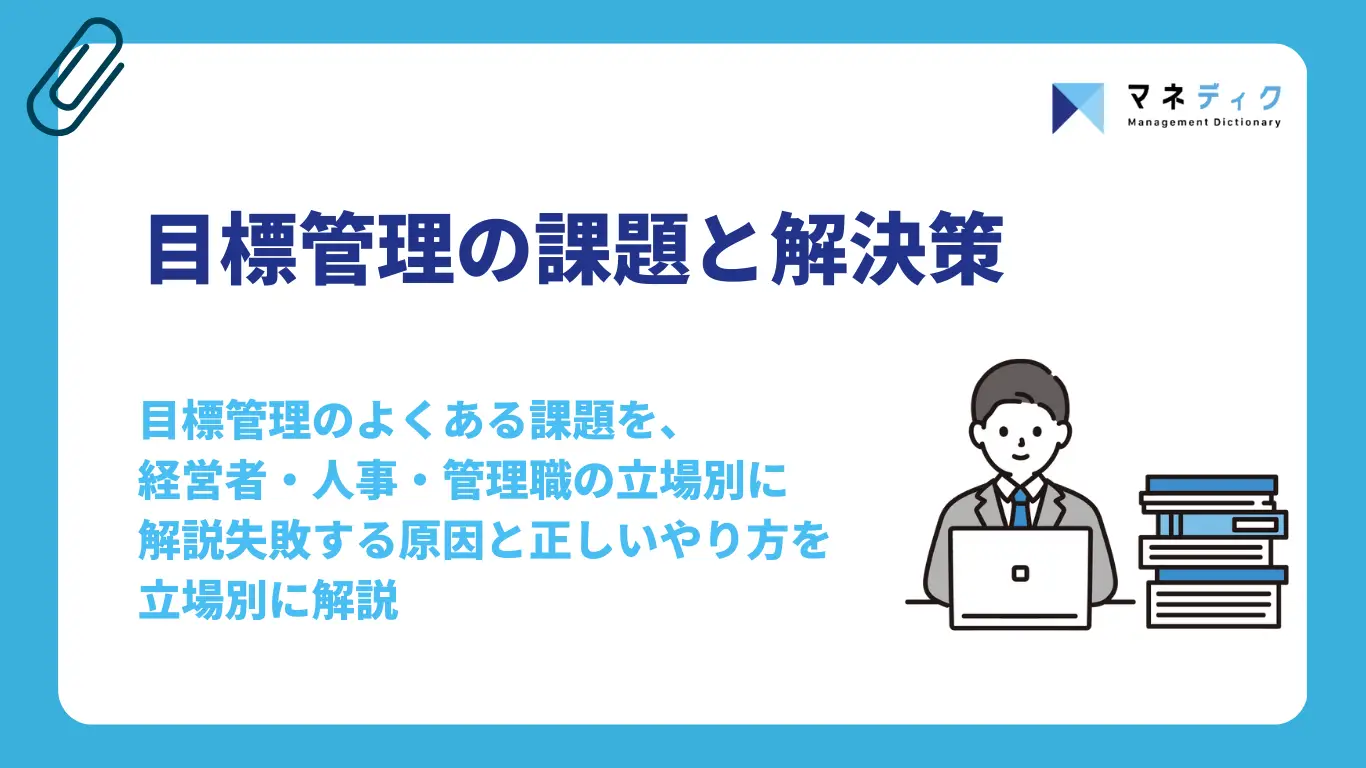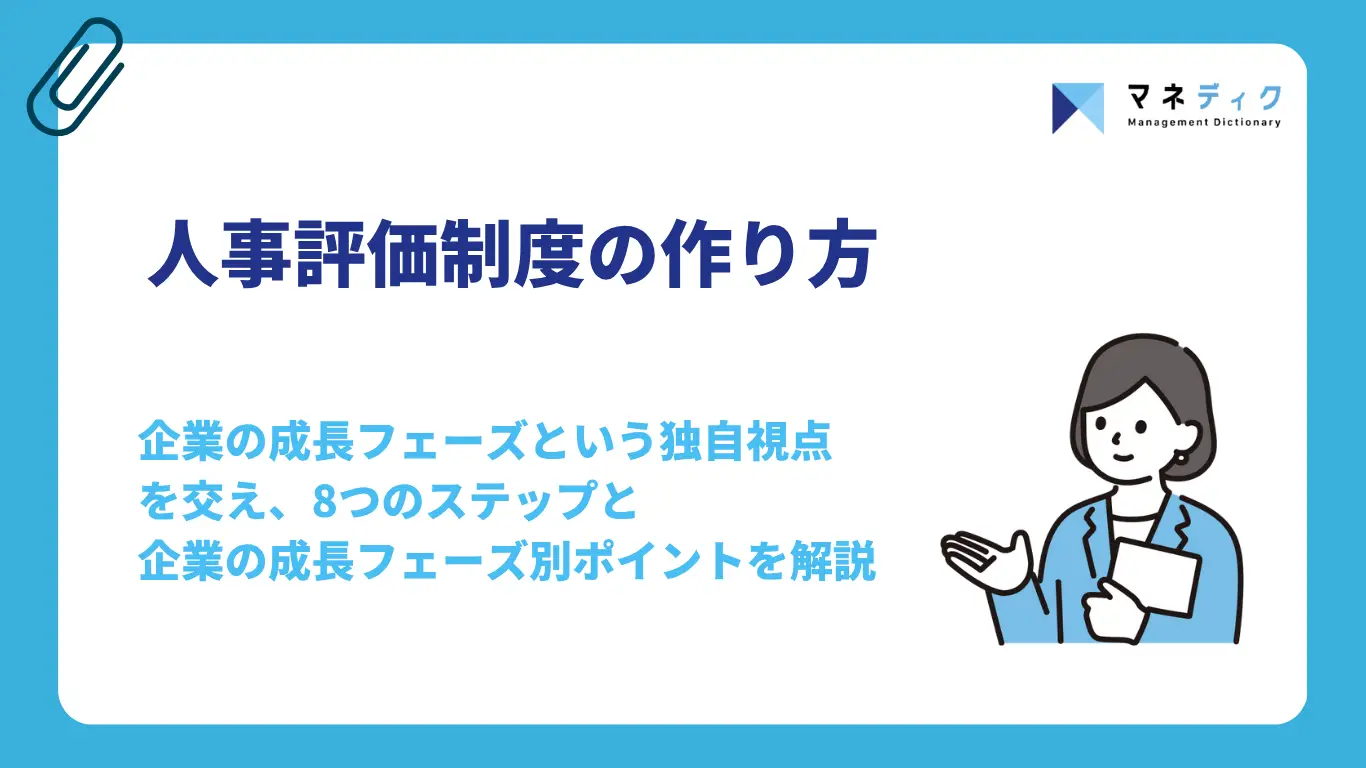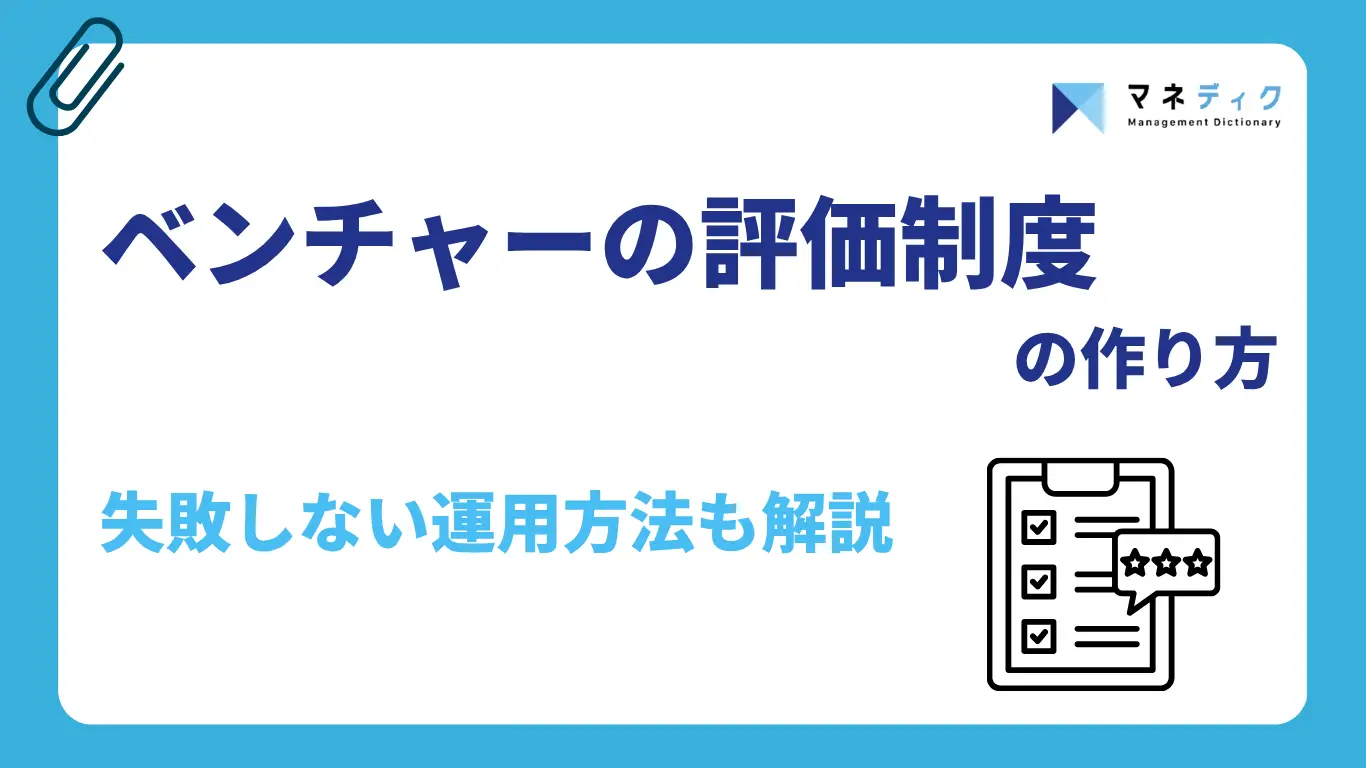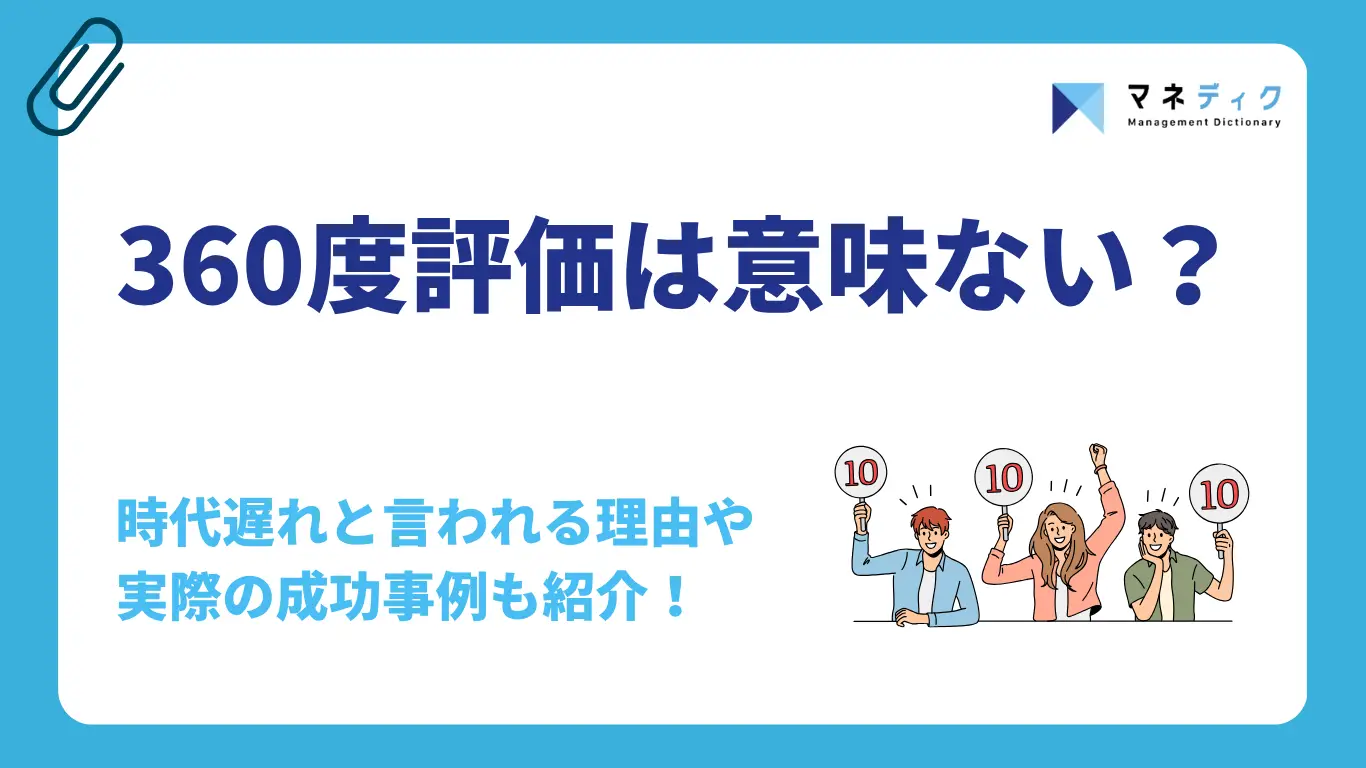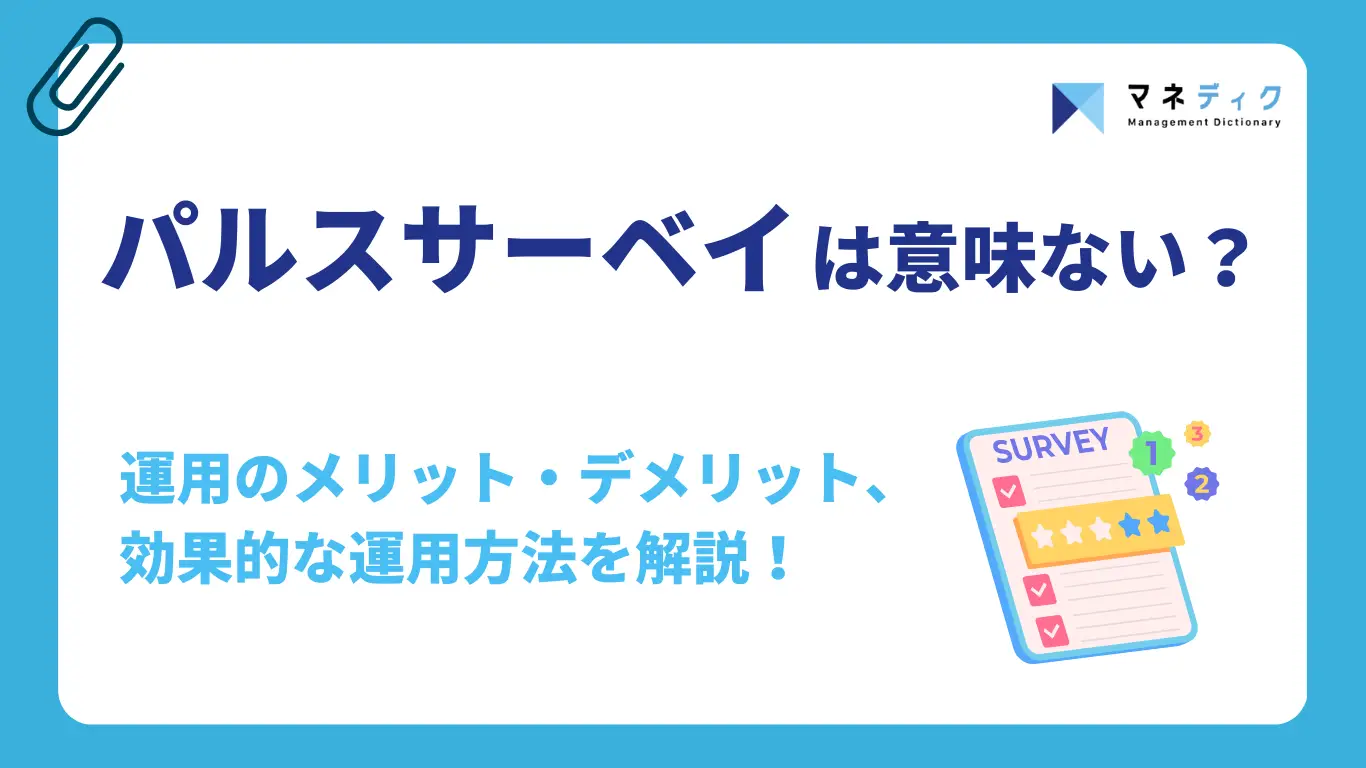納得感のある評価制度とは?作り方の5ステップと不満を解消する運用の仕方を解説
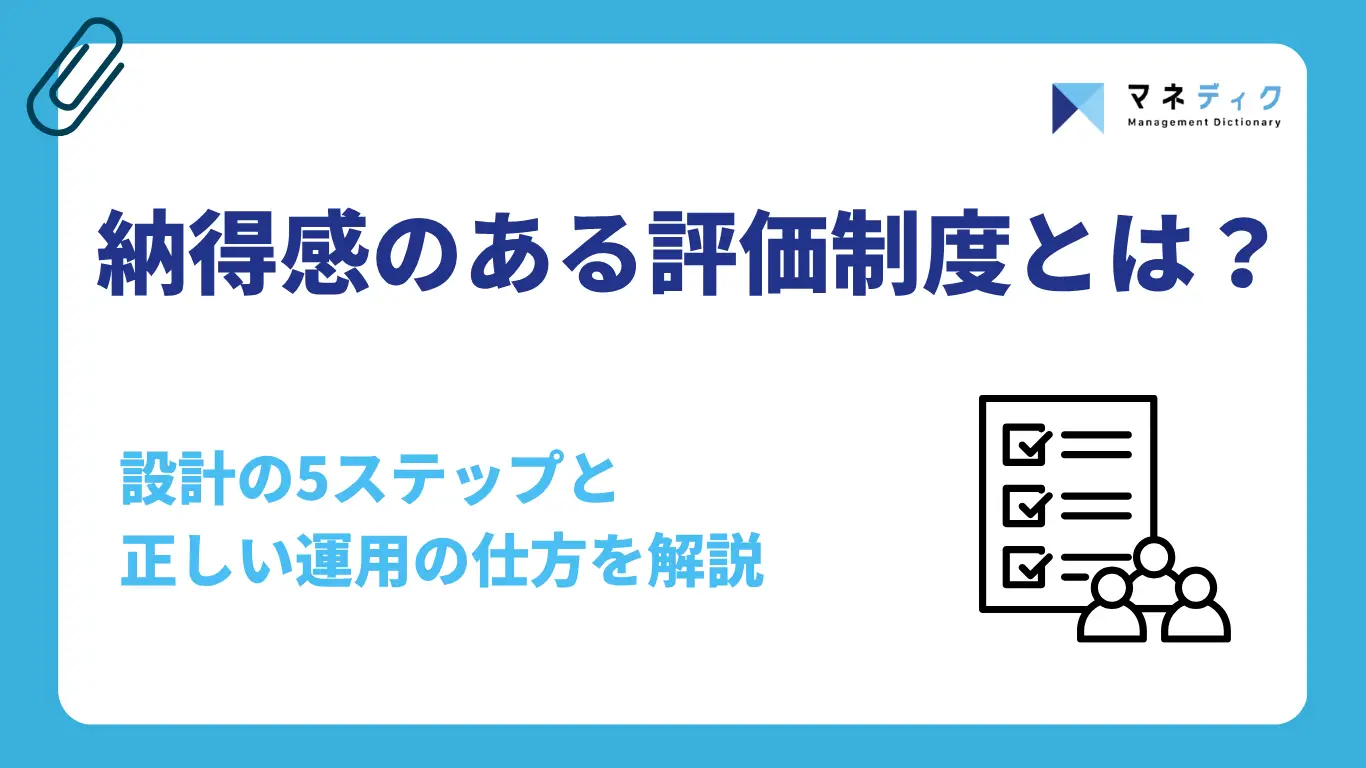
「納得感が低い」評価制度の4つの特徴
「評価基準が曖昧で、上司によって評価がバラバラだ」 「自分の頑張りが正当に評価されている気がしない」
もし、会社でこのような声が聞こえてくるのであれば、それは評価制度が組織の成長を阻害する要因になっている危険なサインです。特に、事業が急拡大するフェーズにおいて、多くの企業がこの「評価の壁」に直面します。
納得感の低い評価制度は、社員のモチベーションを削ぎ、優秀な人材の離職を招きかねません。
その原因は、大きく分けて「制度の設計思想」と「現場での運用実態」という2つの側面に潜んでいます。ここでは、多くの企業で見られる4つの共通点を深掘りしていきます。
特徴1:評価の「目的」が曖昧で、理念と連動していない
納得感が低い評価制度に共通する最大の特徴は、評価制度が「何のために存在するのか」という根本的な目的、つまり「評価フィロソフィー」が組織内で共有されていない点にあります。
企業の理念やバリュー(行動指針)と評価が全く連動していなければ、社員は何を基準に行動すれば評価され、組織に貢献できるのかを理解できません。
例えば、「挑戦を称賛する」というバリューを掲げながら、評価の現場では減点方式で失敗を厳しく追及する。これでは社員は挑戦を恐れて萎縮してしまい、理念は形骸化します。
評価制度とは、企業が大切にする価値観を社員に伝え、その行動を促すための強力なメッセージです。「誰が、何を、どのように実行すれば、会社のビジョン実現に近づくのか」を示せていなければ、それは単なる「査定ツール」に過ぎず、社員の納得感を得ることはできません。
特徴2:評価基準が曖昧で、評価者の「主観」に依存している
「主体性」「協調性」「コミュニケーション能力」といった、聞こえは良いものの解釈が人によって大きく異なる定性的な項目だけで評価しようとすると、必ず評価者の主観が入り込みます。
その結果、「声が大きい部下」や「自分とウマが合う部下」の評価が高くなる、といった不公平感が生まれるのです。
これでは、部下は本質的な成果を追求するのではなく、「上司の顔色を伺うこと」が目的になってしまいます。評価の納得感を高めるには、「主体性」を「定例会議で月1回以上、新たな改善提案を行う」のように、誰が見ても客観的に判断できる具体的な「行動レベル」まで落とし込んだ評価基準の設計が不可欠です。
評価とは、印象ではなく客観的な事実(ファクト)に基づいて行われるべきなのです。
特徴3:評価プロセスが「ブラックボックス化」している
「いつ、誰が、どのように評価を決めているのか分からない」。評価が決定されるまでのプロセスが不透明であることも、社員の不信感を招く大きな要因です。
自分の直属の上司が高く評価してくれても、その上の役員会議で、何の根拠もなく評価が覆される。このような状況では、社員は何を信じて努力すれば良いのか分からなくなります。
大切なのは、評価のプロセスとスケジュールを事前に全社員に公開し、透明性を確保することです。
自己評価、上長評価、そして評価者同士で基準の目線合わせを行う「評価調整会議」など、評価が決定されるまでの一連の流れを明確にするだけで、「会社は公平な評価をしようと努力している」という信頼が生まれ、社員の安心感と納得感は大きく向上します。
特徴4:評価のフィードバックが一方的、あるいは不十分である
たとえ評価結果が本人の期待通りでなかったとしても、その理由が客観的な事実に基づいており、次に向けた具体的な期待やアドバイスがあれば、多くの部下は前向きに結果を受け止め、次の成長へと繋げることができます。
しかし、多くの現場では、上司が結果を一方的に通達するだけの「評定伝達式」で終わってしまっています。
これでは、部下は「評価された」のではなく「ジャッジされた(裁かれた)」と感じるだけです。評価面談は、部下の成長を支援するための1on1の場であり、過去を振り返り、未来のキャリアを共に考えるための重要な対話です。
このフィードバックの質こそが、制度への最終的な納得感を決定づけると言っても過過言ではありません。
納得感のある評価制度がもたらす3つの経営的メリット
評価制度の納得感を高めることは、単に社員の不満を解消するだけでなく、企業経営に大きなプラスの効果をもたらします。これは、継続的な事業成長のための、極めて重要な経営課題なのです。
メリット1:従業員のエンゲージメントが劇的に向上する
自分の仕事ぶりが公正に評価され、会社の成長に貢献できていると実感できる環境は、従業員のエンゲージメントを飛躍的に向上させます。
「正当に評価される」という安心感は、仕事への当事者意識や、より高い目標に挑戦する健全な意欲を引き出します。
エンゲージメントの高い組織は、生産性や顧客満足度の向上、さらには離職率の低下といった具体的な経営成果に直結することが、数多くの調査で明らかになっています。
メリット2:人材の定着と成長を促進する
納得感のある評価制度は、特に優秀な人材のリテンション(定着)に絶大な効果を発揮します。
評価面談を通じて、自身の強みや成長課題が明確になり、この会社で働き続けることでどのようなキャリアパスを描けるのかを具体的にイメージできれば、社員は「ここで成長し続けたい」と感じるようになります。
評価とは、社員の成長を加速させるための羅針盤です。会社が自分のキャリアに真剣に向き合ってくれているという実感こそが、エンゲージメントの源泉となるのです。
メリット3:組織全体の生産性が最大化される
評価制度を通じて会社のビジョンや戦略が現場の隅々まで浸透すると、社員一人ひとりが「会社の目標」と「自分の業務」を接続して考えられるようになります。
「会社がどちらの方向に進もうとしているのか」「その中で自分は何を期待されているのか」が明確になるためです。その結果、全員が同じ方向を向いて自律的に行動できるようになり、部門間の連携もスムーズになります。
評価という仕組みを通じて経営と現場の意思疎通を図ることが、組織全体の生産性を最大化し、事業成長を加速させるのです。
【5ステップで完全解説】納得感のある評価制度の作り方
ここからは、人事責任者や経営者向けに、納得感のある評価制度をゼロから構築するための具体的な5つのステップを解説します。
Step1:企業の「ありたい姿」を定義し、評価の目的を定める
最初に、最も重要な問いから始めます。
「私たちは、どのような組織でありたいのか?」
この「ありたい姿」こそが、評価制度の揺るぎない土台となります。企業のミッション・ビジョン・バリューを再確認し、それを実現するために、社員にどのような行動を期待するのかを言語化しましょう。
評価制度は、この「期待する行動」を社員に指し示し、促進するためのメッセージツールとして設計します。目的が明確になることで、制度の細部まで一貫性を持たせることができます。
Step2:等級制度を設計し、役職ごとの期待役割を明文化する
次に、社員の成長ステップを示す「等級制度」を設計します。
メンバー、リーダー、マネージャーといった等級ごとに、「求められる責任範囲」「必要なスキル」「具体的な行動レベル」を明確に定義します。
これが、社員にとってのキャリアパスの道標となります。自分が今どの位置にいて、次にどの山を目指せば良いのかが分かれば、日々の業務にも目標を持って取り組むことができます。
Step3:バリュー評価と成果評価を組み合わせた評価項目を作成する
評価項目は、「成果(What)」と「行動(How)」の両面から設定することが重要です。
売上などの定量的な成果だけでなく、その成果を出すプロセスにおいて、企業のバリューに沿った行動ができていたかを評価に組み込みます。
例えば、「チームワーク」というバリューがあるなら、「他部署を巻き込み、プロジェクトを成功に導いたか」といった具体的な行動を評価項目に設定します。これにより、「結果さえ出せば良い」という考えを防ぎ、組織としての一体感を醸成します。
Step4:評価プロセスとスケジュールを設計し、全社に公開する
評価がいつ、どのようなプロセスで決定されるのかを明確にし、全社員に公開します。
「①自己評価 → ②上長評価 → ③部門内での評価調整会議 → ④最終決定」といった一連の流れと、それぞれの期間を明記したスケジュールを共有しましょう。
プロセスを透明化することで、評価に対する不信感を払拭し、「会社は公正な評価をしようとしている」という信頼を育むことができます。
Step5:評価者研修を実施し、評価基準の目線合わせを行う
どんなに優れた制度も、評価者である管理職が正しく運用できなければ意味がありません。
評価者によって評価基準にバラつきが出ないよう、定期的な「評価者研修」は必須です。
研修では、評価項目の定義を改めて確認したり、具体的な部下の行動事例をもとに評価のシミュレーション(キャリブレーション)を行ったりします。評価者全員の「モノサシ」を揃えることが、公平な評価運用の鍵となります。
先程も解説しましたが、納得感のある評価制度を作るには、まず組織全体としての方向性を示して社員と合意をしたうえで制度を作ることが重要です。そして、何より評価者になるマネージャー・リーダークラスのメンバーと徹底的にすり合わせをして、評価の仕方や基準をインストールすることが重要です。
とはいえ、「そもそもそこに時間を充てられていない」「ベンチャーにおける評価制度の正解がわからない」「評価制度のすり合わせを含めたマネージャー育成に苦戦している」など様々な課題があるかと思います。
我々マネディクは、これまで300社以上の成長ベンチャー企業をご支援してきた実績・経験をもとに、各社にカスタマイズした評価制度の設計からマネージャーにインストールする実行まで一貫してご支援をさせていただいています。
ご興味のある方は、ぜひ以下の資料をダウンロードしてみてください。

【マネージャー必見】部下の不満をなくす評価フィードバックの技術
制度が整っても、最終的に部下の納得感を左右するのは、現場のマネージャーによるフィードバックです。
ここでは、評価面談で部下の不満をなくし、成長を促すための具体的な技術をお伝えします。
フィードバックの基本姿勢:評価は「伝える場」ではなく「すり合わせる場」
まず、評価面談に対する考え方を改めましょう。
面談は、評価結果を一方的に「伝える場」ではありません。部下の自己評価やキャリアに対する考えに耳を傾け、会社の期待とすり合わせながら、次の成長への道筋を共に考える「対話の場」です。
この姿勢で臨むだけで、面談の雰囲気は大きく変わります。部下は「自分のことを理解しようとしてくれている」と感じ、上司への信頼感を深めるでしょう。
実践テクニック①:事実(Fact)をベースに具体的に伝える
フィードバックで最も避けるべきは、「主体性が足りない」「もっと頑張ってほしい」といった抽象的な言葉です。
これでは、部下は何を改善すれば良いのか分かりません。必ず、具体的な「事実(ファクト)」をベースに伝えましょう。
例えば、「先月のAプロジェクトで、君から一度も改善提案がなかったのは、何か理由があった?」というように、具体的な場面と行動を指摘します。日頃から部下の行動をメモしておくなど、面談の準備が重要です。
実践テクニック②:未来志向の「育成フィードバック」を意識する
フィードバックの目的は、過去の行動を責めることではなく、未来の成長を促すことです。
出来ていなかった点を指摘した後は、必ず「次の半期では、どうすればもっと良くなるか」という未来志向の対話に繋げましょう。
「次の半期は、君に〇〇という役割を期待している。そのために、この能力をさらに伸ばしていこう」というように、期待と育成のメッセージをセットで伝えることが、部下のモチベーションを高める鍵となります。
評価制度に関するよくある質問
最後に、評価制度の設計や運用に関して、人事担当者や管理職からよく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 評価制度は、どのくらいの頻度で見直すべきですか?
A1. 少なくとも年に1回は見直しを行うことを推奨します。
特に、事業が急成長しているベンチャー企業など、組織の状況が大きく変化する環境では、半期に1回の見直しが必要になる場合もあります。
重要なのは、「事業戦略と人事戦略が連動しているか」という視点です。新たな事業が始まったり、組織体制が変更になったりした際は、その都度、等級定義や評価項目が現状に即しているかを確認し、柔軟にアップデートしていく姿勢が求められます。
Q2. 部下が評価結果に納得してくれません。どうすれば良いですか?
A2. まず最も重要なのは、部下の話を傾聴することです。
「なぜそう感じるのか」を感情的にならずに冷静に聞き、相手の言い分を受け止める姿勢を見せましょう。その上で、評価の根拠となった具体的な「事実(ファト)」と、事前に定義された「評価基準」に立ち返って、客観的に説明します。感情論での議論を避け、あくまで事実ベースで対話することが重要です。
そして、過去の評価を議論するだけでなく、必ず「では、次の半期で良い評価を得るためには、具体的にどういう行動を期待するか」という未来志向の話に繋げ、部下の成長を支援するスタンスを明確に伝えましょう。
Q3. 社員をランク付けする「相対評価」は、導入すべきでしょうか?
A3. 相対評価は、人件費の原資が決まっている中で評価のメリハリをつけやすいというメリットがある一方、社員同士の過度な競争を煽り、チームワークを阻害するリスクもはらんでいます。
特に、社員一人ひとりの成長を重視するカルチャーの企業では、個人の成長や目標達成度に基づいて評価する「絶対評価」の方が適している場合が多いです。
自社が評価制度を通じて「何を達成したいのか(目的)」に立ち返り、競争を促したいのか、個々の成長を促したいのかによって、慎重に判断すべきです。
Q4. リモートワーク(テレワーク)の社員を、どうすれば公平に評価できますか?
A4. リモートワークにおける評価の鍵は、「プロセス」や「勤務態度」といった目に見えにくい部分ではなく、「成果(アウトプット)」で評価する仕組みへと転換することです。
そのためには、期初に「何を、いつまでに、どのレベルまで達成すれば評価されるのか」という具体的な目標(OKRなど)を、本人と上司の間で明確に合意しておくことが不可欠です。
また、日々の業務が見えにくい分、週に1度の1on1ミーティングなどを通じて、進捗の確認や課題の相談を密に行い、コミュニケーションの量と質で物理的な距離を埋める努力が求められます。